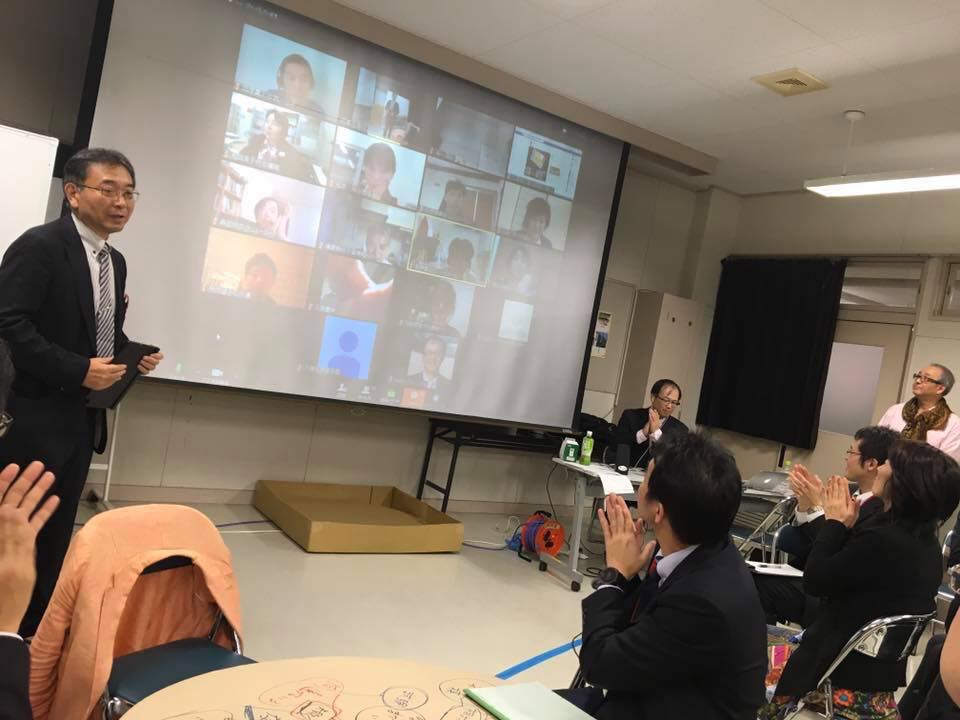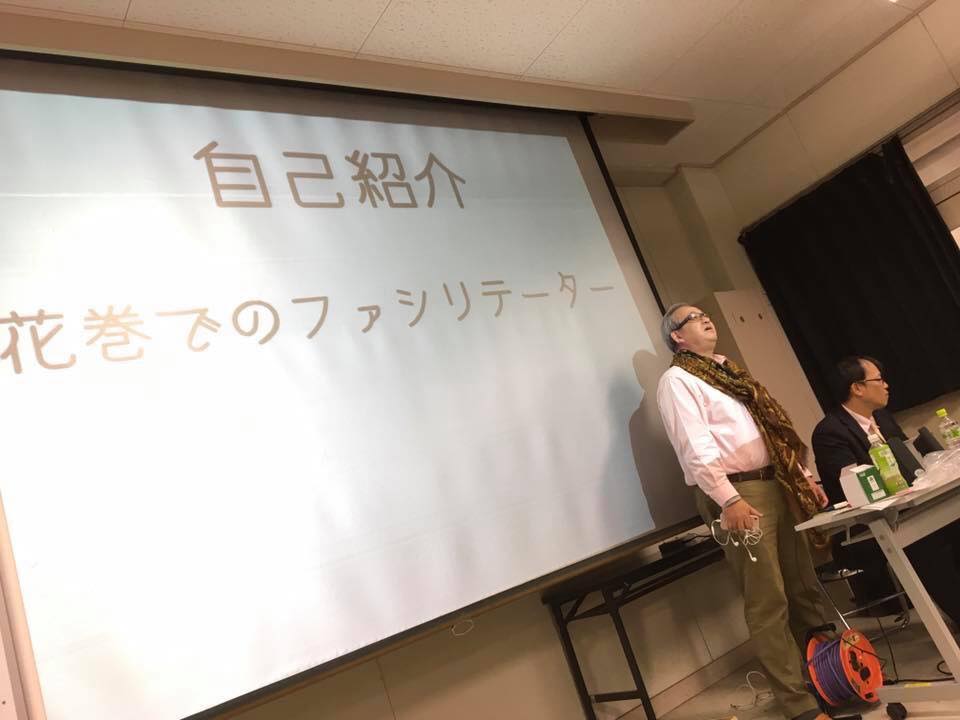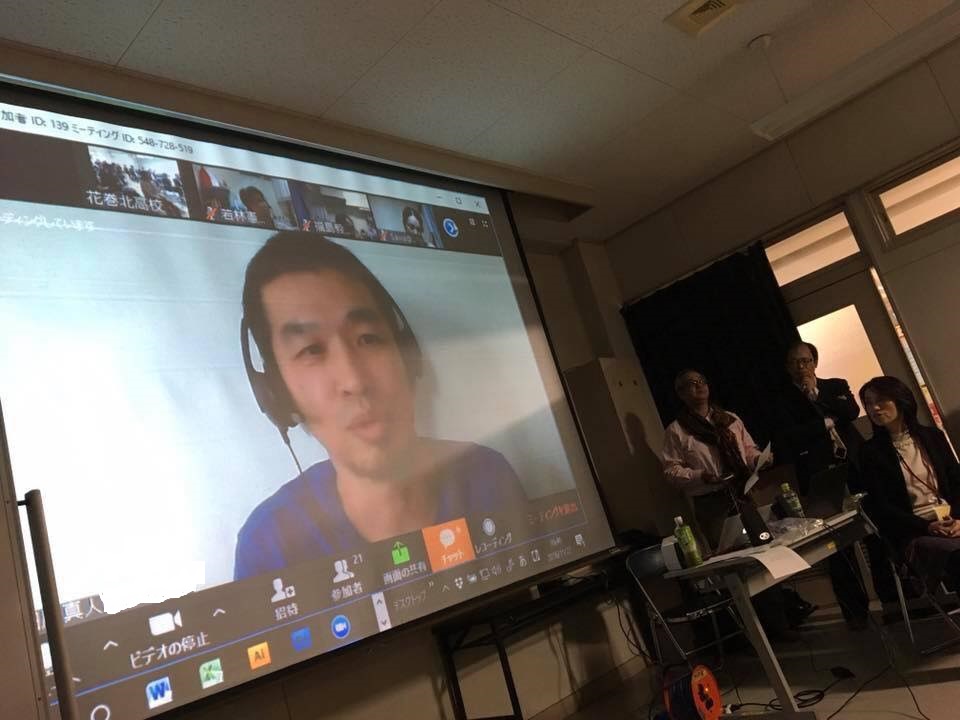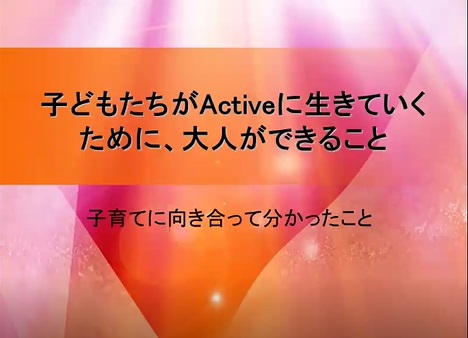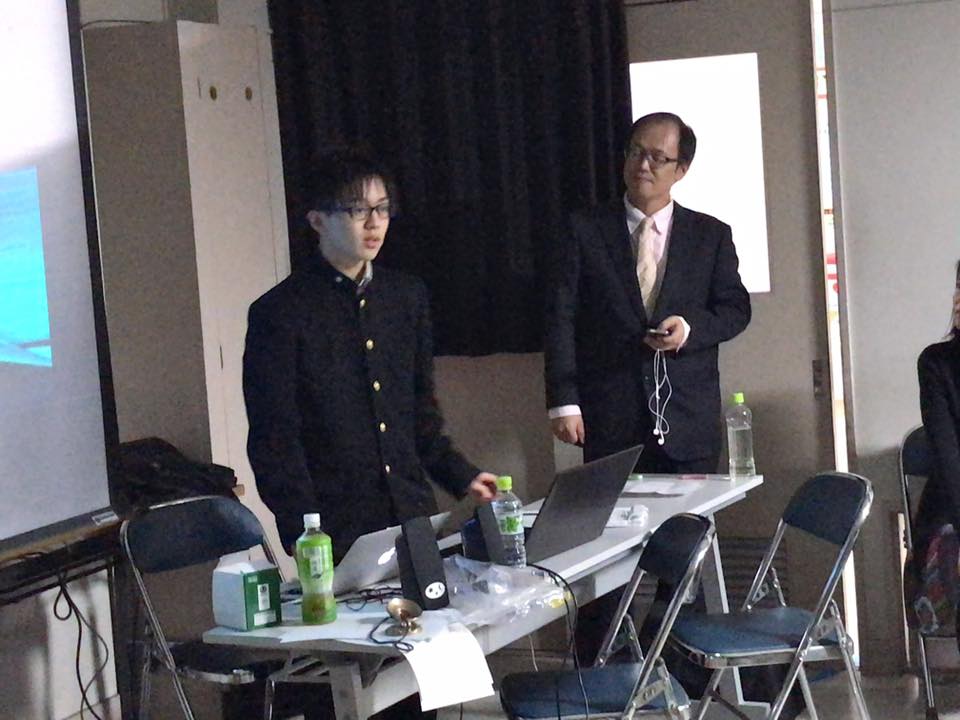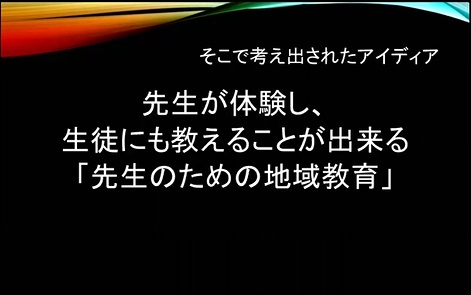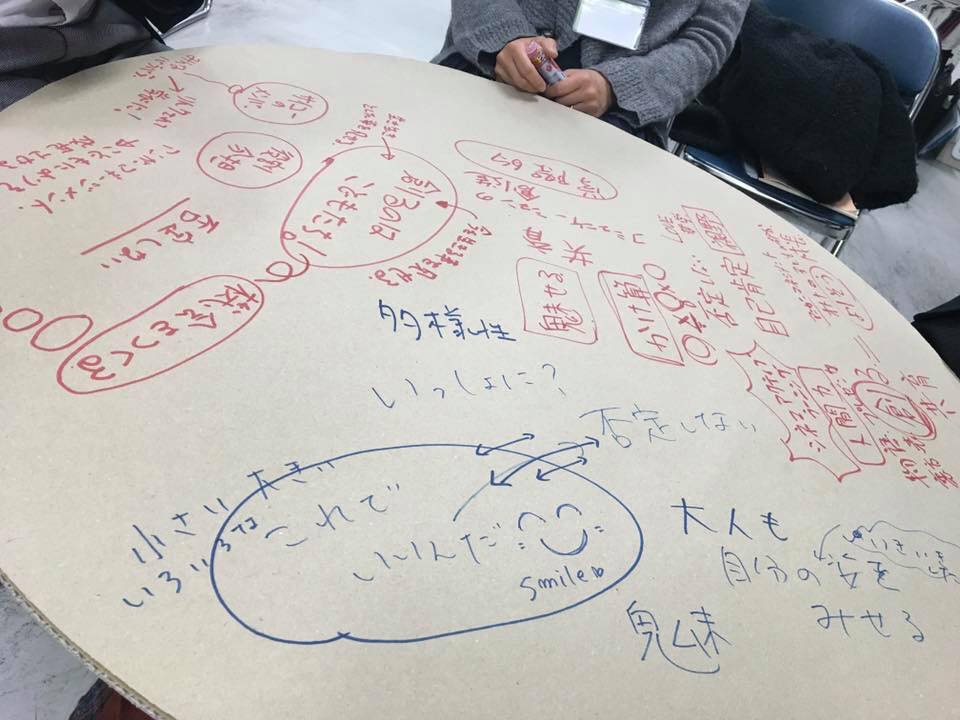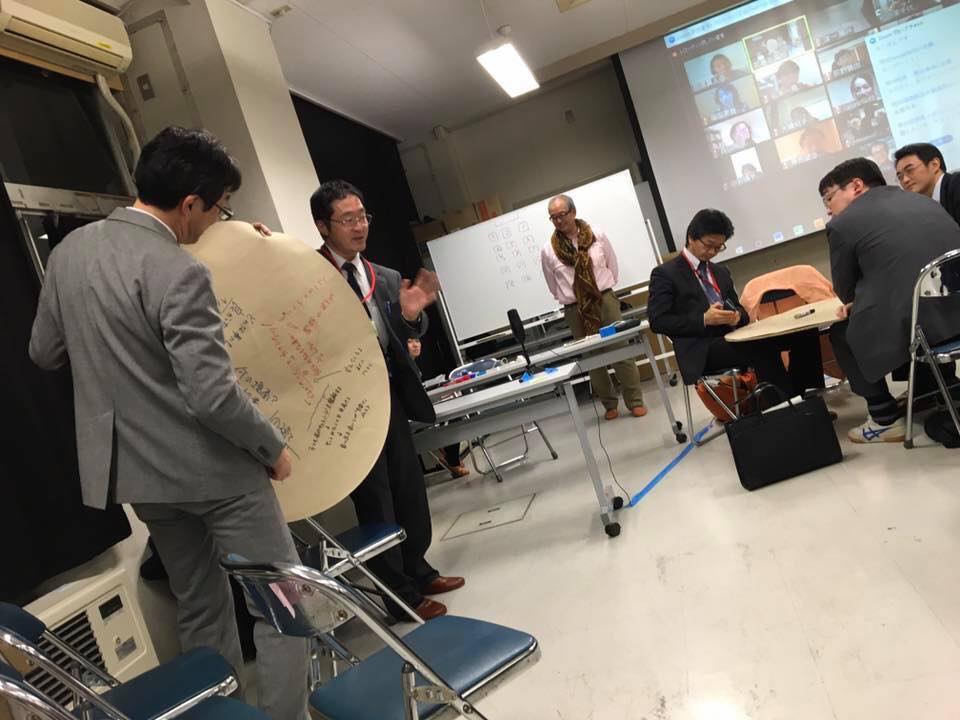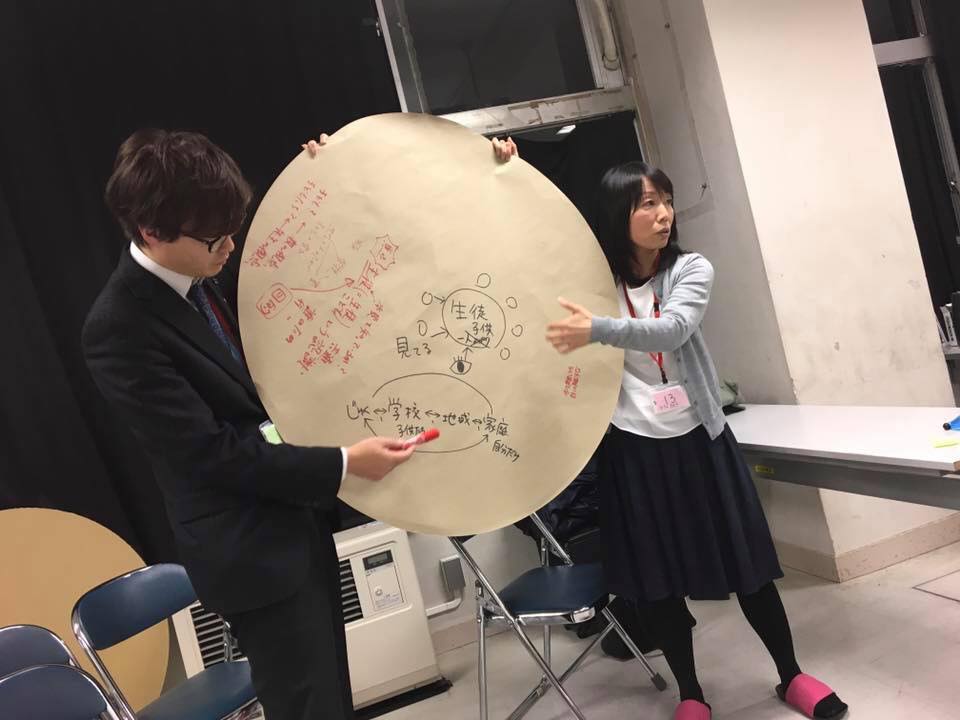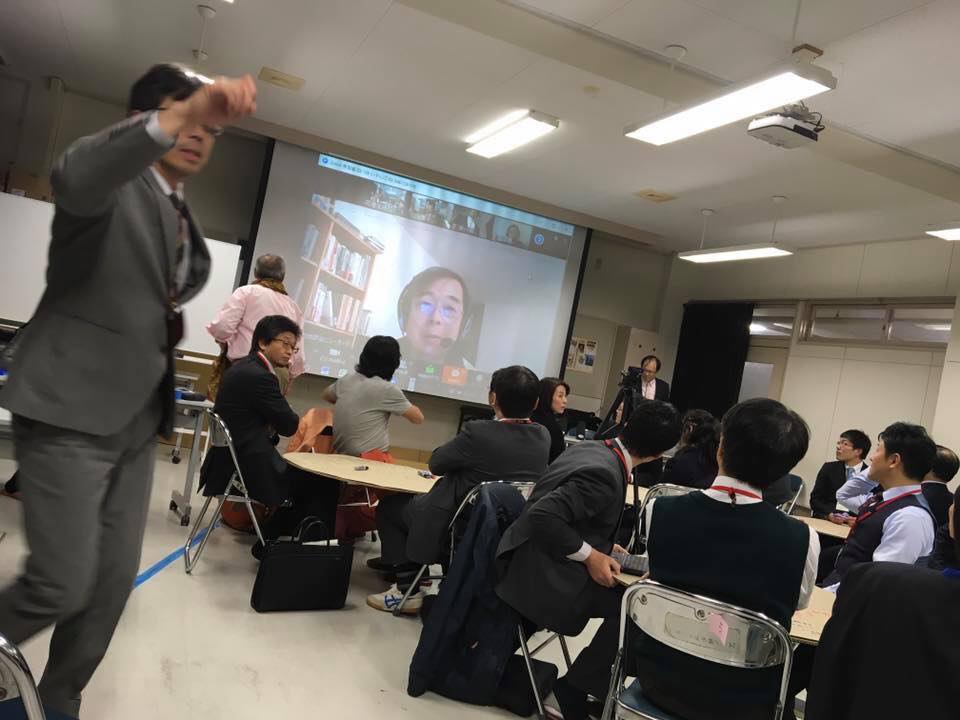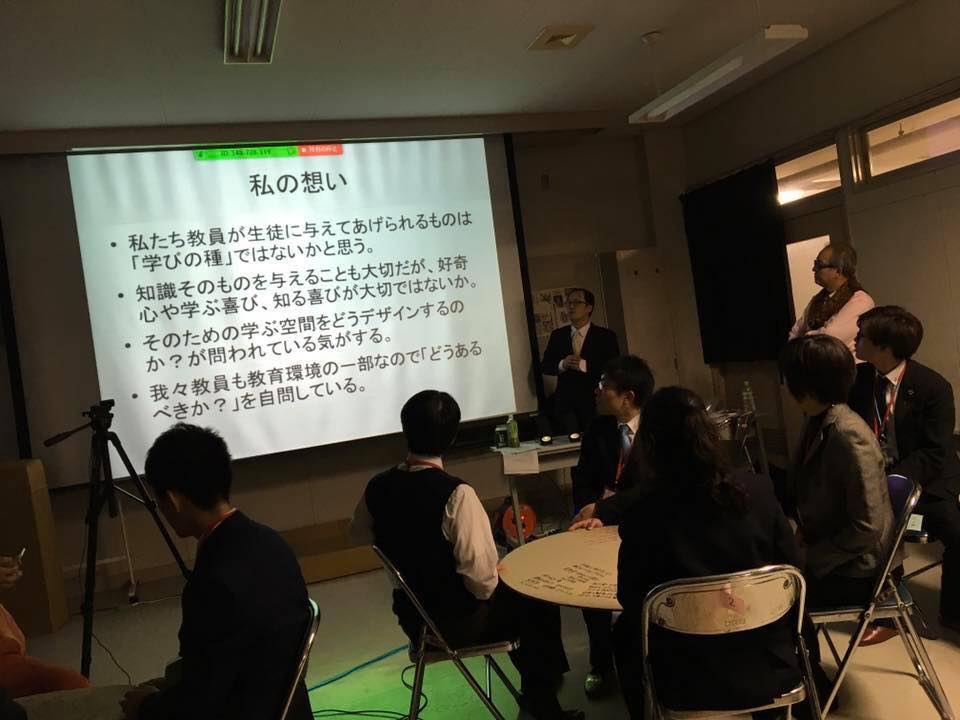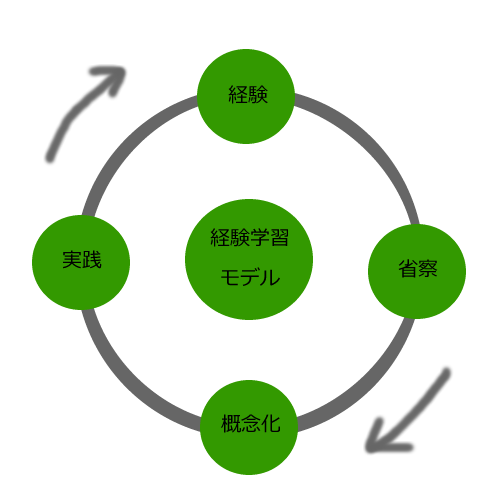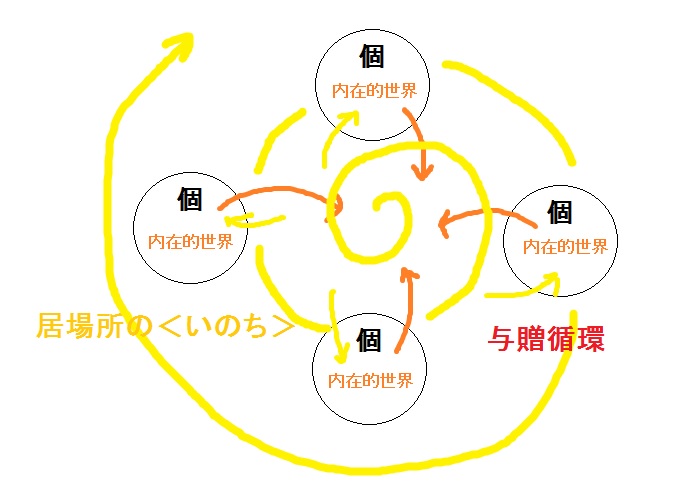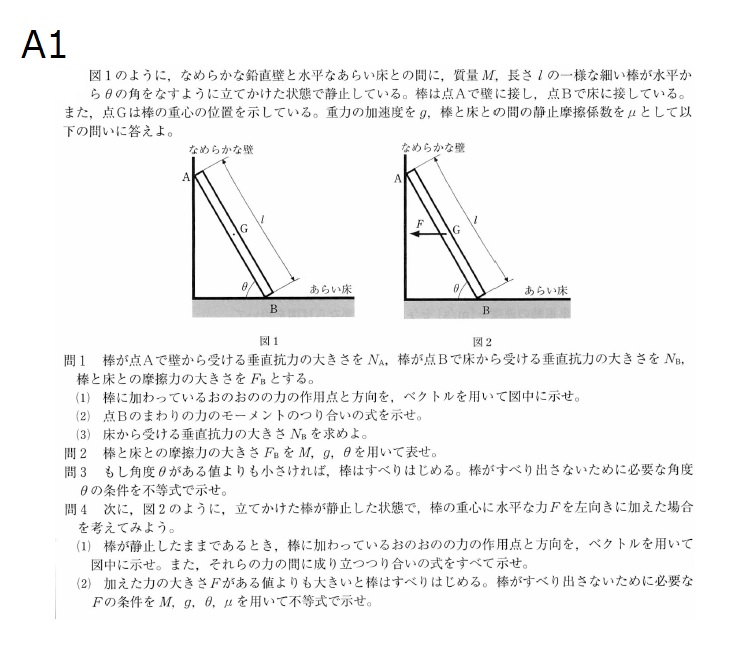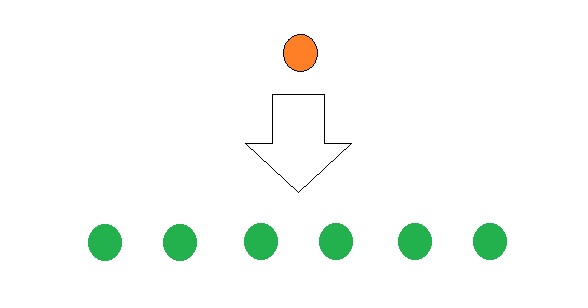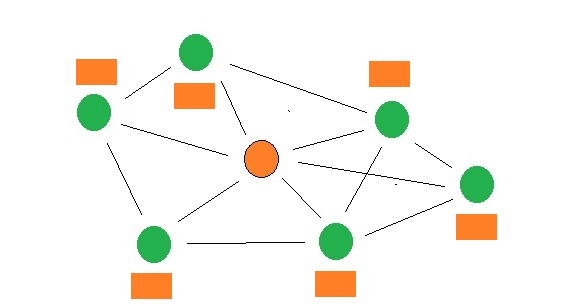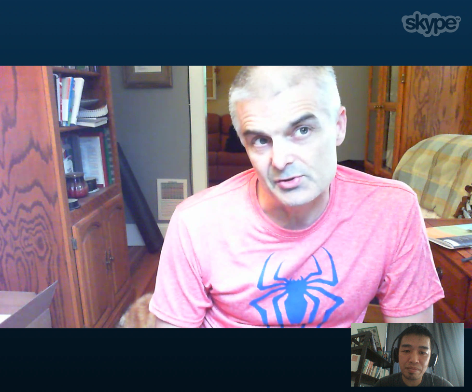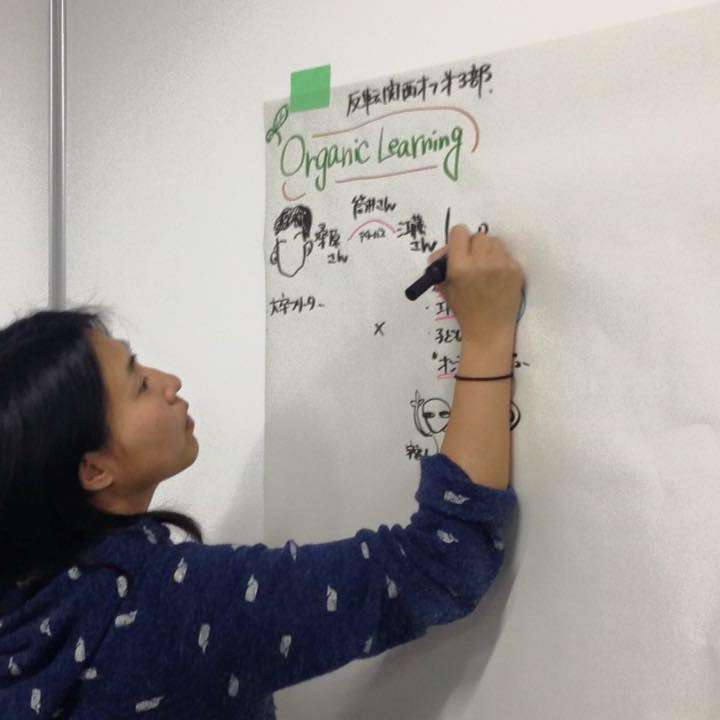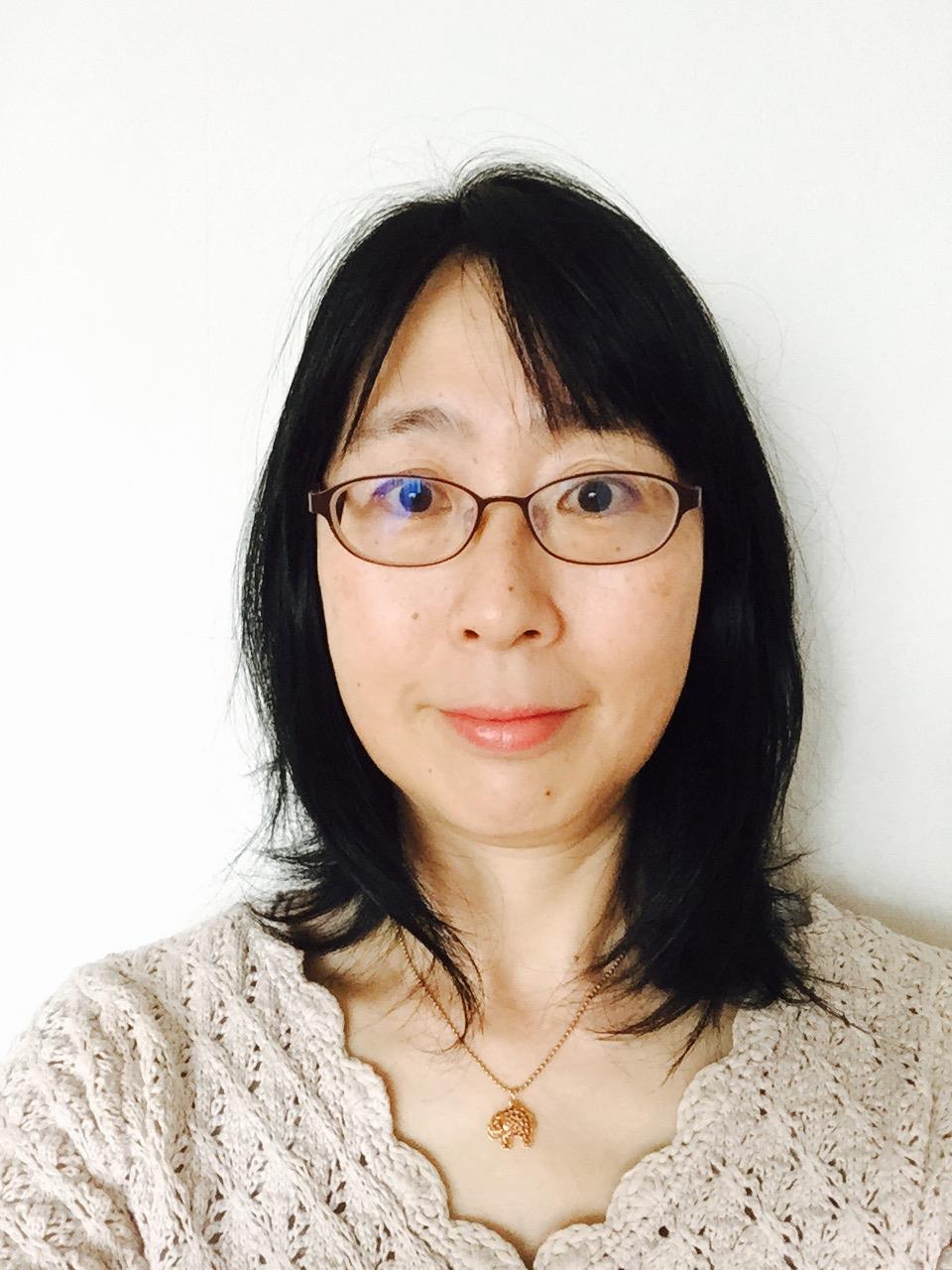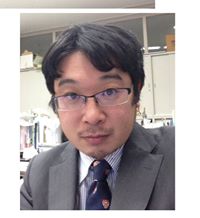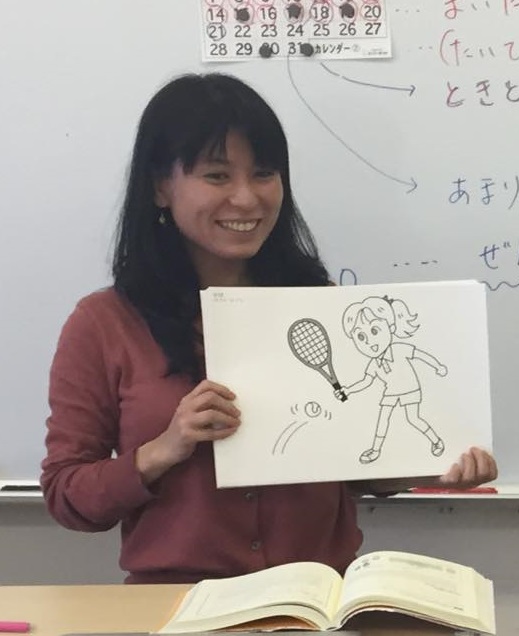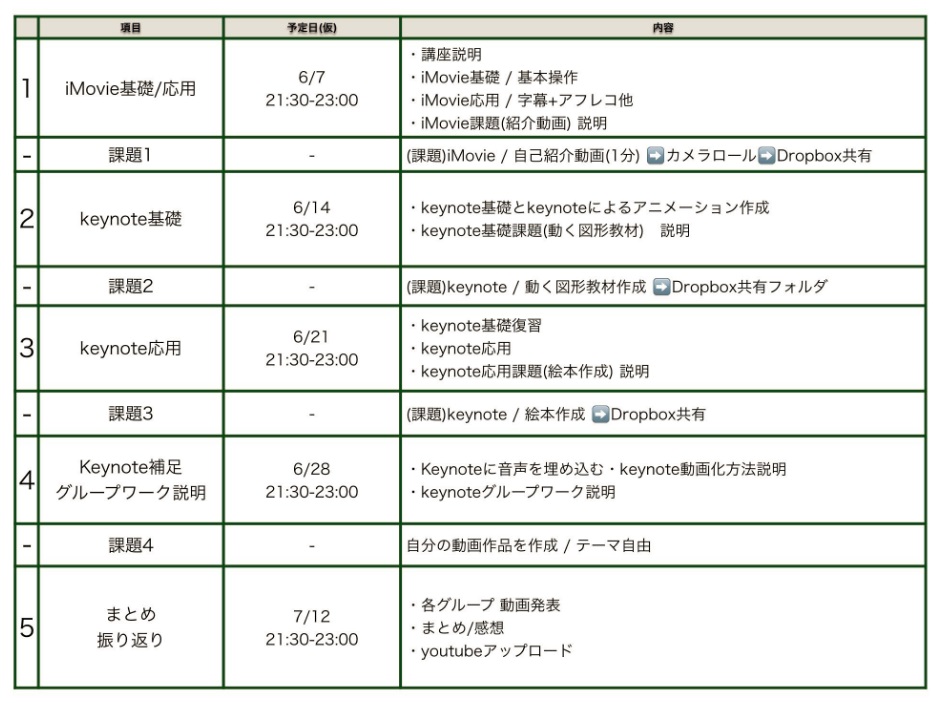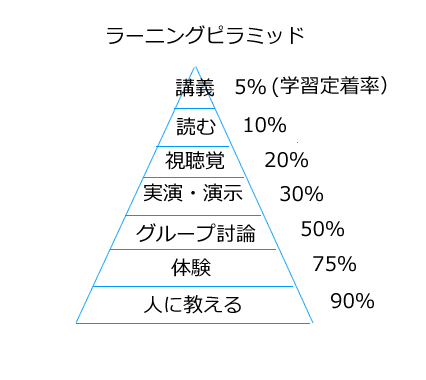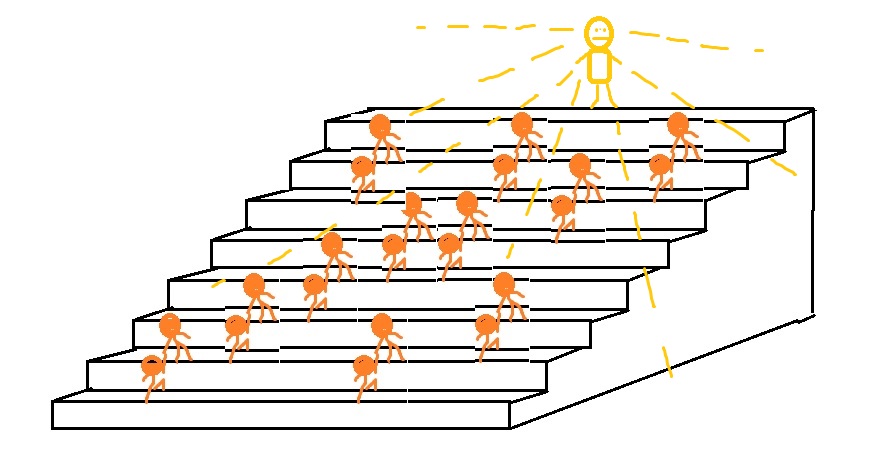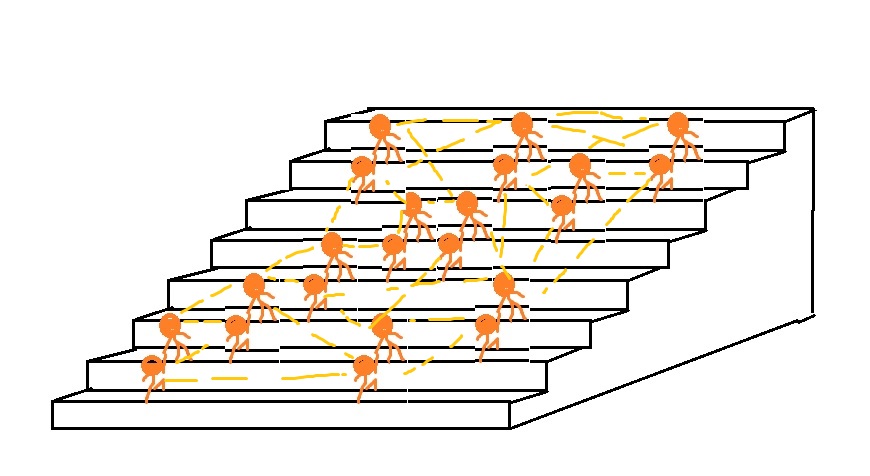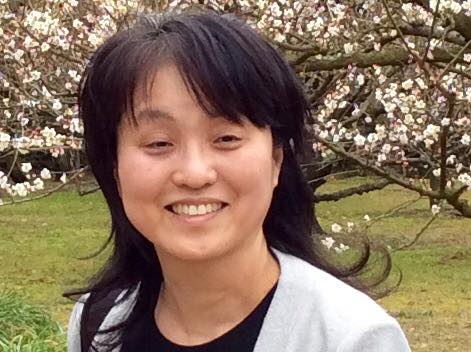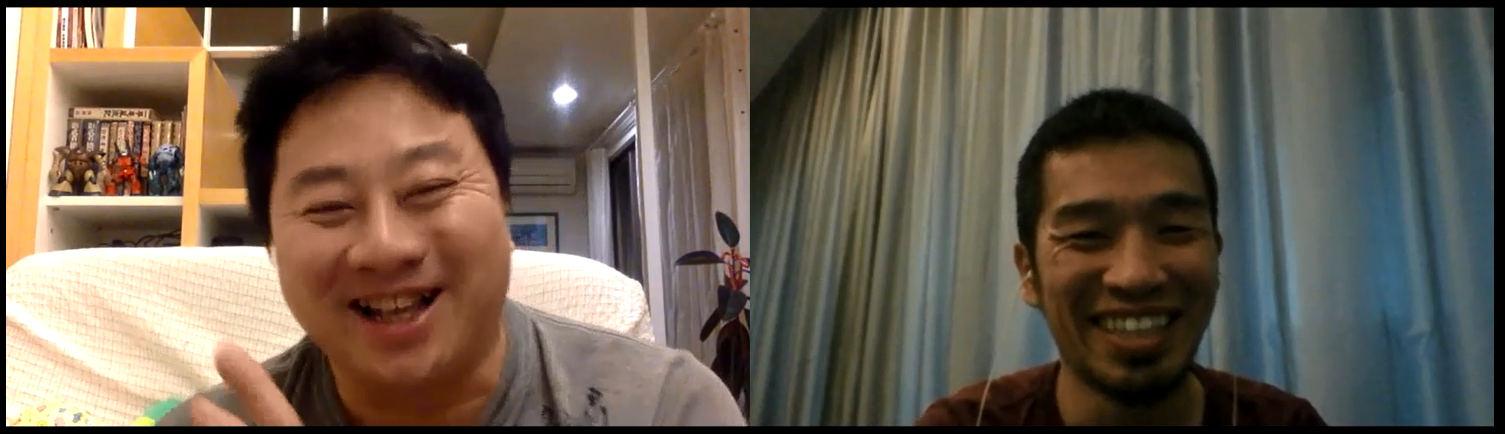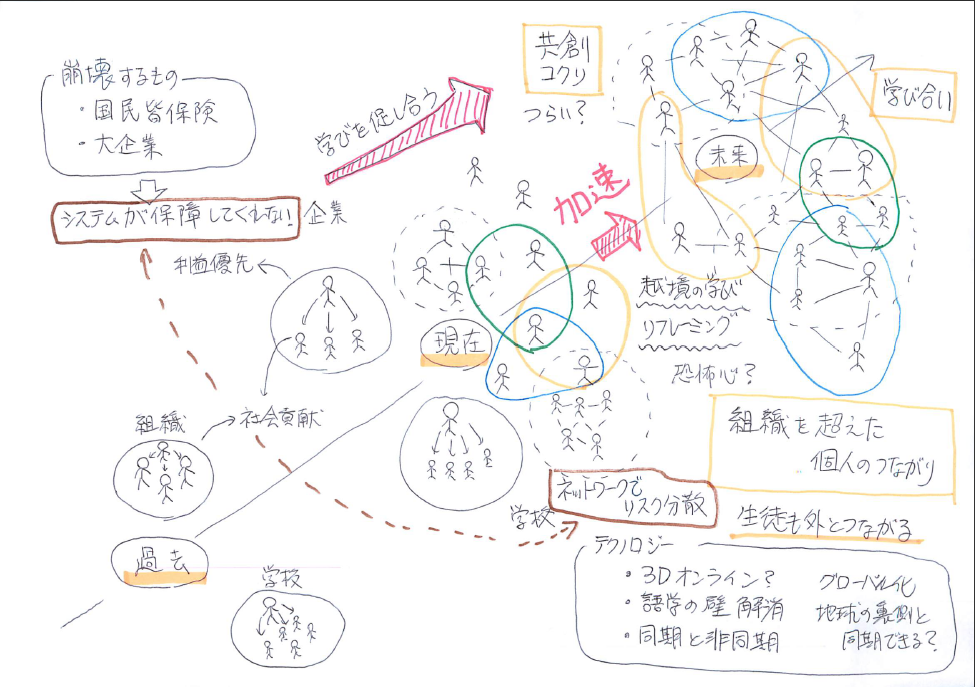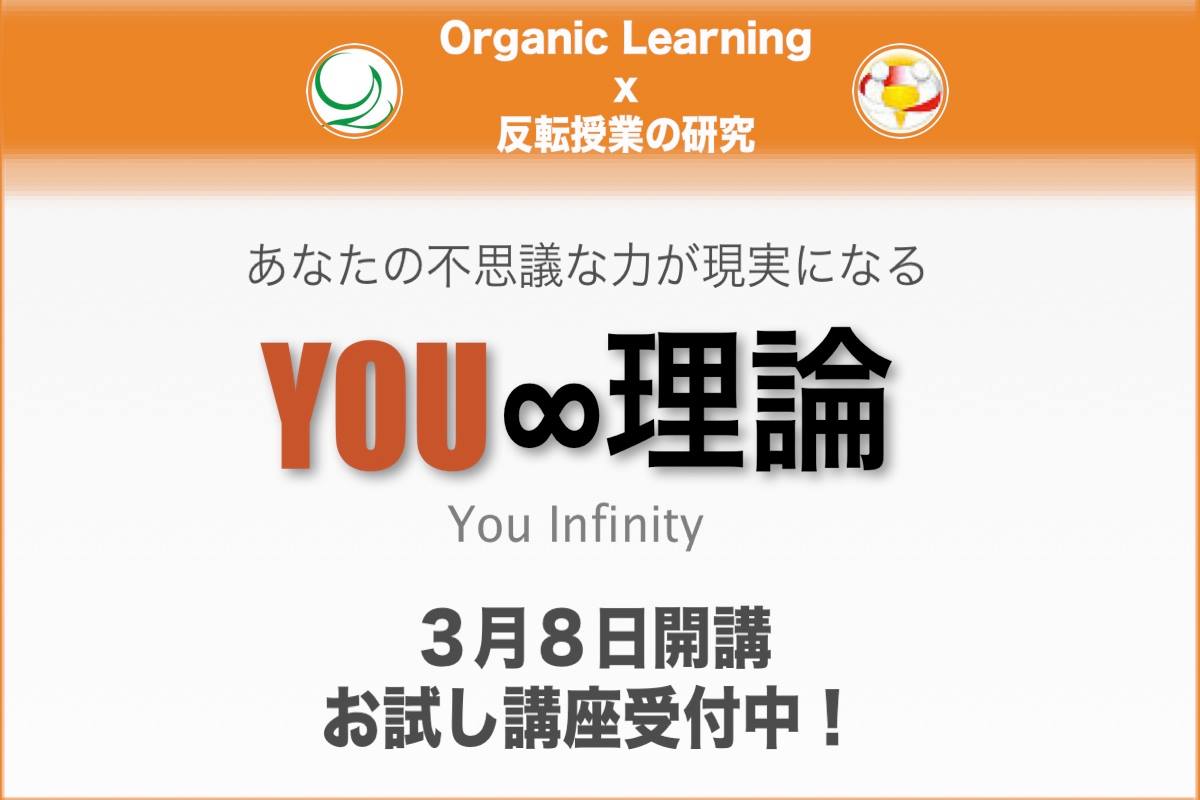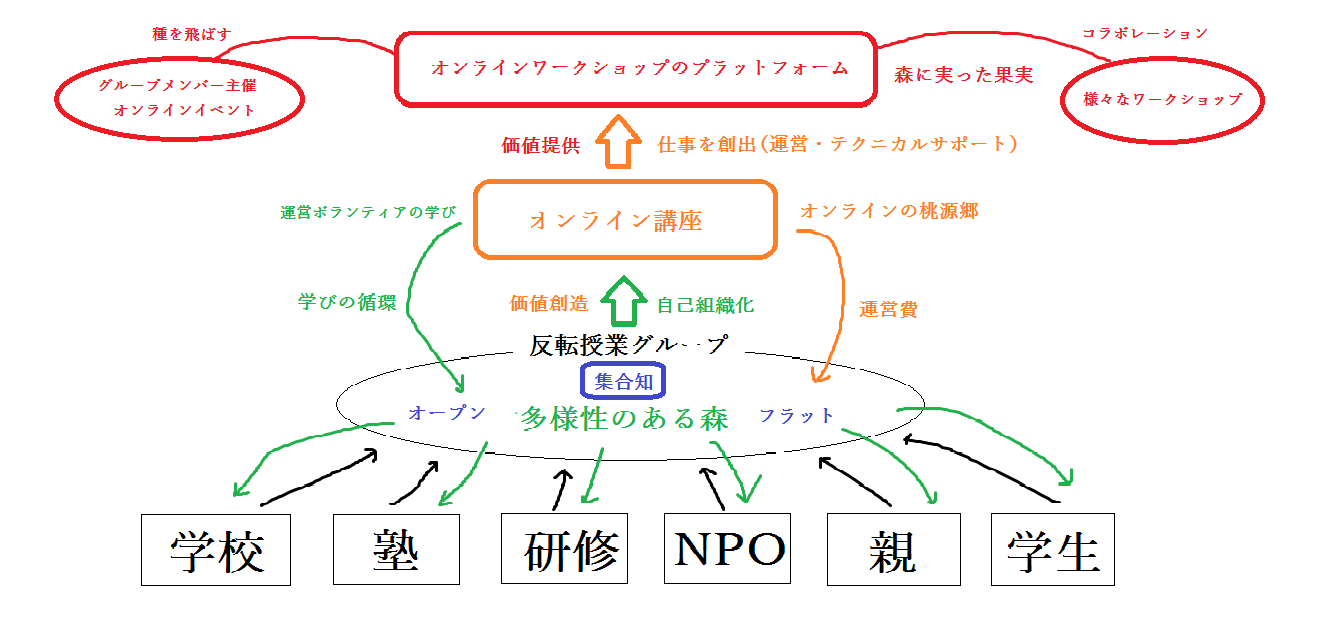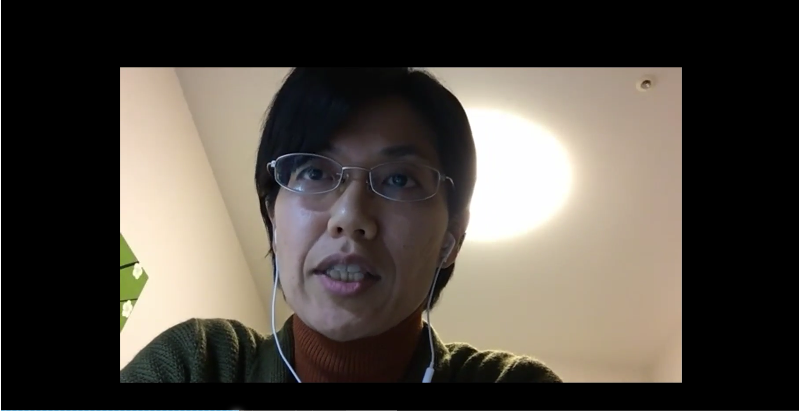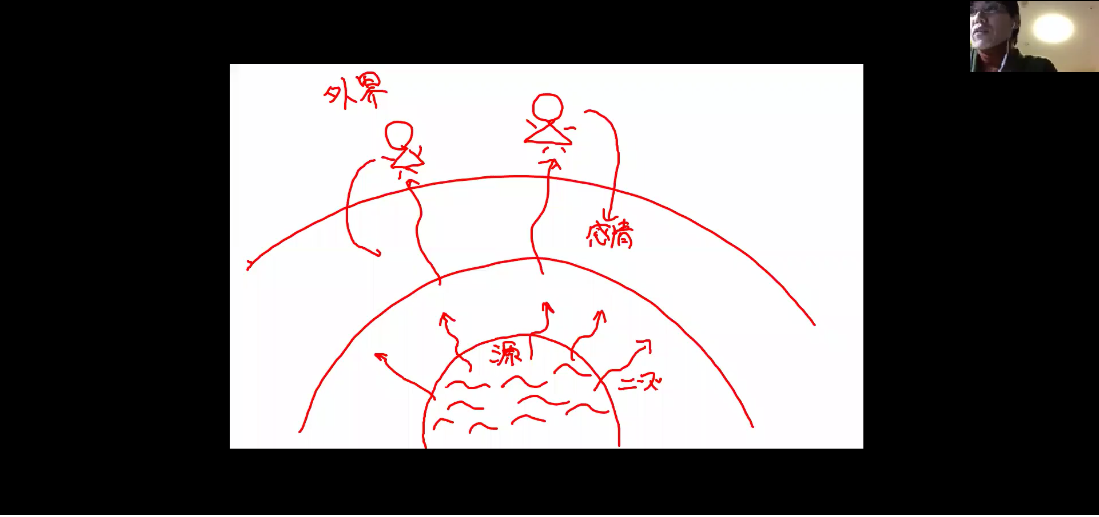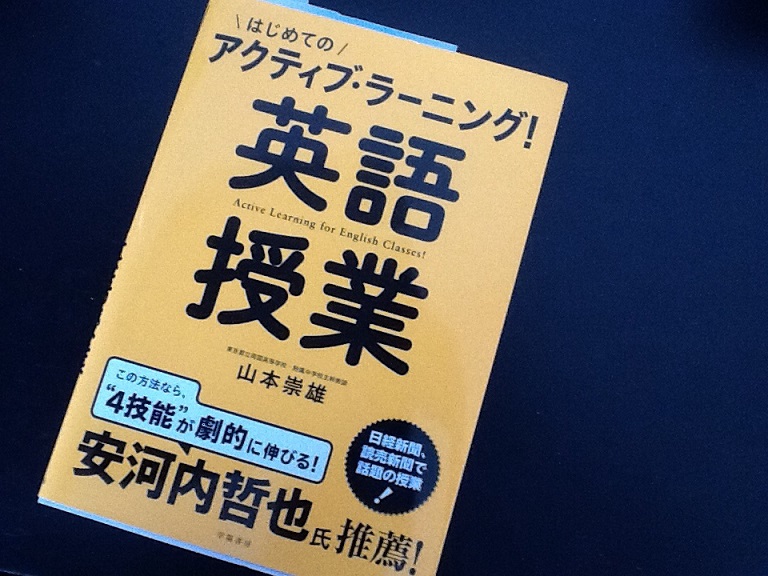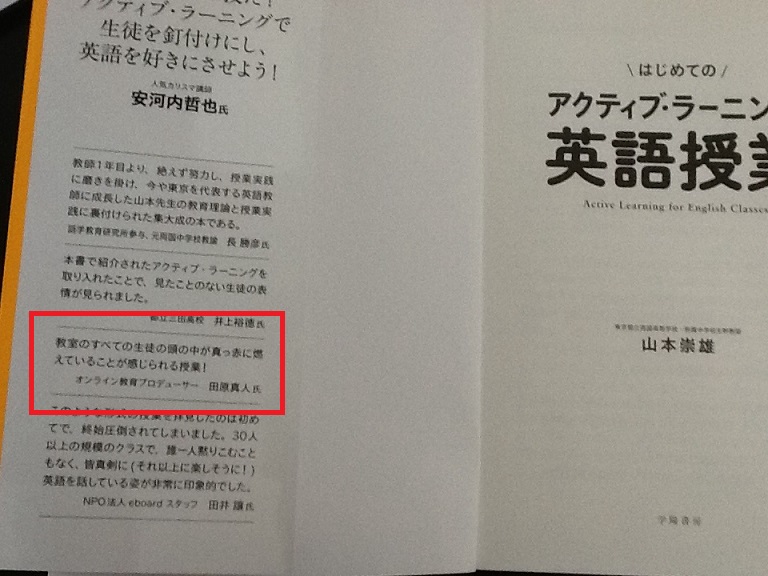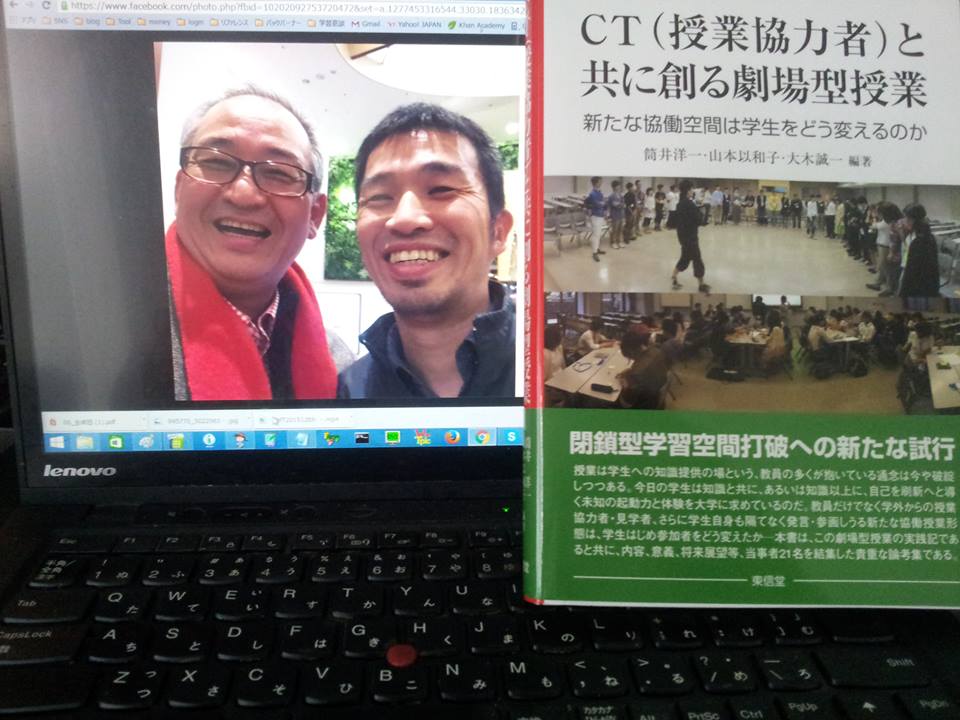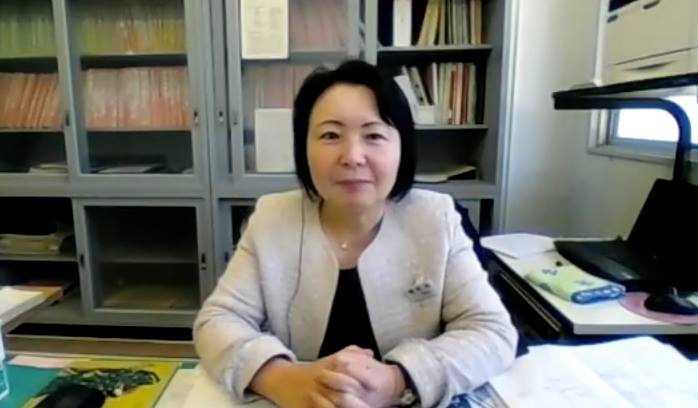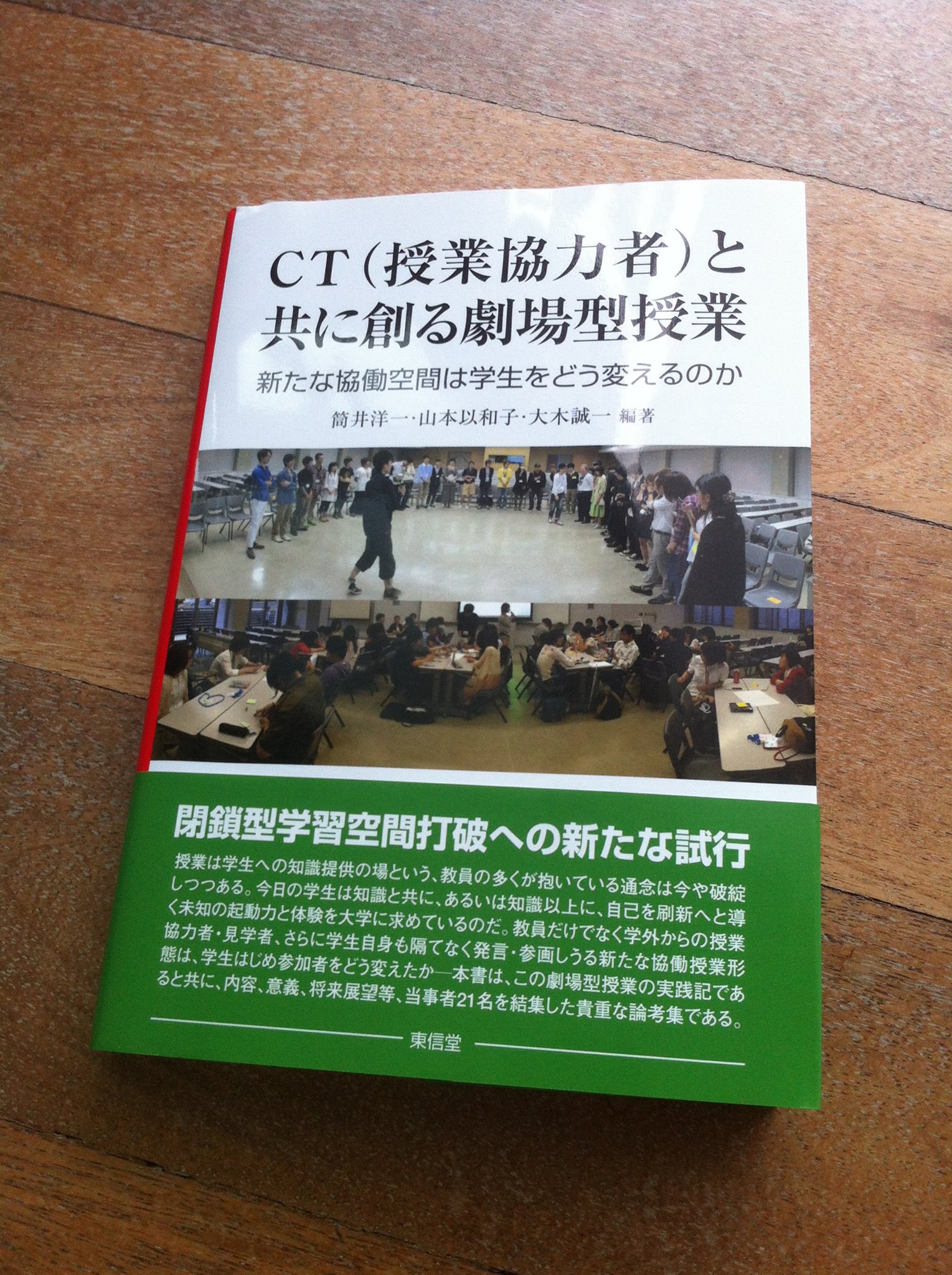フォアグラ型教育~すべての違いを学びの源にする(3)
反転授業の研究の田原真人です。
私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。
そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。
すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク
このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。
凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。
1)311の痛みを学びの源にする
2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却
3)フォアグラ型教育
4)自分自身になっていくプロセス
5)痛みを通してニーズに繋がる
6)マグマセンサーに従って生きる
7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル
8)なぜ「すべての違い」なのか?
9)栽培化された思考から野生の思考へ
10)ゆらぎとリフレーミングによる学び
11)「いのち」の与贈循環
12)全体性が回復されると何が起こるのか
13)周辺部で目覚めた人たち
14)トランスローカル
15)社会が自己組織化するために必要なこと
フォアグラ型教育
「違い」が学び合いのエネルギーとして使われるのではなく、分断の原因になってしまうのはなでなのか?
そのことを考えている中で、『魂の脱植民地化とは何か』という本と出会いました。
そして、この本の著者の深尾葉子さんや、安冨歩さんのグループが、魂の脱植民地化研究をされていることを知り、対話に加えていただきました。安冨さんは、魂の植民地化と脱植民地化を次のように定義します。
魂の植民地化とは、自らのではなく、他人の地平を生きるようになること、である。
魂の脱植民地化とは、他人のではなく、自らの地平を生きるようになること、である。
これらの考え方の触れたとき、工業型社会へ適応する教育には、魂の植民地化を進めていくもの、という側面があったのだと気づきました。では、具体的にどのようにして、魂の植民地化が進んでいったのでしょうか?
(参考記事 『魂の脱植民地化とは何か』を読んで考えたこと)
そのことを考えるヒントになったのが、パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』でした。
フレイレは、教育を次の2つのタイプに分類し、対話によって抑圧から抜け出していくことが大事だと述べます。
銀行型教育:子どもを空っぽの容器だと見なし、銀行にお金を預けるように、容器の中に知識を詰め込んでいく教育
対話型教育:子どもを有能な学習者だと見なし、対話を通して、子どもが主体的に学んでいくことを助ける教育
フレイレの2つのタイプに対して「なるほど」と思う一方で、「銀行型教育」という比喩がピンとこないという感覚がありました。
抑圧と身体の関係性が、比喩からこぼれ落ちているように感じたのです。
そこで、考えたのが、フォアグラの比喩でした。
フォアグラというのは、ガチョウなどの自由を制限した状態で、餌を強制的に口から流し込み、脂肪肝を作って食べるというものです。生徒に知識を詰め込んでいく姿が、フォアグラ生産のガチョウと重なったのです。
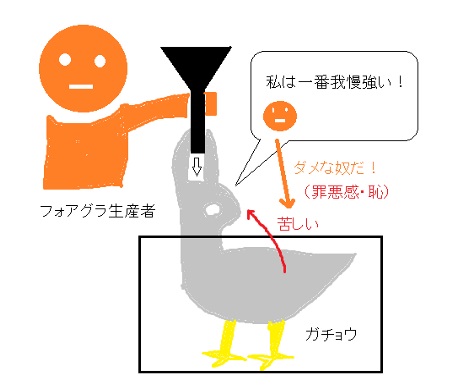
私の頭の中に浮かんだのは、次のようにして魂が植民地化されていく光景でした。
ガチョウは、檻に閉じ込められて自由を制限され、口から餌を流し込まれます。
ガチョウの身体は、「もうお腹いっぱいだ。苦しい」というサインをガチョウの頭に送ります。
その一方で、フォアグラ生産者はガチョウに「口を閉じないで我慢できるのは偉いぞ」と褒めたり、「檻の中から出ていくと餓死するぞ」と脅したりします。
自由を奪って選択肢を減らした上で、アメとムチによって外部から方向付けていくことで、ガチョウは、自分の身体からの声を無視し、フォアグラ生産者の声を自分の内側に取り込むようになります。
自分の地平ではなく、フォアグラ生産者の地平を生きるようになるのです。
内面化したフォアグラ生産者の視点は、自分の身体からの声を抑圧して罪悪感を与えたり、周りのガチョウを抑圧して同調圧力を加えたりします。
フォアグラ生産者の声が「正しさ」として響き、それ以外のものを認められない状態が生まれます。
私は、このような魂が植民地化されていくような教育の仕組みに「フォアグラ型教育」と名づけることにしました。
私は、ガチョウの役も、フォアグラ生産者の役も、どちらも経験してきていて、その両方に痛みを感じています。
でも、その一方で、痛みの奥に、自分の魂を躍動させ、十全に行きたいという情熱を見いだしています。
(参考記事 フォアグラ型教育から対話型教育へのシフト)
12月7日から始まるワークショップでも、痛みの奥にある大切なものを一緒に探求していきます。
参加のハードルをゼロにする試み
このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。
今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。
時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。
田原真人2017冬日本ツアー日程
第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)
第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)
第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)
第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)
工業型社会へ適応する教育システムからの脱却~すべての違いを学びの源にする(2)
反転授業の研究の田原真人です。
私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。
そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。
すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク
このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。
凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。
1)311の痛みを学びの源にする
2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却
3)フォアグラ型教育
4)自分自身になっていくプロセス
5)痛みを通してニーズに繋がる
6)マグマセンサーに従って生きる
7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル
8)なぜ「すべての違い」なのか?
9)栽培化された思考から野生の思考へ
10)ゆらぎとリフレーミングによる学び
11)「いのち」の与贈循環
12)全体性が回復されると何が起こるのか
13)周辺部で目覚めた人たち
14)トランスローカル
15)社会が自己組織化するために必要なこと
工業型社会に適応する教育システムからの脱却
311を経験して感じた分断の痛み。
今の日本は、共通部分で同調的に他人と繋がるという繋がり方が目立ちます。
同調的でないコミュニケーションは、「空気を読まない」として排除されたりするので、同調から外れてはいけないという圧力を感じ、共通部分だけを安全に表現しようとする傾向があると感じています。
このような繋がり方は、311のように、覆い隠せない「違い」が現れたとき、簡単に切れてしまいます。
私が「反転授業の研究」を立ち上げたとき、「多様性のある森をオンラインに作っていきましょう」と呼びかけました。
その背景には、共通部分で繋がる以外の、新たな繋がり方を模索したいという気持ちがありました。
自分の知らないこと、自分が考えたことのないこと、などを場に出してくれる人に感謝し、自分も知っていることやできることを提供し、オンラインでの対話を繰り返していくと、集合知が生まれてきました。
そして、協力して集合知を生み出したという経験によって、人がお互いに繋がりはじめました。
私は、ここに大きな希望を見いだしました。
なぜなら、集合知で繋がるという方法は、「違い」があるからこそ繋がれる方法だからです。
アクティブ・ラーニングのオンライン講座をやったときに、講師の小林昭文さんが、次のように語りました。
「違いは、学び合いのエネルギーになる」
これは、その後の私の活動に、大きな影響を与えた言葉でした。
違いを許容できずに分断してしまう社会を、私たちの教育システムが創り出してきたのかもしれないと考えることは、その教育システムの中で働いてきた私には苦しいことでした。
でも、311で感じた分断の痛みのほうが大きかったので、自分の足下を切り崩していくような感じで問題を見ていくことになりました。
工業化社会は、ボスの指令を正確に忠実にこなしていく労働者を育てる産業化教育によって支えられてきました。未来学者のアルビン・トフラーは、『第三の波』の中で、産業化社会には、次の3つのヒドゥンカリキュラムがあると述べています。
(1)時間厳守
(2)服従
(3)単純な反復作業に耐える
日本の場合は、これらのヒドゥンカリキュラムに加えて、検定教科書を使って教えるため、唯一の「正解」が存在し、それ以外のものは「間違い」であるということを、生徒は暗黙の前提として受け取ってきたのではないでしょうか。
すでに「正解」が確定しているのであれば、それを批判的に捉えるのは時間の無駄であり、むしろ無批判に受け入れて、教えられた方法で素早く「正解」を導き出すスキルを磨いていくほうが、学校においても、社会においても有利です。
社会的な地位や、金銭的な報酬、学歴による序列化などが、すべて、前提を疑わずに受け入れ、「正解」を素早く導き出すスキルを磨くことを後押ししている状況の中で、思考フレームの均質化が起こってきたのではないかと思います。
マジョリティが持つ均一の思考フレームが、常識であり、「正解」となると、それ以外の思考フレームは「間違い」となり、表現することが抑圧されてきます。
その結果、常に「正解」の思考フレームの存在を意識し、そこに対して、欠けている部分を感じると自信を失い、はみ出している部分を感じると、いけないことだとして抑圧するようになってきたのではないでしょうか。
多様性を学び合いのエネルギーとしていくためには、このようなヒドゥンカリキュラムや正解主義から見直していく必要があります。
そして、それが、311のときに顕わになった、「違い」によって分断が生まれてしまう社会を乗り越えるために、教育ができることなのではないでしょうか。
そもそもの部分から、一緒に考えませんか?
12月7日から、私たちの哲学を立ち上げる学びの旅がスタートします。
参加のハードルをゼロにする試み
このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。
今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。
時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。
田原真人2017冬日本ツアー日程
第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)
第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)
第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)
第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)
311の痛みを学びの源にする~すべての違いを学びの源にする(1)
反転授業の研究の田原真人です。
私は、2018年、本気で教育のパラダイムシフトに取り組んでいきます。みなさん、力を貸して下さい。
そのキックオフとなるワークショップを12月7日~2月3日の2ヶ月間で行います。
すべての違いを学びの源にすると決めたらどんな哲学が立ち上がるだろうか?~私たちの教育哲学を立ち上げる共創ワーク
このワークショップのタイトルには、6年間の気づきと学びが凝縮しています。
凝縮されすぎていて、簡単には伝わらないと思いますので、全15回の連載で、紐解いていきながら、自分自身も振り返っていきたいと思います。おつきあいいただけるとうれしいです。
1)311の痛みを学びの源にする
2)工業型社会へ適応する教育システムからの脱却
3)フォアグラ型教育
4)自分自身になっていくプロセス
5)痛みを通してニーズに繋がる
6)マグマセンサーに従って生きる
7)ぷれジョブとの出会いから生まれた共存在サイクル
8)なぜ「すべての違い」なのか?
9)栽培化された思考から野生の思考へ
10)ゆらぎとリフレーミングによる学び
11)「いのち」の与贈循環
12)全体性が回復されると何が起こるのか
13)周辺部で目覚めた人たち
14)トランスローカル
15)社会が自己組織化するために必要なこと
311の痛みを学びの源にする
2011年3月11日に起こった東日本大震災と原発事故は、私の人生を一変させてしまいました。
しかし、この一行を書くときに、自分の内側に痛みが走ります。
津波の被害に遭った沿岸部の人たちのことを思うと、口をつぐみたくなるのです。
福島の避難地区に住んでいた人たちのことを思うと、口をつぐみたくなるのです。
一方で、日立市出身で、水戸ーいわきー仙台を毎週行き来して暮していた私にとって、それは、自分が生きてきた場所で起こった出来事で、現在の浪江町や大熊町の写真を見たりすると、今でも、心が大きく反応してしまい、息が苦しくなります。
自分の内側の痛みは、もっと大きな被害を受けた人のことを考えると表現せずに飲み込みたくなり、311の影響が自分より小さかった人には分かってもらえないんだろうなとあきらめて黙り込みたくなる、ということが、私だけではなく、多くの人に起こっていたのではないかと思います。
避難地区になった場所、ならなかった場所
補助金をもらった人、もらわなかった人
避難した人、残った人
外側から強制的にやってくる違いもあれば、選択をするたびに生まれてくる違いもあります。
今まで「同じ」によって繋がっていた関係性が、「違い」が生まれるごとに断ち切られていくことを体験しました。
本当に粉々になってしまったと感じました。
なぜ、「違い」によって分断が生まれるのか?
本来、人間は、すべて違うはずなのに。
すべての人間が違うことを前提として協力し合う社会だったら、あのような分断は起こらなかったのではないか?
これが、311を体験して、私の中に生まれた問いです。
私は、かつて、他人と違う部分を表現するのを怖れ、「同じ」である部分を選んで表現していました。
しかし、他人と違うからこそ、他人と深く繋がることができることを体感し、「違い」を表現することがこわくなくなりました。
それは、自分自身を大切にすることに繋がり、自分が、今、本当に何をやりたがっているのかを問いかけながら進めるようになりました。
これは、私が311の分断の痛みから受け取ったギフトです。
もし、すべての違いを学びの源にすることを決めたら、どんなことが起こるのか?
一緒に実験しながら、探究しませんか?
12月7日から、私たちの哲学を立ち上げる学びの旅がスタートします。
参加のハードルをゼロにする試み
このワークショップに2ヶ月間、全力投球することに決めています。京都インパクトハブの場所代、企画&運営を手伝ってくれる方への謝礼、田原が2ヶ月間稼働できる資金として、寄付&与贈オークションという形で50万円を目標額に資金調達をします。
今回、参加費として集めることも考えたのですが、このテーマは、できるだけ多くの人と一緒に考えたいし、多くの人に自分ごととして関わってほしいことを考えたとき、寄付&与贈オークションという形が一番しっくり来ました。
時間とエネルギーを持ち寄ってくれる人、お金を持ちよってくれる人、ギフトを提供してくれる人、それらすべてに支えられて、今回のワークショップが実現できたら、ワークショップの新たな形が生まれます。これも、未来を創る挑戦の一つです。
田原真人2017冬日本ツアー日程
第3弾 被災地のフリースクールとともに反転授業を学ぶ(福島×オンライン) (12/18)
第4弾 Frontier Online Community キックオフイベント(福島×オンライン)(12/18)
第5弾 Zoom働き方革命(東京×オンライン)(12/19)
第6弾 学びのシェア会(仮)(12/19)
保護中: 反転ワールドカフェ録画動画(要パスワード)
Flipped Learning Hybrid Cafe session
Internet age began in 1995. 22 years have passed since then and the world has significantly changed.
With the world connected by network, the planet is becoming like one big life form. Knowledge and wisdom has been stored on the internet and anyone can have easy access to a variety of information for free of charge. AI has been developed and there is no doubt it will be introduced in different fields.
Facing such social upheavals, education is moving toward an era of reform.
Brand-new type of education is much-needed as conventional success model will not be applicable to children today.
Flipped Learning may be an answer to learning for the future.
We will explore where education should be headed for the future. World Café, a whole group interaction method focused on conversations, will guide us there.
What is Hybrid Cafe?
World Café is a process for leading collaborative dialogue, sharing knowledge and creating possibilities for action. Groups of people discuss a topic at several tables, with individuals switching tables periodically. In this event, 2-round discussion is held at the venue in Tokyo and online following inspiration talks.
Educators from all over the world will be expected to join the online World Cafe. You can choose either English group or Japanese group. There will be an interpreter at the venue.
Jonathan Bergmann (online)
Jon Bergmann is one of the pioneers of the Flipped Class Movement, leading the worldwide adoption of flipped learning by working with governments, schools, corporations, and education non-profits. Jon is coordinating or guiding flipped learning initiatives around the globve. Jon is also the author of seven books including the bestselling book: Flip Your Classroom.
Masato Tahara (Tokyo)
Flipped Learning Global Initiative Ambassador / IAF Japan Director
Masato is leading the facebook group “Flipped Class Study Group.” In 2013, Masato introduced flipped learning in his online physics course and started running online communities for practitioners of flipped learning. His latest book “ Zoom – Online Revolution” is coming soon.
Online participation is FREE but you must register
Flipped Class Study Group in Japan will host this hybrid session at the 2017 Mirai Sensei Exhibition in Tokyo. The cutting-edge technology will take you to unprecedented conversation that will take place both online and onsite at the conference.
Wherever you are, you can join us. All you need is your computer (or tablet or mobile phone) and an Internet connection.
Join us
When
Saturday, August 26, 2017, from 10:00AM – 12:00 (Japan)
(Friday, August 25, 2017, from 20:00-22:00 (Chicago)
Where
This is an online event.
Program
・Introduction
・Story telling by Masato Tahara
・Story telling by Jon Bergmann
・Instruction for Hybrid World Cafe
・Two rounds of World Cafe Conversation
・Harvest and Closing
反転ワールドカフェ「反転授業はどのような教育の未来を切り開くのか?」
教育の未来を考えるリアルとオンラインを結んだワールドカフェ
インターネット元年といわれた1995年から22年が経ち、世界は大きく変化してきました。
世界中がネットワークで繋がったことで、遠く離れた地域が、相互に強く関連しあうようになり、地球全体が、あたかも1つの生命体のようになりつつあります。インターネット上に知識が蓄積され、誰もが無料で様々な知識にアクセスできるようになってきました。人工知能の開発も進み、今後は、様々な分野で導入されることでしょう。
このような社会の大きな変化に直面し、教育も大きな変革の時期を迎えています。
これまでの成功マニュアルを子どもたちに伝えても、それらは、子どもたちの助けになるとは限らない状況の中、新しい教育が求められているのです。
反転授業は、未来の教育を担う手法の一つとして期待されています。
反転授業によって、どのような教育の未来が切り開かれるのか、ワールドカフェと呼ばれる対話手法を用いて、ともに探究していきます。
リアルとオンラインとを結ぶワールドカフェの進め方
ワールドカフェは、4-5名のグループに分かれて行う対話をメンバーを交代しながら数ラウンド行うものです。今回は、2名がインスピレーショントークを行った後、東京会場とオンラインとで、それぞれグループに分かれて、2ラウンドの対話を行います。
使用言語は英語と日本語です。会場には通訳がつきます。オンラインの対話には、世界中の教育関係者が参加する予定です。英語で対話するグループと、日本語で対話するグループに分かれ、どちらかを希望して参加することができます。
インスピレーショントークを行うのは、次の2人です。
ジョナサン・バーグマン(オンラインで参加)
FLGI(Flipped Learning Global Initiative)代表。反転授業ムーブメントを牽引するリーダーの1人。24年間、シカゴの中学、高校で化学を教えた経験を持ち、その実践の中から反転授業が生まれた。著書『反転授業』は10カ国語に翻訳される。現在は、世界中を飛び回り、各国の政府や学校、企業、NPOなどと連携して反転授業の普及に尽力している。
田原真人(東京会場で参加)
「反転授業の研究」代表。FLGI Ambassador。IAF Japan(国際ファシリテーターズ協会 日本支部)理事。2013年から物理の反転授業に取り組むと同時に、実践者のためのオンラインコミュニティの運営を始める。9月に『Zoomオンライン革命』を出版予定。
お申し込み
日時 2017年8月26日 AM10:00-12:00
場所 会場参加 武蔵野大学有明キャンパス 未来の先生展2017会場
オンライン参加 Web会議室 Zoom
(ビデオ通話の準備が必要となります。スマホやタブレットからでも参加可能)
オンライン参加の申し込みはこちら(無料)
「未来の先生展」へ出展します
「反転授業の研究」の田原です。
2017年8月26日、27日に東京の武蔵野大学有明キャンパスで「未来の先生展」というイベントが行われます。
未来の先生展は、これまでジャンルごとに分かれていた様々な教育の取り組みに横串を通して共創を起こしていこうというチャレンジで、1万人の参加を目指して取り組んでいます。
未来の先生展については、こちらをご覧下さい。
1万人の参加者を結びつけて共創を起こしていくことは、簡単なことではありませんが、もし、そのようなムーブメントを起こすことができれば、本当に教育が大きく変わる可能性があります。
それを起こすためには、二日間のイベントだけでは無理で、二日間のイベントをキックオフにして、その後も繋がり続けてコミュニケーションをとり合い、関係性を育んでいく必要があります。
そのためには、リアルのコミュニケーションだけでなく、オンラインとリアルとを行き来しながら、ドラマを展開していくことが必要になってくると思います。
現在、オンラインコミュニケーションを利用した共創の可能性に気づいている人は、まだまだ少ないです。
私たち「反転授業の研究」が取り組んできたことが、まさに役立つときが来たと感じています。
「未来の先生展」では、UMUというプラットフォームを使い、参加者全員がオンラインで繋がります。
各ワークショップの様子は録画され、動画はプラットフォームで共有されます。
多くのワークショップをZoomで繋ぎ、外部から参加可能にします。
私たちの活躍の場は、イベント当日だけでなく、イベント後のオンラインコミュニティ構築においてもたくさんあります。UMUでの繋がりを生かして、様々なオンラインワークショップを企画していく計画があります。
実際のところ、「反転授業の研究」が、どのように関わり、何を創造できるのかによって、イベントの意味と価値が大きく変わってくるのではないかと考えています。
教育を変えたいと思って、「反転授業の研究」に集って下さっているみなさん、今回のイベントは、大きなチャンスです。
・イベントに東京会場で参加する
・イベントにオンラインで参加する
・イベント後、オンラインでの活動に参加する
という3つの参加が可能であり、どれもが、とても重要な意味を持ちます。
オンラインとリアルとで縦横無尽に繋がり合い、違いから学び合いながら、未来を共に創っていきましょう。
そのために、まずは、8月28日、29日に力を結集していきましょう。
このイベントには、公教育だけでなく、オルタナティブ教育をはじめとした様々なジャンルの教育関係者が集まり、25トラックのワークショップが実施されます。
「反転授業の研究」も、そのうちの1つのトラックを担当します。
出展するワークショップは、以下の8つです。
反転授業ワールドカフェ(8/26 10:00-12:00)
反転授業の生みの親であるジョナサン・バーグマン氏をゲストに迎え、Zoomで世界と繋ぎ、グローバル・ハイブリッド・ワールドカフェを実施します。バーグマン氏と田原がインスピレーショントークを行い、その後、会場とオンラインでそれぞれグループ対話を3ラウンド行います。通訳がつきます。
白板ソフトでワクワク体験 in 未来の先生展(8/26 12:30-14:00)
坂本保代さんによる白板ソフトの体験会です。反転授業に欠かせない動画作りのツールとして、動きのある教材作成ツールとして、大きな可能性を持つ白板ソフトを体験して下さい。
何で通じないの、私の日本語(8/26 14:20-15:50)
日本語教師グループによる「やさしい日本語」のワークショップです。日本語ネイティブとして無意識に使用している日本語を、日本語を外国語として学んでいる人に通じるように使うにはどうしたらよいのか、日本語学習者と一緒に考えます。
世界のみんなと日本語で話そう(8/26 16:20-17:50)
世界中に住んでいる日本語話者(日本語学習者、日本にルーツを持つ人、海外在住日本人など)をオンラインで繋ぎ、多様な視点を持ち寄った対話を行います。
教師のためのワールドカフェ(8/27 10:00-11:30)
教育のパラダイムシフトをテーマにハイブリッド・ワールドカフェを行います。「反転授業の研究」代表の田原真人がインスピレーショントークを行います。
中高の英語を変えるRadical Approach(8/27 12:30-14:00)
「黒板とチョークをぶっ壊せ!」と言う西山哲朗さんによる英語教育ワークショップです。
未来の学び夢マラソン(8/27 14:20-15:50)
過去のSF物語が数十年後には現実になっている現在を見ると、理想を、未来をありありと描くことがゴール近く最短の道ではないでしょうか?発表者が次々に登壇して夢を提示します。
質問作りで未来の学びを(8/27 16:20-17:50)
『たった一つを変えるだけ:教師も生徒も自立する質問作り』で有名な質問作りワークショップを、平野貴美枝さんが行います。
寄付のお願い
今回のイベント実施にあたり、寄付を募らせて下さい。
目標金額 19万円
必要な経費
・バーグマン氏の出演料の50%(50,000円)
・出展者の交通費と宿泊費の補助(約160,000円)
(内訳)
関西ー東京の往復交通費 3名 9万円
その他交通費 約4万円
宿泊費 3名 3万円
現在、「反転授業の研究」のオンライン講座やオンラインイベントからストックしてあるお金が28200円ありますので、残りの19万円ほどを寄付で集められたらと思っています。
3000円以上を寄付して下さった方へは、「未来の先生展」の反転授業の研究トラックの録画動画(8本)を差上げます。
新旧パラダイムに橋を架けるオンラインワールドカフェ
反転授業の研究の田原真人です。
私たちは、200年以上前から続く機械論的パラダイムの終焉期に生きています。
機械論的パラダイムに基づいた社会システムは老朽化し、システム自体が問題を作りだしています。国境を越えて相互依存度が高まっている時代には、長期的な行動計画は、役に立たない物を作り出しています。前提条件の変化により、過去の成功事例は役立たなくなり、「お手本」に従って行動できるように設計された教育システムは、変革を迫られています。
教育、行政、企業など、それぞれの分野で、変化をもたらそうとしている方がいますが、旧来のやり方を大きく変容させていくことは、簡単なことではなく、新旧パラダイムの間の分断が生まれることもあります。
しかし、考え方の違いによって分断を起こすのではなく、違いを学び合いのエネルギーに変えることができれば、新旧パラダイムの両側から協力して橋を架けていくこともできるはずです。
様々な知見を持ち寄り、新旧パラダイムに橋を架け、パラダイムシフトへの道筋を探っていくオンラインワールドカフェを開催します。
みなさんの参加をお待ちしています。
参加方法
次の3つの方法を組み合わせ、効率的に集合知を得ることに挑戦します。
・ウェビナーを利用した一方向的な視聴
・FBグループでのテキストベースの対話
・Zoomを使ったWeb会議室でのグループセッション
進め方
(1)ワールドカフェ参加者のFBグループに参加
・自己紹介
(2)2/27 のウェビナーを視聴(録画視聴も可)
・下町壽男さん
・江藤由布さん
・森田明彦さん
・筒井洋一さん
・杉森公一さん
・田原真人
★ラウンド1
FBグループで行っています。
問い
・インスピレーショントークを聞いてどんなことを感じましたか?
・新旧パラダイムの狭間であなたは、どんなことを感じていますか?
(3)2/27-3/4 ワールドカフェ参加者のFBグループ
・ラウンド1のグループ対話(テキストベース)
(4)3/5 のZoomセッションに参加
・ラウンド2
・ラウンド3
(5)ワールドカフェ参加者のFBグループで振り返り
・ハーベスト
日時
3月5日 20:00-22:00 Zoom対話
場所 オンライン
主催者 反転授業の研究プロジェクトチーム
参加費 投げ銭(0円~)
途中からでも参加できます。(ウェビナー動画を視聴して、対話に追いついて下さい)
申し込みはこちら
「世界と繋がりながら語り合うハイブリッド・ワークショップ」を終えて
「反転授業の研究」の田原真人です。
11月22日に、花巻北高校と世界をZoomで結ぶハイブリッド・ワークショップを行いました。
ハイブリッド・ワークショップというのは、リアルでグループ対話とオンラインのグループ対話を同時に行うものです。
参考記事:Zoomを使ったハイブリッドファシリテーションの可能性
3人の方のインスピレーショントークを聴き、リアル会場とオンライン会場とで同時に3ラウンドのワールドカフェを行いました。
このようなハイブリッドワークショップは、世界でも、まだ事例の少ない最新の取り組みです。その効果を記すことで、後に続く取り組みが出てくることを期待します。
ハイブリッド・ワークショップは3人のファシリテーターの連携が大切
ハイブリッド・ワークショップでは、リアル側のファシリテータ-と、Zoom側のファシリテーター、そして、リアルとオンラインとを繋ぐコネクターの3つの役割が必要となります。
今回は、
リアル側のファシリテーター : 筒井洋一さん
Zoom側のファシリテーター : 田原真人
コネクター : 松嶋渉さん
という役割分担で行いました。
リアル側のファシリテーターの筒井さんが、会場にたいへん和やかな雰囲気を作って下さり、対話が活発に起こっていました。
田原は、Zoom側のファシリテーターとして、音声のミュート管理や、グループワークの設定などを行いました。
3つの役割の中で最も難しい役割がコネクターです。リアルで起こっていることに気を配りながら、オンライン側で起こっていることをイメージし、音声の調整や、ビューの切り替えなどをやっていかなくてはならないため、リアルとオンラインの場創りの豊富な経験が必要となるからです。松嶋さんは、今回のワークショップに備えて、リモートワークジャーニー@萩でハイブリッド・ワークショップを開催し、そこで、リアル側のファシリテーター兼コネクターを体験した上で、万全の準備で今回のワークショップへ臨みました。
参考記事:リモートワークジャーニー@萩でハイブリッド・ワールドカフェ
花巻北高校の会場には60名、オンライン会場には25名が集まり、ハイブリッド・ワークショップとしては大規模なものになりましたが、非常にスムーズに運営することができました。
インスピレーショントークがスタート
主催者の下町壽男さん(花巻北高校校長)が挨拶を行い
このワークショップの軸は、「未来を切り開く子どもたちを創るために、我々は何ができるか」です。
今までは、社会のために、世界のために、子どもがあると考えられてきましたが、それを反転させて、子どものために、社会や世界はどうあるべきかという議論ができれば良いと思います。
と述べ、ワークショップがスタートしました。
その後、リアル側のファシリテーターの筒井洋一さんが自己紹介を行い、
今日の隠れたテーマは、「●●を越えるということを一緒に体験する」ということです。
1つめは、年代や経験を越えるということ。
2つめは、組織や日頃の常識を越えるということ。
と述べました。
最後に、Zoom側のファシリテーターの田原真人が自己紹介を行いました。
動画コンテンツが無料で見られる時代における教師の価値は何だろうか?
生徒が、お互いが異なる視点を持つことに気づき、それを共有することで理解の幅を広げていくことができることに気づけば、場に対する価値を感じることができます。
今日は、日本国内、国外からの多様な視点を共有し、学び会う場を共に体験していきましょう。
その後、Zoomで参加されている方を会場に紹介しました。
ニューヨーク、ニュージーランド、シンガポール、韓国、福岡、長崎、島根、広島、大阪、兵庫、奈良、三重、東京、宮城・・・など、国内、国外から20名の方が参加して下さいました。
最初のインスピレーショントークは、サマンサさん。
10年間、子どもを強烈にコントロールする毒親だったと言うサマンサさんが、「ありのままを完璧と受け入れる=あり完」へとマインドシフトした結果、子どもがアクティブマインドへ急激に変化していったという体験に、リアル会場もオンライン会場も引き込まれました。
続いて、花巻北高校2年生のプレゼンが始まりました。遠野から花巻北高校まで1時間半かけて通っているという彼は、「魅力ある遠野の教育へ」というタイトルでお話をしてくれました。
彼は、地域の魅力や課題を発見するためには自ら体験して学ぶことが重要だが、教師が地域の体験が少ないために十分な総合学習を行うことができないのではないかと述べました。そして考え出した解決策は、次のようなものでした。
このアイディアについて遠野高校の中学校3校の教員に対してアンケートをとったところ、「斬新なアイディアである」という声が多かった一方で、「プログラムの内容が分からず回答できない」と、先行きの不透明さを指摘する声も多く聞こえたとのことでした。これを受けて、Zoom側のチャットボックスには、次のような意見が飛び交いました。
大人が今どのようなことを学んでいると言えるのでしょうか?そして、それが子供の教育とどう違うのでしょうか?
不透明だからおもしろいのに
先生が言いそうなことだわ
答えの有無もあるのかなぁ
不透明だからこそやろう!って先生を説き伏せて欲しい。
先生というのは、予定調和がすきなので
そうですよねー 不透明ほど尊いものないのに
失敗を恐れていますよね。それが教員のマインドセットであり、メンタルブロックになっているのかも。
ほんとうです。
岩手は県内でも広いから、中学高校だとその地域知らない、って新任の先生多いでしょうね~。
失敗させない 正解主義は 結構 日本で支配的なのです
先生が失敗を恐れてたら、子どもにもそれが感染します
どんな結果になっても、これが実現するだけですごいことなのに。。
まったく同感です。
考えさせられるプレゼンだなー

予定では、この後、松嶋渉さんのインスピレーショントークの予定でしたが、松嶋さんの直感により、流れを切りたくないということで、ワールドカフェのラウンド1を先にやることになりました。
ハイブリッド・ワールドカフェ
リアル会場では4人組、オンライン会場では3-4人組に分かれ、ワールドカフェが始まりました。
リアル会場では、「えんたくん」という円形の段ボールに紙を貼ったものが用意され、4人の膝の上に載せてテーブル代わりに使いながらグループ対話を行いました。
オンライン会場では、Zoomのブレークアウトセッション機能を用いて行いました。
ラウンド1の問いは、次のようなものでした。
問1)子どものアクティブさを引き出すために、あなたはどのような関わり方をしたいですか?
15分の対話の後、リアル会場から2名、オンライン会場から2名が感想を共有しました。
仙台の名越さん:「子どもたちのタイプを理解してから、コミュニケーションで後押しをするという意見と、そもそも何をやりたいかが分からないような子をアクティブにするにはどうしたらよいかという意見とが出て、話が噛み合いませんでした(笑)。そういう子たちと共に歩む方法を考えるためにはどうするかということで話がまとまりかけたところで終わりました。」
2番目のグループ:「びびっときたという体験をどのようにさせるのか。そのために必要なのは「あり完」。体験させたことが花を開かせるのを待つことが大人には大切。だから、教師は、「びびっとくる」素材を提供することが大事だと思います。」
ニューヨークの森田さん:「合気道や瞑想をやっている人から「あり完」になるためには、自分の感情をありのままに感じられるようになる必要があり、リラックスしていなければならないという話が出ました。子どもがロールモデルに出会う事も大事ですが、大人が自分自身と向き合って、自分自身を受け入れられるようになることが大事だという話でした。」
ニュージーランドの荻野さん:「ニュージーランドの親は、デフォルトが「あり完」なので、教員がそれをコントロールしようとすると大変です。コントロールするのではなく、それぞれを伸ばしていくのが教員の役割になります。日本の教育の在り方、社会の在り方の枠が、大きな問題になるのかなと思います。どこにボーダーがあるのか、壁があるのかというのが、日本には分かりにくくて、その壁に穴を開けることが難しいことだと感じました。
松嶋さんのインスピレーショントーク
その後、リアル会場とオンライン会場の両方とも、グループメンバーのシャッフルを行い、3人目のスピーカーである松嶋さんのトーク「地域×学校×ICT」が始まりました。
情報の授業を、ICTを活用して地域と結びつけていく松嶋さんの授業は、様々なところで注目されています。その一方で、「それは、松嶋先生だからできる授業ですね。」「その授業は、趣味ではないか」と言われているのだそうです。それに対して、「生徒のために・・」というのは、もしかしたら生徒依存であり、「趣味です」と言ってしまって良いのではないかと思っているとおっしゃっていました。
ワールドカフェ第2、第3ラウンド
ワールドカフェの第2ラウンドの問いは、次のようなものでした。
問2)組織を超える学びをどのように可能にしていきますか?そこにオンラインはどのような役割を果たしますか?
15分程度のグループ対話を行い、次のような声が出てきました。
1グループ目:「子どもたちを見ているということが大事なのではないか。主役が子どもたちであるということを忘れずにいれば、私たち大人、組織がみんなで協力できるのではないか。学校だと、「子どもたち」というように複数になり、1人のときと見る目が変わるが、主役を忘れずにいれば、連携がうまくいくのではないかという話になりました。」
福岡の和田さん:「学校の先生って保守的で、組織を越えて繋がることに対して、最初はとても怖がっていると思います。でも、花巻北に集まっている先生方が、Zoomで簡単に繋がれるんだという体験をまずはやってみるということが大事なんじゃないか。オンラインに来てねというよりは、こうやって押しかける。あちこちにこうやって押しかけていけば、体験してくれた人たちの間にどんどん広がっていくのではないかな。そういう「オンライン黒船襲撃」というのを考えました。」
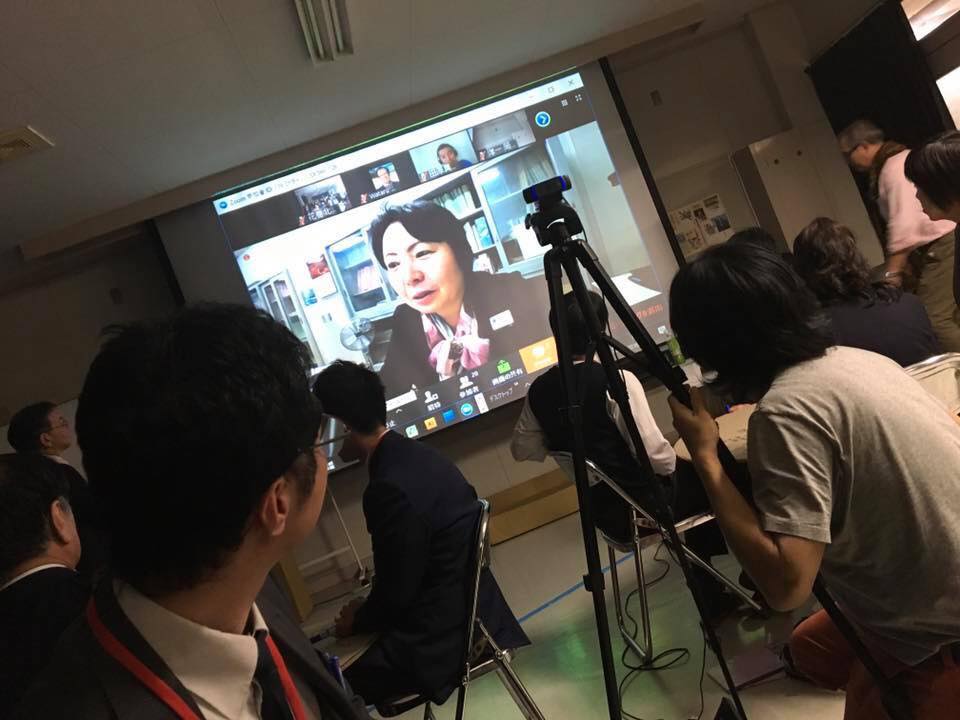
再び、グループメンバーを交代し、最後の問いについて考えました。最後の問いは次の通りです。
問3)未来からの使者である生徒の将来をどのように創っていきますか?
13分間のグループ対話の後、リアルとオンラインからの声を共有しました。
1番目のグループ:「渦は自分たちで創っていくものであり、私たちは生き様を見せていけば良いのだ。」
ロナさん(高2):「私は、担任の先生が大嫌いです。その理由は、「仕事は思い通りにならない。仕事は楽しくないよ。楽しくないのが仕事なんだからしょうがない。」といつも言っているからです。私の周りには、その影響を受けている生徒もいます。そういう大人からガードしてくれる大人のサポートが子どもの未来に繋がっていくのかなと思っています。」
島根から八坂さん:「私が子どもだった頃は、突出して何かができているけど、ダメダメなところもあるという大人がたくさんいたんですが、今は、すべてができなくてはいけないという育て方になっている気がしています。1つでも得意なことがあれば見えてくるものがあると思うので、バランスの取れた大人に育てようとしなくても良いのではないかと思います。」
シンガポールから若林さん:「昔だったら誰もが分かるようなはっきりしたレールが敷かれていて、誰もが同じ方向に進んでいけば良い将来があったが、今はそんな時代ではない。私たちのグループでは、いろんな選択肢があって、しつけをしたり、背中を見せてガイドするのが大人の役割になるのではないか。全くの放任だとうまくいかないかもしれない。例えば、甘いものを食べすぎてはいけないというしつけがあって、食べたらどうなるという問いかけをして選択肢を示してガイドするというのが大人の役割になるのではないかという意見が出ていました。」
ハイブリッド・ワークショップを終えて
今回のような、多様な視点から、お互いに学び合っていくような場を約80名のみなさんが体験したということに大きな価値があると思いました。
このワークショップが実現できた背景には、ICT技術の進歩と同時に、この3年間でお互いに育んできた信頼関係のネットワークがあります。
ワークショップが終わってから、多くの縁のありがたさをしみじみと感じました。
同時に、今回のワークショップでの出会いから多くの創造のサイクルが回っていくはずだという確信を持ちました。
「オンライン黒船襲撃」を、今後もあちこちで展開し、組織を越えた繋がりによって、お互いのメンタルモデルに変容を起こしながら未来を創り出していければと思っています。
みなさん、楽しみながら、共にやっていきましょう!
「教えない授業」が目指すものとは何か?
反転授業の研究代表の田原真人です。
今日は、『なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか』を読んで感じたことを書いてみたいと思います。
私が東京都立両国高校を訪問し、著者の山本崇雄さんの英語の授業を見学したのは2014年の12月のことです。
新聞で両国高校の取り組みが紹介され関心を持ち、一度、見学させていただこうと思ったのです。
見学したいと思った理由は、もう一つありました。両国高校は私の母校であり、その母校が新しい学びのスタイルを取り入れているということで、ぜひともこの目で見て見たかったのです。
実際に授業を見学し、両国高校の先生方とお話しする中で、根底にある想いの部分で共振、共鳴してしまい、次のブログ記事を一気に書き上げました。
都立両国高校を見学して(上)― フォークダンスのように生徒が動く英語の授業
都立両国高校を見学して(下)― 教師の主体的な学びが生徒の主体的な学びを促す
山本さんから、「短い滞在期間で、こんなに理解してもらえるとは・・」というありがたいコメントをいただいたのですが、その理由は、私自身が考えていることや、取り組んでいることと、根底にある想いが共通していたので、そこで起こっている氷山の一角から、水面下の部分を想像できてしまったのです。
山本さんの新著、『なぜ「教えない授業」が学力の伸ばすのか』は、山本さんの授業に対する考えをまとめたものです。いわば「教えない授業」の舞台裏を明かしている本です。
授業見学の後、私自身も「教えない授業」に本格的に取り組むようになったこともあり、今回、本を読みながら、山本さんの言葉の一つ一つによって、この数年間で自分が取り組んできた様々なことが想起され、新たな気づきとともにそれらが言語化されていくという体験をしました。
この記事では、客観的に山本さんの本を紹介するというよりも、山本さんの本を読んだことで私の中に起こった化学反応について書きたいと思います。それによって、「教えない授業」の背後にある考えが、より多くの方に伝われば幸いです。
それは、震災からはじまった
山本さんの「教えない授業」と、私の「反転授業の研究」の活動の共通点はたくさんありますが、出発点になるのは、どちらも東日本大震災がきっかけとなって始まったものだということです。
私自身の場合は、震災そのものも私の人生に大きな変化を与えましたが、それにも増して、「直ちに影響はありません」「福島は完全にコントロールできている」に代表される欺瞞的な言葉の数々がまかり通っていくことに大きなショックを受けたのです。
どのようにして、このような社会ができてきたのかという問いに導かれて考えていくうちに、日本は「立場主義」の社会であり、大人になっていく過程で、自分らしく生きることを手放し、立場に応じて適切な行動をする社会適応インターフェースを身につけていくように外から条件付けられているのではないかと考えるようになりました。
未来学者のアルビン・トフラーは、『第3の波』の中で、大衆教育は、時間厳守、服従、反復作業の3つを叩き込むものだと看破しています。自然と共に生きていた農民を工場労働者として育成するために、学力テストによる序列化と、レールから外れると生きていけないという恐れをアメとムチとして使い、外発的動機付けによって子どもたちを規格化してきたのです。それは、日本においては、その方法が戦前の国民教育に応用されました。戦後も、形を変えて、子どもたちを規格化していく教育システムは作動し続け、その結果として、自分とは切り離され、立場に従って行動する震災後の状況が生まれているのだと思いました。
このような考えは、予備校講師として、まさにその教育システムを支えるべく働いてきた自分自身の存在を脅かすものでした。今まで使っていた叱咤激励の言葉を使うことができなくなってしまいました。発信力が落ちたことで、経営しているネット予備校の収益も落ち込んでいきました。今までと異なるパラダイムへとシフトするためには、ぐーっと暗闇の中に潜っていく必要があると感じました。
その結果、たどり着いたのが、「反転授業」であり、「教えない授業」だったのです。
私にとっての「教えない授業」の役割は、安冨歩さんの『生きるための論語』に出てくる<学習>という言葉を使うとうまく説明できます。安冨さんは、学習を次のように説明します。
「学」という段階では、受け取ったものが何なのか、学ぶ者にはまだ意識化されていない。より正確に言えば、細部に意識が集中してしまうことによって、全体が無意識化されてしまっている。ここには余計なものが染みこんでおり、この行為によって魂は多かれ少なかれ、呪縛されている。
それがある時、「習」によって完全に身体化される。すなわち、細部が身体化され、無意識化されることによって、逆に全体が意識化され、「ああこれか」と分かるのである。そうなることによって、不必要なもの、余計なものは排除される。こうして呪縛から抜け出したときに、人は学んだことを自由に駆使できるようになり、喜びを感じる。
「学」のプロセスに偏った教育をしていくと、子どもの魂は呪縛されていきます。その結果、魂の上に蓋がされ、社会適応のためのインターフェースが構築されていくのだと思います。
私の「教えない授業」では、「学」は動画で各自が学べるようにし、集まって学ぶときには「習」のプロセスを中心に行います。
つまり、「魂の脱植民地化」を促していくのが、私の「教えない授業」です。
震災後、あれ程のことがあったのにもかかわらず、何事もなかったのかのように日常が進んでいくことに、なんとも言えない孤独を感じました。しかし、5年が経ち、震災を受け止めて変化を起こしている人たちが確実に存在していることに大きな勇気をもらっています。
山本さんは、次のような言葉を書いています。
「人間には、ゼロからスタートしなければならないときが来る。教師がいなくても学び続ける子どもたちを育てなければならない。」
震災を通して私が感じたことと、山本さんが感じたことは、もちろん異なるはずです。
でも、山本さんが、震災を受け止めて、行動を始めた数少ない人の1人であるということに、感謝のような気持ちを感じています。
学びのフラクタル構造
教えるのを止めてから、私の存在価値は何なのだろうかということを考えるようになりました。
予備校講師時代には、間違いなく「田原の物理講義」という商品を提供していたのです。
知的好奇心をくすぐり、分かりやすく、成績も上がる・・・という講義こそが、私が提供しているものでした。
講師と生徒との間には舞台の上と下という区切りがあり、舞台の上で演じる役者と、それを見て楽しむ観客という役割分担がありました。
しかし、舞台から同じ場に下りていったとき、そこに役割を隔てるものは無くなったように感じました。
1人の人間として、正直に向き合い、共に学んでいきながら場を創っていくのだということが、舞台を下りて、しばらくしてから腹落ちしました。
私自身も未来がどうなるかが見えているわけではないということを正直に語り、その中で試行錯誤しながら生きていく姿をさらけ出すしかないのだと思いました。結局は、それこそが、私自身が、その場にいる存在価値なのだと思いました。
山本さんの「教えない授業」でも、同じことなのではないかと思います。
山本さんは、確かに教えませんが、生徒を信頼し、成長を願い、見守るという生き様が、生徒に伝わっているのだと思います。
そのことが、とてもよく現れているのが、巻末の付記の佐澤真比呂さんの感想です。
彼女は英語劇の部長として、部員に対してリーダーシップを発揮する立場にありました。
部員が思うように動いてくれない状況の中で、佐澤さんは、次のような気づきを得ました。
愕然としました。それと同時に、もしかして、と思ったのです。以前の先生の役割が、私に変わっただけなのではないか、と。その役割を担う人が変わっただけで、実際は何も変わっていないのではないか、と。これは、恐ろしい仮説です。しかし、そう考えると様々なことに納得がいきました。今やる気がある人は、自立して歩き始めることができている人なのでしょう。だとすれば、やるべきことは一つしかありません。
その気づきから、佐澤さんは、徐々に「教えない部長」になっていくのです。
そして、その体験を通して、山本さんの姿勢を深く理解できるようになっていきます。彼女は、最後に次のように述べます。
この1年間を振り返ると、先生は私たちに対して直接的に何かを「教えて」下さることはほとんどなかったけれど、その姿勢から教えて下さったことならたくさんあります。その最たるものは、やはり「自立して歩いて行く力」でしょう。先生にも口出ししたかったことは山ほどあったはずです。しかし先生は何もおっしゃいませんでした。私たちが学習する機会を奪わないために、です。
愛情をかけられた子どもは、そこから学び、同じ方法で愛情をかけられるようになっていくのだと思います。それは、教師と生徒との間でも同じことだと思います。
教師と生徒の関係や、親子の関係から学んだことが、生徒同士のグループ内で再現され、体験を通して理解が深まっていくという学びの仕組みこそ、学校という場に集まって学ぶ本来的な価値なのではないでしょうか。
両国高校には、活発な教師の学び合いのコミュニティもあり、真摯に学んでいく教師の姿勢が、自然な形で生徒に伝わる仕組があります。
私が「反転授業の研究」で実現したいのは、学校内に学習コミュニティがなくても、オンラインで学び合うことで、お互いに励まし合って真摯に学んでいく姿勢を整えていく場を創ることです。
私たちは、今、教師の本来的な存在価値と向き合う場面に遭遇しているのだと思います。
山本さんの「教えない授業」は、これからの教師の存在価値を姿勢によって示しているものではないでしょうか。
対談:炭谷俊樹(ラーンネットグローバルスクール)×田原真人
探究学習を行っているラーンネットグローバルスクール代表の炭谷俊樹さんと対談させていただきました。
ラーンネットには、「先生」はおらず、代わりに「ナビゲーター」と呼ばれる人たちがいて、普通の教師とは違った役割、アプローチ、関係性で子どもに接しています。
ラーンネットで実施している「ナビゲーション講座」は、ナビゲーターの接し方、声かけの仕方を学ぶことができ、大変人気があります。
先月、この「ナビゲーション講座」を、はじめてZoomを使ってオンラインで行いました。
オンライン講座の企画と運営をお手伝いさせていただいたことをきかっけに、炭谷さんと繋がり、対談させていただくことになりました。
教育に対する想いに、多くの共通点がありました。
対談:江藤由布×田原真人
江藤由布さん(近大附属高校英語科教諭・一般社団法人オーガニックラーニング共同代表)と「反転授業の研究」代表の田原真人がZoomで対談しました。
『生きるための論語』からAL型授業の本質を学ぶ
反転授業の研究の田原真人です。
私たちは、なぜ、アクティブラーニング型授業や反転授業を行うのでしょうか?
「知識基盤型社会に必要な21世紀スキルを身につけるため」という説明がされることもありますが、私は、この説明に違和感を感じます。
私が、問い直したいのは、学力テストによる序列化、社会的地位による序列化を外発的動機付けに使われることで学習回路が阻害されてしまうという仕組みです。
そのように条件つけられた環境の下では、生徒は、疑問を感じたり、深く考えることを止め、丸暗記したり、反復練習したりする方が、短期間で高得点を取れるということを学んでいくのです。
この学習回路が阻害される仕組みを維持したまま、「21世紀スキル」を移植しても、それが、新たな序列化の要素になるだけです。
どのようにすれば、生徒が自分で考え、主体的に学ぶような環境を作ることができるのか?
そのような環境において、教師の果たす役割は何か?
自分で考え、主体的に学ぶ生徒たちが増えたとき、組織や社会はどうなっていくのか?
そんな問いを心に抱いて、活動をしてきましたが、この問いに対して、大きなヒントになる書籍と出会いました。
それが、安冨渉著 『生きるための論語』です。
君子は周辺の小人を感化して学習回路を開く
私自身には、論語を読み解ける素養がないので、以下のことは、安冨さんの論語解釈を読んで、そこから感じたことであることを、最初にお断りしておきます。
安冨さんは、論語における「学習」を、次のように解読します。
「学」という段階では、受け取ったものが何なのか、学ぶ者にはまだ意識化されていない。より正確に言えば、細部に意識が集中してしまうことによって、全体が無意識化されてしまっている。ここには余計なものが染みこんでおり、この行為によって魂は多かれ少なかれ、呪縛されている。
それがある時、「習」によって完全に身体化される。すなわち、細部が身体化され、無意識化されることによって、逆に全体が意識化され、「ああこれか」と分かるのである。そうなることによって、不必要なもの、余計なものは排除される。こうして呪縛から抜け出したときに、人は学んだことを自由に駆使できるようになり、喜びを感じる。
私が、今の教育システムに対して感じている違和感は、安冨さんの言葉を借りると、「学」により魂が呪縛された状態を生み出すことに重点が置かれ、「習」により呪縛から抜け出して、無駄なものを自ら選んで捨てることで主体性を確立することがおろそかになっているのではないかということになります。
では、「学」と「習」とが十分に作動するためには、どのような構えであれば良いのでしょうか?
安冨さんは、それを、君子と小人の対比によって説明します。
君子:学習回路が開いている人。自分を常にモニタリングして、人の言うことに耳を傾け、自分の間違いに気づいたら、直ちに受け入れ、更に自分の行動を改める。
小人:学習回路が閉じている人。自分の過失を認めてしまうと、全人格を否定されたように感じるため、言い訳をし、行動を修正できない。
君子の在り方は、経験学習サイクルを回すことが身についている人の在り方に似ていると感じました。
自分の行動を真摯に振り返り、間違いに気づいたら直ちに修正していくという在り方が君子なら、学習者が経験学習サイクルを回せるように支援していくアクティブラーニングは、いわば、「君子を育てる教育」なのではないでしょうか。
しかし、人間は、周りの影響で君子にも小人にもなり得る存在だと思います。小人の在り方をしている人は、どのようにして君子へと変わっていくのでしょうか?
それに対して、安冨さんは、次のように述べます。
君子がいれば、周辺の小人は感化されて学習回路を開く。
この言葉は、私たちが対話を重ねる中で出会った「LearningがLearningを促す」「学び続ける教師が、生徒の主体的な学びを促す」という言葉と重なるものだと思います。
教師が君子として振る舞い、教室の生徒たちの学習回路を開き、生徒たちを君子へと導いていくというのが、私たちの目指すアクティブラーニングや反転授業だと考えると、すっと腹落ちする感覚がありました。
実際、反転授業の研究の活動を通して出会った、小林昭文さん、下町壽男さん、和田美千代さん、江藤由布さんなどアクティブラーニングのトップランナーたちは、常に学び続けながら、自分の心と繋がった率直な言葉を発信しています。そして、その在り方に周りが感化されて、学習回路が回り、変容の連鎖が起こっています。
君子による呪縛なき秩序形成
安冨さんによると、孔子は、君子による学習に基づいた社会秩序を考えていたのだそうです。
それが、どのようなものなのか、コミュニケーションと学習の関係から考えていきます。
まずは、小人が集まった社会に生まれる秩序について考えてみましょう。
小人は、学習回路が閉じていて、自分の行動を修正しないので、相手との違いを無視し、同じものを共有しているという思い込みを形成します。これを、「同」と呼ぶのだそうです。
この延長線上に生まれるのが、共同体への帰属意識の形成により、お互いに呪縛し合う秩序です。
学習回路が閉じている小人は、学んだことによって魂が呪縛されている状態から、「習」によって抜け出すことができずに、他人の地平で生きる「魂が植民地化された状態」になっていきます。
言い方を変えれば、小人であふれている社会は、少数の権力者に支配されやすい状況だということになります。
一方、君子は、学習回路が開いているので、コミュニケーションを通して発生する相互の違いを学び合いのエネルギーに変えて学習回路を回していきます。お互いが自分の心に忠実に従って言葉を交わすことで、一時的に紛糾する状態である「乱」になりますが、それを途中経過として、尊重のある動的な調和状態である「和」に達します。
君子は、学習回路の正常な作動を守り抜き、自分の地平で生きるので、他人からの支配を受けにくく、自分たちの活動によって調和を生み出そうとします。
私たちは、オンライン講座を運営するときに、安心安全の場を創り、心を開いて対話していくと、しばしばカオスに陥り、その先に一体感のあるチームが生まれるというプロセスを何度も体験しました。それぞれが、お互いを尊重し合いながら、自由にコミットメントしていくと、場にエネルギーが流れ、個の能力の足し合わせ以上の成果をチームで達成することができました。それが、「和」の状態なのだと考えると納得がいきます。
「和」が達成されると、安心感と幸福感を感じられるようになり、よりいっそう、場に対して自分を投げ出していくことができるようになります。
私は、アクティブラーニングや反転授業で目指すものは、学習者に、この「和」を体験させることなのではないかと思います。
学んだことを、自分の中で消化して、余計なものを捨て去って身体知として身につけることで個性が磨かれていき、自分自身と繋がりながらコミュニケーションを取ることで「乱」を超えて「和」へ至るという体験こそが、未来を創る能力を育成すると思うのです。
私たちが、2013年に反転授業の研究を始めたとき、私たち自身がグループワークや対話などの経験を十分に持っていないことを自覚し、オンラインでの学び合いを通して体現することを目指してきました。オンラインの学び合いによって教師が主体的に学ぶことではじめて、教室での生徒の主体的な学びを促すことができると考えたのです。
試行錯誤をしながら、学び合いのオンライン講座を続けていく中で、受講者だった和田美千代さんから、「この豊かな場は、まさにネット果樹園だ」という言葉をいただき、オンラインに「和」を体現することができたと感じました。
そのとき、「この体験を広めていけばいいのだ」という強い確信が生まれました。そして、実際に、体験を共有した人たちが、教室の実践に生かしてくれるようになってきました。
安冨さんの『生きていくための論語』を読み、私たちが進む方向が間違っていなかったのだと大変勇気づけられました。
アクティブラーニングという言葉が、現在、急速に広がり、アクティブラーニングという授業形式を取り入れようとしている教師も増えています。
しかし、重要なのは形式ではありません。
教師自体が学習回路を開き、常に周りのすべてから学んでいるときに、それに感化された生徒たちも学習回路を開き、教師の率直なフィードバックを頼りに学習回路を回し、グループ学習の中で「和」を体験するということが重要なのだと思います。
そのような体験をした生徒たちが、社会に出て、自分の心と言葉とを一致させ、「乱」の状態になることを恐れずに君子として行動していってくれるはずです。それが、調和のとれた社会秩序を形成することに繋がっていくことでしょう。
私たちの多くは、社会秩序というものは、法律や規範によって作られているものだという幻想の中で生きています。
小人は規範に従って「同」になりますが、君子は自らの心に従い、魂の作動を頼りに行動します。
生徒たちの魂の作動を押さえ込み、学力テストによる序列化によって適応行動へと誘導していく教育は、小人を生み出していく結果を生み出しているのではないでしょうか。
私たちを取り巻く社会秩序は、小人の在り方が広がっていることによって維持されているように思います。
より調和の取れた社会を作るために、教育の世界で私たちができることは、まず自分たちが君子の在り方を体現し、生徒を感化することによって、世の中に君子を増やしていくことなのではないかということを、安冨さんの本を読んで感じました。
対談:長谷川伸(関西大学)×田原真人(反転授業の研究)
反転授業の研究の田原真人です。
関西大学の長谷川伸さんと対談させていただきました。
学生が授業への参加度を高め、分かる喜びを感じることができるために、どのような工夫をしているのか。
長谷川さんが、強い関心を持って取り組んでいるゲシュタルト療法について。
感情の抑圧と魂の植民地化の関係。
そんな話をしているうちに、バラバラだった要素が繋がり、アハ体験が起こりました。
対談:筒井洋一×田原真人
反転授業の研究の田原真人です。
私たちのグループが運営するオンライン講座では、運営ボランティア制度を導入しています。
これは、京都精華大学で筒井洋一さんが行っていた授業に導入されていたCT(Creative Team)にヒントを得て、導入したものです。
本家本元の筒井さんは、現在、京都精華大学を退官され、大学を社会に開いていき、社会を大学に繋げていく新しいチャレンジを始めています。
前回行われたオンライン講座では、筒井さんが運営ボランティアとして加わってくださいました。
筒井さんが、今、チャレンジしていることや、オンライン講座に運営ボランティアとして参加して感じたことなどについて、対談しました。
一から多、そして、循環へ
反転授業の研究の田原です。
先日、オンライン講座「iPad/iPhoneでつくるカンタン動画作成」が終了しました。
運営チーム24名
受講者24名
という構成で、1ヶ月間にわたりオンラインで学びあいを続けてきました。
反転授業の研究のオンライン講座では、
自ら学ぶ楽しさを感じられるような場つくり、
自分ごととして関われるようにする仕組みづくり
ということをずっと考えてきています。
オンライン講座で、運営チームや、受講者として体験したことを、各自の現場での取り組みに生かしてもらいたいと思い、参加型の組織運営、主体的な学びにこだわってやってきました。
講座をスタートしたころから考えると、運営チームのチームビルディングも、オンライン講座での学びも、かなり深まってきたと感じています。
今回は、今までよりも、さらに一歩前に進んだような感覚がありました。
そのきっかけとなったのは、当初、運営ボランティアとして参加していた川上さん、跡部さん、松島さんが、自らの判断で受講者に回ったことでした。
講座が良いものになるために、それぞれがどうしたらよいのかを考えたときに、運営ボランティアよりも、受講者で参加したほうが全体としてプラスになると判断してくれたのだと感じました。
それを受けて、
・無料で参加する運営ボランティア
・37,800円を払って参加する受講者
という2つの選択肢の中間の選択をできればよいのではというアイディアが生まれました。
ここが、0か100かになっていることが、各自の判断によるスムーズな調整を妨げているような気がしたからです。
それで、運営ボランティアのみなさんには、
・自分の貢献の度合い、
・学びの度合い、
・オンライン講座への応援の気持ち
などを総合的に考えて、自分にとって、もっともしっくりくる金額を自分で決めて払ってもらうことにしました。
もちろん0円もありということで。
このように、信頼をベースに、調整を場にゆだねることで、学びと収益のバランスが、より調和の度合いの高いところに移動するように感じています。
今回、運営チームの中で、様々な役割が自然発生しました。
運営統括が指示を送るのではなく、
「こんな役割があったらいいんじゃないか?」
と考えた人が、勝手にその役割をやり始め、
そのことにみんなが感謝を示していく。
そうすると、チーム全体の思考力が利用できるようになり、
一人じゃ目が届かないところに目が行き届くようになり、
チーム全体で講座をサポートできるようになってきました。
機械論的に組織を組み立てるときは、
最初に役割を定め、
そこに人を当てはめていきます。
これは、多から一をつくる仕組みです。
しかし、生命論的な組織では、
まずはみんなで集まり、
それぞれが自分のやりたいことや、
自分がやれることを考えながら、
ぐちゃぐちゃと動いているうちに、
自然とうまく役割分担が生まれてきて、
いい感じでチームが流れていきます。
生き物は、受精卵から始まり、
細胞が分化してシステムを作り、
循環を生み出していきます。
一から多、そして、循環
というのが、生き物の仕組みだと思います。
生き物のような自己組織化が、
まさに運営チームや、講座全体に生まれていたように感じました。
自己組織化が起こると、
場からエネルギーがわきだし、
参加している人たちの活きも引き出され、
どんどん元気になっていきます。
それが、何とも言えずうれしいです。
講座が終わり、
オンライン講座の在り方も、
そろそろ次のステップに進むときが来たかもしれないと
感じています。
次のステップについて、
皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。
熊本×反転G vol.7 〜自主避難所の運営。震災からこれまで、そしてこれから 〜 6/26
6月26日(日)のお話会でゲストになってくださった野村順子さんの録画を公開いたします。
・なぜ野村さんが震災直後から状況を判断しながら自ら避難所を運営していけたのか
・熊本震災のニュースが他県で話されなくなってきた今、被災者、支援者はどのような局面を迎え、どのような気持ちで過ごしているのか
・野村さんの視点から、被災者ではない私たちができること、これから熊本復興に必要だと思われること
など知ることができます。
ぜひこの録画をご覧いただき、改めて熊本震災のことについて考えていただけたらと思います。
no.1
no.2
動画を作ると人生が変わる(7)~ドラマが起これば未来がやってくる
反転授業の研究の田原真人です。
10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。
動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた
動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる
動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった
動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる
動画を作ると人生が変わる(5)~コミュニケーションを改善する
動画を作ると人生が変わる(6)~多様性が学びに繋がる仕組み
動画を作りはじめると、生身の自分の存在意義が問われてきます。
自分のやっていたことの多くは、動画で置き換えられる。いや、むしろ、動画にしたほうがよかったりするという状況の中で、生身の自分がやるべきことは何なのかという問いが自然と生まれてくるのです。
「教師の仕事の中で、動画に代替されないことは何なのか?」
動画を作ることは、この本質的な問いを生み出すトリガーになります。
この問いが、あなたを別の次元へと連れて行ってくれます。
動画を作ると人生が変わるのです。
意識を向けると世界が広がっていく
僕は、最近、「意識をどこに向けるか」ということが大事だと考えるようになりました。
意識を向けると、世界のその部分が拡大していくのだということを実感しているからです。
人間は、意識を自分の内部に向けることもできれば、外部の世界に向けることもできます。
個人が社会の部品として組み込まれていくのではなく、個人と社会とが、お互いに活きを引き出すような関係になるためにはどうしたらよいかと、ずっと考えているのですが、最近は、個人の意識が、内部世界と外部世界とを循環することが大事なのではないかと思い始めました。
工業化社会の労働者を大量に作り出す教育は、テストによる序列化という仕組みを作り、アメとムチによって生徒の意識を外部世界に向けて来たのではないでしょうか?
大量生産、大量消費の社会は、人々の欲望にアクセスし、人々の意識を外部世界に没頭させてきたのではないでしょうか?
その結果、内部世界がしぼみ、同じような思考パターンを持った人が大量に生み出されるという状況が生まれているのではないかと思います。
そのような教育を受け、そのような社会で育ってきた自分にも、それは当てはまります。
意識を内部世界に向けること、つまり、「自分が、自分について考える」ということは、自己言及的な行為です。
自己言及のサイクルをぐるぐる回すと、差異が増幅されて拡大していきます。
つまり、意識を内部世界に向けていくと、個人が自然と多様化していくのです。
一方で、欲や怖れに対する反射的な反応には個人差はほとんどありません。外部から欲や怖れにアクセスされ、単純な反応を引き出されているうちに、同じインプットに対して、同じアウトプットを返していくような大量の人間が生まれてきます。
これは、人を外から操作するときに使われてきた方法であり、大量生産型の教育や、大衆操作にも利用されてきた方法です。
人間の欲望は、本来は、有限のものです。お腹がいっぱいになれば食欲が治まるように、普通は物理的な限界に達して減衰していきます。
しかし、テクノロジーの発展によって、欲望をバーチャルな世界へ移すことができるようになり、欲望を無限にかきたて、意識を常に外部に留めさせることができるようになってきました。
これは、とても大きな危険性を持っているのではないかと思います。
このような時代においては、人間の意識を内側に向けていくことを学ぶことが、かつてないほど重要になってきているのではないでしょうか。
生徒の意識を内部世界へ向け、自ら問いを持って学び、内部世界を拡大していくことを支援することが、現代の教師に求められている役割なのではないでしょうか。
動画を作成することで、教師が新たな役割の重要性に気づき、役割をシフトするのであれば、この連載のタイトルにあるように、「動画を作れば人生が変わる」のです。
教室の壁は、「檻」から「細胞膜」へと変化する
生徒を欲と怖れによって支配する仕組みが発動するためには、例えば、次のような条件が必要です。
1)外部と遮断し、文脈を固定する。
2)アメとムチによって、意識を常に外側に向け、疑問を持たずに競争させる。
教室が、支配の場であるときには、教室の壁は、生徒が逃げられないように閉じ込めておく檻の役割を果たします。
このような問題に気づいた教師たちは、生徒が自ら学ぶための場つくりを始めています。
そのような学びが起こるための条件は、以下のようなものになるかもしれません。
1)外部に開いていて、人も情報も行き交う。
2)問いを持つことが尊重され、お互いの自由な活動が認められる安心安全の場
このような場で、教師が、幅を持った文脈を作ると、生徒たちの活動が生まれてきます。
その活動に対して注意深く観察し、受容し、励ましていくと、活動量が上がっていき、相互の関係性の質も上がり、場を舞台としたドラマが展開するようになり、全体が一つの生き物のようになり、場に<いのち>が創発してきます。
場に<いのち>が生まれると、そこに展開するドラマが、生徒たちに多様な役割を与え、生徒たちの「活き」を引き出していきます。
単純ではない創造的な状況において、各自が何をやったらよいのかを考えることで、生徒の意識は内部と外部とを循環し、外部世界から刺激を受け取りながら、内部世界を拡大していきます。
このとき、教室の壁は、外部と内部を緩やかに隔て、内部の化学反応の可能性を高める細胞膜のような役割をします。
細胞膜によって囲まれた空間の中で、場の<いのち>も、内部と外部との循環を起こしながら、<いのち>のドラマが展開していくのです。
まずは、私たちから体現していこう
反転授業の研究がスタートした2013年頃、頻繁に話題になっていたことがあります。
それは、
「自分たちが体現していないものは伝えられない」
ということです。
教室に愛を起点とした与贈循環を起こし、場の<いのち>を創発させたいのであれば、まずは、自分たちの学び場に、そのような循環を起こし、その体験から学んでいくことが大切なのではないかと思いました。
こうして、反転授業の研究が主催するオンライン講座が始まったのです。
はじめてから3,4回目のときに、オンラインの場が安心安全の場になり、一体感が生まれました。
バラバラだった「私」が集まり、講座を通して「私たち」というグループが生まれたという実感がありました。
分からないことがあっても、場に助けを求めれば、誰かが助けてくれて進めるようになる互恵互助の関係が生まれ、幸福感が場に満ちるようになりました。
この体験を、次の講座、次の講座へと繋いでいくためにどうしたらよいかと考えた末、運営ボランティアという仕組みが生まれました。
オンライン講座を体験し、場の<いのち>の自己組織化を体験した人たちへ一括メールを送り、希望者は運営ボランティアとして参加できるようにしたのです。
怖れのサイクルが回ると、フリーライダーが大量に出たらどうしようという心配が生まれますが、愛を起点とした循環は、相手を信頼することから生まれるのです。
運営ボランティアという仕組みは、反転授業の研究のオンライン講座の大きな特徴となり、講座を提供する人と消費者という枠組みをぼやけさせ、役割を流動化させ、それぞれが自由に動き出しやすくなる状況を生み出しました。
今回の受講者は、未来の運営ボランティアであり、未来の運営者であり、未来の講師なのです。
そのような学びの循環に迎え入れていくというような気持ちで、オンライン講座の告知を行っています。
運営チームのメンバーは、毎回異なりますが、オンラインの場に生まれる<いのち>は、ずっと継続し続けているのです。

すでに新しいドラマは始まっている
「iPad/iPhoneを使ったカンタン動画作成」の講座は、ICT教育を広める団体Sensei TIPSと、反転授業の研究とのコラボ講座ということで、プロジェクトがスタートしました。
コラボ講座は、3回目なのですが、運営チームの中にオンライン講座を体験していない人が含まれることや、運営チームの人間関係ができていないところからプロジェクトがスタートするので、非常に難しいところがあります。
しかし、異なる経験を持つ人が入ることで、新しい可能性が産み出されるというメリットもあります。
Zoomでミーティングを行い、運営チームのチームビルディングを進めていたときに、熊本震災が起こりました。
プロジェクトの活動に集中することが難しくなり、一度、活動を中断しました。
1カ月の中断の後、プロジェクトを再開したのですが、約20名の運営チーム自体も自己組織化的なプロセスで動いているので、動き出すまでに時間がかかります。
お互いに思いがうまくかみ合わず、各自が身動きが取れない状況になりました。
プロデューサー役の僕は、この身動きが取れない状況は、どこから生まれているのだろうかということを一晩寝ないで考えた末、場に対しての洞察を述べた15分ほどの動画を作成し、チームで共有しました。
それをきっかけに、各自が想っていることを外に出しはじめ、エネルギーが循環し始めました。
チーム内からいろんなアイディアが出てきて、それを次々に実行していきました。
運営チームの意図が明確になり、各メンバーが意図に沿って自由に動けるようになってきました。
そんな中で、1つのドラマが生まれました。
運営ボランティアとして参加していた川上政嗣さんが、資金面でも運営チームを支援したいという理由で、受講者に回ったのです。
運営チームで学ばせてもらいつつ、受講者として学べないかという提案でした。
川上さんに続いて、跡部弘美さんも、受講者の申し込みをしました。
同じような気持ちで、運営ボランティアに参加してくださっている人がたくさんいることを知りました。
2人の愛を起点とした行動が、運営チームの一体感を高め、講座に学びの渦を巻き起こしていくための核が生まれました。
この行動をきっかけに、運営ボランティアか受講者かの2択以外の選択肢を作ったほうがよいという議論が生まれました。
オンライン講座に受け継がれてきた場の<いのち>は、今回の場にも確かに受け継がれています。
未来は誰にも分かりません。
未来が不安定であることを怖れると、大きいものや強いものに頼り、安定を求めたくなります。
周りの行動を縛り、すべてを予定通りに進めたくなります。
しかし、生きているということは、常に不安定なのだということを認めて、不安定なまま、自分の<いのち>を創造の場に注ぎ込んでいくとドラマが生まれます。
このドラマは、参加者に生きがいを与え、予想を超えた素敵な未来をもたらしてくれます。
僕が、先の見えない状況の中でいつもつぶやいているのは、「結果を求めずに、ドラマを起こすことに集中せよ」ということです。
ドラマが起これば、未来がやってくるのです。
すでに、ドラマは始まっています。
あなたも、このドラマに加わりませんか?
申し込みの締め切りは、本日(6月3日)です。
動画を作ると人生が変わる(6)~多様性が学びに繋がる仕組み
反転授業の研究の田原真人です。
10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。
動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた
動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる
動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった
動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる
動画を作ると人生が変わる(5)~コミュニケーションを改善する
教師がコントロールしている空間では、生徒は規範に従おうとします。
教師がコントロールを手放すと、はじめて、生徒は自分らしく振る舞うことができるようになります。
各自の自分らしい振る舞いが、自分と仲間の学びにどのように繋がっていくのを理解すると、学びの連鎖や循環が起こりはじめ、ドラマが展開していき、学習コミュニティが生まれていきます。
反転授業の研究のオンライン講座では、いつも上記のようなプロセスが起こるので、それが、自分が運営する物理ネット予備校(フィズヨビ)でも起こせるのか、試してみました。
多様な背景を持った受講者が集まった
5月に物理の学び方を学ぶための2週間の講習会「フィズヨビ講習会(第1期)」を行いました。
受講費は後払いで、受講者が自分が受け取った価値を自分で判断して決めて払うという形式を初めて採用しました。
集まった受講者は、
・東大を目指す高校生
・物理を得意になりたい高校生
・イギリスでインターナショナルバカロレアのコースで学んでいる高校生
・医者を目指している多郎生
・物理を高校で学ばなかった大学生
・働きながら医学部学士編入を目指す人
・医学部再受験のために勉強している社会人
・医学部再受験を目指す看護士
・新しい木造建築スタイルを確立するために大学に入り直そうとしている建築家
・高校時代に物理からドロップアウトしたのでリベンジしたい社会人
・元中学の理科教師
・物理を教える塾講師
・物理を教える高校教師
などなど
物理に対する理解度も、参加の動機も多様な中で、どのような学びを生み出すことができたのでしょうか?
物理の教師である私が何かを教えようと思っても、参加者が多様なので、全員が満足するような講義をすることは不可能です。
ですから、扱う力学の内容について、動画とPDFの資料を用意し、1週間に2問の問題を出し、参加者はそれを解いて写真に撮り、アップロードしていき、お互いにコメントしていくという形式を取りました。
この形式なら、受講者は自分のペースで学ぶことができ、自分の参加目的に応じた行動を取ることができます。
学び方の仕組みを共有したオープニングセッション
オープニングセッションでは、はじめに、私がコルブの経験学習サイクルについて説明しました。
実践 : まずやってみる
経験 : 何かしらの結果が出る
省察 : 振り返って気づきを得る
概念化 : 気づいたことを言語化して新しい実践に繋げる
一人で勉強していると、実践と経験の間を往復するだけになってしまうことが多いですが、グループで一緒に学び合うことで、他の人の考え方に触れることができ、省察と概念化をやりやすくなります。
実践と経験は、各自がマイペースで行う。
省察と概念化は、それぞれの実践からヒントを得て進める。
このように、個人でやることと、集まってやることとを整理したことで、講習会でやるべきことが明確になりました。
その後、「誰かの理解を助けようとして説明するときに、省察と概念化が起こる」と述べ、「助けを求める行為は、誰かに省察と概念化のチャンスを与えること」になるのだから、どんどん助けを求めていこうと呼びかけました。
そして、この学びのメカニズムをグループ全体が理解したときに、自分たちだけで学び合えるコミュニティが生まれるはずだから、それをゴールに設定しました。
導入として話したことは、こちらです。
ドロップアウトしかけた人たちの気づき
Moodleに問題をセットし、受講者がフォーラムに各自の解答をアップし始めました。
勉強が進んでいる人は、早速、問題の解答を作成してフォーラムにアップしましたが、物理の初心者は、当然ながら簡単にはできません。
毎日のように、メールでマインドセットについての話を送っていましたが、直感的にドロップアウトしかけている人が出ている気がして、急遽、Zoomで、お助けルームを開きました。
集まった人たちは、「できる人ばかりで、自分は間違った場所に来てしまったと思い、このままフェードアウトしようかと思いました」と言っていました。
そこで、どんなことを感じているのかを各自が話し、それを共有し、もう一度、学び合いのプロセスについて話し合い、「分からないを発信することが、自分だけじゃなく、周りにとっても役立つ」ということを確認し合いました。
1日1アクションを目標に、とにかく発信するという声が、受講者の中から出てきました。
1週目の振り返りセッションでは、
「中途半端なものを、中途半端なままで出す」
「途中で分からなくなったら、そこまでのものを出せば、誰かがヒントをくれる」
「不完全なものを出しても大丈夫という安心感が大切」
といった気づきを共有することができました。
ブレークアウトセッションで、コミュニケーションを十分にとったことも、学び合いをするための安心安全の場つくりに役立っていたと思います。
学びが爆発し始めた第2週
2週目に入り、受講者の活動量が一気に上がりました。
ドロップアウトし始めていた人が、不完全な解答を出し始めたことで、場がぐるぐる回り始めました。
教える、教わる、他の人の考えを参考にする、励ます、励まされる、提案する・・・
自分のどんなアクションが、他の人のどんな学びに繋がるのかが、だんだんと見えてきて、それぞれが、よさそうだと思うことを自由にやり始めたのです。
学びが勢いよくグルグルと循環し始めました。
他の人が考えたことにヒントを得て、別の人が図を描いてみる。
それを見た別の人が、さらに、発展させた考察をする。
そんな相乗効果が生まれてきました。
例えば、次のような問題を出しました。
この問題に対して、外力Fを大きくしていったときに、作用線の様子がどのように移り変わっていくのかの考察し、図にまとめて整理する人が現れました。
その様子を見ていて、これをアニメーションで示せたら分かりやすいだろうなぁーと思ったので、先日、住ノ江さんに教わったやり方でKeynoteアニメーションを作り、受講者に示しました。
アニメーションにすると断片的な理解が統合され、理解が一気に深まるんです。
しかも、ちょうどよいタイミングで、ちょうどよいものを出すというのが大きなポイントだと思いました。
十分に疑問が熟しているときに、その疑問に答えるようなものを見せることができたときに、学びが深まるのだと思います。
そのためには、スピード感が大事で、手軽に思った通りのものを作ることができる必要があります。
受講者の反応を見て、ビジュアル教材の使い方をよく理解できました。
感動のフィナーレ
第2週の振り返りセッションは、豊かな収穫の場となりました。
第2週には、あきらかに不連続な変化が多くの受講者に起こりました。
不連続な変化は、「気づくこと」によって起こります。
気づくためのヒントが場に溢れていたからこそ、不連続な変化が起こりやすくなったのです。
そして、そのことをみんなが理解したからこそ、場にエネルギーを一緒に投げ込んでくれた仲間に対する感謝が溢れ、感動的なフィナーレになりました。
ブレークセッションでは、どのルームも笑い声が溢れ、楽しそうに話をしていました。
そして、ここで学んだことを生かして、この仲間で学びを続けていくことを確認し合っていました。
反転授業は「学び方を学ぶ」ためのもので、それがうまく機能すると、教師がいなくても、自分たちだけで学び合える状況になります。
教師にとっては、生徒が独立した学習者になることこそがゴールなのではないでしょうか。
多様な背景を持った参加者が集まり、その多様性が視点の多様さを生み出し、物事を多面的に見て気づくことができる豊かな場を生み出しました。
そして、違いが学び合いのエネルギーになり、多くの不連続な変化が起こりました。そして、みんながエンパワーされて元気になりました。
こんな場を創りたかったんだという実感がありました。
僕の中にも、作りたかった現実を出現させてくれた受講者に対する感謝が溢れました。
僕自身も「助けて」を言う
分かりやすい価値を掲げて、それを販売するというやり方では、このような場は生まれません。
人は、体験したことがないことをイメージするのが難しいのです。
だから、フィズヨビ講習会の価値を伝えることに、僕は、とても苦労しています。
そのことを正直に話し、価値を体験したみなさんの力を貸してほしいと伝えました。
多様性のある場での学びは、各自が受け取るものも様々なので、受講料を自分で決め、まだ、体験したことのない人に価値を伝えるという意図で、講習会に対して感じたことを書いて下さいとお願いしました。
参加者の方からいただいた感想の一部を紹介します。
◆hk246さん
学校ではできない理想的な学びができた、これに尽きます。年代や理解度、目指すものなど、置かれた環境がばらばらな人たちが集まって共に勉強し、助け合うことのできる場はそうそうないと思います。
分かる人が分かっていない人に教え、またみんなで同じ問題について「学び合い」をすることで共に理解が深まり、全体がレベルアップすることができているのだと感じました。
また、雰囲気もとても良かったため問題を解いてアップするだけでなく、質問したり答えたりし易かったです。
このような学習ができればと思っていたので、今回の講習はとても楽しく有意義なものとなりました。次回も参加させていただきたいと思います。ありがとうございました!
◆寺本さん
力学の理解が深まりました。質問をしたり、質問に答えたり、他の方の答案をみたり、他の方の議論を読んだりすることで、理解が深まったように感じます。
◆マッスルきたむらさん
建築関係の仕事をしている社会人のものです。
高校の時に物理は完全に落第し、物理からは目を背けて生きてきました。しかしながら、業界の構造自体も、新築から維持管理の時代へと変わって来はじめ、物理(特に力学)とは無縁ではいられなくなってきました。
そこで、今回一念発起し、物理の苦手意識をなんとかしたいという思いで、フィズヨビ講習会に参加しました。
しかしながら、勢いで参加はしてみたものの、参加メンバーが大学受験希望の方や物理の先生という強者ばかりでした。初回の時点で、「失敗した。場違いだった。」と思い、2回目からは不参加のつもりでいました。
しかし、2回目の前日に、ふと前回の動画を見なおしてみたら、「この講習会は、参加者が多様でバラバラあればあるほどサイクルが回りますよ」というメッセージがあり、「ひょっとしたら、自分の落第体験や引っかかっているところを共有できたらメッセージの意図がわかるかもしれない」と思い直し、しぶしぶながら参加しました。
参加してこの話を共有したら、「その気持ちや考え方わかる」と、とても暖かく受容してもらったことで、とても楽しくセッションを終えることができ、いつの間にか、物理の問題に向き合っている自分がいました。
それからは、少しずつ自分の不完全な解答をアップし、参加者のみなさんにフォローしてもらうことで、また次に進めるという好循環が生じました。
こうして3回目の直前になんとか、1題が完答できたことで、「もうこれで物理とも向き合える」という自信ができあがり、とても楽しい状態で終えることができました。
今後も、この繋がりが維持できる仕組みになっているので、挫折することがあっても助けてもらえるという安心感がこの講習会でできあがっていました。
とても画期的な講習会で、今はワクワク感でいっぱいです。ありがとうございました!
今後も、この講習会がさらに大きく進化していくを願っております。
「反転授業の研究」と「自分の場」を往復する
今回のフィズヨビ講習会を成功させることができたのは、「反転授業の研究」のオンライン講座の体験があったからです。
そこで様々なチャレンジを重ねながら学んできたことを生かし、さらに発展させてフィズヨビ講習会を実施しました。
僕だけでなく、多くの人が、「反転授業の研究」での学びを、各自が作っている学び場へ生かして発展させています。
そして、その体験を、「反転授業の研究」が運営するオンライン講座に持ち寄ってくれることにより、さらに進化しています。
各自が実践と経験を積み重ね、オンライン講座に集まって省察と概念化をすることで、お互いに気づきを深め合い、成長しているのです。
ここでも、個人での学びと、集まっての学びとの間の循環が生まれているのです。
信頼関係で繋がり、学び合うことのできる仲間は、何物にも代えがたいほど貴重なものです。
6月に実施するオンライン講座「iPad/iPhoneで作るカンタン動画作成」でも、多くのドラマが起こることでしょう。
僕達は、この学び合いの循環の中に、多くの人たちを誘うことができたらと思っています。
今回、新たな学びの仲間と出会うことができるのを心から楽しみにしています。
動画を作ると人生が変わる(5)~コミュニケーションを改善する
反転授業の研究の田原真人です。
10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。
動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた
動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる
動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった
動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる
反転授業やアクティブラーニングに取り組むようになり、
一人だけがずっと話していて、他の人が黙っている
という状況って、不自然だなと感じるようになりました。
どうしてこの状況が生まれるかというと、教師の頭の中に知が局在しているからです。
教師一人が話し、生徒が黙って聞いているときは、生徒のほうが教師の話す速さに理解の速さを合わせなければなりません。
10%くらいの生徒は、分かり切ったことを繰り返すのに飽き飽きしているかもしれませんね。
30%くらいの生徒は、教師が進むペースが速すぎてついていけなくなっているかもしれません。
このようなことが起こることを防ぐために、生徒をレベル別にクラス分けしたり、できる生徒が先へ進みすぎることを制限したりすることもあります。
このような問題は、教師が一方的に知識を教えるという方法が創り出しているものです。
では次に、動画を使って、教師の頭の中をコピーして増殖させてみましょう。すると、こんな感じになります。
生徒は、それぞれ自分の理解度のペースに合わせて学ぶことができるようになります。
他の人に説明しようとすると、理解が深まり、学習定着率が高くなるので、教師は、学び合いが起こるような組み合わせを見つけて繋いでいきます。
話をしているのは教師だけでなく、生徒も教師も、同じように、必要に応じて話をしながら学んでいきます。
このような学び方の場合、生徒のレベルの違いや、理解の方法の違いは、問題になりません。
違いは学び合いのエネルギーになるからです。
教師の役割は、自分の中の分からなさや、中途半端さを表現して助けを求められるように、生徒のマインドセットを整えていくことになります。
動画は、関係性を良くしていくことに役立つ
教師が一方的に話し、生徒は動かずに聞いているという空間には、ある種の権力が働いています。
そのような権力は、信頼関係を築いていこうとするときにマイナスに働くのではないでしょうか。
呼吸をするときには、息を吸ったり、吐いたりをバランスよく繰り返します。息を吸ってばかりでは苦しくなります。
コミュニケーションも同じで、聴いたり、話したりをバランスよく繰り返すのが、一番楽で自然なのではないかと思います。
動画を使うと、そのような自然なコミュニケーションを通して学んでいく環境を作ることができるのです。
2015年に反転授業の産みの親であるジョナサン・バーグマンさんにインタビューを行いました。
彼が言っていたことで、とても印象的な言葉がありました。
それは、私がバーグマン氏に、「今の活動のゴールはどこにあるのか」と質問したときの返事でした。
私は、ゴールがあるかって分かりません。ただ、一つだけシンプルなゴールがあります。子どもたちは、このやり方で本当に学ぶことができるということです。それと、このやり方は、先生と子どもたちの関係をよくします。もし、ゴールがあるとすれば、人々の関係をよくしたいということです。生徒と先生、生徒同士、先生同士。他にゴールはないと思います。
一方的な関係性には歪みがあります。
動画を使うと、コミュニケーションを改善し、教師や生徒の関係性を改善しながら、よく学んでいける環境を作ることができる可能性が生まれます。
私は、ここに大きな可能性を感じています。
動画を作ると人生が変わる(4)~動かすと理解できる
反転授業の研究の田原真人です。
10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。
動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた
動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる
動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった
講義動画を作り、受講生がマイペースで学べる環境づくりを進めていくうちに、自分を取り巻く環境に変化が生まれました。
様々なソフトが販売されるようになり、動画を作る方法にバリエーションが生まれてきました。
ThinkBoardは、「リアルでやっている授業をバーチャルでもできる」ソフトなんです。
でも、もしかしたら、リアルではできなかったような学びをバーチャルならできるのではないかと思い始めました。
物理シミュレーションを動画にする
最初に考えたのは、物理実験をオンラインでやれないかということでした。
Youtubeに「物理エンジンで●●してみた」という動画シリーズが上がっていて、すごく興味深かったのです。
こういう仮説を立てて検証するような学びをするために物理エンジンを使えないかと考え、様々な可能性を探りました。
スウェーデンの教育ソフトであるPhunやAlgodooなどで、物理の問題集に出てくるような設定を再現してみようとしたりしました。
しかし、「軽くて伸びない糸」が、これらのソフトにはないためうまくいきませんでした。
さらに探していくうちに、アメリカの会社が作っているInteractive Physicsというソフトに出会いました。
これは、なかなかの優れもので、運動している物質のv-tグラフを同時に示すことができたり、リアルタイムで変化する速度や力をベクトルで表示できたり、重心から見た光景を表示できたりします。
つまり、リアルの実験では見えないものまで見えるようにしてくれるのです。
リアルの実験の臨場感にはかないませんが、リアルではできないことができるのが物理シミュレーションだと思いました。
ここにも、リアルの代替ではないバーチャルがあったのです。
これはすごいと思い、アメリカの会社に問い合わせ、日本からも購入できるようにしてもらいました。→ Interactive Physics
自著『日本一詳しい物理基礎・物理の解き方』に含まれている力学の問題設定をすべてInteractive Physicsで作り、読者が運動をイメージで捉えやすくしました。
シミュレーションをやってみると、問題設定にない状況が再現されるので、物理現象の全体像が見えてきます。
力学以外のシミュレーションも使いたいと思って調べたところ、コロラド大学がPhET Interactive SimulationsというWebサイトを作っていて、そこに大量のシミュレーションがあり、無料で使用できることが分かりました。
特に電気回路のシミュレーションは優れもので、自由に回路を組み立て、コンデンサーやコイルにどのように電流が流れるのかを見ることができるのです。
説明がしにくかったことを、電気回路のシミュレーションを組み立て、それをカムタジアスタジオなどのスクリーンキャストソフトで録画して動画にして説明すると、一発で理解してくれました。また、リンク先を紹介して、自分でも回路を組み立てて学ぶように勧めました。
動かすことで分かりやすくなるのは物理だけじゃない
2015年に「パソコンで作る!カンタン動画作成」というオンライン講座を実施しました。
そこに30名以上が集まり、白板ソフトでアニメーションを作り、カムタジアスタジオで録画するという方法で動きのある動画を作成しました。
その体験は、僕にとって衝撃でした。
物理や数学の概念獲得に「動き」が役立つのはイメージできていたのです。
しかし、ありとあらゆる科目で、「動き」が理解に役立つのだということを体験し、それまでの常識が崩壊しました。
例えば、これは、講座を受講した内橋朋子さんが作成した古典の敬語を説明する動画です。
教師の工夫次第で、いろいろな分野で「分かりやすさ」を改善できるのだということに気づきました。
また、一度作成してしまえば、生徒がいつでも視聴することができるようになるので、「敬語については、この動画を見てごらん」と指示することで、その場で対面で説明する時間がなくても、生徒の理解を助けることができるようになるのです。
思考の制約が外れる
動く教材を作成するようになり、今まで、黒板やホワイトボードに手書きで書いて授業をするという制約に、思考も制約されていたことに気づきました。
道具が変われば、アイディアも次々と湧いてきます。
アイディアが湧いてきたときに、簡単にそれを形にできる方法を知っていて、そのときに10分くらいの作業で動画を作っていくようにすると、いつの間にか積み重なっていき、1年もすれば、生徒の理解を助けるライブラリができあがり、そのライブラリは、教師の分身として休まずに働いてくれる心強い味方になります。
動く教材を作ってみると、言葉で説明しても理解できなかったのに、視覚的に説明するとすぐに理解できる生徒が存在することにも気づくようになります。
それを見て、今までの授業は、言語的な理解が強い生徒に有利で、視覚的な理解が優位な生徒には不利だったのかもしれないと思うようにもなりました。
動く教材を作って動画化することで、様々な個性を持った生徒が、自分に合った学び方を選択することができるようになればと思います。
動く教材を作る方法は、いろいろありますので、いくつかの方法を試してみて、自分にとってやりやすい方法を確立するのがお勧めです。
長く続けるコツは、隙間時間にカンタンに作れること。
日常生活の中に、上手に動画作成の時間を組み込んでみてください。
動画を作ると人生が変わる(3)~学習環境を整える人になった
反転授業の研究の田原真人です。
10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。
動画講義が、「リアルの代替ではないバーチャル」であり、受講者が倍速再生や一時停止を使いながら、自分の理解のペースに合わせて動画で学んでいるのを見て、2008年頃には、僕のマインドは大きくシフトしました。
動画で学べるのであれば、教師が同じ授業を繰り返すよりも、動画でいいじゃないかと思ったのです。
僕は、教室で教えるのがとても好きで、生徒たちの注目を浴びて「教師を演じる」ことに快感を感じていましたが、それは、今後、動画に置き換わっていくことになるのだということを実感したのです。
そして、次の時代の教師の役割は、学習環境を整えることになると思いました。
通常、生徒が学んでいく流れは、次のようなものだと思います。
(Step 1) 教師の授業を聴き、内容を理解する。
(Step 2) 問題を解き、理解度を確かめる。
(Step 3) 分からないことがあれば、教師に質問する。
(Step 4) 繰り返し練習して定着させる。
このような学んでいく流れの中の、どこをITによって代替可能なのだろうかということを考えるようになりました。
そして、もしかしたら、代替以上のプラスの効果を生み出す方法はないだろうかと考えたのです。
教える仕事をしている人なら、誰もが感じていることだと思いますが、生徒から来る質問の多くは同じものです。
それは、ある意味、自分の教え方の分かりにくさを反映しているものなので、それをフィードバックとして、教師は説明の仕方を改善しているのだと思います。
でも、誰にでも分かりやすい説明というものは存在しないし、すべてを「説明の改善」で解決できるわけではありません。
だから、「講義動画」+「Q&A」という組み合わせで学べるようにしたらどうかなと思ったのです。
Q&Aと講義動画を紐づけておいて、分からないことがあれば、その講義に関連付けられているQ&Aを読んで、それで解決しなかったらQ&Aに新規投稿して回答してもらう。
このようにすれば、効率よく学べる学習環境が整えられると思ったのです。
この試みは、結構、うまくいって、今、学んでいる受講生は、「動画講義+10年分のQ&A」という学習環境で学んでいます。
自分では疑問に感じなかったことを、他の人の質問を読むことで気がつくことができ、理解が深まるという体験が語られています。
10年前の受講生の質問が、今、学んでいる人の役に立ったりしているのです。
断片的な情報が、適切に蓄積され、使えるように配置されることで、全体として価値を持ってくるという側面に気づくことができました。
動画を作り始めたことで、自己イメージを教師から、学習環境を整える人へシフトすることができたのです。
動画を作ると人生が変わる(2)~理解速度にシンクロさせる
田原です。
10年前に動画を作り始めたことで、人生がどのように変わってきたのかを連載しています。
予備校講師だった僕にとって、講義は、ノウハウのすべてを詰め込んだ「商品」でした。
生徒の関心を惹きつけ、笑わせ、楽しませ、理解させ、問題を解けるようにし、成績を上げるという物理の講義。
その商品を売ることによって対価を得ていたのです。
講義のすべてを動画にしたときに、実は、半信半疑でした。
生の空間だからこそ、自分の講義は光を放つことができるのではないか。
動画にすると、講義のパワーが半減してしまうのではないか。
そんなことを思ったのです。
しかし、PCレターの開発者の三上さんとのやり取りから、今まで考えたこともなかった新しい可能性を感じることができ、動画にすることに対して気持ちがポジティブになりました。
リアルの代替じゃないバーチャルを目指す
PCレター(現在のThinkBoard)を開発したのは、北海道の浦河町という小さい街に住み、電気屋を営む三上博正さん。
不便な田舎に住んでいても、都会に負けない教育を受けられるようにしたいということでPCレターを開発したのです。
その三上さんがこだわっていたのが、
リアルの代替じゃないバーチャル
という言葉でした。
三上さんは、「リアルが一番いいのだけど、仕方がないからバーチャルで!」という扱いが、たぶん我慢ならなかったのだと思います。
リアルとバーチャルは別物。
臨場感ではリアルには叶わないかもしれないが、別の部分でリアルよりも優れた部分を作れば、リアルの代替じゃないバーチャルを作れる。
それが、三上さんの信念でした。
そして、それを象徴する機能が、倍速再生でした。
僕は、倍速再生には、最初は懐疑的でした。
自分の講義は、話す速さとか、間合いとか、そういうものも考えて作っていると思っていたので、それが、ピヨピヨと倍速再生されるのが嫌だったのです。
だから、最初は、倍速再生可能に設定していませんでした。
でも、三上さんの信念に押されて、渋々、倍速再生可能な講義ファイルを作りました。
受講者の反応は、僕の予想を裏切るものでした。
ほぼすべての受講者が、倍速再生で講義を視聴し始めたのです。
受講者は、次のような動画視聴法を編み出しました。
1)最初から2倍速で通して見て、全体像を把握する。
2)2度目も2倍速で視聴し、分からないところは等速に戻し、一時停止したり、繰り返して再生したりする。
3)3度目は、4倍速で視聴し、例題などの前で止めて、紙に書いてやってみる。
こんな感じで勉強すると、90分の動画講義であっても集中力が途切れずに、どんどん学べるというのです。
「リアルの代替でないバーチャル」は、確かに存在するということを実感しました。
その年、受講者とのオフ会に出席すると、参加者から「田原先生のしゃべりが遅く感じる。2倍速じゃない田原先生には違和感がある」と言われました。それほど、倍速再生が与えたインパクトは大きいものでした。
理解の速度と再生速度をシンクロさせる
僕の動画講義は、予備校の90分の授業をそのまま動画にしたので、90分~120分と長いです。
その後、「長い動画は集中力が持たないから、長くても15分までにしたほうがよい」ということが言われるようになりました。
それも一理ありますが、知識が細切れになってしまうデメリットもあります。
90分間で、部分と全体とが響きあって理解が深まる構成というものもあったりするので、長い動画には、長い動画なりのメリットもあります。
そもそも、なぜ、集中力が15分しか持たないのでしょうか?
面白い本なら1時間でも2時間でも読みふけることができるのに、動画だと15分で集中力が切れるのはなぜなんでしょうか?
ということを考えていて気がついたことがあります。
動画の速度が、理解の速度よりも早い → ついていけないのでストレスを感じる。
動画の速度が、理解の速度よりも遅い → まどろっこしくなって飽きてしまう。
対面だと、話している速度と、理解の速度にずれがあっても、結構、耐えられるんだと思います。
でも、動画だと、耐えられる幅が小さくなるので、15分くらいが限界・・・・・。
ということなんじゃないかなと考えています。
しかし、もし、動画の再生速度を自分で自由に変更できて、自分の理解の速度に合わせることができたら、ストレスを感じることなく動画講義を受講できるようになります。これが、フィズヨビ生に起こっていることです。
動画の再生速度と、理解速度とをシンクロさせることが、とても重要なのです。
そして、そのようにして学ぶことができる動画講義は、リアルの講義の代替ではなく、新しい価値を生み出しているのです。
熊本×反転G vol.6 〜地元の生活や状況を語ってもらう会再び〜 5/18
5月18日に行った熊本×反転G vol.6 〜地元の生活や状況を語ってもらう会再び〜 の録画動画をUPします。
スピーカーは熊本市東区で保育園を経営する北崎恵理さんです。
印象に残ったのは、次のようなことでした。
「避難所に託児所が立ち上がって子どもが溢れ、ストレスが溜まっている一方で、否認化の保育所は子どもが避難によりいなくなって経営が苦しくなっている。需要と供給を柔軟にできないのか。」
「震災後の子どもの問題行動が、出はじめている気がする。でも、初めてのことなので、本当にそうなのか、見方が分からない。」
「自分たちで動かなくてはならないので、どう動いたらいいのかの参考になる情報をもらえるのが助かる。」
「上のほうでやり取りしている感じで、日常生活のところは放置されている気がする。日常生活は待ったなしで進んでいく。」
動画をご覧ください。
動画を作ると人生が変わる(1)~自分の分身ができた
反転授業の研究の田原真人です。
オンライン講座の運営チームでやり取りをしている中で出てきたのが、
「動画が作れるようになると人生が変わる」
という言葉でした。
一瞬、「人生が変わるは、大げさだろう!」と思ったのですが、僕自身の人生が大きくシフトしたきっかけが、10年前に動画が作れるようになったことでしたので、自分が、どのように動画作成に関わってきて、それによって、どのように人生が変化してきたのかを振り返りつつ、連載していきたいと思います。
様々な種類の動画を作成してきましたので、いろいろな動画の作り方のメリットやデメリットを比較し、みなさんが自分に合った作り方を見つけるためのガイドにもなればと思います。
予備校の物理の授業をネット配信
今から11年前の2005年4月。
当時、河合塾で物理を教えていた僕は、自分の物理講義をネットで配信できないかなと考えました。
その理由は2つ。
・自分が改善を重ねてきた教え方を、もっと多くの人に知ってもらいたい
・ずっと同じことを繰り返し授業をしているのだから、動画でいいのではないかと思った。
予備校では、50-70人ほどの教室で、一斉講義型の授業をしていましたが、ある程度、教え方が固まってくると、同じ授業を繰り返すことになるのです。あるとき、まるで自分が授業を行う機械であるかのような錯覚を覚えました。
まずは、受講してくれる人がいるのかどうかを知りたいと思い、まぐまぐから『たのしい≪たとえ話≫で直感的に分かる物理の考え方』というメールマガジンを発行しました。
このメールマガジンが、大好評で、最終的には3500人ほどの読者を獲得し、まぐまぐで殿堂入りのメルマガとなりました。
そこでは、このようなたとえ話を配信していました。
それまで教室の中で話していたことをアレンジしてメールマガジンで配信していた結果、大きな反響があり、物理をネットで勉強したい人がたくさんいて、その目的も多様なのだということに驚きました。
それで、メルマガ読者向けに物理講義をネット配信することにしました。
でも、当時は、iPadもなかったし、簡単に講義動画を作ることができるツールがなかったんです。
それで、ひたすら自分が授業で話している内容をテキストに打ち込み、図を挿入し、Latexで組版してPDFファイルにして配布しました。
このようなものを、全範囲について合計50講作りました。
1つの講義を作るのに要する時間は、4-6時間。
朝から夜まで予備校で授業をしていましたので、PDF講義を作成する時間は、主に深夜でした。
先に受講料をいただいて、毎週配信ということに決めたので、50週間に渡り、睡眠不足の日々が続きました。
仕事を終えて家に戻ってくると11時。ちょっと休んで12時から3時までPDF講義作成・・・。
そういう日が、週に何度もありました。
30代の体力が余っている時期だったからこそできたことですね。
この講義で学んで、成績がすごく上がったという高校生や、受験生が出てきました。
東大に合格した人も出てきました。
受講者からのフィードバックがたくさん届くので、それに励まされて、なんとか50週間やりぬきました。
今までは、教室で教えなければならないと思っていた自分の思い込みが崩壊し、工夫次第でオンラインで学べる環境を作ることができることに気づきました。
動画講義との出会い
PDF講義を20講くらいまで作ったときに、受講生の方から、
「田原先生、このソフトで講義を作ったらどうでしょうか?」
と勧められたのが、PCレター(現在はThinkBoard)というソフトでした。
教えてもらったWebサイトを訪問してサンプル講義を見てみると、PCの画面をホワイトボード代わりにして、教師が音声で説明しながら手書きの文字を書き込んでいきます。
今でこそ、カーンアカデミーなどでおなじみとなった形式ですが、2005年当時は、そのようなものを見たことがなかったので、興奮しました。
これを使えば、PDF講義ではなく、予備校でやっている講義をそのまま配信できると思ったのです。
それで、PDF講義の受講者に相談しました。
「PDF講義から、PCレター講義に切り替えるのはどうでしょうか?」
PDFに比べて、PCレターのほうが情報量も表現力も圧倒的に上なので、喜んで賛成してくれると思ったのですが、
「PDFファイルを印刷して、電車の中で読みながら勉強しているので、パソコンでしか見れないPCレターだと困ります。」
「私はMacなので、PCレターが見れないので、PDF講義のほうがよいです。」
というような声が返ってきて、結局、50講分を最後まで作り終えてからPCレター講義を作ることにしました。
PDF講義の場合は、予備校の90分の授業の内容を半分くらいに減らして作成していたのですが、完成までにかかる時間は4-6時間。
ところが、PCレターの場合は、講義でしゃべるのと同じことをどんどん話しながら、黒板に書くのと同じようにペンタブレットで画面に書いていけばよいので、90分講義を作成するのに要する時間が120分くらいです。
作業光景は、こんな感じ。

作った講義動画は、このようなものです。
※ThinkBoard形式をmp4に変換し、youtubeにアップロードしてあります。
このやり方に変えて、講義作成に要する時間が、大幅に減りました。
それから何年間も、キャリーバックにノートPCとタブレットを入れ、宿泊先のビジネスホテルで、夜、動画講義を作り続ける毎日を送りました。
当時、僕以外に、毎晩毎晩、動画講義を作っている人は世界中にもほとんどいなかったと思います。
サルマン・カーン氏がカーンアカデミーを始めるのよりも前でしたから。
このようにして、予備校講師として一番脂が乗っている時期の講義を、すべて動画講義として保存することができました。
フィズヨビの受講生はどんどん増え、毎年400名ほどが、僕の動画講義で物理を学んでくれるようになりました。
動画が自分の分身として働いてくれるようになり、自由な時間が生まれたことで、生身の自分は、次のステップへ進むことができるようになりました。
動画講義作成が、僕の人生を大きく変えたのです。
しかし、それは、同時に別のジレンマを生み出すことになりました。
第23回反転授業オンライン勉強会「iPad/iPhoneで教材を作ってみよう」
反転授業の研究の田原真人です。
インターネットが発達し、個人が情報を発信することができる時代になりました。
誰もがブログやFacebookで自分の考えを発信できるようになったことで、共感による繋がりが生まれ、それは、社会に変化を与えるほどのインパクトを生み出しています。
スマホの普及率が高くなったことで、写真や動画をシェアすることが簡単になりました。Youtubeが誕生し、個人がアップロードした動画を世界中の人が視聴することができる時代へ突入しました。
ポケットからスマホを取り出し、指でタップするだけで撮影でき、その場でアップロードして共有できるようになり、動画が以前とは比べ物にならないほど身近なものになったのです。
動画を教育に生かしていこうという試みは、このような社会インフラの変化の中で、必然的に起こったものだと思います。
iPadが創り出した無限の可能性
みなさんは、iPadがどんな可能性を創り出しているのかに気づいていますか?
実は、私も、つい数日前まで気づいていませんでした。
何かを表現したいと思ったとき、
(1)それを表現するための技術を習得する。
(2)その技術を使って表現する
というプロセスになると思います。
iPadは、「技術習得に要する時間を大幅に短縮する」ことを可能にしたのです。
通常、新しいソフトを使いこなすためには、マニュアルを読んで、チュートリアルに従ってやってみたりするわけで、一人ではマスターできないことも多いです。
ところが、iPadは、次の2つの方法によって、マニュアルなしでも、いきなり使えるようになっています。
(1)1つのアプリの機能を絞り込んである。
(2)操作方法を標準化してある。
iPadのアプリは、アイコンを見ながら、適当にタップすれば、マニュアルを読まなくても使えるようになるんです。ボタンや操作法も標準化されているので、1つのアプリを使えるようになれば、他のアプリも、直感的に使えるようになります。
つまり、マニュアルを見ながらソフトの使い方をマスターする労力を、大幅に節約できるようになるんですね。
その結果、いきなり、アイディアを表現する作業に進むことができるわけです。
このメリットに、みなさん、気づいていましたか?
iPad/iPhoneアプリには、動画加工に関するアプリが数えきれないほどあります。
それらを使いたいと思ったら、ダウンロードしてちょっと触ってみれば、マニュアルなしで直感的に使うことができます。
そして、加工した動画をiMovieなどでまとめて編集すれば、自分のアイディアを形にした動画を作ることができます。
動く教材でも、講義動画でも、プロモーション動画でも、ブランディング用の動画でも・・・
あなたが創りたい動画を、カンタンに創ることができる可能性をiPad/iPhoneは、持っているのです。
しかも、持ち歩きが簡単なので、移動時間などに編集作業をすることができるのもありがたいです。
私に、このiPadの秘密を教えてくれたのが、iPadの達人、ICTコンサルタントの住ノ江修さん。
そのときのインタビューはこちら
住ノ江さんは、いち早く、iPadの可能性に気づき、自腹で2000個以上のアプリをダウンロードして、様々な検証を行ったのだそうです。
そして、それを教育の様々なシーンで利用するための方法を提案しています。
オンライン勉強会では、下の動画のような感じで、住ノ江さんがiPadをスクリーンシェアしながら、お話してくれます。
勉強会の内容は、以下の通りです。
第1部 講演「iPad/iPhoneで教材を作ってみよう」
第2部 実践! Keynoteを使って教材を作ってみよう
オンライングループワーク(時間によっては、行わないこともあります)
第2部では、教材作成を体験しますので、お手元にiPad、または、iPhoneを用意して参加してください。
また、あらかじめ、Keynoteアプリをインストールしておいてください。
※これらのデバイスをお持ちでない方は、この時間は見学となります。
日時:5/30(月) 21:00-22:30
場所:オンラインルーム Zoom
参加費:無料
登壇者:住ノ江修さん
タイトル:iPad/iPhoneを使った教材作成
iPad/iPhoneを使った教材作成
登壇者 住ノ江修
(プロフィール)
iPad/iPhoneのダウンロードしたアプリは2000以上。
寝る時以外はiPadを常に持ち歩いている。
初代iPadに出会ってからソフトバンクの代理店においてiPadコンサルタントとして業務を行い幅広い業種にiPadを導入し研修を行う。
導入に関わったiPadの台数は3000台以上。
実施したiPadセミナーは200を超える。
現在は私立小学校のICT教育室 室長として教職員にICT及びiPadの研修を行い授業における効果的なICT活用実践及び提案を行っている。
またiPadによる電子教材・動画を作成を行い作成指導を積極的に行っている。
第1部 登壇者 住ノ江修さん
・動画の種類
・動画のメリット
・どう作る?
・動画で使えるアプリ
・Keynoteでのスライドアニメーション作り方実演
第2部 オンライングループワーク
iPadまたはiPhoneを用意していただき、実演を参考に教材作成を行います。
事前に、お手持ちのiPadやiPhoneにKeynoteをダウンロードしていただく必要があります。
iPadやiPhoneをお持ちでない方は、その時間は見学になります。
その後、オンライングループワークを行います。
お申し込み方法
(1)このページからお申し込みください
(2)自動返信メールに参加方法が書いてありますので、指示に従って参加してください。
※自動返信メールの内容
●●様
反転授業オンライン勉強会、運営担当の田原真人です。
このたびは、勉強会にお申し込みいただき、ありがとうございます。
日時 2016年5月30日(月)21:00-22:30※20:30からルームをオープンします。
第1部 スピーカー 住ノ江修さん
第2部 オンライングループワーク
ビデオ会議に参加できる用意(マイク&Webカメラなど)を
ご用意ください。また、第2部で使用するiPad/iPhoneを手元にご用意ください。
当日は、Zoomというビデオ会議室を使用します。
ルームURL
(メールでは、ここにURLがあります)Zoomの使い方については、以下の記事を参考にしてください。
(1)パソコンからアクセスする場合
http://zoom-japan.net/?p=54(2)iPad or iPhone、その他、スマホの方
http://zoom-japan.net/?p=17※PCからだと、ルームURLをクリックするとインストーラーが自動的に
ダウンロードされ、それをクリックすると自動的に繋がります。※何も始まらないときは、「downloard & run zoom」を
クリックしてください。※iPhoneやiPadからの場合は、Meeting IDの入力を求められますので、
(メールでは、ここにMeeting IDがあります)
を入力してください。※お願い【重要】
第2部のグループワークでは、ZoomのBreakroom機能を利用しますが、
アプリが最新版であることが必要です。以前にZoomアプリをインストールされている方は、
最新版に更新しておいてください。最新版へのアップロード方法はこちら
http://zoom-japan.net/?p=110
それでは、当日お会いできることを楽しみにしています。
田原真人
info@flipped-class.net
熊本×反転G Vol.5〜防災の専門家の話を聞いてみよう〜 5/10
岐阜大学 流域圏科学研究センター 流域情報研究部門 小山真紀准教授にお話をうかがいました。
防災の専門家である小山さんの話を手掛かりに、これから何ができるのかを考えました。
iPad/iPhoneで作るカンタン動画作成
「反転授業の研究」の田原真人です。
6月に実施するオンライン講座は、iPadやiPhoneを使って簡単に教材を作成したり、動画を作成&編集したりする方法を学ぶ講座です。
私は、動画を使った学習に10年前から取り組んでいます。
自分で動画を作成できるようになり、人生が変わりました。
10年前、私は、予備校でやっていた物理の授業を動画で作り、約400人の受講者が自分のペースで学べるネット予備校を立ち上げました。
現在は、動画を予習課題として用い、Web会議室で振り返りセッションやオンライングループワークを行うオンライン反転授業を実施しています。
動画を自由に作成できるようになり、その活用法を身につけたことで、教育だけでなく、活動の範囲が一気に広がり、人生が大きく変わりました。
この体験を、多くの人に分かち合えたらと思っています。
今回の講座では、簡単な操作で、表現力豊かな動画を作成できるように、iPad/iPhoneを利用した動画作成方法を学びます。
iPad/iPhoneアプリの直感的操作が分かりやすい
動画教材を作る方法はたくさんありますが、複雑なソフトウェアを使って動画を作ることは、初心者にとってはハードルが高いです。
ソフトウェアの使い方をマスターすることで苦労して、動画作成までにたどり着けない可能性もあります。
また、せっかく操作を覚えても、しばらくしたら忘れてしまい、使えなくなってしまうこともあります。
その点、iPad/iPhoneアプリは、機能がシンプルで、初心者でも直感的に操作できるというのが大きな特徴です。
操作方法やボタンが標準化されていて、1つのアプリの使い方をマスターすれば、他のアプリも簡単に使えるようになります。
例えば、
どのアプリでも追加は、「+」マーク
などというように、アイコンが統一されているんですね。
その他の機能も、どこをタップすれば何ができるのかは、アイコンを見れば予想がつくようになっています。
だから、1つのアプリの使い方をマスターした瞬間、世界中に溢れるアプリを、同じような感覚で使えるようになってしまうのです。
一般的には、簡単な操作でできるものは、できることが限られる場合が多いです。
でも、iPadの場合は、数えきれないアプリがあるので、それらを組み合わせることにより、無限の可能性が生まれます。
通常は、新しいソフトウエアを使いこなすことは難しいことですが、操作方法やボタンが標準化されていると、苦労なく使えるようになります。
操作を覚えることが簡単なのに、できることが無限大
これが、iPad/iPhoneが、操作方法の標準化によって創り出した新たな可能性なのです。
本講座では、第一歩としてKeynoteというアプリを使います。
Keynoteの使い方を学んでいるうちに、実は、潜在的に無数のアプリの使い方を学んでいます。
Keynoteなどで作成した動きのある素材を動画化して、iMovieという動画編集ソフトに入れます。
あるアプリで素材を創り、iMovieで編集するというフローは、大きな拡張性を持ちます。
なぜなら、
様々なアプリで素材を創り、それらをiMovieで編集してつなぎ合わせる
ということが、操作の標準化によって簡単にできるようになるからです。
ここには、ものすごい表現の可能性があります。
私たちは、みなさんに、この可能性へ続く道を作りたいと考えています。
iPadの達人とは
講師を務めるのは、iPadの達人、住ノ江修さんです。
住ノ江さんは、iPadが持つ上記のような可能性にいち早く気づき、自腹で2000個以上のアプリをダウンロードし、それらを組み合わせることによってどのようなことができるようになるのかを試したのです。
通常であれば、2000個のアプリの使い方を、マニュアルを見ながら一つ一つ覚えていかなければなりません。
しかし、iPadの場合は、操作の標準化によって、初めて使うアプリでも最初から直感的に使うことができます。
そのため、操作方法を覚えることに労力を使わずに、アイディアを形にすることにエネルギーを注げるようになるのだそうです。
iPadの場合は、1つ1つのアプリの機能はシンプルですが、それらを組み合わせれば複雑なことができるようになります。
1つ1つのソフトウェアで完結しているPCとは、発想法が違ってきます。
2000個以上のアプリの特徴が頭に入っている住ノ江さんは、それらを組み合わせることによって様々なものをiPadで実現することができます。
だから、住ノ江さんは、iPadの達人なのです。
住ノ江さんがiPadと出会って人生が変わった物語は、次のインタビュー記事をご覧ください。
第3回アクティブ・ラーニングフォーラムでの講演も大きな反響がありました。
どんな人が対象なのか?
この講座は、受講者中心の講座です。
KeynoteやiMovieの基本操作をマスターした上で、お互いに学び合いながら、自分が作りたい教材や動画を創っていきます。
あなたは、どんな教材や動画を作りたいですか?
次の動画をご覧ください。
どんな教材や動画が作れるようになるのか?
この講座では、Keynoteアプリでアニメーションなどの動きのあるスライドを作り、iMovieで動画編集して音声や音楽などをつけていくという方法を取ります。
Keynoteは、表現力豊かなアプリなので、あなたの創造力次第で様々な動画を作ることができます。
イメージしやすいようにいくつかの事例を紹介します。
◆図形をアニメーションで動かしながら説明する算数の動画
◆古典の敬語
◆英語の発音動画
◆黒板に投影するための英語教材
レーザーポインターで読む箇所を示しています。
◆動く絵本
◆プロモーション動画
◆ブランディング動画
◆講座案内
Keynoteだけでなく、様々なアプリで画像や動画を加工し、それらを組み合わせてiMovieで編集して作成したのが、次の講座案内動画です。
※この講座は、住ノ江さんが所属するSensei TIPSと反転授業の研究とのコラボ講座という形で運営します。
動画が作成できると何ができるのか?
はじめに、「動画作成ができると人生が変わる」と書きましたが、どんなことができるのか、具体的に書いていきたいと思います。
(1)マイペースで学ぶ学習環境を作ることができる。
生徒が、内容を理解するまでに要する時間は、人それぞれです。決められた時間内に理解するという制約が、理解できない生徒を創り出している可能性があります。動画を用意して、理解できるまで何度でも繰り返して学べる環境を作ることで、救われる生徒が出てきます。
(2)理解を助けるビジュアル教材を作ることができる
図形などを動かすことで説明が分かりやすくなる場合があります。概念を理解するときに、視覚化して動かしてあげることで格段に理解しやすくなる場合があります。Keynoteを使って動く教材を作ることで、理解を助けることができます。
(3)予習、復習用の教材として使う
予習に興味を引くような動画を見せて授業の動機づけをすることができます。また、授業では扱わなかった応用的な話を動画にしておいて、「興味のある人は見てごらん」と示すことができます。動画を気軽に作れるようになると、「授業時間内で教えられること」という制約から自由になり、授業の工夫の幅が大きく広がります。
(4)反転授業
教える内容を動画にして予習として課し、授業中にアクティブラーニングなどを行う反転授業を実施することもできます。実践→結果→省察→概念化というコルブの経験学習サイクルを考えたときに、特に、省察と概念化の部分では、他人の考えに触れることが学びを促進します。一人で学ぶことと、協力して学ぶこととをうまく組み合わせることにより、相乗効果を生み出すような授業をデザインすることが可能になります。
(5)マニュアル・商品説明・自己紹介動画
動画は文字に比べて情報量が多いので、操作方法や特徴などを分かりやすく伝えることができます。
(6)プロモーション動画
イベントなどを行うときに、イベントの魅力を伝える必要があります。そのときに役立つのが動画です。いくつかのアプリを組み合わせることで、魅力的な動画を作って伝えることができます。
(7)想いを伝える動画
世界を変えようと思ったら、自分の想いを発信する必要があります。
想いを動画で伝えると、声から感情が伝わり、あなたの想いが伝わりやすくなります。
インターネットを通して共感で繋がる時代において、動画は想いを伝えるための重要な表現なのです。
動画の活用法を学ぶことができる仕組み
動画を作れるようになっても、動画の活用法を理解しないと宝の持ち腐れです。
その点、私たちのオンライン講座は、みなさんを2つの点で強力にサポートすることができます。
(1)オンライン講座自体が、動画を活用した学びのデザインになっている。
この講座は、動画を参考に一人で学ぶことと、助け合って学ぶこととを組み合わせることで、相乗効果を生み出して学べるデザインになっています。
コルブの経験学習サイクルをイメージしてください。
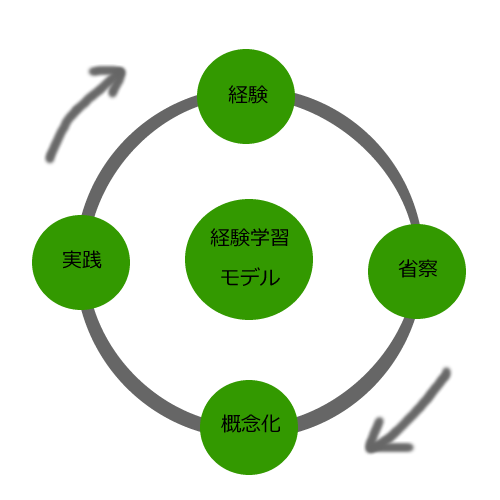
実践 : 解説動画などを見ながら、まずは、下手でもいいから作ってみます。
経験 : すると、できたところと改善したいところが出てきます。
省察 : どうすればうまく作れるのかを考えるときに、一緒に学んでいる人の実践を参考にするのがとても役立ちます。それを見ながら、自分の作業を振り返っているうちにいろいろな気づきがあります。
概念化 : 周りの人の活動をヒントにして、次は、こうやってみようという考えが生まれてきます。
実践と経験の段階では、動画などを見ながらマイペースで制作活動を進めていきます。
省察と概念化の段階では、学びの友の存在がとても役立ちます。
それぞれが、全く違うタイプの動画を創っていたとしても、違うからこそ、お互いに参考にしたり、アイディアを盗み合ったりして、協力して動画作成のスキルを上げていくことができます。
動画を教育に利用したいと考えている人にとっては、このような講座デザインを学習者として経験することは、かけがえのない経験になると思います。
(2)全国に学び合える仲間を作ることができる
私たちのオンライン講座は、約20名の運営チームにより進めていきます。その中には、動画を使った実践をしている人が多数おり、交流することで多くの具体的、実践的な取り組みに触れることができます。
さらに、オンライン講座で上記のような学び合いのメカニズムを理解し、協力し合える関係性を気づいた仲間は、講座が終わっても学び合いを継続することができます。
それぞれが自分の現場で動画を使った実践を行い、様々な経験をし、学びの友と共有することで刺激し合って省察や概念化を進めていくことで、動画を使った実践を講座が終わっても深めていくことができるでしょう。
新しいオンラインでの学び方
反転授業の研究は、参加型のオンライン講座という新しいジャンルを切り開きました。
一般的には、オンライン講座は脱落率がとても高くなります。
しかし、「反転授業の研究」が運営するオンライン講座は、学習者中心の考え方に基づき、様々な工夫をしており、過去10回の講座では、修了率が90%以上(そのうち4回は脱落者ゼロ)という驚異的な修了率を達成しています。
世界最高の教授陣を揃えたMOOCsの講座の修了率が、わずか7%だということを考えると、90%以上の方が最後までやり遂げるオンライン講座というのは、まさに奇跡の講座です。
その秘密は、双方向のコミュニケーションを十分にとりながら学ぶところにあります。
オンラインであっても、受講者同士、受講者と運営チームのコミュニケーションの機会が十分にあり、講座に関わる人同士でしっかりと知り合うことができます。
励まし合って学ぶ仲間がいることで、やりがいが生まれ、脱落しない仕組みになっているのです。
講座は、Moodleと呼ばれるプラットフォーム内に作られたフォーラムでの非同期の学び合いとWeb会議室Zoomを使ったリアルタイムセッションから構成されます。
Web会議室を用いたリアルタイムセッションは、講座開催中に全部で5回行われ、ここでは講師によるレクチャーや、小グループでのワークなどを行います。
Zoomを使ったグループワークの様子 ※写真は「ファシリテーション・コーチング講座」のときのものです。
Web会議室Zoomを使ったワークの後、課題をDropboxへアップロードして共有します。Moodleは、受講者全体の情報共有とチームごとのコミュニケーションの場として利用します。チーム内で相互にコメントし合って助け合ったり、他のチームの様子を見に行ったりしながら、お互いに参考にしながら進んでいきます。
その他に、週に1度、オンラインの雑談部屋を開きます。まじめなリアルタイムセッションとは違って、飲み物を用意して、リラックスした気分で参加す る雑談部屋では、笑い声が溢れ、本音トークが飛び交います。同じ講座に参加している受講者同士で交流できることもこのオンライン講座の魅力の一つです。

※写真は「ファシリテーションスキル入門」のときのものです。
このオンライン講座は、オンラインであっても、「会っている」「参加している」という実感を感じることができます。
その結果、これまでの講座では、講座終了後も受講者同士の関係性が継続し、多くのコラボレーションや、オンラインの学習コミュニティが生まれています。
オンライン講座から生まれる人と人との繋がりという副産物も、この講座の大きな価値と言えます。
この講座を学ぶことで得られるもの
・プレゼンにおける演出幅が広がります。
・商品説明または授業における効果的スライドアニメーション作成が出来るようになります。
・反転授業で使用する動画を作成できます。
・マニュアル/商品説明/自己紹介動画を自分で作成出来るようになります。
・iPhone/iPadでここまで出来るのか?!と驚いていただけます。
・仕事や趣味の幅が広がります。
・動画を使った学びのプロセスを体験できます。
・全国に学びの友を作ることができます。
私たちの想い
ICTによって教育を変えたいと考えて活動しているSensei TIPSと、トップダウンで降りてくる管理の矢印を「反転」させ、学習者中心の学びを実現するために活動している反転授業の研究の想いが重なり、この講座が生まれました。
講師の住ノ江さんが人生を賭けて取り組んでいるiPadを使った実践が、反転授業の研究が独自に生み出したフラットで自由な学び空間の中で受講者に分かち合うことができたら素敵なことだなぁと考えています。
フラットで自由な学びを実現するためには、運営者がガチガチに場を管理するのではなく、場から生まれてくる流れに沿って動いていくことが必要です。
この場に想いを持って参加してくれる方の熱量によって、この講座は生き物のように動いていくものになるはずです。
私たちは、約20名の運営チームを結成し、みなさんの参加をお待ちしています。
一緒に化学反応を起こし、素敵なドラマを起こしていきませんか?
講師・運営チーム紹介
講師:住ノ江修
iPad/iPhoneのダウンロードしたアプリは2000以上。
寝る時以外はiPadを常に持ち歩いている。
初代iPadに出会ってからソフトバンクの代理店においてiPadコンサルタントとして業務を行い幅広い業種にiPadを導入し研修を行う。
導入に関わったiPadの台数は3000台以上。
実施したiPadセミナーは200を超える。
現在は私立小学校のICT教育室 室長として教職員にICT及びiPadの研修を行い授業における効果的なICT活用実践及び提案を行っている。
またiPadによる電子教材・動画を作成を行い作成指導を積極的に行っている。
運営統括:平野貴美江
運営統括の平野貴美枝です。
関西にある私学の中高一貫校で英語を教えています。また、今回コラボさせていただくSensei TIPSの共同代表もさせていただいております。Sensei TIPSは元々、全国の先生方のICT活用の困り事を解決したい、という想いから生まれました。誰がいちばん困ってるかというとそれはわたしです笑自分が困っているので自分で団体を作りました。
英語はICTとの親和性が高く、単純に黒板に本文をプロジェクターで映すだけでも授業が効率的、また効果的になります。また、外国のことを学ぶためには生徒がイメージしやすいような画像や動画も必要不可欠です。
…とは言っているもののわたしも試行錯誤しながらの授業実践を繰り返しており、決してICTにも動画作成にも精通しているわけではありません。現在、文法の解説動画を作っていますが、これはパワーポイントのスライドとzoom(今回使う革命的WEB会議システムです)の録画機能を合わせた簡単なものです。i phone/i Padには優秀なアプリが多くあり、できればそれですべての授業をしたいと思っています。
オンライン講座は受講者として、また運営として何度か参加させていただきました。今回は統括ということで大変緊張しております。
みなさんに安心安全の学びの場を提供するとともに一緒に学んでいけたらと思っています。わたしができればみんなできますよ!
プロデューサー:田原真人(反転授業の研究主宰、オンライン教育プロデューサー)
早稲田大学の博士課程で生命現象の自己組織化やカオス理論について研究。大学院時代に価値観が大きく転換し、大学院を中退して物理の予備校講師になり、河合塾などで10年以上教えました。2004年から物理ネット予備校(フィズヨビ)を立ち上げ、動画講義やMoodle、Web会議室を使ったオンライン教育に取り組む。学びエイドでは、鉄人として「動画を使った学び方」というコースを担当しています。
2012年から始めたオンラインコミュニティ「反転授業の研究」の活動を通して、自己組織化、オンライン、教育という3つのキーワードが自分の中で結びついたことで、オンラインにコミュニティを自己組織化させて教育にパラダイムシフトを起こしていくことに使命感を感じるようになりました。「反転授業の研究」は、現在、約3800名まで増え、様々な活動が自己組織化しています。
今までやってきたオンライン講座運営&プロデュースの経験を生かして、みなさんが充実した学びを体験できるように支援していきますので、よろしくお願いいたします。
運営:中山涼一 (未来学校プログラミング教室代表・SenseiTIPS Founder)
中国上海出身。97年来日。2001年大学卒業後、販売管理・財務管理システムの開発を2年間担当しました。2003年帰化後、中国語会話教室設立、反転授業を取り入れながら社会人向けの中国語を教えました。2015年、12年間運営してきた中国語会話教室を閉め、大阪初小中学生向けのプログラミング塾「未来学校プログラミング教室」を設立、現在小中学生にゲームやアプリ制作を通して、プログラミングを教えています。さらに中高生にはiPhoneアプリやWindowsアプリケーションの開発も教えています。近年日本でもプログラミング教育が注目され、多くの学校は積極的にプログラミング授業を取り入れようとしています。現在小中学校への出張プログラミング講座も増えてきました。
さらに2015年教育支援団体SenseiTIPSを設立、先生向けのICT支援活動も始めました。デジタル教材の制作やプログラミングの応用などのセミナーを定期的に開催しています。その中、今回講師を務める住ノ江先生のKeynoteの活用講座は大変ご好評をいただき、今後さらに本格的な教育支援を踏み出したいと考え、社団法人の設立を進めています。
今回住ノ江先生の動画作成オンライン講座で、受講生のみなさんの学習サポートができればと思い、運営スタッフとして参加させていただきます。みなさんと一緒に楽しい動画を作りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
運営:坂本保代
みなさま、こんにちは!運営の坂本と申します。
株式会社マイクロブレインという人工知能を得意とするソフトの会社に所属しながら、福祉の仕事と市内の小学校の臨時職員として掛け持ちで仕事をしています。反転授業の研究のグループでは、昨年度はWindows版「白板ソフト」の動画作成の講師をさせていただき、貴重な経験をさせていただきました。今回の運営は初めてでドキドキですが、どうぞ、よろしくお願いいたします。反転授業の研究のグループの皆様は、とてもアクティブな方が多く講座をきっかけに、実際にお会いして、交流も広がり、とても有意義な1年でした。オンライン講座は、年々バージョンアップされて、新しい学びを生み出し、沢山の出会いと共に、日々刺激を受けています。もちろん「keynote&imovie」を学ぶことでiPad,iPhoneの活用が大きく拡がることに加えプラスαで、新しいオンライン講座の仲間も増え、一緒に学べ、毎日が充実する楽しみは、経験した人だけが得られる素晴らしい体験だと思います。
共に学びを広げていけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!
運営:永島宏子
皆さん、こんにちは。
キャリア教育コーディネータの永島宏子と申します。
栃木県出身で、大学では化学を学んでいました。
卒業後、制御機器メーカーでエンジニアとして働いていましたが、双子の出産を機に退職し、10年間専業主婦で過ごしました。
子育ての中で、PTAの役員を経験して、教育に関心を持ち、キャリア教育の勉強を始めました。
今は、探求型のキャリア教育プログラムの開発販売を行う会社に勤めています。
昨年Zoomで田原さんに出会い、以来様々な素晴らしい出会いを経験して大変刺激を受け、これからの歩む方向を探しているところです。
今回の講座では、運営という位置づけですが、iPad、iPhoneは全くの初心者です。
かなり不安ですが、プロの先生方の教えをしっかりマスターして、サクサク動画が編集できるようになりたいと思っています。
皆さんと一緒にチャレンジできたらうれしいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
運営ボランティア
反転授業の研究が運営するオンライン講座では、受講者として学んだ方たちが、運営ボランティアや運営者、講師になり、役割を変えながら、様々な学びを生み出しています。
オンラインの場での学び合いを体験した方たちが、運営側として場創りに加わってくれることで、オンラインの場の熱量が上がり、自己組織化が再現されやすくなります。
運営ボランティアのみなさんとの交流も、この講座の価値の一つです。
青木芳恵
ボランティアスタッフの青木芳恵です。普段は神戸六甲山にある探究型オルタナティヴスクール「ラーンネット・グローバルスクール」のナビゲータとして、子ども達が本来自ら持っている「学ぶ力」を引き出す場作りと授業を行っています。人が感じる小さな「あ」や「お」というスイッチを、言語非言語問わず形にしていくという学び方に心惹かれています。
学びが多様化する中で、動画が持つ意味は実にさまざまです。反転学習や授業教材としてインプットの入り口となる動画はもちろん、自分の学びのアウトプットとして「動画で伝える」ことも珍しくなくなってきました。どう伝えるか?どう伝えるか?どう可視化するか?この講座を通して、私もともに学んでいきたいと思っています。
ラーンネット・グローバルスクール
http://www.l-net.com
大隅紀子(日本語教師)
今回ボランティアをさせていただきます大隅紀子です。千葉にある大学で留学生に日本語を教えています。
昨年からオンライン講座で色々学び始め、世界が広がっていくのを感じています。動画作成は初心者ですので皆さんと一緒に動画作成ができるようになりたいと思っています。初心者目線で講座をサポートさせていただきます。。
オンライン講座は、その内容だけでなく、地域を超えた人と深くつながるという魅力もあります。楽しみながら一緒に学びましょう。よろしくお願いします。
川上 政嗣
運営ボランティアをさせていただきます、川上 政嗣と申します。福岡県立高校で国語の教員をしております。
現在、生徒の頭脳をアクティブに動かす授業作りに頭を悩ませています。その中で、オリジナルの動画作りは手段として有効であると思っています。
私は自分のITに関するスキルはかなり低い方だと自覚しています。テクニカルなサポートはできませんが、皆さまが快適に学べる環境を作るために陰から支えることができればと考えています。
皆さま、これから始まる学びの旅にどうぞご一緒しましょう!
倉本龍
倉本龍(くらもとりょう)といいます。滋賀県にある私学中高で教員をしています。
iPadやiPhoneは公私問わず長年利用しています。
特にkeynoteやiMovieは直感で操作できる部分が多く、PCでの編集に戻れなくなるほど簡単に作ることができます。
運営ボランティアとして、様々な面でみなさまのサポートをしたいと思っています。
よろしくお願いします。
佐藤正憲
今回ボランティア参加させていただきます佐藤正憲です。公立高校で情報科を教えています。田原さんの動画作成講座では2年前から「Explain Everythngで作る動画作成」「パソコンで作る!カンタン動画講義の作り方」に生徒として参加していました。どちらの講座も中でいろいろと発見があり、それを発表することで共有があり、講座全体が非常に楽しいものとなりました。主体的に学ぶことの楽しさをまたこの場で共有できれば、そしてその手助けをできれば幸いです。必要なものは好奇心(とちょっとのデバイス)だけです。
一緒に学びましょう!
筒井洋一
30年間、大学教育に関わってきました。当初は、ドイツ国際政治を専攻していました。
その後変転を重ねて、1993年から、大学初年次教育で日本語表現法の代表を務めて、地方の国立大学から挑戦をおこなってきました。1995年から、インターネットを使って、ドイツの大学と私がいた富山大学の演習とでネット授業を計5年間おこないました。
2006年頃から、ファシリテーションやコーチングを学び、その後の大学改革の基礎を築きました。
2013年から15年まで、大学の授業に毎週見学者と授業ボランティアが関わり、かれらが授業を創る試みをしてきました。
それに関する本を出版しました。これまで筒井が取り組んできた授業動画は、以下です。
2013年前期、京都精華大学「グループワーク概論」
https://youtu.be/-Vm6p50-QX8授業関係者と一緒に以下の書籍を出版しました。
筒井 洋一、山本 以和子、大木 誠一編著
『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業―新たな協働空間は学生をどう変えるのか』
東信堂、2160円
http://amzn.to/1RPt9KS
松嶋渉
山口県の公立高校で教員をしています。教科は商業で主に情報系(プログラミングやWebデザイン)の授業を担当しています。動画を使った授業を科目や単元に合わせて学期に数回実施しています。授業動画作成ではWindowsPCではCamtasiaやScreencast-O-Maticなどを使用し、タブレットではiPadのExpiainEverything,iMovieを使用して作成しました。
一昨年の2月に行った反転授業の感想を生徒同士のインタビュー形式にして撮影しiMovieで編集しました。
現在は萩商工高校の情報デザイン科で「キャリア教育×ICT×地域活性化」をテーマにしたPBLを行っており、昨年度からはサイボウズのkintoneを利用した「学校を越えた強いチーム作り」を目指して取り組んでいます。
今回はiOSでの動画作成講座と言うことでkeynoteやiMovieなどを楽しく作って行きたいです。今回はボランティアスタッフとして参加いたします。受講生の皆さんの助けになれるように取り組んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
松谷愛
運営ボランティアの松谷あいです。奈良県でユニークな英会話スクールをしています。
ユニークポイントを3点。
①英語の先生を育てる講座をはじめて6年目突入です。
②たったの1か月で発音がネイティブ並みになれること。英語のスピーチやプレゼンテーションをされる方に大人気です。
③入場制限ポリシーあり!夢を語らないと入会できない「あつらえコース」その夢のために、一人一人のレッスンをオーダーメイドであつらえます。
上記、全てのコースで、反転動画教材を用いて、②と③は、オンラインでも受講可能です。
教室名は、ハヤ イングリッシュアカデミー。
実は、名刺を渡すたびに、いつも同じ質問を受けます。
「なんでハヤ イングリッシュアカデミーなんですか?」
このネーミングをしたのは、「ハヤシ」でもなく、「ハヤオ」でもありません。「すみだ」です。
ハヤ = 88 = 早 = 速 = 流行(る)
縁起のいい末広がりの8
早(ハヤ)く上達する工夫が盛りだくさん
講師の話す英語が速(ハヤ)い
今、一番流行(ハヤ)りの英会話スクール
まさかっ、ダジャレだったの?!
“どこよりも早く上達できる英会話スクール”を作ろう♪
8年前、そんな想いを込めてちょっとダサいネーミングをしました。
そして、88(ハヤ)の8を横にすると、∞無限(infinity)。
どんな人にも、そしてどんな組織にも無限の可能性があると信じております。その可能性はエネルギーによって引き出されます。本講座の場のエネルギーを高める意ために、一生懸命学びの伴走をさせていただきます。
加えて、大好きな動画作成をサポートできるということで、勝手に気合が入っております。
↓ 私の動画作品は、“HAYATube”をご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCZ6bLwpJDIKuLakalbAXVGw
それでは皆さまにお会いできること、楽しみにしております♪
松本一見
今回ボランティアとして参加します松本一見です。クラス内で行えることの限界を感じ、何かいい方法がないか探っていくうちに反転教育に興味を持ちはじめました。
反転教育に欠かせないものの一つに動画があります。私はICTスキルがそれほどないので重い腰がなかなか上がらなかったのですが、反転教育の研究グループやオンライン講座で知り合った方々の実践に感銘を受け、簡単な動画を作り始めました。まだまだ作成に時間がかかりますが、できたときの嬉しさはもちろん、作った動画を繰り返し見て勉強してくれている学生を見るとやってよかった、次も頑張って作ろうと意欲が湧いてきます。
今回の講座は「リンゴ」のツールを使って、初心者でも簡単にできる動画作成の方法を学びながら、講座受講生、ボランティアと一緒に動画や実践のディスカッションも行えるものになっています。講師の動画作成の知識の豊富さはもちろん、ボランティアにも日常的に動画を作成し、使っている教師も多いので、きっといろいろな刺激を受け、それが次のアイデアに結びつくことと思います。
動画を作って授業などに実践してみたいけど…と躊躇している皆さん、この機会に私たちと一緒に動画作成と実践について学び合ってみませんか。きっとワクワクする新しい世界が広がるはずですよ!
武藤哲司
武藤哲司と申します。群馬県の私立校で教員をしています。日本の生物学と国際バカロレアの生物の授業を担当しています。また校務分掌として情報管理者をしています。これまで、参加者でお世話になっておりましたが、初めてボランティアスタッフとして参加させていただくことになりました。皆さんの学習のお手伝いをする中で、すこしでもお力になれればと思うと同時に、共に学び、もりあげることの出来る一員でいたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
私自身の実践としては、動画とEducanonなどのオンライン教育システムを組み合わせた授業デザインを模索しています。PPT, Keynote, Prezi等は日常的につかっており、動画作成ではiPadのShowMe, Educreationsを使用して作成したことがありますが、なにぶん腰を据えて研究する時間がとれず、広く浅くつまみ食いして中途半端だと自身でも感じております。今回の講座では、iOS、Keynoteの機能をしゃぶりつくすとのこと。なにがでてくるか、わくわくしています。
ワークショップ形式で学ぶオンライン講座
この講座は、解説動画、MoodleでのフォーラムセッションとWeb会議システムZoomによるリアルタイムセッションを組み合わせて、5週間(リアルタイムセッション5回)のオンライン・ワークショップ形式で行います。
【対象】
KeynoteとiMovieを使って動画講義を作れるようになりたい人
【受講前に準備していただきたいもの】
今回のオンライン講座はテレビ会議/Zoomをしながらお手元のiPhone*またはiPad*で操作していただきますので、下記の(1)と(2)を満たしている方のご参加をお待ちしております。
(1)iPad or iPhone
*iPhone(5以降) *iPad(第2世代以降)
KeynoteやiMovieといったアプリを使い、教材や動画を作成します。
Keynote・iMovieは事前にiPhone/iPadにダウンロードしておいてください。また、Moodleにモバイルからアクセスしたい方は、「Moodle touch」という360円のアプリを利用すると使いやすいです。
アプリダウンロード費用は受講者の方のご負担になります。講座費用には含まれません。
尚iPhone/iPadのOS及びKeynote/iMovieのバージョンは最新のものにバージョンアップしておいてください。
(2)パソコン(Mac or Windows)
インターネットに接続可能なパソコンをご用意ください。作成したKeynote教材をもとに動画作成するときに使用します。
また、Web会議室Zoomでのリアルタイムセッションのときに、iPad/iPhoneを画面共有して操作方法を確認し合うときにも利用します。
※iPad/iPhoneは持っていて、PCは持っていない方などは、動画化など一部の作業ができませんが、それ以外の作業は参加できます。詳しくは、お問い合わせください。
【講座の進め方】
6/5, 6/6 Zoomの接続テスト
講座スケジュールは、以下の通りです。
リアルタイムセッションでは、講師の説明を受け、その後、チームに分かれてオンラインで話し合います。
その後、Moodleのフォーラムを使い、1週間、チームで助け合いながら課題を作成し、作成した課題は、Dropboxへアップロードして全体で共有します。
第4回と第5回の間に2週間の制作期間を設け、チームで助け合いながら、講座で学んだことを生かして自由な作品を各自が作成します。
Q&A
Q リアルタイムセッションに参加できない日があるのですが大丈夫ですか?
A リアルタイムセッションは、翌日以降、録画動画が見れるようになりますので、そちらで確認していただくことができます。
Q パソコンが苦手ですが、サポートはしてくれますか?
A Dropbox、Moodle、Zoomの使い方については、動画マニュアルを配布しますので、それに従って操作してください。Keynoteでの教材作成や動画作成については、チーム内で助け合いながら進めて下さい。
Qリアルタイムセッションには、iPadから参加できますか?
AZoomは、iPadなどのタブレット端末や、スマートフォンから参加可能です。あらかじめZoomのアプリをダウンロードしておく必要があります。
QiPadは持っていますが、パソコンは持っていません。講座に参加可能でしょうか?
A第4週、第5週でKeynote教材を動画にし、その後、iMovieで編集して完成させます。iPadだけだとKeynote教材を動画にできないのですが、同じチーム内のPCを持っている人や運営チームが動画にする作業を代行することは可能です。それをご了承いただいた上で、参加いただくのであれば参加可能です。
QMacは持っていますが、iPadやiPhoneは持っていません。講座に参加可能でしょうか?
A講座で行う操作説明は、iPadのkeynoteやiMovieの説明になります。MacのKeynoteやiMovieは、操作画面が違うため講師はサポートすることができません。Macを持っている方同士の助け合いフォーラムなどを立ち上げて、自主的に問題解決していく形になります。その条件でよろしければ、参加可能です。
お申込み
講座名:iPad/iPhoneで作るカンタン動画作成
申し込み締め切り:2016年6月3日(金)
定員:40名 (定員に達し次第、締め切ります)
開講期間:6月7日(火)~7月12日(火)
※5週間の講座期間中にZoomによるリアルタイムセッションを5回行います。
リアルタイムセッションの日程:
第1回:6/7(火) 21:30-23:00 iMovie基礎/応用
第2回:6/14(火) 21:30-23:00 Keynote基礎
第3回:6/21(火) 21:30-23:00 Keynote応用
第4回:6/28(火) 21:30-23:00 Keynote補足・グループワーク説明
(オンライングループワーク)
第5回:7/12(火) 21:30-23:00 まとめ・振り返り
この他に雑談ルームを5回開催します。
受講料:37,800円(税込)

分割払いについては応相談です。質問がありましたらこちらからお問い合わせください。
熊本×反転G vol.4 〜東北のあのころは熊本のこれから〜 4/29
4/29(金) 21:00-22:30に実施しました。
東日本大震災の体験を共有する試みの第2弾ということで、宮城県にある東北学院中学校・高等学校教諭の名越幸生さんにお話をうかがいました。
東北学院中学校・高等学校教諭・名越幸生さん(1)
東北学院中学校・高等学校教諭・名越幸生さん(2)
熊本×反転G「支援を反転する〜熊本でこれから起こることを経験者に聞く会〜」4/25
4/25(月) 21:00-22:30に実施しました。
スピーカーは岩手県立花巻北高等学校校長の下町壽男さんと、陸前高田市で避難所運営をされている佐藤一男さん
前回のvol.2では、6名の熊本県在住の学校の先生が宇土市、阿蘇市、高森町、熊本市東区(益城の隣)などの現状を、写真や中継映像を交えて教えてくれました。
話す側・聴く側双方にとって貴重な機会であるとともに、「安心安全の場」とはこういうものか!と実感しました。
第3弾は東日本を時の話を聞いてみる会を実施しました。
この後熊本では、日常ではない日常生活が始まります。
何が起こるのか、 何をしてきたのか。
経験者にいろいろ聞いてみました。
1)岩手県立花巻北高等学校校長の下町壽男さん
2)桜ライン311(陸前高田市) 佐藤一男さん
熊本×反転G vol.2 〜地元の生活や状況を語ってもらう会〜 4/22
4月22日に、Zoomに集合し、熊本から地元の生活や状況を語っていただきました。
1)八代清流高等学校教諭の豊田拓也さん。
2)熊本市内高校教員の寺本幸信さん
3)翔陽高等学校教員井上梢さん
4)東稜高校教員豊永亨輔さん
次回は、4/25(月) 21:00-22:30
【zoom×kumamoto vol.3 〜熊本でこれから起こることを経験者に聞く会〜】
スピーカーは岩手県立花巻北高等学校校長の下町壽男さん。
第3弾は東日本を時の話を聞いてみる会を実施します。
この後熊本では、日常ではない日常生活が始まります。
何が起こるのか、 何をしてきたのか。
経験者にいろいろ聞いてみましょう!
以下のグループが主催していますので、興味のある方は、グループへ参加申請してください。
「熊本X 反転G 支援を反転する」フェイスブックグループ
https://www.facebook.com/groups/1184907291520560/
【対談】古新舜(映画監督)× 田原真人(反転授業の研究)
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
映画監督の古新舜さんと対談させていただきました。
古新さんとは、昨年、反転授業の研究グループで出会い、第3回アクティブラーニング・フォーラムでコラボするなど、縁を紡いできました。
古新さんとは、共通点が驚くほどたくさんあります。
古新さんが巣鴨学園で中学、高校生活を送っていたとき、田原は、数学の非常勤講師として勤務していた。
古新さんも田原も、早稲田大学理工学部応用物理学科出身
古新さんも田原も、物理の予備校講師になった。※古新さんは駿台予備校で、田原は河合塾。
というわけで縁の強さを感じているわけですが、今回、対談させていただき、改めて、価値観の部分でも共鳴し合うところがたくさんあることを感じました。
熊本×反転G 「支援を反転する」
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
熊本地震について、私たちにできることはないだろうかという想いから、4月18日の夜、倉本龍さんの発案でZoom対話が行われ、熊本と各地を繋いで2時間以上、話をしました。
熊本から、 溝上広樹さんと、 前川修一さんが参加してくださいました。
それぞれが、自分たちの想いとつながりながら語り、耳を傾け合い、様々なアイディアが出てきたのですが、始まってから1時間半ほどたったところで 筒井 洋一さんから出てきた「支援を反転する」いうアイディアは、反転Gで学び合ってきた自分たちの在り方を象徴するようなもので、そのアイディアが出てきたことで、視界が開けた気持ちになりました。
熊本に住み、福岡の高校で勤務する前川修一さんは、倫理の授業で「地震と人間」という授業を行ったそうです。
http://blog.ict-in-education.jp/entry/2016/04/18/171833
前川さんが勤務する明光学園高校には、熊本から通っている生徒もおり、生徒によって地震体験に大きな差があるそうです。
しかし、私たちがこのグループで学んできたのは、「違いは、学び合いのエネルギーになる」ということだと思います。
それを、この状況で、まさに実践された前川さんに心から感謝の気持ちを伝えたいです。
昨日のZoom対話でも、同じことが起こっていました。
熊本で地震を体験している人と、別の土地にいて直接体験していない人とが話すことによって、オンラインの場に循環が起こり、その場から、双方がエンパワーされるという感覚がありました。「発信することで、発信者の自己肯定感が高まり、エンパワーされる」というのは、アクティブラーニングの実践を通して、私たちが気づいてきた大切な仕組みだと思います。
溝上さんが、落ち着いた様子で熊本の状況を話してくださり、それによって、場に安心感が広がっていきました。また、そのことは、溝上さんをエンパワーすることにも繋がっているように感じました。
筒井さんのアイディアに乗って、「支援を反転する」というプロジェクトを始めたいと思います。
熊本からZoomで発信してもらい、それに耳を傾け、拡散していきたいと思います。
「違いは学び合いのエネルギーになる」が、もっと広い範囲で起こるように動きを起こしていきましょう。
2016年4月18日熊本より
(1) 前川さん所感(6:30)
(2) 前川さん・溝上さんの現地情報共有(4:13)
(3) 阿蘇地域の現地からの情報(12:49)
(4) 熊本県民愛(7:23)
学びのパラダイムの転換をコミュニティ・ラーニングへ拡張する
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
教える仕事をしている皆さんは、授業をつくるときに、どのような生徒像を想い描いていますか?
今、プロデューサーとして関わっている「YOU∞理論」の講座で、情報を発信していくペルソナを考えるワークをしているときに、ある気づきがありました。
それは、
僕は、かつて物理ができなかった頃の自分自身に対して授業をしている。
ということでした。
自分が乗り越えるのに苦労した「物理を学ぶ」という壁を、予備校の先生に手助けしてもらって超えることができ、そこに大きな感謝の気持ちがあるので、今度は、自分が手助けする側に回ろうということで予備校の講師になったんだなと気づきました。
そして、教える側になり、教え方を工夫しているうちに、自分の思考がどんどん体系化していって、効率よく教えられるようになりました。
学びの原理
ラーニング・ピラミッドで考えると、教えることが一番学習定着率が高いわけですから、毎日、大勢の前で授業をしている予備校講師が、教室の中で一番学習定着率が高い存在なわけです。(ラーニング・ピラミッドの正当性については、様々な考えがありますが、ここでは立ち入りません)
これを、抽象化すると、このように言うことができます。
自分がかつて超えた壁の手前に立ち止まっている人に対して、自分の経験をもとに手助けしていくと、自分の思考が体系化されていく
学びの原理からアクティブラーニングを考える
アクティブ・ラーニングというのは、「自分が超えた壁の上から、壁の手前の人が超えるのを手助けすることによって、自分が壁を超えたプロセスを振り返ってメタ化することができ、思考が体系化される」ということを学びの原理に置いているのではないかと思います。
教壇に立って教えている予備校講師の自分が、教室の中で一番学んでいたのであれば、そのような組み合わせを教室の中にたくさん作れば、生徒の頭が活性化し、生徒の思考が体系化されていくのではないでしょうか。
このとき、教師の役割は、ファシリテーターとして教室全体に目を配り、生徒のマインドを整えたり、学び合いが起こる組み合わせを作ったり、学び合いがうまくいっていないところを支援したり・・・ということになるでしょう。
このやり方には、とても良いところがあります。
アクティブラーニングを実践するとすぐに気づくのは、生徒の思考の癖は様々であり、自分にも生徒と同様に思考の癖があるということです。
自分と似た思考の癖を持つ生徒には、うまくアドバイスできても、自分とタイプが違う生徒にはうまくアドバイスできないこともあります。そのときに、様々な「壁を超えるためのアドバイス」を生徒同士で共有することで、様々な思考の癖を持つ生徒が、壁を超えやすくなるのです。
学びの原理をコミュニティラーニングへ拡張する
アクティブラーニングを通して、学習コミュニティの中に学びの原理が共有されていくと、ファシリテーターなしで自発的に学び合いが進んでいくようになります。
メンバーそれぞれが、自分が助けられそうな機会を見つけ、他の人を手助けすることで、自分の思考を体系化して学んでいくわけです。
壁の前で立ち止まると、あちこちから支援の手が伸びてきて、壁を超えると、支援した側から「学びの機会を与えてくれてありがとう。あなたのおかげで思考を体系化できました」という感謝の言葉が返ってくるという文化が定着すると、コミュニティ全体が学びに溢れて加速していきます。
これが、僕の考えるコミュニティ・ラーニングです。
コミュニティ・ラーニングが起こっている空間では、できないことがあることは、「恥」ではなく、「他人に学びのチャンスを与える機会」となります。
この空間は、Give and Giveが成り立つ空間です。
Give and Giveが成り立つと、学びが泉のように湧き出し、学びは加速していくはずです。
このようなことは、単なる夢でしょうか?
僕は、そう思いません。
「反転授業の研究」では、すでに、コミュニティ・ラーニングが起こり始めています。
それを体験した教師の皆さんが、教室を変えていったとき、世界のあちらこちらでコミュニティ・ラーニングが起こり始めるはずです。
プロジェクトや組織の中でコミュニティ・ラーニングが生まれれば、その結果として価値創造が起こりやすくなるでしょう。
そうなれば、もっと自由に、もっと楽に、もっと豊かに生きられる社会が現れるのではないでしょうか。
第22回オンライン勉強会「教師も学ぶ!生徒も学ぶ!」
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
第22回反転授業オンライン勉強会は、兵庫県内の私立中学校高等学校で国語を教えていらっしゃる内橋朋子さんにお話しいただきます。
内橋さんは、分野横断型の総合学習に長年取り組まれていて、現在は、アクティブラーニングも実践されています。
日時:3/16(水) 21:30-23:00
場所:オンラインルーム Zoom
参加費:無料
登壇者:内橋朋子さん
タイトル:教師も学ぶ!生徒も学ぶ!
※第2部では、ビデオチャットを使ったグループワークを行いますので、ビデオチャットの用意をお願いします。ビデオチャットの用意をされていない方は、メインルームでテキストチャットによるコメントでの参加となります。iPadやiPhoneからの参加も可能です。
教師も学ぶ!生徒も学ぶ!
(プロフィール)
兵庫県内の私立中学校高等学校の国語科教諭
神戸大学教育学部国語科卒業
今年度4月に高校1,2年生の生徒全員にiPadを採用したのを機に、オンライン動画作成講座を受講。そこで動画作成の方法のみならず、学び合うことの豊かさに触れたことから、この「学び」を教室での自分の教科の授業に取り入れたいと思うようになりました。
SNSなどもっての外と思っていましたが、Facebookで多くの先生方からいろいろと教えていただき、また実際にもお会いする機会にも恵まれ、今までただ目の前の生徒に対応するために行ってきたことと、今取り組もうとしているアクティブ・ラーニングとのつながりも見えてきました。
これらのことは自分一人あるいは、自分の学校の中にとどまっていては起こりえなかったことで、自分も発信し、周りの方の考えにも影響されて、明日の自分ができあがっていくのだという思いを強くもっています。生徒のアクティブ・ラーニングを日々考えていることが、教師のアクティブ・ラーニングにつながっています。いえ、逆かもしれません。教師がアクティブ・ラーニングの学びを体験することが、生徒のアクティブ・ラーニングにつながっていくのかもしれません。たった1年の間に私に起こった変化とその奥にある今までの取り組みなどもお話できればと思っています。
(参考)
総合学習からALへ精神は受け継がれていく!内橋朋子さんインタビュー (パスワードはグループ内で公開しています)
キャリアガイダンス「教科・行事・特別授業を結び付け、隣人愛を持って社会に貢献できる力を育成」
お申し込み方法
(1)このページからお申し込みください
(2)自動返信メールに参加方法が書いてありますので、指示に従って参加してください。
※自動返信メールの内容
●●様
反転授業オンライン勉強会、運営担当の田原真人です。
このたびは、勉強会にお申し込みいただき、ありがとうございます。
日時 2016年3月16日(水)21:30-23:00※21:00からルームをオープンします。
第1部 スピーカー 内橋朋子さん
第2部 オンライングループワーク
ビデオ会議に参加できる用意(マイク&Webカメラなど)を
ご用意ください。
当日は、Zoomというビデオ会議室を使用します。ルームURL
(メールでは、ここにURLがあります)Zoomの使い方については、以下の記事を参考にしてください。
(1)パソコンからアクセスする場合
http://zoom-japan.net/?p=54(2)iPad or iPhone、その他、スマホの方
http://zoom-japan.net/?p=17※PCからだと、ルームURLをクリックするとインストーラーが自動的に
ダウンロードされ、それをクリックすると自動的に繋がります。※何も始まらないときは、「downloard & run zoom」を
クリックしてください。※iPhoneやiPadからの場合は、Meeting IDの入力を求められますので、
(メールでは、ここにMeeting IDがあります)
を入力してください。※お願い【重要】
第2部のグループワークでは、ZoomのBreakroom機能を利用しますが、
アプリが最新版であることが必要です。以前にZoomアプリをインストールされている方は、
最新版に更新しておいてください。
最新版へのアップロード方法はこちら
http://zoom-japan.net/?p=110
それでは、当日お会いできることを楽しみにしています。
田原真人
info@flipped-class.net
保護中: YOU∞理論(分割)
対談動画:ブリッジの田中力磨×反転授業の田原真人
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
生徒の主体的な学びを促す教師にとって、一番大切なのは「在り方(Being)」ではないでしょうか?
しかし、「在り方(Being)」というものは、とても捉えにくいものです。
いったいどのようにして「在り方(Being)」について考えればよいのでしょうか?
また、教師の在り方は、生徒にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
滋賀県で専属コーチ・ブリッジという教室を開いている田中力磨さんは、在り方(Being)にずっとこだわって、生徒と接しています。
今回、Zoomで対談させていただき、お互いの考えていることをオープンにした結果、様々な気づきがありました。
iPadの達人!住ノ江修さんインタビュー
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
学校にiPadなどのタブレット端末が入ってくるようになり、個人でも所有している人が増えていますが、僕を含めて多くの人は、iPadのポテンシャルのうち、ほんのわずかしか引き出していないのではないでしょうか?
ホワイトボードアニメーションについて作り方を調べていたときに、住ノ江修さんのYoutube動画を見て、「iPadアプリだけでもできてしまうのか??」と驚きました。
それで、住ノ江さんがiPadで作成した動画などを見せてもらうと・・・・
驚きの動画の数々。
鼓動するメタルも。
iPadを使ったプロジェクションマッピングまで。
iPadが広げる予想をはるかに超えた驚きの世界がそこにありました。そこで、iPadの達人、賢明学院小学校ICT教育室長、住ノ江修さんにインタビューさせていただきました。
映画監督になりたかった大学時代
―― iPadで作られているものを拝見して、びっくりしているんですけど、すごいですよね。
オタクというか、マニアというか(笑)。初代iPadが発売されてから、iPadに関わることがありまして、もともと映画監督になりたいという気持ちがあったので、いじっているうちにどんどんはまっていって、iPadのおかげで、今の仕事にも就けているんです。
―― 映画監督になりたかった頃からiPadまでまっすぐ繋がってきたんですか?それとも、いろいろな紆余曲折があったのですか?
映画監督になりたい気持ちは、いったん落ち着いて、普通の大学生活を送りました。大学は、関西学院大学なんですけど、そこには、8mmフィルムを使った自主映画のサークルがあったんです。関西で自主映画で有名な私学といったら関学だったので、行ったんですよ。
―― へぇー、それは、全く知りませんでした。そこにアンテナが立っている人からすれば、「関学に入ったら自主映画やれる!」みたいなことになっていたんですね。
そんな感じがあったんです。親が専門学校じゃなくて大学へ行けという感じだったので、関学のすべての学部を受けて、商学部だけに補欠合格したんです。高校では、偏差値がクラスの中で低いほうで、先生も僕を見捨てていたんですけど、突貫で勉強したら、何とか転がり込めたんですね。
それで、映画を何年か撮ってました。
その他に、大阪に海遊館という水族館があるんですけど、そこで、夜だけ映画を上映する海遊館シアターというのがありましてそこで映写技師のバイトをしていました。もうお亡くなりになりましたけど、ジャック・マイヨールさんを描いたフリーダイビングの映画の「グランブルー」という映画のイベントで来ていただいたりしました。
転職を繰り返していたときにiPadに出会って人生が変わった
―― 映画を仕事にしようとは思わなかったのですか?
自分の映画の才能のなさに挫折しまして、普通のサラリーマンになることにしました。
新卒で通信事業者のツーカーホン関西に1995年に入社しました。ちょうど携帯の自由化が始まった年でした。同期はレベルの高い人ばかりで、大学もそうですけど、ラッキーで転がり込んだので、周囲についていけず落ちこぼれていきました。ツーカーホン関西で10年程勤めて逃げるように転職しました。
逃げの転職ですから上手くいくわけもなくその後、転職を何度も繰り返し社会的にドロップアウトしかけたんです。
―― その難しい状況から、どうやって抜け出したんですか?
そうこうしていると関西の大手塾に2010年にご縁があって、そこに教務課長として入りました。
その年、iPadが出たときで、印刷物とかイベントとかの管理が紙の手帳では追いつかないので他の人がiPadを使っているのを見て、「ええな!」となって、iPadを使い出しました。iPad関係のアプリは2000以上ダウンロードして、仕事の工程管理とかをしているうちに、iPadに詳しくなりました。ですがその職場で、3か月くらい多忙できちんと休みが取れない日が続いたりとかしまして、身体を壊す寸前まで働きづめの時期があったんです。
そのころ、関西にあるソフトバンクの大手代理店が、iPadの法人向けのコンサルや教育ができる人が欲しいということで、声をかけてくださって、そこで3年ほど、法人向けにいろんな業種に対してiPadってこんなことができますということをお伝えし提案営業をしていました。
医療系、教育関連、営業、流通関連、物流とか、幅広い業種に関わり業種別の分析をして、アプリや業務改善提案を行いまた導入セミナーをしてきました。3年間で大小合わせるとセミナーを200回以上やっていたと思います。
ソフトバンクさんの汐留の本社で100人規模のセミナーもやらせていただいたこともありました。
―― 教育分野には、どのような経緯で関わるようになったのですか?
そのソフトバンクの代理店から、今勤務している私立の賢明学院にiPadを200台納めていた経緯があって、今度新しく小学校にiPadを導入するので、先生方へ3日間の研修依頼を受けて研修を実施しました。その研修きっかけで、向こうからお誘いのお声をかけていただき移りました。
所属としては、賢明学院小学校のICT教育室で室長というのをやっているのですが、学校だけにいると、ノウハウが溜まっても、他に共有できないので、賢明学院小学校の中にある子会社に所属して、賢明に派遣されているという形にしてもらっています。週の3日~4日は賢明にいて、残りは、他の学校や会社に提案や営業を行っています。
元々、独立したいという気持ちがありましたので、今の形になっています。現場で培ったノウハウを蓄積してKeynoteで教材を作ったりとか、いろんな授業で事例を蓄積し、最近では大阪教育大学の学生さん向けにICT特別講義をやったりしています。
今、僕が実践蓄積してきたノウハウを共有しないともったいないなという気持ちがすごくありまして、社団法人を立ち上げて先生向けのICTのコーチングをするような場を創るのと、教育者を目指す大学生に対して講座をやってあげたいという思いがすごくあります。
今は、そのような活動をしながら、趣味と実益を兼ねて、映画が好きなので、コマ撮りをやったりしています。このようなことをiPadだけでできるんですよということを見せられるとインパクトがあるみたいです。
一点突破して道が開けると、すべての経験を生かせるようになる
―― 住ノ江さんのキャリア形成の流れは、面白いですね。計画していけないものですよね。突き進んでいくと、誰かが見つけてくれて導いてくれてという繰り返しですよね。
なんなんでしょうね。僕も最初のツーカーホン関西にいたら安定していたと思うんですけど、そこからドロップアウトして、職を転々としていて、すごく自分に自信がなかったんですね。ですがiPadに出会って、「これは、すごい」と思ったんです。僕みたいなシステム音痴の人間でも、ここまで可能性を広げて、人に語れるくらいになれるんですね。自分の生涯のパートナーに会ったような感じです。
これを、もっと極めていきたいと自然に思いソフトバンクの代理店の頃,営業の仕事を終えて、11時ころに家に戻ってきてから深夜2時、3時まで、翌日の訪問先のお客様へのiPad提案資料を作ったりとか、そういうことをやっているうちに、自分の引き出しがどんどん出来ていってiPadセミナーなど出来るようになってきました。
そうしているうちにいろんな方からお声をかけていただいて、ご縁が広がり、教育業界というやりがいのあるところに現在関わらせていただけるようになって、とてもありがたいと思っています。
―― 僕も、ドロップアウト組なので、分かりますね。僕の場合は、ゼロになってしまったときに、目の前のことにがむしゃらにやっていったら、手持ちの札が何枚か持てるようになってきて、その組み合わせでいろいろなことができるようになっていきました。反転授業と出会ったときは、今までやってきたことがすべて結びついてきた感覚があって、自分は、ここに来るためにいろんな経験を積んできたんじゃないのかという感覚がありました。住ノ江さんが、iPadと出会ったときも、そうだったんじゃないかなって思ったんですけど、いかがですか?
それは、ほんまにそうです。僕は、ツーカーホン関西を出てから、塾が母体の会社に転職し社会人向けのICTとかWebデザインの専門学校で働いていたんです。入ったとたんに半年後に部門を閉めると聞かされ、システム会社に移ったんです。システム会社では、メーカーさんに人を派遣する形なんですけど、システムの考え方が身に着きました。家を買った直後に東京転勤になって戻ってこれないかもしれないって言われて、転職して、物流センターでデータベースはこうなっているんだって経験させてもらって、その後、先ほどのiPadに出会った関西大手塾に行きついたんですね。
肉体労働もしたし、いろんなところを転々としてきたんですけど、転職しだした年齢が33とか34とかなので、世間的に厳しいじゃないですか。
でも、どうしてそんな年齢で転職できたかということを分析すると、転職活動の面接前に面接を受ける業界のことを徹底的に調べて、この会社に入ったらこのようなことをしたいという具体的なプラン案や新商品の提案書を作成して行ったのが良かったようなんです。
ソフトバンクの代理店に入って法人営業をするときに、いろんな業種にiPadを提案する時にその転職活動時のいろんな業種を勉強していた経験がとても役立ちました。お客様のところにiPad提案に行ってる時にお客様から
「住ノ江さん、流通で働いていたの?」
「業界常識を何故知ってんの?」という話になるんですよ。こんなそんなでいろんな業種にご縁をいただいて医療機関から開業医向けiPadセミナーのご依頼を受けたりしています。最近、医療系の法律が変わって、テレビ電話等による遠隔診療が認可されたらしいんですが、お医者さんとつながりのある商社さんから相談を受け、テレビ会議システムのZoomを紹介し遠隔医療実施の提案をしようとしてます。僕の頭の中では、海外に家族で住んでいる人で、現地医療受診が不安な方に遠隔で医療相談に乗ったりとか、過疎地の医療に役立てたりとか、いろんなことができそうだって思っています。
iPadから僕の世界がどんどん広がっています。田原さんと同じで、一本突き抜けると、道がバタバタっと開けていっていることを、今、すごく感じています。
―― 開けていくと、今まで使えていなかった中途半端なリソースも、組み合わせて使えるようになるんですよね。
そうそう。ジャンクかなって思っていたものが、価値を持ち始めるんですよね。
僕は、Youtubeの動画でコマ撮りやってますけど、それを見て、声をかけてくださる方がいたりします。
一生懸命やっていたものは、無駄にならずに、後で良い意味で繋がるんですよね。
仕組み作りの発想が、仕事に余裕と創造をもたらす
―― 住ノ江さんは、転職のときに、業界のことを分析して、普通の人がやらないレベルまで準備して行ったりしていたわけですよね。日常の業務も、大変だけど、あと一歩進めて、仕組みを作るところまでやれば、成果が大きく変わってきますよね。
僕も、予備校講師をはじめたときに、こんなに予習と授業に明け暮れていたら、いつまでたっても自由な時間が創れないと思いました。それで、一度解いた問題の解答プリントをスキャンして電子化し、テキストを作るための問題を2000題くらいTexで入力して、それらをデータベース管理しました。問題番号を並べてコンパイルすれば、予備校のテキストと解答プリントがプリントアウトされて、ほとんど予習しなくてよいという仕組みを作ったんです。データーベース化する過程で、副産物として、大学入試の物理の出題傾向や出題頻度、難易度が頭の中に入って、模試の問題なども難易度に合わせてすぐに作れるようになりました。それを5年目までにやったことで、時間的にも余裕ができて、本の執筆をしたり、フィズヨビを始めたりすることができたんです。そのときは大変ですけど、長期的に考えれば、仕組み作りをしたのが大きかったです。
その通りですよ。現場を見ていると、学校の先生って忙しいんですよね。保護者対応があったり、問題を起こした生徒への対応があったりとか。ただ、今まで、中小企業で仕事をしていて、業務改善をやっていて思ったのは、ちょっとがんばってエクセルで表を作るだけでも全然違いますよね。
ソフトバンクの代理店のとき、支店が東京、名古屋、関西にあって、誰が何台売って、粗利がなんぼだという日々の営業活動を電話で確認して、ボードに
書いていってたんです。部長が不動産出身の人で、ボードに書くことで実績に対する意識を持たせる意図だったんだと思います。でも、夕方の6時から6時半まで、毎日電話で実績を聞き合う作業が、年間にしたらどれだけ無駄な時間を使っているんだろうと思ったので、すべての人にグーグルのアカウントを取らせて、表を作って、個人が自分の成績を外出先からでもスマホ等で書き込んでもらい自動集約できるようにして、個人の成績や全体実績も自動的にグラフで出るようにする仕組みを2日くらいで作ったんです。僕は、プログラマーじゃないので、単にエクセルの組み合わせみたいな感じで作ったんですね。そんなふうに業務改善できて思ったのは、人間って、頭ではこうやればよいと思っていても、忙しいから、結局やらない人が多いんだと。それで、新たな事に投資できる有意義な時間を無駄にしているんですよね。
―― そうなんですよね。忙しいけれど、もうちょっと頑張って仕組みを作るところまでやらないと、その忙しさがずっと続くわけですよね。
教育現場もそんな感じで、先生も忙しくて、資料をグーグルでも何でもいいからデータベースに入れて、共有フォーマットを作って、教材を作って入れておけば、学年が変わっても使えるわけじゃないですか。
それを、忙しいからしない。でも、僕は、3カ月死ぬ気で業務もやりながら改善やれば、劇的に仕事が変わるというのを、今まで経験で分かっているので、本当に良くしたいなって思っているんですね。
Keynoteで解説を小出しにして、生徒に思考させる時間を与える
―― 住ノ江さんは、Keynoteについてのセミナーなどを行っていますが、Keynoteを使うメリットは、どんなことなんですか?
よく僕がKeynoteを教育現場のICT事例で出している理由としては、思考させる間を与えられるからなんです。算数を例にあげると算数の教科書って、全部結果を書いてあるじゃないですか。見ると分かった気になるけど、考える過程を省いています。算数は紙芝居みたいに、次はどうなるだろうって考えさせること/間がすごく大事だと思います。それがKeynoteなら算数の問題や解説を小出しに表示でき思考の間を作れる事が出来るので算数の勉強にはKeynoteはとてもいいと思ったんです。
あと、教科書だと児童が下を向いてしまいますが、Keynoteを使用して授業で使用する際は教科書を閉じさせてKeynoteで作成した教材を見せます。そうすると先生は児童の顔を見て授業が出来て児童の表情で授業の理解度を把握できます。
またKeynoteのアニメーション機能を使用することにより、算数の図形とか、概念をアニメーション/動画で説明すれば児童の算数に対する理解がとても速
いというのが分かったんです。例えば、円の中心点があって、そこから距離の等しい点をどんどん繋いでいくと円になるというような事もアニメーションにして円になっていく段階をアニメーションで見せてあげると児童は教科書よりよく理解できるようなんです。学習における意識づけや、動機付けをする意味においても、Keynoteアニメーションによる段階的提示が大事なんだなって分かったんです。それで、今、算数の教材を作っていて、学年ごと、単元ごとに整理していっているんですね。Keynoteで作っておくと、あとでアフレコで音声を入れられるので、反転授業用の動画コンテンツとしても成り立つんですよね。
それをやっているうちに、賢明だけでは、もったいないなって思うようになりました。このノウハウを、他の学校の先生にも提供していけば、先生は児童/生徒と向き合える時間がもっと増えていい授業が行えるじゃないですか。
今教育現場ではシステム会社から販売された学習ソフトに合わせての授業とか、タブレットを一人一台持たせて問題の送受信すればアクティブラーニングだってみたいな風潮が一部あるのですがもっと根本的なこと、ICTによって先生が生徒と向き合う時間を増やすための仕組み作り(共有電子教材作成など)の必要性を今、強く感じているんです。
直感的に使えるiPadが、新たな発想を生み出す
―― 住ノ江さんから見て、iPadは、何がすごいんですか?
プレゼンをやるときに皆さんに言っているんですけど、僕は、もともとすごく口下手で、システムとかパソコンがすごく苦手で、はじめはひらがな打ちしかできなくて、会社に入った当時は、表も作れないので、先輩からいびられて泣いてたんですね。
そんな人間でも、直感的に使いこなすことができる、新たな発想が生まれるこのiPadというデバイスというのは、すごいと思うんです。
簡単で直感的にやれるというのが、iPadの凄さだと思います。
パソコンでPhotoshopというソフトを使うと、すごく機能が深くて、ちょっと背景とかを消したいというときでも、どこをいじったらいいのか分からなかったりするんですね。でもiPadとかだと、背景を消すだけのアプリが100円とか200円とかで売っていまして、そういうものを使うと、ど素人でも、パソコンがなくても、簡単にいろんなことができるんです。僕がYoutubeにいろんな動画を上げているのは、iPadだけでもこんなことができるんだよというのを見せたいからなんですね。
これは、仕事も人生も変えることができるすごいデバイスだと思うんですよ。
―― Photoshopなどが高機能なのに対して、iPadのアプリは、1つ1つは機能が限られていて、シンプルなものが多いですよね。
そうなんです。字幕を入れるだけのアプリとか、いらないものを消すだけのアプリとか、単機能のアプリも多いです。
機能が絞られていて、触ると直感的に勝手にできるんですね。そこが素晴らしいと思います。
―― 住ノ江さんは、iPadで何かをやろうとするときに、「このアプリとあのアプリを組み合わせればできるな」というような発想をするんですか?
アプリを2000個以上も落としているんで、何を使えばいいのかが分かるんです。
例えば、「アニメーションで動く絵本を作りたいんだけど、どうしたらいい?」と言われたら、「Keynoteを使ったアニメーションを作って、背景はこのアプリで作って・・・」というように、パパパッと繋いじゃうんですね。
そこに行きつくまでの過程では、こういうことがしたいというものがあると、それをできるアプリをいろいろ探して、発見していってたんです。そのときに、仕事でも趣味でも応用がすごく効くということに気付いたんです。iPadは、道具をどう使うかということを、いい意味で、考えさせてくれるんですね。
変な話ですけど、システム会社の人にiPadの使い方を教えに行ったことがあったんです。
名刺管理アプリの使い方、帳票をスキャンして枠を指定すると簡単にデジタル入力できるアプリの使い方とか、僕からすると当たり前のことなので、システム会社のSEとかPGとかの人ならみんな知っているだろと思いながら紹介すると「おぉ!」ってなるんですね。
それを見たときに思ったのは、知識と知恵というのは違っていて、うまいことコーディネートしたり、繋げ合わせたりする能力というのは、プログラマーがコードを打てるというのと違うんだなと思いました。
「住ノ江さんが、SEやPG上がりの人だからでしょう」と言われるんですけど、「僕は、前はパソコンも持っていないような人で、iPadだけでこれだけできるのは、僕がすごいんじゃなくて、iPadがすごいからなんです。」ということをセミナーでよく言っているんです。「だから、あなたにもできるんです」という説得力を持つことができるんです。
組み合わせて創り出す工夫は、特撮と同じ
―― 特撮って、効果を出すためにいろんな工夫をするじゃないですか?部品を組み合わせて、メタな情報を上手に創っていく感覚なんじゃないかなと思うんですけど、そういう感覚と、アプリを組み合わせて機能をコーディネートしていく感覚って近かったりしますか?
たぶん、そこはすごく一緒なんです。特撮で、こういう映像を作りたいけど、これだけの予算と、これだけの物しかない。じゃあ、それをどう使ったらいいねん。どうしたら、目指しているものに近いものを創れるんやということになるんです。昔の映画って、本当にそうやって作っていたと思うんです。
僕は、もともとは特撮映画監督になりたかったので、それが、iPadとリンクしているんでしょうね。
―― 面白いですね。僕も、そういう工夫がすごく好きで、よく「使い方の発明」という言葉を好んで使っているんです。開発するというレベルの発明じゃなくて、あるものをどう使うのというレベルで発明していく人もいると思っているんです。
僕は、そっち系ですね。
―― 僕も、どちらかというとそっちが得意で、そこに喜びを感じるんですよ。ものを製作した人が意図しない使い方を見つけたときに「勝ったな」って思うんですよ。笑
分かる分かるーー。設計者の思惑を超えて、こんなことできんねん!というやつですよね。
―― そうそう。「自分が作ったものが、こんなところに使われているのか、何考えたんだこいつ!」みたいなことになったら面白いなって。
自分で工夫して、新しい使い方とか価値を発見するのって、楽しいじゃないですか。
むっちゃ楽しい!笑
僕も、Youtubeで上げている動画とかで、普通はアフターエフェクトとか、高いソフトを使ったらできることを、2個か3個のアプリを組み合わせて映像を作っていたりして、パソコンの詳しい人から、「これって、どうやって作ったん?」と聞かれたときに、「200円のアプリと300円のアプリを組み合わせて、背景をこれで変えたらできて・・・」と言ったら、「そういう発想があるんや?」と言われたんですよ。
それがうれしくて、王道じゃないけど、工夫して価値を見出すのが、すごい好きなんですよね。
―― ちょっとハッカーマインドですよね。みんながお金をかけて決められたとおりにやっているところを、安いアプリを組み合わせてショートカットできる道を探し出したことで、新しい価値を生み出していくということですからね。
自分が勉強したことが、他人の役に立つのがうれしい
サラリーマン時代に嫌だったのが、上司から言われた通りにやる人だったんです。それだと、責任転嫁もできるじゃないですか。上司に言われたからやったんですって。
営業時代も、上司から「俺の言う通りにしてたらいいんや」と言われると、「それは、検証しましたか?」とすぐに思ってしまって、独自のやり方をして営業の成績を上げて、上司から何も言われないようにしたりとか、していたんです。
やはり、見直すとか、新たな角度からやらないと、マンネリ化すると、よくてせいぜい現状維持、市場変化とか環境変化があると悪くなるだけじゃないですか。常に何かを良くすることを考えて、情報を入れて、自分は営業だからシステムのことは知らんでいいということじゃなくて、システムのフローチャートの考え方を営業に応用できるようにしたりとか、垣根を持たずにいろいろ繋げていくと、いろんなことがプラスになって、自分が勉強したことが、他人にお話するとお役に立てるのがうれしいんです。
―― 実際に、本当にいろんなところから相談を受けていますよね。
iPadのおかげでお医者さんから相談を受けたりとか、教育関係でセミナーをしたりとか、動画配信をする会社からも相談を受けたりとか、いろんなことに、お役に立てるのがうれしいですね。
面白かったのが、落語家のプロデュースしている方から相談受けたこともあるんです。それで、古典ネタじゃなくて、ギリシャ神話をネタにしてプラネタリウムの真ん中で落語をやりませんかって提案したりしました。
ものの角度とか組み合わせとかを工夫して、新しいものを創って、みんなが喜んでくれて、それを見て、自分がハッピーになりたいなという気持ちがあるんです。
学校の先生のICTに対する壁を破壊してあげたい
―― 住ノ江さんが、今、教育の分野でやりたいと思っているのは、どんなことですか?
僕は、学校の先生のICTに対する壁を破壊してあげたいんです。特別なものだとか、システムに詳しくないからできないとかではなくて、人間が使う道具であって、仕組みは難しいかもしれないけど、決まった流れで結果を出しているだけなので、お作法さえ覚えたら、応用が効きますよ。と伝えたいんです。
今日も、大阪教育大学に行って教育現場におけるICT事例紹介という特別講義をさせてもらって、学生からの講義感想アンケートを見てみると、多かったのが、大学ではこういうICTの授業がないということだったんです。
大学にiPadが100台くらいあるらしいんですが、ほとんど使われていないようなんです。iPadの起動とか、インターネットの使い方程度のものなんです。なのでiPadのいろんなアプリを応用して教材を作成したりとかの経験がないんですね。
先生になると、忙しすぎて新しいことをする余裕がないと思うので、教育大学の学習過程で、ICT機器の使い方だけではなくて、活用方法の講義/授業をしてあげたいなってすごく思うんです。
―― それは、教師が自分でICTを使った工夫できるようになる力をつけるということですか?
自分で活用できる応用力と、事例をうまいこと組み合わせてあげて、ステレオタイプではなくて、広く考えて活用できるようになってほしいんですよね。
例えば、異業種のiPad活用方法も、授業のヒントになるよねというような感じで、システムと授業をうまいこと融合させてあげて、先生も楽に、生徒も楽しくなるような授業をやるお手伝いを、むっちゃしたいなって思っているんです。
―― iPadを使って、いろんな角度から見るとか、いくつかの物をリンクさせて応用していくこととか、学校に今までなかったような種類の学びを入れていける可能性もありそうですね。
僕は、落ちこぼれだったので、僕ができるんだったら他の人もできますよというのが、言えるんです。僕が営業で自信を持てたのは、対面恐怖症で、説明下手で、理解も遅かったんですよ。友だちで10のうち3を聞いたら理解する子もいるのに、僕は10のものを何回も繰り返して説明してもらわないと無理だったんです。
理解が遅い僕が分かるような伝え方、教え方ができたら、誰でも分かるということじゃないですか。
頭の賢い人は、それが、逆にできないですよね。理解が遅い人間だからこそ、本当に誰でも分かる伝え方の理論が構築できるじゃないですか。
それが、僕の武器だと分かったんです。そのおかげでどの業種に行っても、専門用語とかじゃなく、たとえ話をしながら、身近な例で話すことによって、いろんな業界で僕の説明を受け入れていただいたんです。
そういう部分と、直感的に触れて、組み合わせによっては、1が10にも100にもなる可能性を秘めているiPadと、すごく相性がよかったんかなって思いますね。
―― 理解が遅いって、鵜呑みにしないということともつながっていますよね。生徒とかでも、すぐに分かったというけど、浅く理解して、表面的に処理してしまう生徒と、いちいち突っかかって時間がかかるんだけど、身体に染み込ませていく感じだったりする生徒がいて、後者は、時間がかかるけど、身に着けたものを、いろんな風に応用できるようになったりするんですよね。でも、学校現場では、時間内に理解することが求められるので、ゆっくり深く理解したい生徒をサポートできるといいですね。
僕が、よくジグソーパズルに例えるんですよ。ある程度のところを埋めていくと、急に全体像が見えて、一気に埋まるときがありますよね。
システムが分からないと言っているお客さんに「焦らんでいいですよ。やれることからやっていくうちに全体像が見えてきます。焦って、分かったという人ほど伸びないんです。ゆっくり考えながらパズルを埋めていくと、急に景色が変わりますから」という話をいつもするんです。
僕みたいな不器用な人で、あきらめている人が、iPadやったら、仕事も人生も変えられるんだって伝えたいんです。
僕が、iPadで、これだけいろんなことができているんですから、ちょっと見方を変えるだけ、できないという思い込みを外すだけで、絶対変わりますからということを言うと、みなさんの認識が変わってくるのが楽しいです。
―― 転職たくさんしているけど、その経験を生かしていない人もいますよね。住ノ江さんの場合は、様々な経験を、全部自分の中で繋げて一枚の絵にしていっているところがとても印象的です。
嫌な経験も、いい経験も、すべて自分を助けてくれているなというのは思いますね。
僕は、すべてが先生と言うのは、変な話ですけど、物流センターで働いていた女性の方が、パートなので言われたことしかしないんですけど、物流って無駄を省いて出荷を早めるために、作業工程を常に見直していきます。そこの考えや過程が素晴らしいんです。
考え方とか細かい技とかを教えていただいて、時間内に押さえるとか、出荷ミスをしないためのチェック体制であるとか、すごいんですね。僕は、4大出ているとか、有名企業に就職したというプライドがあってせいで、その物流の仕事をしているときは、はじめとても辛かったんです。でも、みんな先生だなって思えた時に、物流のパートの女性からも学べるし、お医者さんからも学べるし、教師からも学べるし、営業とか建材屋さんからも学べるし、すべてのことから吸収できるんだなって思いました。そういうことが、今、一気につながってきて、自分の中のパズルが埋まりだしている感じがあるんです。
―― そういう雰囲気が、外に発散されている感じがあります。
Youtubeに出している動画とか、しゃべっている感じとか、いろんなところから幅と厚みを感じるんです。アウトプットしているものを見れば、そういうのって分かりますよね。氷山の一角を見たときに、水面下にどれだけ大きい塊があるんだろうかという予想がつきますよね。
今、ぐぉーーって来ている人が、非言語的に発散している何かがあって、本人もそれにワクワクしているような雰囲気を、住ノ江さんから感じるんですよね。
自分の中で、iPadでこんなに人生も仕事も変えられるくらいの可能性があって、ICTに関しては学校の改革もできるし、授業形態も変えられると思っていて、そういういろんなアイディアが溢れるくらいあるんですけど、それを目に見える形にして、誰でもできるようにしていく作業を早急にしたいなって思っているんです。
それはしなくちゃいけないけど、一方で、iPadでプロジェクションマッピングをしたり、舞台演出をしたりとか、Zoomとタブレットを使って、不登校の子どもたちが勉強する場を創ってあげて、勉強って面白いんやで、Keynoteで作った教材とZoomを使えばできますよね。その子たちが感じている「私なんかには無理」という思い込みをバリバリっと剥がしてあげるお手伝いができるかなという可能性が見えてきたんです。
―― アイディアを実現するために考えていることはありますか?
今度、中山涼一先生と平野貴美江先生とで、一般社団法人を立ち上げようと言っています。
ICTの教員向けの資格認定みたいなものを作って、教員を目指す人たちに対しても教育体制を作って、私学に対しても、定額で契約をして、学校の先生がZoomで僕に質問できるようにするとかして、全国の学校を繋いでいって、教員を目指す方もサポートできる体制ができたらいいなって思っています。
教育を変えるっていうような偉そうなことは言えないんですけど、働きやすい環境を作るということはできると思います。例えば教材も共有しないで、大きなわら半紙に貼って、毎回作って、赴任先が変わるたびにリセットされていたものを、データベース化できたら、教師の時間の損失を押さえることができるし、勉強が得意じゃない不器用な子が、動画とかで勉強を面白いって思えるようになることのお手伝いができるんじゃないかって思っているんです。
インタビューを終えて
住ノ江さんは、様々なものを縦横無尽に直観によって結び付け、その組み合わせによって価値を創り出すのが、とても得意な人なんだなという印象を受けました。
それは、決められたことを効率よく処理していくことを求められる学校教育や、大企業においては、相性がよくなかったため、秘められた能力を発揮しきれていない状態だったかもしれません。
しかし、iPadという非常に相性のよい道具と出会ったことで、住ノ江さんの能力が外側へ表出していく道筋ができ、人生が開けていきました。
頭の中にストックされている2000個以上のアプリを、縦横無尽に結び付けて、様々な価値を生み出していくのは、住ノ江さんの独壇場です。
興味深いのは、iPadという大きな強みができたことで、それと他の経験とを結び付けて、新たな価値を生み出していることです。これまでの様々な経験も「アプリ」のように頭の中でチャンク化され、
iPad+(様々な経験)=新しい価値
というように価値創造に利用できるようになり、仕事を広げているのです。iPadという大きな強みが生まれたことで、住ノ江さんの「結び付けて価値を生み出す」という能力が、より広い分野で生かせるようになっているのです。そして、住ノ江さん自身が実感されているからこそ、「すべてが先生」という言葉が出てくるのだと思います。
僕が印象に残ったのは、住ノ江さんが、自分の体験を分かち合いたいという気持ちを持たれているところです。秘めた能力が、1つのことをきっかけで表出していった経験が、多くの子どもたちの役に立つのではないかと考えているところが、ICT教育に携わっている原動力になっているところが素晴らしいと思いました。
住ノ江さんのように繋げて価値を生み出す人は、繋げられる要素が増えるほど、指数関数的に生み出せる価値が増えていきます。ジグソーパズルが埋まってきて、大きな絵が見えてきたという住ノ江さんの今後の活動が、とても楽しみです。
組織の枠組を超えて、個が繋がり共創する未来へ向けて
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
昨年の9月に、「反転授業が創る未来を語ろう!オンラインワールドカフェ」を行い、私たちがどんな未来を思い描いているのかをサーチしました。
そこで浮かび上がってきたのは、
個が組織の枠組を超えた越境の学び合いをしながら、マインドセットをリフレ―ミングしつつ共創する未来
というものでした。
リアルの世界では、肉体を1つしか持たないために、同時に複数の組織に所属することが難しいですが、オンラインでは、その制約から解き放たれ、複数のグループに同時に所属することができます。すでに、そのことに気づいた人たちが、次々にFacebookグループを立ち上げ、タケノコのようにニョキニョキとオンラインコミュニティが生まれています。
オンライン上に安心安全の場が数多くできるようになると、活発な知的交配が可能になり、お互いの思考を参照し合いながら言語化していくプロセスが加速し、集合知によって様々な価値が創造されていくようになります。これは、「反転授業の研究」ですでに起こっていることです。
その活動に参画しているうちに、ダイナミックに境界を更新しながら変動するアメーバ型組織の中では、「苦手なところ」よりも「自分が力を出せるところ」が、重要になってくることに気づきます。
私たちは、これまで、「自分が力を出せるところ」よりも、「苦手なところ」に意識を向けがちでした。
そして、自分は、ダメだなぁーと嘆くことが多かったのです。
これは、大量生産の規格品人材を生み出すプロセスの中で、取り換え可能なパーツとして育成されてきた結果、多くの人たちが不必要に自信を奪われて来たのだということではないでしょうか。
でも、私たちが想い描く未来では、「自分が力を出せるところ」のほうが、「苦手なところ」よりも圧倒的に重要です。
あなたが、力を出せることは何ですか?
これは、生きていく上で大切な問いなのに、ほとんど問われることがなく過ごしてきた人が多いのではないでしょうか?
安心安全の場での交流が活発になっていくと、自分自身を閉じ込めていたマインドの存在に気づいて、それを一つずつ解除していくような変化が加速していきます。そして、自分の根本に潜んでいる想いとつながり、生命エネルギーを噴出させて勢いよく飛び出していく人たちが、次々と現れるはずです。
組織の枠組を超えて飛び出してきた人が、それぞれの想いを語り、お互いに手を繋ぎ、違いから学び合いながら、価値創造をしていくことが当たり前になる未来は、もうすぐやってくるはずです。
そんな未来を出現させたい。
周りを見渡すと、すでに、組織の枠組を超えて飛び出してきた人たちがいることに気づきます。
その中の二人が、近大附属高校の江藤由布さんであり、職業「桑原恭祐」と言ってはばからない桑原恭祐さん。
江藤さんは、こんな人(画像をクリック) その(1)~その(10)を読むと分かります!

江藤さんは、田原が2回インタビューをした唯一の人。変化のスピードが速すぎたので、もう一度、インタビューすることになりました。
自律的な学びを促す教師は、TeacherからExpert in Learningへと役割を変える
桑原さんがどんな人かを表現するのは難しいのですが、これらを読むとイメージがつかめると思います。
アクティブラーニングが、「クラウドの時代」を生きる若者を育てる
フィズヨビダイアログ「未来を創る人~人生は、出逢い・発見・創造~」
桑原さん自身の言葉で語るオンライン講座の魅力はこちら
彼らは、様々な枠組みを越境し、一般社団法人オーガニックラーニングを設立し、リアルとオンラインを行ったり来たりしながら、学びの渦を引き起こしています。
彼らの活動は、私たちが想い描く未来を出現させていくための力強い「芽」であると感じています。
この大切な「芽」を育て、大きな森を創っていくために、オーガニックラーニングと反転授業の研究とがコラボして「YOU ∞ 理論」というオンライン講座を実施します。
この講座は、江藤さん、桑原さんに続いて飛び出していこうとしている人たちをサポートしていく動きになると思います。
尖ったイノベーターの二人が、想い描く未来を創るために膠着した社会の壁を突破していくのを、反転グループの田原真人、平野貴美江、倉本龍が、それぞれの強みを持ちより、講座を全力でサポートします。
今、自分を閉じ込めている枠組から出ていきたくてうずうずしている人は、ぜひ、無料オンライン説明会に話を聴きに来てください。
2/21 (日)21:30-22:30
2/23(火)21:30-22:30
3/ 1(火)21:30-22:30 ← 田原はこの日に参加
講座の詳しい内容は、こちら↓のカッコいいサイトをご覧ください。
保護中: 総合学習からALへ精神は受け継がれていく!内橋朋子さんインタビュー
【CCC×反転G】50人のオンラインの学びの旅がスタート!
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
オンラインで簡単にグループワークができたら、世界はどんな風に変わるだろうか?
そんなことを2年前から妄想し、Webシステムの開発に取り組んだり、既存のツールを組み合わせてみたり、いろんなことを試してみました。
そうこうしているうちにテクノロジーが進歩し、ZoomというWeb会議室システムを使って、僕が思い描いていたワークを実現できるようになりました。
ちょっと大げさな言い方ですが、僕たちは、今、世界を変えることができる道具を手に入れました。
僕達は、2016年2月2日の夜に、住んでいる場所という制約を超えて、由佐美加子さんという日本有数のファシリテーターが創る場に集まり、グループに分かれてお互いに耳を傾け合いました。
Co-Creation Creators(CCC)と、反転授業の研究グループ(反転G)との間で、様々な縁が紡がれた結果、総勢50名がオンラインに集って学びあうという、前例のない学びの旅が始まりました。
全体性から生きるAuthentic Leadership 基礎特別編
ここに参画してくださったすべての方に感謝しつつ、今起こっていることを書き留めておきたいと思います。
それは、1つのセミナー動画から始まった
2015年5月、反転Gでおなじみの福島毅さんからFacebookにメッセージが届きました。
「この動画、絶対に見て。これは、すごい動画だから。見たら感想を教えてください。」
送られてきたのはYoutubeにアップされている3時間ほどあるセミナー動画のURLでした。
この動画の中で、CCCの由佐美加子さんは、怖れに対する反応が、いかにして人々の間に分断を生み出すのかということを、鋭くえぐりだしています。
リーダーが「これが正しい」という情報を発信すると、「正しい/間違っている」という二項対立に陥り、多くの人に怖れの反応を引き起こし、分断が生まれていく。
これを回避するために、由佐さんは、「信じていることを純化させて、祈りとして発信する」「美に触れると元気になる」と語ります。
由佐さんの動画を見て、今までどうやって乗り越えていったらよいのか分からなかった溝を乗り越える道が見え、光が差したような感覚がありました。
そして、興奮して、感じたことをブログに書きました。
由佐さんの動画は、それ自体が、まさに”祈り”としてインターネット上に解き放たれ、反転授業の研究の人たちの心にも変化を引き起こしていきました。
2つの波がシンクロしてオンライン講座が生まれた
反転授業の研究では、主体的な学びをどのように起こしていくのかがテーマになっています。
教室では、教師は、生徒が自ら動きやすくなる環境を作り、生徒から出てきた主体的な動きにフィードバックをかけて増幅していき、主体的な活動を引き出していくことを目指します。
それじゃあ、教師同士の学び合いも、主体的な学びにしていこうということで、参加型のオンライン講座をやっています。
受講者で参加した人が、運営ボランティアになり、運営になり、講師になり・・というような循環が起こり、参加形式を様々に変化させながら学の場が、繰り返し創造されています。
その学び合いを通してオンライン講座運営の集合知が生まれ、オンラインでありながら、心が通い合う場が、毎回生まれるようになってきました。この運営ノウハウと運営スタッフを外に出していき、組織の枠組を超えた学びを創造しながら、更なる循環を起こしていきたいと考え始めたのが、2015年10月頃でした。
ちょうどその頃、CCCの皆さんもオンラインワークショップの可能性に関心を向けはじめていて、お互いのタイミングが絶妙なタイミングでシンクロし、コラボレーションによってオンライン講座を開催することになりました。
受講生から運営ボランティア、運営という形で参画してくる文化を持つ反転授業の研究に対し、CCCもファシリテーター養成コースの修了生が活動に参画してくる文化を持っていて、それぞれのコミュニティが大事にしていることの間にもシンクロがありました。
CCCのファシリテーター養成コースの修了生が8名、反転Gの運営ボランティアが6名が運営チームに加わり、講師や運営と合わせて18名の運営チームが結成されました。
コラボレーションが決まってすぐ、CCCパートナーの藤本海さんが、僕に会いに来てくれて、その後、反転Gが主催するファシリテーション・コーチング講座を受講生として体験してくれました。
藤本さんが、CCCでやっている講座と、反転Gのオンライン講座のフレームとをすり合わせる役割を果たして下さり、いっしょに様々な部分の擦り合わせをしたり、検証をしたりしながら講座開催の日を迎えました。
Breakout Sessionを使ったグループワーク
今回、はじめて実現したのは、ZoomのBreakout Session機能を使ったグループワークです。
受講者32名を4人ずつの8チームに分け、各チームにメンターが一人ずつつき、5名からなる学習チームを作りました。
はじめに、それぞれがチームに分かれてチェックインを行いました。
ZoomのBreakout Sessionを使うと、これを1クリックで行うことができます。
ホストがBreakout Sessionをスタートすると、40名が各チームへと別れていきました。トラブルなくルームの移動が起こるために、何度も繰り返して検証作業をしていたので、全員が無事にルーム移動をしたときには、思わずガッツポーズをしていました。
その後も、メインルームに50名全員が集まって話を共有し、また5人ずつ8チームに分かれるという動きを2度繰り返しました。すべてトラブルなくスムーズに移動でき、オンライングループワークの無限の可能性を感じました。
由佐さんの話が脳に直接響いてくる
セッションの途中で、由佐さんのレクチャーが1時間ほどありました。
iPadからZoomにログインし、オンラインホワイトボードを共有し、そこに図や文字を書きながら、NVCの世界観について語ってくれました。
今まで由佐さんのワークショップに出たことのある皆さんからは、
みーちゃん(由佐さん)の声が、脳に直接響いてくる。
一番近くの場所で聴いているみたいな臨場感がある。
という声が上がり、オンラインだからこそ話に集中しやすいという面もあるという気づきが生まれていました。
また、受講生が、話を聴きながら感じていることをチャットボックスに書き込み、由佐さんが、それを見ながら話をするというやり方を取ったのですが、話が相手にどんな風に響いているのかが分かり、話しやすかったというフィードバックが由佐さんからありました。
これだけの規模と内容のオンラインワーク講座は、前例のないものなので、みんなで未体験ゾーンに突入していますが、その第一歩を無事に通過することができ、ホッとしています。
そして、これからどんなことが起こっていくのかワクワクが止まりません。
次のレポートをお楽しみに!
山本崇雄著『はじめてのアクティブ・ラーニング 英語授業』レビュー
オンライン教育プロデューサーの田原真人です。
2014年の12月に母校、両国高校を訪問し、授業見学をしてきました。
そのときに見学させていただいたのが、英語科の山本崇雄さんの授業でした。
授業見学のレポートは、下記の記事をご覧ください。
都立両国高校を見学して(上)― フォークダンスのように生徒が動く英語の授業
都立両国高校を見学して(下)― 教師の主体的な学びが生徒の主体的な学びを促す
山本さんの授業を見ていて、すごく印象に残ったのが、ペアを変わるたびに、相手に挨拶したり、お礼を言ったりするということでした。
ここには、なぜ、ペアやグループで学ぶのかということの本質にかかわるテーマが隠れているように思いました。
この度、山本さんが出版した『はじめてのアクティブ・ラーニング 英語授業』では、授業で行っている活動の背後にある考え方が種明かしされています。
何を目的にしてアクティブ・ラーニングをやるのかを明確にし、その目的と様々な活動をリンクさせていくというところに、山本さんの授業の真骨頂があるのではないかと思いまいます。
山本さんの著書、『はじめてのアクティブ・ラーニング 英語授業』を読み、英語のアクティブラーニングの実践と、その背後の考えについて気が付いたことを書き連ねていきたいと思います。
ちなみに、僕のコメントも、表紙の裏に載せていただいています。
自立した学習者を育てるためのアクティブ・ラーニング
本をめくると、一番最初に、
「自立した学習者を育てるためのアクティブ・ラーニング」
という言葉が、目に飛び込んできます。
また、英語のアクティブ・ラーニングを次のように定義しています。
①英語の「学び方」を能動的に英語で学ぶ活動
②英語を使って多様な考え方を能動的に学んだり、自分の考え方を表現したりする活動
このように、自分にとっての授業の目的、自分にとってのアクティブ・ラーニングの定義を作ることは、AL型授業を実践していく上で、非常に重要なことだと思います。
これには、2つのメリットがあると思います。
1つ目は、生徒と常に共有していくことで、生徒が、日々の活動を大きな目的に結び付けやすくなるというところです。
2つ目は、教師にとって、授業のやり方を試行錯誤するときの指針になることです。定義と目的が明確になっていれば、そこに照らすことで、授業実践を磨き上げていきやすくなるのです。
試しに、山本さんの目的が達成された状況の教室を思い浮かべてみます。
すべての生徒が「自立した学習者」であり、
英語の学び方を習得しており、
英語を使って多様な考え方を能動的に学ぶことができ、
かつ、学んだことを英語で表現することの重要性を理解している状況。
そのとき、教室で教師の役割とはどんなものになるのでしょうか?
生徒は自分たちで学び始め、それぞれが自分に合った学び方で学びながら、お互いに自分の考えを表現したり、お互いから多様な考え方を学び取ったりし始めるでしょう。
僕が見学した、山本さんの「教えない授業」では、まさにそのような状況が実現していました。。
山本さんは、前でタイムキーパーとしてベルを鳴らしたり、目標を確認したりするだけで、生徒が自分たちで協力し合いながら学びあっていました。
山本さんは、第1章で受験対策についても述べています。多くの教師が、授業をアクティブ・ラーニングに変えたら、受験対策が弱くなるのではないかと心配しているからです。
しかし、大学受験をゴールにせずに、それを通過点にしてその先も役立つ英語力をつけていくということは、同時に受験を通過できる力が自然に身についていくということでもあるのです。今後、「話す力」を測るスピーキングテストが受験に導入されるようになれば、普段から英語で表現することを鍛えている生徒たちは、さらに力を発揮することになるでしょう。
実際に授業見学した僕の印象は、「これを続けていけば、間違いなく英語力は伸びるだろうな」というものでした。授業における生徒の活動量が多く、生徒の頭の中が、まさに「アクティブ」になっているような授業だったからです。
すぐに取り入れられる授業の工夫
第2章、第3章では、英語のアクティブラーニングの具体的な実践方法が紹介されています。
1つ1つの方法の説明では、実際に使用しているワークシートなども公開され、具体的にやり方が説明されています。
さらに、冒頭で述べた目的との関係性が、いたるところに登場します。
方法+その背後の狙い
という組み合わせが、この本を価値あるものにしているのではないかと思います。
?たとえば、「ペアワーク」のところでは、活動の終わりに「Thank you」とパートナーに感謝の言葉を言うように指示したり、相手の良いところを発見するように指示したりするということが、大切なことだと言われています。
これは、生徒がクラスを自分の居場所だと感じることができたり、自己肯定感を高めたりすることに役立つと考えられているからです。
それは、「発音の学び方」にもつながってきます。ここでは、「教師がモデルを示す前に、生徒自身に発音させてみる」ということが提案されています。これは、間違いを恐れずに英語を話す態度を育てることが意図されています。間違いを恐れないで行動できるためには、教室が安心安全の場になっていることが必要なので、ペアワークでの大切にしてくることと深く関連してくるのです。
さらに、「勉強法の共有」では、各自が気づいた学びの本質を惜しげもなく披露していくことで、救われる生徒が出てくることが紹介されています。
ドリカムプランの産みの親の和田美千代さんは、アクティブラーニングの本質を、「互恵・共創・集合知」と言っていましたが、山本さんの授業でも、その精神が全体に広がっています。
自分だけで学ぶよりも、耳を傾けてくれる相手がいて、自分とは違う考え方を披露してくれる仲間がいて、そこに自分も貢献していくことで自己肯定感を高めながら学ぶことができるということに気付いたときに、自分も相手も生かしながら学ぶことができる自立した学習者になっていけるのではないでしょうか。
山本さんの授業には、そこへ向かっていくための様々な工夫が凝らされているのです。
生徒による授業
山本さんの「教えない授業」は、授業の一部を生徒に任せたり、教科書の内容を生徒だけで学ばせたり、というように、生徒の力がついてくるにしたがって、教師はコントロールを手放していきます。
そして、究極のコントロールの手放しが、生徒による授業です。
山本さんは、次のように語ります。
いつか授業全体を生徒に任せてみましょう。教師のコントロールを離れたとき、はじめて主体的な学びが生まれます。そして、この主体性は10年後、20年後の生徒の生きる力へとつながるのです。
山本さんの授業は、いろんな工夫がされていてすごいです。
でも、一番すごいところは、覚悟を決めてコントロールを手放すマインドだと思うのです。
対談:ホラクラシー型経営の武井浩三×反転授業の田原真人
「反転授業の研究」を主宰しているオンライン教育プロデューサーの田原真人です。
反転授業では、教師が権力の象徴である教壇から降り、生徒に対するコントロールを手放してファシリテーターの役割をすることで、生徒の主体性を引き出していくことが重要になります。
これは、全員参加型の共生・共創社会を創るための力を、教室の中で育んでいこうという未来を見据えた活動なのです。
そのような未来の社会では、多くの組織が、今のようなトップダウン式のヒエラルキー組織ではなく、フラットで柔軟なホラクラシー組織になっているのではないでしょうか?
海外に目を向けると、すでに、『奇跡の経営』で有名なリカルド・セムラーのセムコ社や、アメリカの靴のオンライン小売であるザッポスのように、社内の管理を極力減らし、生き物のような組織を作って成功しているところがあります。
そんな中、「反転授業の研究」では、次のブログ記事がとても話題になりました。
日本にも、経営者がコントロールを手放し、フラットな組織を作って経営しているところがあるということに興味を持ち、ダイヤモンドメディア株式会社代表の武井浩三さんと対談させていただきました。
ホラクラシー型経営はブラックミュージックに通じる
――以前、日本ファシリテーション協会(FAJ)会長の平井雅さんとお話したことがあるんです。平井さんは、ずっとジャズをやっていて、その後、ファシリテーションの世界に入ったんだそうです。そしたら、ジャズとファシリテーションは、場から即興的に生まれてくるところがとてもよく似ていて、ジャズをやっていた経験が、ファシリテーションにとても役立っているっておっしゃっていたんですね。武井さんは、若いころにかなり本格的にバンドをやっていたというのを記事で読んだんですが、それは、今のホラクラシー型経営と結びついているんですか?
かなり近いと思いますね。音楽って、完全に個人事業主じゃないですか。誰にやれと言われるわけでもなく、自分が好きだからやるもので、それしかないじゃないですか。
その感覚って、仕事を楽しむこととか、自分のやることすべてに通じています。音楽をしながら、仕事を始めたときの僕の感覚としては、それと同じでしたね。年齢も性別も国境も関係なく、音楽は完全に実力主義なので、うまい奴は、うまい奴とやりたいし、下手な奴はしょうがない。その労働観は、今も全く変わらずですね。
経営のスタイルだけじゃなくて、実際の経営のところも、先ほどおっしゃられていたみたいに、アドリブというか、その場その場で柔軟に対応していくという考え方は、音楽、特に、僕がやっていたブラックミュージックに通じるところがあるなと思っています。僕は、R&Bとかが好きで、そのアドリブって、日本人はあまり持っていないんです。ホラクラシーの組織って、ピラミッドみたいに型にはまっているわけじゃなくて、その場その場でふわふわ形を変えていくみたいなイメージなんです。それってまさに、ブラックミュージックなんですよね。
空気を読んでいくみたいな感覚なんです。でも、この空気を読む力というのが、結構、センスが必要だなというのを最近、痛感していますね。
――それは、面白いですね。僕は、野球をやっていたんですよ。特に昔の少年野球って監督が偉くて、監督の指示通りに決められたことをきっちりやるってものだったんですよね。あれは、即興とか空気を読む力とかを育てることの逆を行っていますね。
実は、僕も、幼稚園から中学3年生まで、ずっと野球をやっていて、それが息苦しくてやめたんですよ。監督が、あれしろ、これしろって言って、右打ちだったのを、無理やり左打ちに変えられて、嫌だったのに嫌って言えなくて・・みたいな。
――そういう構造が、学校も含めて、いろんなところにありますよね。
反転授業とホラクラシー型組織の類似点
―― 記事を読んでいて面白かったのは、目標設定をやめたら、問題が無くなったというところだったんです。
「反転授業の研究」で似たようなプロセスがあったんです。もともとこのグループを始めたころは、僕は、旧いビジネスモデルの中にいて、「反転授業」というキーワードは来るぞ!と思って、ブログを作ったりして、人が集まる仕組みを作っていたんですね。それで、これを将来的に収入の柱の1つにしようという個人的な目標設定があったんですね。
でも、反転授業に対する理解が深まってくるにつれて、場をフラットにして生徒の主体性を引き出していくという反転授業の考え方と、自分のビジネスモデルとの矛盾が大きくなってきたんです。
ちょうどファシリテーション入門という講座をやるときに、関係性をフラットにしてアメーバ型組織を作っていくときにファシリテーションが重要な役割を果たしていくんだって言っている講座がピラミッド型になっているという矛盾が生じたんです。それで、苦しくなってきてしまって、その気持ちを打ち明けたら、場が転換して、みんなが助けてくれるようになったんです。
そのときに、自分が勝手に作り出していた目標設定が問題を創り出していたんだなって思ったんですよ。それで、そういう自分勝手な目標設定を止めて、流れに乗っていこうと思ったら、そういう問題が発生しなくなったんですよ。
それで、そのときに出てくるものに乗って、自然な流れに任せていけばいいんだなということをそこから学んだんですよ。その経験が、武井さんの「目標設定をやめたら、問題が無くなった」という話とシンクロしたなって思ったんですよ。
全く一緒だと思いますね。
反転授業は、どのくらいやられているんですか?
――僕自身は、2年くらいです。反転授業というもの自体が、まだ新しいんですよ。この2,3年で出てきたものなので。
でも、コミュニティでやり取りしているうちに、問題意識がどんどん深まっていって、活動の焦点が変わってきていますね。
もともとは、自宅学習と教室での学習の順番を反転して、動画で予習して、教室でワークをするというものが反転授業なんですが、何のために反転するのかというと、教室内のヒエラルキー構造を弱めて、生徒が主体的に動けるようにしていくためなんですね。そのためには、教師の役割や、リーダーシップの取り方が変わるんです。そうすると、学校の組織運営も変わらざるを得なくなってきますよね。そうすると、ドミノ倒しのように下から上へとボトムアップの変革の波が生まれてきたんですよ。
そうしたら、だんだんと動画が・・みたいな話じゃなくなってきて、マインドセットが変われば、どっちだっていいじゃんみたいな感じになってきているんですよね。
なるほどですね。教育とホラクラシー経営というのが、僕の中でもリンクしているんです。最近は、オルタナティブ教育が盛り上がっていますが、特に、サドベリーとかに興味があります。東京サドベリースクールの理事長は、まだ、30代なんですけど、その方と、最近すごく仲がよくて、話を聞くことが多いんですよ。彼らの視点から話を聞くと、教育の実践がある程度うまくいくというのは、アメリカの実証実験とかをもとに自信を持っているそうなんですけど、今の課題は、サドベリーのようなオルタナティブ教育で育った子どもを受け入れてくれる企業がないってことなんだそうです。教育は、育つところまでは自由にやってくるのに、企業に入ったら、いきなり上下関係があったりするわけです。もっと受け入れてくれる企業を増やしてほしいから、ホラクラシーを広めてほしいって言われています。教育とホラクラシーは別の問題じゃなくて繋がっているんだって感じましたね。
外発的動機づけをなくし、Beingの価値に報酬を払う
――教育というのは、社会がまずあって、その社会に適応する部品を作っていくためのものだという文脈で語られることがよくありますよね。でも、岩手県の大野高校の校長先生をやっている下町壽男さんは、全員参加型の共生社会を作るために、自分たちは参加型授業をやるんだって言っているんです。今ある社会に対して適応するんじゃなくて、これから創りたい未来に対して自分たちは教育をやるんだって言って、管理職が覚悟を決めて学校ごと変えていっているんですよ。そういう人たちって、全国に散在していたんです。それが、インターネットによって結ばれてきて、出会うべくして出会ったみたいな感じで、次々に繋がってきているんですよ。
田原さんのビジョンというか、反転授業のムーブメントが、どのように広がっていくというイメージを持たれているんですか?
――目指しているのは、生き物としての人間の復活ですかね。反転授業というのは、主体性教育なんですよね。主体性というのは何かなといったら、巨大なシステムに依存して弱められてしまっている部分を、自分に取り戻していくということなんじゃないかと思うんです。だから、人が集まって、いろんなものを自分たちで手作りでやっていくという営みが、あちこちで起こっていく中で、失っていた自信を取り戻していくというようなムーブメントが起こればいいなって思っています。
うちの会社も全く同じで、ワークライフバランスとか、バランスを取るとか言っていますけど、うちの会社の価値観でいくと、仕事とプライベートって、そもそも切り離せないと思っているんです。特に、IT社会になると、いつ仕事しているのかというのがものすごくあやふやですよね。うちなんか、IT企業なので、家でも仕事できてしまうし、スマホでもできてしまうし、考えることが仕事だとすると、お風呂に入って考え事していても仕事だし、区別する意味がないよねってことになるんです。出社して何日間働いたらいくらという時間を給料として考える報酬体系というものも意味をなさないし、仕組み自体を変えていくしかないよねということで、自分たちで手探りで変えている状態なんです。
そういう風に掘っていけばいくほど、その人が何をしたらいくらということじゃなくて、その人自身の価値がいくらなのかという風に考えないと値段をつけられなくなっていくんですよね。自然と、自分は何者なのか、会社に対して、お客さんに対して、どんな価値を提供しているのかというところと結びついていきますし、バランスというと、違う2つのものをバランスとるというイメージですけど1つですよって。分けて考えないほうが自然なのかなって思います。
――それには共感しますね。ワークライフバランスって、仕事は我慢して働いて、プライベートを充実させるという考えが背後にあるじゃないですか。お金のために我慢しなくちゃいけない時間を人生の中に作らなくちゃいけないなんて嫌だなって思うんですよ。僕は、10年前に夫婦で会社を作って、当時は予備校講師だったので、あちこちの校舎をまわって授業しつつ、自分の会社でオンライン予備校を運営していたんです。全部、自分の人生の時間をどういう風に使うかという話だから、プライベートと仕事を分けないということを、その頃から口に出して言っていたんですよ。
今は、オンライン化が進んでいるから、自分の価値って、すごく曖昧になってきていますよね。
特にBeingの部分が発揮する価値ってありますよね。ファシリテーターが場をホールドしているときに、その人が何をしているかって言われても難しいですよね。
そうなんですよね。我々がホラクラシー組織を作るときに、すごく苦労したのが、報酬体系が一番苦労したんです。その枠組みというのが、一番、人間に圧力を与えてくるところなんです。業務単体でいくと、誰でもそれを楽しんだりできると思うんです。いざ、それがお金の話になると、ほとんどすべての会社には等級のようなものがあって、このランクまで行くと、いくらからいくらまでのレンジで、次に行くといくらで・・というように決まっているんですよね。給与の名称でいくと、職能給、職務給、能力給の3つになるんですが、それは、その人のBeingではなくて、havingとかdoingに対しての報酬体系なんです。これがあると、人間っていきなり窮屈になるんです。「この仕事をするといくら」というのが頭に浮かんじゃうんです。そうすると、自然と給料が取りやすい仕事に流れて行ったり、習熟度が高まれば高まるほど給料を上げやすくなるので他の仕事をやらなくなっていったりするんです。1つのことを極めたほうが給料を上げやすいという仕組みなんで、必然的に社内での人の流動性がどんどん低くなっていくんですよ。ヒエラルキーとホラクラシー、役職とかがあるとかないとかだけじゃなくて、給料がどうやって決められるのかというところもテコ入れしないと、本当に自由で流動的な組織ってできないなというところに行きついて、そこから掘り下げていったんです。
――お金と役職って、外発的動機づけがかかってくるところだから、そこをいじらないと、自分から動くという仕組みを作れないですよね。
とにかく、ダニエル・ピンクが言うような外発的動機づけをなくすということを、うちの会社では徹底的に行っていて、外発的動機づけになり得るものというのが、金銭的なものと、役職なんですよね。役職って、ほとんど今は動機づけなんですよね。本来は、ビジネスを健全に回すために機能があって、それを誰が担当しているかという後付けでしかないのに、こいつのほうが年齢が上だから役職強そうな名前にして・・みたいに、実態とはかけ離れたものが生まれていっているんですよね。そういう無駄をどんどん取っていくと、本当に何もなくなるんです。
3年くらい前は、いろんな制度を作ったんです。でも、そういう制度を作れば作るほど、逆に自分たちが窮屈になっていって、自由になるために仕組みを作ったはずなのに、そのために窮屈になるという逆転現象が起こった時期があって、それで、いろいろ悩んで、これはやめても大丈夫か、これはやめたらやばいかということを考えながら、皮を剥いでいくような感じで、いろいろ取っていったんですね。それで、取りすぎて失敗したこともあったんですよ。例えば、管理会計を止めちゃおうと言って、会計をものすごくルーズにしたら、本当に危なくなって(笑)、これは、取ったらいけないものだったんだって分かりました。
でも、大体のやつは、取っても問題がなくて、その中の一つだったのが目標設定だったんですよね。目標は成長する上で必要不可欠だと思っていたんですけど、そもそも成長って何だろうって考えると、意味が分からなくなってきたんです。目標設定って量的な成長に向かいがちなので、会社自体の成長というのはなかなか目標に落とし込めなかったりしますし、目標管理をしっかりすればするほど、うちの会社で実際に起こったこととしては、奇跡が起こらなくなるんですよ。
すべてが想定内に収まってくるので、トラブルも減るけど、奇跡も減るという感じになるんです。
結果とプロセスと労働時間を透明にして共有すると、勝手にバランスを取れていく
―― それは面白いですね。でも、リスクってどんな感じで分散しているんですか?ヒエラルキーだと、トップが権力もあるけど、リスクも背負っているんだよという形でセットになっているわけじゃないですか。フラットにすると、会社が危なくなったときのリスクとかは、どういう風に分散されているんですか?
どうやって分散させるためのインフラを整えるかというと、情報インフラなんですよ。データーマネージメントなんです。うちの会社は、とにかく自由なんですけど、データ管理だけは徹底的に仕組みを作っていて、財務系のものだけじゃなくて、アクション履歴という誰が何をしたかというプロセスが見えるようになっているんです。営業人員であれば、何件電話をしたとか、何件訪問したというのを全部取っていますし、プログラマーであれば、どんなタスクをこなしたかとかというように、どの業務にどのくらい時間を費やしたかということを日次で取っているんです。それを1カ月単位で集計しています。そうすると、結果とプロセスと時間の因果関係が見えるようになるんです。これが見えるようになった上でオープンにして、みんなで同意しながらものごとを進めていくと、勝手に分散するんです。
――給与も自分で決めるので、売り上げが下がっているときは、その状況もオープンになるから、自分たちの給料も自分たちの判断で下がらざるを得なくなるんですね。そういう意味で、リスクが分散されるわけですね。
昔は結果だけを共有してコミュニケーションを取っていたんですね。そうすると全然うまくいかなくてケンカしちゃうんですよ。「会社の業績は下がっているけど、俺はスゲー頑張っているから上げてもいい」みたいなことが起こるんです。そういう言い合いになったときに話し合っても着地しなかったんですね。それで、価値観がずれているからかなって思って、もっと話し合えば解決するかと思って、もっと話し合ったんですけど、話し合えば話し合うほどケンカしちゃうんですよね。それで、結果が生まれるまでのプロセスと時間というのも見えるようにすればいいと思ったんです。ITのたとえで言うと、ホームページにグーグルアナリティクスが入っていないのに、この部分をこう改善したほうがいいよって言っても、何の信憑性もないじゃないですか。でも、データがあれば、どのコンテンツが人気があるかというのが一目瞭然ですよね。それと同様に、会社組織全体にアナリティクスのようなものを導入しないと合理的なコミュニケーションは全く取れないんです。でも、逆にこれを導入したことで、全員の自由度が高まったんですよ。
それまでは、労働時間が短いことに対する後ろめたさが残っていたんですけど、やることをやっているというプロセスを見せられれば、労働時間が短いということに対する後ろめたさも自然と消えますし、周りの人も理解できるし、感情論にならないんです。このあたりは、仕組みを作らないと次へ進めなかったですね。
――それは、ITが可能にしたことなんですね。だから、今、可能になってきた経営スタイルなんですね。
そうですね。10年前とかだったら無理だと思いますね。
自然体になると、不自然に対する感度が高まる
――ふつう経営にチャレンジするって、ビジネスにチャレンジするという意味合いが大きいと思うんですけど、武井さんの場合は、ビジネスの対象である不動産関連のことにチャレンジするのと同時に、経営スタイルにもチャレンジしているということですよね。そして、経営スタイルのチャレンジのほうがフォーカスされているという部分もありますよね。
枠で言うと、ビジネスよりも会社のほうが大枠じゃないですか。僕は、1回、ビジネスだけにフォーカスして起業して失敗したという経験があるもので、会社作りをしっかりしないとというところから始まっているんですけど、8年間、今の会社をやってみて、会社作りとビジネス作りはイコールだって感じているんです。今、我々が取り組んでいる新しいビジネスモデル、不動産の流通のイノベーションというところにテコ入れをしているんですけど、それは、我々のような組織にしている企業じゃないと思いつかないんですよ。こういう経営スタイルをしていると、不自然なものがすごく目につくようになるんです。「それは、明らかにおかしいでしょ」「そもそも表面的な問題の前に、根本に問題があるでしょ」という感じで、理不尽なものとか、不自然なものにすごく敏感になると思うんですよ。われわれは、最初は不動産業界にマーケティングシステムを提供していて、競合他社は、みんなそこで争っているんですけど、やっているうちに、そもそも業界の仕組み自体に問題があるよねというところに、どうしても気が付いてしまうんです。不自然なので気持ち悪いという感覚があるんです。
――普段から不自然をなくしているから、身体全体、組織全体がセンサーみたいになってくるんですよね。
そうです。そうです。田原さんもそうだと思うんですけど、ただそれだけというか、それを良くしていくためのものを作ろうよということになるし、うちの会社のみんなも同じことを肌で感じているので、そうだよねって同意してくれるんです。自分たちがやっていることに対する確信というものも自然と生まれてきて、それがエネルギーになります。そして、そういうエネルギーがあるからこそ、長期的な視点で取り組めるということもあります。今、ようやく新規ビジネスが収益化し始めたんですけど、収益化するまでに3年半かかっているんですね。それまで別のビジネスで収益を上げていたんですけど、普通のベンチャーって3年半も無収益で投資し続けられないんですよ。特にITベンチャーは、早くキャッシュ化して、さっさと会社を大きくしてという成長志向が強い中で、うちの会社は、ひたすらコツコツと土台作りを続けられたというのは、こういうマインドセットというか感覚を持っているからだと思うんです。
自然の摂理を味方につける
――自然の流れに沿っているものは、絶対に強いという信念があると、自分たちのやっていることが自然の流れに沿っているから絶対に大丈夫という確信が持てるじゃないですか。そういうのがないと、突っ込めないですよね。それがあるから、みんなが信じて、続けられるわけですもんね。
うちの会社で話し合いの中でよく出てくるキーワードが「自然の摂理」なんです。うちの会社は、自然の摂理なんだから、そこには、良いも悪いもないし、傍から見たらすごくシビアな一面もあります。自然の摂理にフォーカスすると、人間の感情が付け入る隙がないんです。人情とかで曲がった意志決定がされているかどうかというのが、すぐに感じられるんです。普通の会社だと、こいつは頑張っているからとか、長く働いているからとかいうのが考慮に入ってくると思うんですけど、全部透明にすると、そういう小細工ができないんですよね。いろいろ試してきた中で気づいたのが、自然の摂理って、あんまり頑張らなくてもよくて、全部透明にしてみんなに見えるようにすると、勝手に組織が浄化されていくんですよ。
――それは、すごいですね。僕なんかは、生活の基盤が別にあって、それとは別にオンラインコミュニティの運営をやっているから、ある意味、おもいきった実験がやりやすいんですよね。失敗しても、また始めればいいやってことになるので。企業体は、みんなの生活をがっちり抱えているから、そこでやっているというのが、本当にすごいなって思います。
しがらみは増えますね。それを、一つ一つ紐解いている感じですね。
生き物とホラクラシー型組織の関係
――武井さんの書いているものの中に、複雑系とかホロンとかという言葉が出てきて、それは、僕の中でも大きなキーワードなので、おおぉって思ったんです。それらは、どういう位置づけ何ですか?
もともと鈴木利和さんから、そのキーワードを教えていただいて、ソフィアバンクのの田坂広志さんのことを知ったんです。田坂さんを、僕はすごく好きなんです。田坂さんが、複雑系マネージメントということをすごく研究されていて、組織は複雑になればなるほど、生き物のようにそれ自体が意志を持っていくと言うんですね。田坂さんが、よく例えるのが、「魚を捌いたら、魚は死んじゃうだろ。身体を切り裂いて分解すると生き物は死ぬんだ。今の経営スタイルというのは、そういうことをやっている。分析をしたり、分断をしたり、分けていくということは、意識を切り刻むことなんだ。身体を切れば切るほど、組織としては弱っていく。だから、我々は、一切切り刻まないで、1つのものとして大切に扱っていく。」ということなんです。そうすると、自然とホロン=全体性が生まれるんです。部分と全体って区分けするわけでも無くて、部分でもあり、全体でもあり、自分と他人は、同じ組織の中だと繋がっているので、分けること自体がナンセンスだと思っているんです。だから、うちの会社には、階層もなければ、事業部のような縦割りもないんです。
でも、やっていて、現実問題にぶつかることがあって、役職がなくていいねというのは、皆さん言うんですけど、ビジネスを回していると、役割分担は必要になってくるじゃないですか。役割分担をすればするほど、ダイナミズムが生まれますよね。貨幣経済が、そもそも、それぞれが分業することによって、生産性が高まるということですよね。なので、その原理自体は、やっぱり必要で、それぞれが自然と自分が得意なところで役割分担していくということなんです。うちの会社は、組織図はないんですけど、ビジネスモデルを健全に回す上で、営業機能とか、マーケティング機能とか、開発機能とか、管理部門とか、身体の内臓みたいに臓器は必要なんですよ。ただ、細胞が、どこに行っても適応できるみたいに考えています。企業体と身体のつくりは、似ているなって思っています。組織自体も、そんな風に設計して、身体が異物を取り込んだときにどうやって排除するかというプロセスと、我々みたいな組織の異物を取り除くプロセスは、同じにしないといけないと思っています。でも、今の世の中は、脳みそが勝手に、こいつは良い、悪いって判断しているけど、人間の身体だともっと自然に排除されていくわけじゃないですか。経営陣は脳みそみたいなもので、でも、脳みそがすべてを判断しているわけじゃなくて、身体のほとんどは、心臓もそうですし、勝手に動いていますよね。そういうイメージで、組織を作っていますね。
――僕は、大学院で個体の境界をテーマに研究していたんですよ。当時、東北大にいた澤田康次さんが、個をどうやって定義するかという研究をしていたんです。ヒドラを遠心分離器にかけてバラバラの細胞にすると、細胞同士がコミュニケーションを取って、そこから再生して、多細胞体のヒドラに戻るんですけど、どの段階で、多細胞体の個が生まれたのかって調べていたんですよ。それで、情報を受け取る量と生成する量に注目して、半分に切ったときに情報生成量の割合が減るようだったら、組織になることによって情報が生成していたんだから、組織に個が生まれていたというように考えるって言っていたんですね。細胞の単なる寄せ集めなら、半分に切っても、ただ分けただけで、何も失われないんですね。集まったことによって生まれたものがあれば、それが、切ったときに失われてしまうわけです。
細胞がコミュニケーションを取る中で、自動的に分化が起こるんですけど、分化の比率って、自動的に調整されるんです。たとえば、細胞性粘菌なら、胞子になる細胞と柄になる細胞との比率が4:1くらいになるんです。半分に切っても、それぞれの細胞集団の中で、また4:1に再分化するんです。その比率調整のメカニズムがどうなっているのかという数理的メカニズムも、研究していたんですよ。そこでカギを握るのは、情報の共有なんですよ。細胞集団が、1つの場を共有して、細胞の時間スケールと、場の変化の時間スケールがマッチングして、部分と全体が分けられない状況になると、その場を通して1つのシステムになって、全体として安定な状態へと落ち着いていくんですよ。だから、武井さんの会社で、データを共有するインフラを作ったというのが、自己組織化が起こるために本当に重要な役割を果たしているなって思いました。
情報と流通が変われば、必然的に社会構造の相転移が起こると思うんです。論理的に考えれば、インターネットとか、LCCとかが、社会構造を変えるための制御パラメータの役割を果たすと思います。生命とか生態系のアナロジーで、全体で広く情報が共有されれば、不自然なものは崩壊して、自然の流れとして自己組織化が起こって、落ち着くところに落ち着いていくはずなんじゃないでしょうか。
本当にそうですね。会社の中で情報をオープンにしていくと、勝手に権力も発動できなくなるんですよね。変なことをやると、明らかに突っ込みどころ満載になるわけじゃないですか。「お前偉そうなこと言っているけど、お前の給料、なんでそんなに高いんだよ。」とか。嘘がつけなくなるんです。でも、そういう風になると、これは、やってみて面白かったんですが、透明にすると隠し事ができなくなるんで、やましい気持ちすら起こらなくなるんですよね。経費も全部オープンで、いくらでも使っていいけど、使った額と内容が誰で見れてしまうんで、ちょろまかしてやろうという気持ちも起こらないんです。
――禁止されたりしないと、ルール破れないというのもありますよね。隠れる場所もないですもんね。
隠れる場所がないと、隠そうという気持ちが生まれ無くなって、そうなると、相手に対する猜疑心が生まれ無くなるので、人間関係がめっちゃよくなるんですよ。やましさがない中でのコミュニケーションになって、本質でのぶつかり合いができるんです。これは、やっていく中で、気が付いたことです。
販売する側とお客さんとの関係をフラットにしていく実験
――去年から、仙台のSawa’s Cafeというシェアカフェの運営の相談に乗っているんです。店主のさわさんという方は、元公認会計士なんですが、311の後、お金や、社会の在り方に疑問を持つようになって、それを変えていくための場を創りたいということでシェアカフェを創ったんです。でも、お金を稼ぐためにやっているわけじゃないということもあって赤字続きで苦しくなってきたんですね。でも、これは、すごく面白いプロセスだなって思ってコミットしているんです。いよいよどうにもならなくなってきたので、Sawa’s Cafeの存続を願っているお客さんとか、共感して集まっている人80人くらいで「Sawa’s Cafe持続化プロジェクト」というfacebookグループを立ち上げて、その中で、カフェの経費とか、利益とかを全部オープンにしたんです。そしたら、予想をはるかに上回る赤字なんですよ。笑 でも、情報を共有したことで、持続化プロジェクトの中で、その数字がみんなごとになって、それぞれが、アイディアを持ち寄って動き始めたんですよ。
それは、究極ですね。
――お客さんだった人が、クラウドファンディングの情報とかを調べてきてくれるんです。「今月は、あと10万円利益でないと家賃払えません」みたいな途中経過が見えるようになってきて、危機感を共有したことで、みんな、自分がやらねば!って感じになっているんですよ。イベント使用料を見直したり、実現したい未来とか、想いを確認したり、そういうことを、お客さん(だった人)と一緒に考えられるようになったんですね。
すごいですね。それ! その話は、うちの会社でも、実は何回か出たことがあって、うちの会社の内情を、外に対しても全部オープンにしちゃおうかって。そしたら、ファンのお客さんとかが助けてくれるんじゃないかっていう意見も出たんです。でも、さすがに個人個人の給料とかまでもオープンにするのはどうかなっていうことでやっていないんです。
――Sawa’s Cafeも一般公開じゃないですもんね。コミットしてくれている80人くらいの間でオープンにしているってことですからね。でも、オープンにしたことで、確実に場が転換して、次のステップに進んでいるんです。カフェという形態のままで続くかどうかは分からないし、別の形に変わっていくかもしれないけど、そこにコミットしている80人が望むような形になっていくと思うんですよね。
すげぇー。それ、めっちゃ面白いですね。
企業再生って、民事再生とかよりも、そういうやり方のほうがうまくいきそうな気がしますけどね。
――これって、生きていることとは何かということと関係していると思うんですね。このカフェも店主が存続させたいと思っているわけじゃなくて、みんなが存続させたいんだったら、その願いによって存続するし、みんなが存続を願っていないものなら無くなればいいでしょってことなんです。存続させたいという想いが集まってくるのなら、そこから何かしらの形が創造されるでしょってことなんです。手放してしまえば、なるようになっていくんじゃないかと思うんです。
いやー、その世界観は、まさに自然の摂理ですよね。
ニーズを満たしあう関係性をデザインする
――武井さんもご存知の由佐美加子さんのところのCCCとコラボで2月にNVCのオンライン講座をやるんですが、そこの運営に店主のさわさんを加えて、オンラインの運営ノウハウを持ち帰ってもらう予定なんです。Sawa’s Cafeは、創造的な場になっているので、オンラインでも発信してもらいたいなって思っています。
いやぁー、僕の会社も、もっともっとオープンにしたいですねー。笑
――今の僕の役割って、組織の枠組を超えた広い意味のマネージメントだなって思っていて、創造がうまく起こるような組み合わせを見つけてきて場を創るって感じなんですよね。いろんな人と話をしたり、アウトプットしているものを読んだりして、この人たちで集まったら面白いことが始まりそうというのが感じ取れるようになってくるので、集まって一か月くらいワイワイやる。また別のところで違うものが始まるから、そこに巻き込んだら、その人の人生にとっていい感じになりそうだなという人を巻き込んでワイワイやるって感じなんです。そういうプロセスが、ぐるぐる回っているんです。それが、完全にオンラインで回っているから、それぞれが組織に所属していても、組織の枠を超えて集まって何かができるんですね。
そこで、お金をもらう人と、ボランティアで活動する人と、お金を払う人というのがいるんですね。そのバランス調整をどうするかというのがあるんです。ある程度ゆだねると、感動的な状況が生まれるんです。過去にオンライン講座を経験した人のリストに運営ボランティア募集の案内を投稿すると、希望者からメールが来て、運営+ボランティアの10人くらいのチームができて、講座が始まるんです。最初は、フリーライダーが出てくるんじゃないかという恐れがあったんです。でも、サービス提供側とお客様という関係性を変えて、境界を曖昧にして、オープンでフラットな関係にしていくと、参加者のほうが調整してくれるんですよ。「私たちの年代がお金を払う側に回らないといけないから、受講者で参加します」とか、「運営ボランティアをやりたいけど、お金も払いたいので払います」とか、そんな感じになって来たんです。こちらは、感謝して受け取ることにして、その人たちが求めているものを満たせるような場を一生懸命作るということになって、ポジティブな空気が溢れるんですよね。
この間、共生革命家のソーヤ海さんと話したときに、彼が、「ニーズを満たしあう関係をデザインするのがパーマカルチャーの考え方だ」って言っていたんですね。それは、植物だけじゃなくて人間同士の関係も同じだって。僕は、お金を払うことで貢献したいというニーズもあるんだなって思ったんです。自分にもそういうニーズあるんですよ。お金の払い方も含めて、きっちりしたものを緩めていくと、何かできそうだなって気がしているんです。
そこもゆだねちゃうんだ。
――武井さんも同じ感覚があると思うんですけど、1つ壊してみて、大丈夫そうだったら、もう1つ壊してみたくなるじゃないですか。
分かります。
生き物のような組織を循環させていく
反転授業は、田原さんのビジネスなんですか?それとも別のものなんですか?
――今は、非常にあいまいなところに位置していて、最初はビジネスマインドでスタートしたんですけど、やっているうちに問題意識が深まっていって、社会的なムーブメントに近づいてきています。オンラインのワークショップのノウハウが集合知的にできてきたんです。すごいやつが。これは、自分だけで作ったものじゃなくて、グループの集合知でできてきているものだから、共有財産なんですよ。そして、そうやってできてきたオンラインの学び場が人材育成の場にもなってきているなって気が付いたんです。教師にとって、オンライン講座の運営をやるということは、学校にいながら、学校以外の社会に出て働く経験を持つことができるということだったりするんです。その経験は、学校に戻れば、キャリア教育とか進路指導に役立つ体験にもなると思います。未来の働き方を先取りするような体験をしていることになるので。次々運営ボランティアという形で人材が育成されてくるので、その人たちを外に出していく場を創ろうということで外とコラボする機会を作っていくのが自然だなと思って、ワークショップやっている人とかとのコラボレーションを企画しています。そうすれば、根から吸い上げた水が葉から蒸散していくように、いろんな人が反転授業の研究を通して外に出ていけるなって思っています。それで、最初のコラボが、CCCとだったんです。
最近気づいたのは、形は変わっても、精神が受け継がれていけばいいのかなってことなんです。10年前くらいにも主体性教育の盛り上がりがあって、そこで創造のサイクルを回した人たちが、今、コミュニティに加わってきてくれているんです。考え方がすごくシンクロしているのを感じていて、僕たちの活動は、その人たちの精神を受け継いでいるんだなって思うんですね。「反転授業の研究」も、いつかは役割を終えて衰退すると思いますが、運営のノウハウをマニュアル化して配っているので、そこで学んだ人たちが、たんぽぽの綿毛のように飛んでいって、別のところで創造のサイクルを回してくれれば精神は受け継がれていきますよね。そういう動きも生き物っぽいなって思います。そういう循環こそが生き物だなって思います。
あぁ、いいですね。なるほどー。
――オンライン講座をやったときに、すごい幸福感があったんですよ。困ったことがあっても、それをオープンにすることができて、みんながよってたかって助けてくれるので、参加者も運営もお互いにサポートされている感じがあって幸福感があったんです。それで、参加者の一人が、「ここは、ネット果樹園か。オンラインの桃源郷か」みたいなことを言ったりしていたんです。その体験があったときに、こういうことがあちこちで起こればいいんだなって確信したんです。プロトタイプができたなって実感があったんです。たぶんその確信と同じものを武井さんも持っているんじゃないかって思うんですけど、いかがですか?
田原さんのおっしゃる「支えられている感」というのを、僕なりに感じるところがあります。給料とかをオープンにしてやっていると、その人のプライベートも見えてきて、会社が利益を上げて、分配することによって、みんなの人生が支えられていているというところまで繋がっていくんです。逆に言うと、自分の人生を自分一人で支えなきゃいけないという恐怖感から解放されるんですよね。「みんなも俺の人生を支えてくれているんだ」って思うと、ちょっと楽になるんです。今は、自立つしなくちゃいけないと言われますけど、自分一人で立つのは大変ですよね。自立しながら、支え合いながら、というようになると組織全体としてうまく賄えるんですよね。そうするとすごく楽になりますね。
――だから、ホラクラシー経営が広がってほしいですよね。新しい働き方とか生き方のプロトタイプを武井さんが創られているんだなって気がしますね。
そうですね。お手本になりたいなって思っていますね。
対談を終えて
武井さんとお話して、見ている世界や、体験しているものがとても近いと感じました。試行錯誤をしながら、人間同士の新しいつながり方を土台にした組織づくりをしている武井さんの口から出てくる言葉は、オープンでフラットなオンラインコミュニティを自己組織化させようとしている僕にとってヒントの宝庫でした。
場を創る人がコントロールを手放して自然の流れに委ねると、みんなが楽に動けるようになって共創が起こっていくというのが、まさに自然の摂理なんだなって思います。
それを教室の中でやるのがアクティブラーニングや反転授業で、企業体の中でやるのがホラクラシー型経営。
アクティブラーニングや反転授業で育った生徒たちが、将来、あちこちにホラクラシー型の組織を作っていくと世界は変わっていくのだという未来図を思い描くことができました。
ドラマが起これば未来がやってくる
「反転授業の研究」の田原真人です。
不確定な時代を生きていく上で、僕が心のよりどころにしている言葉があります。
それが、
ドラマが起これば未来がやってくる
という言葉です。
自分が思い描いている結果を手に入れようとして、そこに固執していると、思うようにならない現実をすべて敵に回すことになり、心身共に消耗していきます。
でも、力尽きたその果てに、自分の思惑を超えた大きな流れに身を任せることができると、自分が思いもよらなかった未来がやってきて、後から振り返ってみると、すべてが必要なプロセスだったと感じられるような結果が得られたりするのです。
そのような経験を繰り返すうちに、
結果を求めてもしょうがない。大きな渦が生まれ、自分を手放してそこに巻き込まれていくことでドラマが展開すれば、未来へたどり着くことができるのだから、ドラマを起こすことに意識を集中していこう。
そんな風に考えるようになりました。
クラウドファンディングを通して気づいたドラマの持つ力
2年ほど前からクラウドファンディングに関わるようになりました。
僕の場合、関わると言っても、自分が資金集めの主体になったことはなく、勝手におせっかい応援団を作っていくという関わり方です。
自分の問題意識と強くシンクロする人がときどきいて、その人がアウトプットしていることを読んでいくうちに、この活動にコミットしていきたいというスイッチが入るんですね。
自分で自分のことを「応援してくださーい」と言うのは、なかなか難しいです。
でも、利害関係のない人が、「あの人を応援しようよ!」と言っていくのはやりやすいです。
だから、応援者の存在が、クラウドファンディング達成のカギを握ることが多いです。
それで、主体になっている人には、「僕達の聞きたいのは、あなたの想いだから、とにかく想いを連載の形でアウトプットしていってください」とお願いします。
そして、そのアウトプットに自分の想いをシンクロさせながらSNSなどで拡散していきます。
そうすると、その想いが祈りのように広がっていって、そこに共振、共鳴した人たちが続々と集まってくるんですね。
そして、だんだんとシンクロが強まっていってうねりが大きくなっていきます。
でも、そうはいってもクラウドファンディングの締め切りは近づいてきて、達成は厳しい状況になってきたりすることもあります。
心の中に様々な想いが行き来し、そこに関わってきた人の心も大きく揺れ動き、そこからさまざまなアクションが生まれてきます。
クラウドファンディングの締め切りに向かってドラマが展開していくんですね。
その中で、ふっと気づくわけです。
本当に大切なことは、クラウドファンディングを達成してお金を得ることではなく、主体者の想いに人が集まってきていて、様々なアクションを自分から起こしてくれているドラマそのものなのだということに。
そして、ドラマが大きく展開すると、クラウドファンディングを達成したかどうかに関わらず、必ず未来がやってきます。
そこに関わったすべての人が、それぞれに大きな学びを収穫し、マインドセットが変わり、世界に対する信頼感を強めます。
そして、毎回、つぶやくんです。
やっぱり、ドラマが起これば、未来がやってくる。
大学の教室でドラマを起こしていく
ドラマには、様々な要素があります。
先の見えないカオスの中で、困難にくじけそうになり、仲間と助け合い、自分のこだわりや怖れを手放すと、予想もしなかった展開が生まれ、未来がやってくる・・・・。
これこそ、まさに学ぶということなんじゃないかなって思います。
それを、大学の教室でやってしまっているのが、京都精華大学の筒井洋一さんの「グループワーク概論」
筒井さんが始めた劇場型授業は、まさに授業の中でドラマが展開することを意図しているものだと思います。
この授業にずっと関わっている大木誠一さんのコメントを引用します。
劇場型授業が教室に創りだした場は、日常生活のインフォーマルな学びと学校に代表されるフォーマルでアカデミックな学びを接続するための機能を持っています。「学び」というと、学校を想像されるでしょうが、人の学びの大部分は、普段の生活にあるインフォーマルな学びです。これが、「人は生まれた時からアクティブな学び手である」といわれる所以です。人は、誕生した時から周りに人達とつながることで、いろいろなことを学んできています。しかし、いま、多くの学生や生徒は、日常生活のインフォーマルな学びと学校のフォーマルな学びを接続することに成功していません。
「オープンでフラットな場」とは、大学の境界を越えて教室に参加したすべての人が構成するインフォーマルな「カオス(混沌)」です。そして、この「カオス」は、すべての参加者の日常(インフォーマルとフォーマルの両方)と、教師と学生で構成される教室というフォーマルな場の中間に位置している新たに創りだされた場です。
この場では、最初、参加者同士の関係性が生まれていないために、参加者の役割が不明確で、手探りの状態です。この場の参加者は、主体的かつ能動的に他の参加者と関係性を作りだし、この場での役割を自ら見つけ出す必要があります。
振り返りの時、初めての見学者は、「どのように振る舞えばよいかよくわからなかった」とよく言われます。これは、すべての参加者が感じている疑問です。CTは、当日の進行を任されているためにより強くこの疑問を感じているはずです。
授業が始まって間もなく、CTと学生の間に「想い」の食い違いが必ず生まれ、教室に対立や矛盾が生まれてきます。これを上手く解消し、見学者を巻き込みながら学生と一体となって教室に新しい「学びの場」を創りだすことが、CTと学生に求められていることです。CTが、先行してこの活動に取り組むなかに学生が巻き込まれ、なかにはCTと同じ役割を果たす学生が出てきます。
劇場型授業では、CTの成長が目に見えて著しいものになっています。しかし、これに巻き込まれた多くの学生にも、明からな変化や成長が見られます。そして、その変化は、学校外の活動への積極的な参加へと結びつく場合もあります。
上手くデザインされ、細部にわたって構造化された授業デザインでは、この動的な変化は起こりません。「安心で安全な場づくり」と「失敗できる環境づくり」は、この授業のプロセスから生まれる途中経過とその結果を示していると考えています。この授業のスタートは、不安で不確実な混乱した状態で、何が起こるかわからない状況です。この社会の現状と近似した「カオス」こそが、この授業の本質です。
すべての参加者の出発点である「カオス」のなかで生まれる対立と矛盾から、「安心で安全な場」と「失敗できる環境」が生み出され、最終的に「学びのコミュニティ」を形成されていくことがこの授業の狙いです。
インフォーマルな学びと学校のフォーマルな学びを接続する場は、参加者自らが主体的かつ能動的に関係性をつくりあげなければ崩壊する大変もろい地盤です。しかし、この試練をとおして、学生は自らのインフォーマルな学びと学校のフォーマルな学びを接続することができるのではないでしょうか?そして、この参加者すべての試練の軌跡を、全体として眺めると、それはこの場の創りだす「創発」現象と視ることができると考えています。これこそ、「21世紀型スキル」のようなジェネリックスキルを育成する場のアプローチとして重要視されているものではないでしょうか。
クラウドファンディングを経験した僕たちは、共にカオスの海を乗り越える冒険をしたことで、冒険の後に信頼で結ばれたコミュニティが誕生するという経験を何度もしました。そして、それこそが価値があることなのだと気づきました。
大木さんが、最終的に「学びのコミュニティ」が生まれていくことを授業の狙いとしているというところに、僕たちの経験との強い類似点を感じました。
外から現れる見学者の存在も、場へ不確定性を加える役割を果たしていると思います。
その不確定性は、固定した着地点を目指す場合にはマイナスになるかもしれませんが、ドラマが、よりドラマチックに展開することを意図するのであればプラスになります。
「ドラマが起これば、未来がやってくる」のです。
新たなドラマの始まり
僕は、今、『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』のレビューを連載という形で書いています。
その理由は、何かというと、「あ、新たなドラマが始まった」と感じたからです。
学びを未来型に変えていくために、京都精華大学で生まれた劇場型授業を外へ出していこう、そのために、本を執筆しようということで動き出したプロジェクトは、出版を引き受けてくれる出版社が見つからないという困難にぶつかりました。
そこで、筒井さんが自己資金を投入してリスクを背負い、教員、CT、見学者が協力して共同執筆することでこの本が生まれました。
この本が4000~5000部程度売れないと、筒井さんは赤字なのではないかと思います。
ドラマが展開する舞台は、すっかり整いました。
僕は、このドラマに加わりたい。
これから待ち受けている困難を共に乗り越えることで、ドラマを展開させていき、筒井さんたちと学びのコミュニティを形成したいのです。
まだまだドラマは始まったばかり。
これから生まれるであろう渦に巻き込まれたい人は、ぜひ、コミットしてきてくださいね。
全体性から生きるAuthentic Leadership 基礎特別編
「反転授業の研究」の田原真人です。
工業化社会のパラダイムが終焉を迎えつつあり、そこに適応するための成功マニュアルや教育システムが大きく揺らいでいる時代に、私たちは生きています。
学校は、生徒に正解を暗記させる教育から、生徒自身が自分の根っこの想いを発見し、繋がり、共創していくことを支援する教育へとシフトしていくことが求められ、アクティブラーニングや反転授業が注目されるようになりました。そこでは、教師に求められる役割は、TeacherからFacilitatorやCoachへと変化します。これは、今まで生徒を管理し、知識を教えることを役割としてきた教師にとって、マイインドセットを大きく変容させることを意味します。しかし、どうすれば、マインドセットを変え、生徒を受容して支援できるようになるのでしょうか?
親が子どもの幸せを願う気持ちはいつの時代でも同じだと思います。でも、社会的地位が必ずしも幸せと結びつかなくなってきている時代になり、親が子どもに正解を与えることは難しくなってきています。子どもが自分らしく輝いて、生き生きと幸せな人生を送るために、親はどのような支援をすることができるのでしょうか?
教師や親が、子どもとどのように関わっていけばよいのかというテーマについて、私たちはオンラインの学び合いを重ねて来ました。その中で、CCCの由佐美加子さんを通して、U理論やNVC(非暴力コミュニケーション)と出会いました。そして、由佐さんが語る「良い・悪いの二元論の世界観から、在る事が在る、全体性の世界観へのシフト」こそ、転換期を迎えている私たちに必要なものなのではないかと考えるようになりました。
ちょうどその頃、オンライン講座の可能性を探っていた由佐さんと話す機会があり、想いが共鳴し、合同会社CCC(Co-Creation Creators .LLC)と「反転授業の研究」のコラボレーションによるオンライン講座が実現しました。
NVCの定義や、講座の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
オンラインで学ぶメリット
私たちは、オンラインでこの講座を扱っていきます。
オンラインで開催する理由は、以下の通りです。
1.オンラインのツールが発達し、オンラインにおいても円滑なコミュニケーションを取りながらこれを学べる環境が整ってきたこと
2.仕事や育児が終わった夜に自宅からアクセスでき、全国どこからでも会場に出向くことなく参加できること。
3.学習の足跡がオンライン上に残り、後から復習できること。また反転学習方式を取り入れることで、事前の予習を可能にし、受講者のスタートラインの凸凹を揃えられること。
CCCが提供している『全体性から生きるAuthentic Leadershipシリーズ』は2015年に開始し、毎回募集が告知されてから2時間足らずで満員御礼、キャンセル待ちになってしまうほどの大変好評な講座です。ただ、物理的にも時間的にも人数を増やしたり開催回数を増やす事が難しく、ニーズに応えきれてない状態だったのだそうです。
また、東京に通うのが困難な地方在住の方や、育児中でワークショップに参加する事が難しい方々などにもなかなか機会を提供する事が出来ないジレンマを抱えていたのだそうです。
「反転授業の研究」が実施している参加型のオンライン講座のフレームにCCCの『全体性から生きるAuthentic Leadershipシリーズ』を乗せることで、これまで参加が困難だった方へ講座を届けることができるようになりました。
新しいオンラインでの学び方
オンライン講座というと、動画などを見てひとりで学ぶイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?
また、拘束力が弱いため、オンラインだと最後までやり遂げられないというイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。
「反転授業の研究」が運営するオンライン講座は、学習者中心の考え方に基づき、様々な工夫をしており、過去6回の講座では、脱落者が10%以下(そのうち2回は脱落者ゼロ)という驚異的な修了率を達成しています。
その秘密は、ビデオ会議室を使った独自の講座運営方法にあり、オンラインであっても、非常にコミットメントが高まる仕組みになっています。
講座は、Moodleと呼ばれるプラットフォーム内に作られたフォーラムでの非同期の学び合いとWeb会議室Zoomを使ったリアルタイムセッションから構成されます。
Web会議室を用いたリアルタイムセッションでは、講座開催中に全部で5回行われ、ファシリテーターによるレクチャーや、小グループでのワークなどを行います。
Zoomを使ったグループワークの様子 ※写真は「ファシリテーション・コーチング講座」のときのものです。
Web会議室を使ったワークの後、課題をMoodleへアップし、他の受講者が提出した課題を読み、相互にコメントし合うことによって更に気づきを深めていきます。
その他に、週に1度、オンラインの雑談部屋を開きます。まじめなリアルタイムセッションとは違って、飲み物を用意して、リラックスした気分で参加す る雑談部屋では、笑い声が溢れ、本音トークが飛び交います。同じ講座に参加している受講者同士で交流できることもこのオンライン講座の魅力の一つです。

※写真は「ファシリテーションスキル入門」のときのものです。
「反転授業の研究」が運営するオンライン講座には、受講者間の繋がりが深まっていく仕組みがあります。
それは、オンラインであっても、「会っている」「参加している」という実感を感じることができるからかもしれません。
その結果、これまでの講座では、講座終了後も受講者同士の関係性が継続し、多くのコラボレーションや、オンラインの学習コミュニティが生まれていま す。
ファシリテーター・運営チーム紹介
ファシリテーター:由佐 美加子 (Mikako YUSA) CCC パートナー幼少期からヨーロッパ、アジア、 米国で育ち、米国大学卒業後、 国際基督教大学(ICU)修士課程を経て野村総合研究所入社。その後リクルートに転職し、事業企画職を経て人事部に異動。以降、様々な場をつくるファシリテーターとして人と組織、社会の覚醒と進化を探求し続ける。
2005年、米国で組織開発修士号を最高成績で修了。2008年にNVCと出会い、自身の子育ての中でその素晴らしさを体感し、数々のワークショップに参加するようになる。2013年にBay NVCのリーダーシッププログラムに参加し、その学びを分かち合う「全体性を生きるコミュニティー」を通して日本各地でNVCを共有する活動を始める。
企業組織やその核となっているリーダーたちに自己共感や共感に基づくコミュニケーションを様々な形で導入する傍ら、合同会社ファミリーコンパスを立ち上げ、2015年は家族の中でNVCの精神を体現する親を増やしていく活動を本格化する予定。
『U理論―過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』訳者
『未来を変えるためにほんとうに必要なこと』監修
運営責任・オーガナイザー:藤本 海 (Kai FUJIMOTO) CCCパートナー大学卒業後、株式会社キャリアデザインセンター入社。 転職情報誌『type』や転職サイト『@type』の運営に携わる。 営業として数々の記録(2年連続年間MVP・売上ギネス等)を残し、入社3年目で最年少マネージャー、5年目には最年少で部長に昇進。営業部長、@type編集長、事業推進室室長を兼任しながら猛烈に働き、 自社のIPOや東証への上場にも貢献。
震災後、世の中の価値観がシフトしていくのを感じつつ、『自分の心が何に震え、何に感動するのか分からなくなった』と唐突に退社し、海外16カ国を放浪。
2012年に株式会社doorz創業に取締役兼CMOとして参画。同社の海外研修プログラムが「日本の人事部 HRアワード」でプロフェッショナル部門最優秀賞を受賞。
翌年、現パートナーと共に合同会社CCCを設立。年間200日以上『場』に身を投じ、組織の変革やリーダーシップ開発、個人の変容をサポートする「場」のファシリテートに携わる。現在も「人間が本物として生きる」をテーマに自己探求を進めながら、個人と組織の可能性を拓く「場」と「機会」を創り続けている。
合同会社CCC
http://www.cc-creators.com/
運営責任・オーガナイザー:田原真人(Masato TAHARA) 反転授業の研究主宰、オンライン教育プロデューサー
早稲田大学の博士課程で生命現象の自己組織化やカオス理論について研究。大学院時代に価値観が大きく転換し、大学院を中退して物理の予備校講師になり、河合塾などで10年以上教える。2004年から物理ネット予備校(フィズヨビ)を立ち上げ、動画講義やMoodle、Web会議室を使ったオンライン教育に取り組む。現在は、オンラインでの反転授業、ワールドカフェ、ワークショップ、ダイアログなど、オンラインでの場創りに取り組んでいる。
2012年から始めたオンラインコミュニティ「反転授業の研究」の活動を通して、自己組織化、オンライン、教育という3つのキーワードが自分の中で結びついたことで、オンラインにコミュニティを自己組織化させて教育にパラダイムシフトを起こしていくことに使命感を感じるようになった。「反転授業の研究」は、現在、約3700名まで増え、様々な活動が自己組織化している。
2014年にU理論と出会い、価値観が大転換した自らの経験を言語化できるようになったことから、CCCの活動に興味を持つようになる。教育や育児の世界にNVCの精神を届けるために、今まで培ってきたオンライン講座のノウハウを利用できることに喜びを感じている。
『微積で楽しく高校物理が分かる本』
『日本一詳しい物理基礎・物理』
『物理をこれから学びたい人のための科学史・数学』
など著書10冊
運営:松嶋渉(Wataru MATSUSHIMA) 山口県立萩商工高等学校 情報デザイン科長
映画関係、出版関係の仕事を経験し、30歳から教師としてのキャリアを始める。主にICT教育に携わっており、授業ではプログラミングやWeb制作に関することを教えている。
本業での活動の一端が、2015年12月発行のリクルートのキャリアガイダンスで全国の「学び合い、挑戦し続ける教師たち」8人の中の1人として紹介された。
http://souken.shingakunet.com/career_g/2015/12/2015_cg410_23.pdfICTを利用した反転学習にも取り組み、2014年に実教出版の小冊子に寄稿している。
「ICTを利用した反転授業『ビジネス基礎』」→http://www.jikkyo.co.jp/download/detail/69/9992656674現在では本業の教育活動と並行して地域やオンラインでの活動に携わっている。
直近携わったオンライン講座では、受講生31名、スタッフ14名の運営総括として活動し、オンライン講座に関しての多くの知見を得る。
地域のボランティア活動の一環として地元コミュニティFMでDJも行っている。
http://www.haginet.ne.jp/users/nanako775/personality/profile.html#matsushima
運営:ギュンター知枝(Chie GUENTHER) 徳島大学非常勤講師
徳島大学非常勤講師・パステル和(NAGOMI)アート公式インストラクター京都市立芸術大学音楽学部(声楽専攻)卒業後ドイツに渡り結婚。7年間ドイツに住む。その後帰国して通訳・翻訳・司会・会社員を経て、現在徳島大学でドイツ語の非常勤講師をしながら自宅でパステル画のワークショップを実施。
2013年秋より「反転授業の研究」に参加。オンラインで多くの「学びの仲間」を得る。また、「反転授業の研究」主催のオンライン講座で運営ボランティアを2回経験し、地方在住で学び続けることへの大きな可能性を感じる。
【目指しているのは、半径10メートルの人たちをちょっとだけ幸せにすること】
ふと目の前に現れた蝶々や、遠くの花火みたいに
何かを「する」ことによってではなく
そこに「在る」ことで人の心に小さな幸せをもたらすような存在になりたいです。「こんな生き方もありだ!」という一例になれたら、と思い
地方に住んでいても、家にいることが多くても
世界とつながって進化していく方法を模索中です。
運営ボランティアのみなさん
このオンライン講座では、運営ボランティアが大きな役割を果たします。運営ボランティアが入ることで、場がホールドされ、オンラインに安心・安全の場が生まれます。
運営ボランティアの皆さんとの交流も、この講座の価値の1つだと思います。
佐藤さわ(Sawa SATO) 仙台Sawa’s Cafeオーナー
みなさん、はじめまして!
宮城県仙台市でSawa’s Cafeというコミュニティカフェをやっている佐藤さわと申します。震災後、おカネのために自分の時間を切り売りして働く働き方に疑問を感じ、公認会計士としてそれまで10数年勤めていた監査法人を退職し、会計士の登録も抹消して、すべての人がつながることのできる場所を目指してカフェオーナーになりました。
年収はそれまでの10分の1以下になりましたが、幸福度は10倍、いや、100倍くらいアップしました。
なにより、幸せの「質」が以前とは全然違うように思います。
それは、今している仕事が、「自分のニーズ(心の奥底の生命エネルギーと繋がった欲求)」とつながっているからだと思います。
由佐さんのワークショップを通して、みなさんがご自分のニーズとつながり、私のように幸福度がアップすることを心から願っています。
今回は、田原さんのご厚意により、運営ボランティアに加えていただくことになりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
スギオカカズキ(Kazuki SUGIOKA)株式会社青い街代表
東京造形大学の研究過程を終了した後、渡米。河原温氏や川島猛氏のアシスタントをしつつ、自らの作品制作や論文執筆にいそしんだ。
帰国後は、広告代理店、出版社勤務を経て、デザイン制作会社のマネージメント職に就任。最多50人の部署をまとめる一方、未経験者のスキルアップに注力し、デザインの基礎講座やデッサン講習会等を社内で企画・運営した。しかし、震災後の社会変化(中でもあからさまな情報操作)に違和感を覚え、一時は鬱状態となる。結果として前職を退職することにもなったが、多くの人の支えもあって復調。
現在は、デザイン関係の仕事をベースに、新しい時代の在り方を模索する活動を続けている。たとえば、アートの「見せる」「見せられる」という一方通行性は、従来の教育システムと類似していると思う。
反転学習の持つ可能性は、さまざまなジャンルに波及・発展させうるのではないだろうか。
ワークショップ形式で学ぶオンライン講座
この講座は、解説動画、MoodleでのフォーラムセッションとWeb会議システムZoomによるリアルタイムセッションを組み合わせて、4週間(リアルタイムセッション5回)のオンライン・ワークショップ形式で行います。
【対象】
ファシリテーションとコーチングに関心があり、コミュニケーションスキルを改善したいと考えているすべての方
【受講前に準備していただきたいもの】
(1)Webカメラとマイク付の端末
リアルタイムセッションでは、各自がビデオチャットで参加しますので、Webカメラとマイクがついたパソコン、または、タブレット端末、スマートフォンをご用意ください。
(2)パソコン
インターネットに接続可能なパソコンをご用意ください。Moodleのフォーラムセッションに課題を提出していただくのに必要となります。
【講座の進め方】
1/31,2/1 Zoomの接続テスト
Web会議室Zoomでのリアルタイムセッションは、全部で5回行います。内容は以下を予定しています。
第1回:02/02(火) 21:30-23:00 NVCの世界観と意図
第2回:02/11(木) 21:30-23:00 NVCの世界を構成するフィーリングとニーズ
第3回:02/23(火) 21:30-23:00 自分につながるとは?〜自分の感覚を感じきる〜
第4回:03/04(金) 21:30-23:00 エンパシーとは?〜NVCの基本プロセスONFR〜
第5回:03/11(金) 21:30-23:00 統合(第1回〜4回までの内容を振り返り、統合します)
リアルタイムセッションの間に、Moodleのフォーラムへの課題提出や相互コメントを行います。
Q&A
Q リアルタイムセッションに参加できない日があるのですが大丈夫ですか?
A リアルタイムセッションは、翌日以降、録画動画が見れるようになりますので、そちらで確認していただくことができます。
Q パソコンが苦手ですが、サポートはしてくれますか?
A 運営チームがテクニカルサポートを担当します。Moodleの使い方や、Zoomの使い方については、動画マニュアルを配布しますので、それに従って操作してください。操作方法が分からないときは、いつでも相談してください。接続トラブルについても対応します。
Qリアルタイムセッションには、iPadから参加できますか?
AZoomは、iPadなどのタブレット端末や、スマートフォンから参加可能です。あらかじめZoomのアプリをダウンロードしておく必要があります。
お申込み
講座名:全体性から生きるAuthentic Leadership 基礎特別編
申し込み締め切り:2016年1月30日(土)
定員:30名 (定員に達し次第、締め切ります)
開講期間:2月2日(火)~3月11日(金)
※4週間の講座期間中にZoomによるリアルタイムセッションを5回行います。
リアルタイムセッションの日程:
第1回:02/02(火) 21:30-23:00 NVCの世界観と意図
第2回:02/11(木) 21:30-23:00 NVCの世界を構成するフィーリングとニーズ
第3回:02/23(火) 21:30-23:00 自分につながるとは?〜自分の感覚を感じきる〜
第4回:03/04(金) 21:30-23:00 エンパシーとは?〜NVCの基本プロセスONFR〜
第5回:03/11(金) 21:30-23:00 統合(第1回〜4回までの内容を振り返り、統合します)
この他に雑談ルームを4回開催します。
受講料:32,400円(税込)
定員に達しました。キャンセル待ちをご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

バーチャル空間を活用したオンライン反転授業
「反転授業の研究」の田原真人です。
『ワールドカフェをやろう』の著者、香取一昭さんからの依頼で、ラーニング・ファシリテーション研究会に参加しました。
テーマが「バーチャル・ファシリテーション」ということで、僕がやっている「バーチャル空間を活用した反転授業」の実践を発表させていただき、その後、研究会のみなさんにZoomを使ったオンラインワールドカフェを体験していただきました。
企業研修などで活躍されている皆さんに、オンラインワールドカフェを体験していただき、その活用方法について考えていただいたことは、僕にとっても大変刺激的な体験でした。
実践発表では、
・物理ネット予備校のオンライン反転授業
・「反転授業の研究」のオンライン講座
の2つについて、主にお話しさせていただきました。
実践発表の動画をこちらで公開しますので、感想などを教えていただけるとうれしいです。
『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』レビュー(2)
「反転授業の研究」の田原真人です。
『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』を読みながら、「反転授業の研究」の歩みを振り返っていき、連載レビューの形で皆さんと共有したいと思います。
CT(授業協力者)とは何なのか?
筒井さんの「グループワーク概論」や「情報メディア論」の一番大きな特徴は、何といってもCT(授業協力者)の存在だと思います。
教員と学生の中間に位置し、教員の代わりに教壇に立って授業を進めるが、教員でも学生でもない存在。
CTとは、いったい何なのか?
CTとは、どのような役割を果たしているのか?
CTを導入することで、どのような効果が生まれるのか?
このような疑問についての自分なりの答を知りたくて、筒井さんの授業に出会ってから、様々な仮説を立てながら考えてきました。
「反転授業の研究」に運営ボランティアを導入し、CTと似た役割を担ってもらうようになり、様々な気づきがありましたが、それは、果たしてCTとどこが同じで、どこが違うのかという新たな疑問も生まれました。
『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』の第2章では、多くのCTや見学者が、自らの言葉で語っており、僕にとっては、それらの言葉が、まさに「気づきの宝庫」でした。
劇場型授業という新しい試みを体験したCTや見学者の言葉は、まさに未来の教育が生まれつつある現場からの実況中継で、同じように試行錯誤を重ねている僕達にとって、多くのヒントがありました。
以下で、特に印象に残った部分を紹介したいと思います。
第2章 学生が学びたくなる授業の工夫
CTや見学者は、どのような想いでこの授業へ参画してきたのでしょうか?
第2章を読み通して、大きく3つに分類できそうな気がしました。
(1)学生時代の体験から、自分が受けたかった授業を自分で創ってみたい。
(2)教える側の問題意識から、学生が主体的に学ぶ場創りを学びたい。
(3)新しいことが生まれている魅力的な場に関わっていきたい。
そして、最初の段階では、CTの意識は、「どのような授業を創るのか」という点に向いていきます。CT内でも異なる想いの擦り合わせをしながら、同時に授業を創っていく作業は、かなり大変だったのではないかと思います。
しかし、CTの語りを読んでいくと、ある時点で、意識が学生との関係性へと向かっていきます。これが、とても興味深いです。いくつか引用してみます。
桑原恭祐さん
モジュール2の最後の授業、私たちは、私自身やCTの役割をはき違えていたことに気付いた。CTが各ステークホルダーの意見を汲み取り、CTがすべてまとめて、CTがすべて授業を創る・・・すべてCT内で完結させようとした結果、問題が山積みになり解決できないほど膨れ上がってしまった。モジュール3をどう設計すればよいか、霧がかかって見えずにいたのである。
(中略)
モジュール2最後のリフレクション会では、学生が授業へのさらなる改善要望や自らの成長目標を実施前よりもはっきりと発信してくれるようになった。このことは私たちにとってもありがたく、それが大きな道しるべになった。
出町卓也さん
教授から見た学生だけでなく、CTから見た学生という視点が加わることで、学生を多角的に捉えることが可能になる。その結果として、学生の良い面を知る機会が向上し、彼らの価値を高める働きとなる。そこでCTは、教授とは別の授業担当者として、参加学生全員への目配りをすることが大切である。ただニックネームを覚えるだけでなく、誰がどのような人物か、その存在を認識すること。小中高では当たり前のように行われていた存在の認識を再度、大学の授業で体感させることで、学生に授業の一員であるという認識と自分の存在がCTや教授に覚えられているという自己の肯定感を生み出す。参加してくれている学生一人一人を大切にする支援が、CTの最も重要な役割であると私は考えている。
矢野康博さん
重要なのは、いかにCTが人としての魅力をしっかりと伝えた上で、学生たちとの関係性を築いていけるかということなのだと思います。常に教壇に立つ教授には質問しにくいことを聞ける距離感を、CT自らがつくりあげていく。それが授業に対する学生の理解度に大きく影響しているように感じましたし、そこにCTの存在意義があるのだと思います。
吉田美奈子さん
「CTと学生って近いようで、遠いよね」
この言葉によって、学生の近くにあることがまずCTに求められている仕事だということが全員分かったのである。そこで寄り添うための役割や居場所をCT3人がそれぞれに探る日々が新たに始まった。
はじめは、CTの役割とは何かということをCTも知らない状況でスタートし、授業つくりをしながら学生と関わっていく中で、試行錯誤の中から「CTとは何か」ということを発見していくところが非常に興味深いです。
そして、ほとんどのCTが、学生との信頼関係を構築することや、自分たちが学生から学ぶことの重要性に気付いていくというところに大きなドラマがあり、この授業の醍醐味が詰まっていると思いました。
CTが弱みを含めて自分をさらけ出すことで、学生も自分を出せるようになり、役割を超えた個人と個人の関係性が生まれてくるようになっていくというプロセスは、人間関係の本質的な部分なのではないでしょうか。
CTが学生との関係性との間に信頼関係を構築できるようになると、教室が安心安全の場になってきて、その中で自由に動くことによってコミュニケーションに関する様々な学びが生まれてきているように思います。
見学者の松井智晶さんが、鋭い指摘をしていました。
学生にとってどういう存在か分からないけれど、なんとなく親しみを感じる人が教室内にたくさん存在することは、従来の授業構造から学生を自由にしていた。つまり、この授業において学生は教員だけを意識するのではなく、『周りのすべてを意識して行動する』のである。学生同士、CT、見学者、教員で作られた場の中で教員のみの顔色をうかがう学生はいない。この場の中で自分がどうふるまえばよいのか、自律的に考え行動せざるを得ない環境であったともいえる。
筒井さんが語っている「教室の学びと社会の学びとを近づけていく」という理想は、言い換えれば、教室内に複雑な関係性を持ち込みつつも、安心安全の場を創り、失敗を許容してチャレンジできるようにしていくことなのだと思います。
CTが、学生との信頼関係を構築することの重要性に気づき、教室が安心安全の場になったとき、まさに、社会の縮図としての学び場が実現したのかもしれません。
お互いが受け入れられていることを感じている空間では、失敗が許容されるので、枠組みから出てチャレンジしやすくなります。その結果として、学生の中からも授業つくりに参画してくる人が出てくるなどの現象が起こっているのではないかと思いました。
居心地のよい場が生まれたことで、結果として、学生の脱落率も減り、「人に会いに来る」という感覚で授業に参加してくるようになるのだと思います。
また、第2章を読んで、複雑な関係性は、各人の様々な側面を明らかにし、相互理解を深める効果を持つのだということに気づきました。
CTを対等に扱う筒井さんを学生が見ることで、学生は筒井さんが誰にでもオープンな人であることを理解したり、学生がCTに話す様子を見て、筒井さんが、学生やCTの長所を見出したりすることができるのです。
四方八方に張り巡らされたコミュニケーションのネットワークは、相互理解を立体的にし、お互いが長所を発見していくことを可能にするのだと気づきました。
学習コミュニティへの誘い
「反転授業の研究」のオンライン講座は、当初、脱落率の高さに悩んでいました。
50%以上が脱落してしまったという苦い経験もありました。
リアルの教室に比べて、オンラインは拘束力が弱いので、気軽に脱落できてしまうのです。
脱落率を減らすために様々な工夫をした結果、たどり着いたのは、「雑談ルーム」や「放課後ルーム」という場を創り、受講者と運営チームの間のコミュニケーションの機会を増やすということでした。
現在は、運営ボランティアが雑談ルームのマスターを担当し、毎週、夜遅くまでビデオチャットでおしゃべりをしています。
講座のセッションとは別に交流の機会を設けたことで、講座の脱落率は激減し、脱落率は、10%を切り、0%も何度か達成しました。
ここでは、共感と想いで繋がった運営チームのコミュニティが安心安全の場を創り、そこに、受講者を招き入れて、運営チームと受講者を合わせた学習コミュニティが形成されるというプロセスが働いているように思います。
学習コミュニティの一員となり、自分の存在が学習コミュニティの中で認知されているという実感が、脱落しにくい状況を生み出しているのです。
このような自らの体験を通して筒井さんの授業を見ると、筒井さんの周りにCTや見学者からなるゆるやかな学習コミュニティがあり、そこに学生が暖かく迎え入れられているという姿が浮かび上がってきました。そして、授業に参加している学生も学習コミュニティの一員として認知されることによって、授業は居心地のよい空間になり、様々な人と関わりながら学ぶことのできる場になっているのではないかと思いました。そうなっているからこそ、筒井さんの授業では、学生の脱落率が非常に低くなっているのではないでしょうか。
ところで、コミュニティと学習コミュニティの違いとはなんでしょうか?
僕は、「メンバーが周りのすべてを参考にしながら、試行錯誤したり、振り返ったりして、協力しながら自律的に学んでいくコミュニティ」を学習コミュニティと呼んでいます。
安心安全の場の中で、失敗することが許容され、すべてのメンバーが試行錯誤や振り返りをして経験学習サイクルを回していくときに、周りに学びあっている人がいることで、試行錯誤のアイディアを得ることができたり、振り返りのときに異なる視点からの気づきが得られたりして、成長が大きく促されます。
そして、自分だけでは学べないことを、コミュニティのおかげで学べているという実感が生まれ、コミュニティのメンバーに対する感謝が生まれます。
「反転授業の研究」のオンライン講座では、運営ボランティアが学びの伴走者として、学習コミュニティでのマインドセットや学び方を率先して体現していきます。
筒井さんの授業では、CTが、協力して壁を破りながら成長していくことで、この場で求められている在り方を体現しているのだと思います。
それにより、学びが学びを促す、成長が成長を促す、という動きが生まれているのではないでしょうか。
筒井さんが果たしている役割は、その「在り方」によって、学生、CT、見学者に安心安全の場を創ることなのかもしれません。
最近、筒井さんは、高校や専門学校などの授業見学をして回っています。
筒井さんが知識をアップデートして進化していくことが、また、筒井さんの授業に新しい風を吹き込むことに繋がり、新たな展開を生み出しそうな予感があります。
ドラマが起こると、人の心が大きく動き、その中で成長していきます。
2016年も、筒井さんの授業では、様々なドラマが起こることでしょう。そして、そのドラマに巻き込まれた人たちすべてが、大きく成長していくはずです。
第21回反転授業オンライン勉強会
「反転授業の研究」の田原真人です。
第21回のオンライン勉強会でお話し下さるのは、福岡県でAL推進を牽引している和田美千代さんです。
和田さんは、ドリカムプランの産みの親でもあり、アクティブラーニングやキャリア教育を通して生徒の主体性を育む教育に関わられてきました。
常に新しいことにチャレンジしてきた和田さんが、今、考えていることや感じていることをお話しいただけたらと思います。
日時:1/18(月) 21:30-23:00
場所:オンラインルーム Zoom
参加費:無料
登壇者:和田美千代さん
タイトル:柔らか温かなリーダーシップ(仮)
※第2部では、ビデオチャットを使ったグループワークを行いますので、ビデオチャットの用意をお願いします。ビデオチャットの用意をされていない方は、メインルームでテキストチャットによるコメントでの参加となります。iPadやiPhoneからの参加も可能です。
柔らか温かなリーダーシップ(仮)
(プロフィール)
公立高国語科教員
高校生の主体的進路学習城南高校ドリカムプラン企画者
現在は福岡県教育センターでAL普及推進の仕事
この9月からオンライン講座受講、ネットの中に新しい学びの場、ネット果樹園発見
Uダイバー
アクティブラーナー
(内容)
みなさん、こんにちは。和田美千代です。
1月18日の勉強会は「AL時代のリーダーシップ -みんなで降りれば幸せだ(笑)-」と題して、私の経験をお話します。(少々、いやかなり、まな板の上の鯉的な気分です)
まずは、「何を話したらいいか」という私の「助けて」に、いろいろアドバイスをくださった皆様、本当にありがとうございました。
どんな話をしたら皆さんが喜んでくださるか、あれからずっといろいろ考え緊張していました。
その緊張が昂じていったある時点で、気づきました。「安全安心な場作り」を目下のテーマとしている自分が、緊張して不安だらけの場にいるなんて、なんかおかしくない?
成功させようと思うから緊張するし不安になる。ここは安全安心の場、失敗が許される。「成功」や「うまくいくこと」を手放せばいいんだ。
これ以上もこれ以下もできない、等身大の自分を晒せば、そこから皆さん何かしら見つけて拾ってくださる。そう思うと楽になり、緊張していた自分がほほえましく、笑えました。
答えはいつも自分の中にある。自分の体に耳を澄まして、自分が今???と思っていること、
困っていることをテーブルにあげます。皆さんお助けくださいm(_ _)m
私は県立高校の校長を経験して、平成27年4月から、県教育センターでアクティブラーニング(以下AL)普及推進の仕事をしています。
そのためにALについて自分も学び続けている訳ですが、ALについて学べば学ぶほど「これは授業や学習だけの話ではなくて、私たちの働き方とか、在り方も変えていくものではないか?」と感じています。
「反転授業の本質は教師が権威にならずに、主体的な学習の支援に回ること」下町先生のインタビューの中にある田原さんの言葉です。
これってそのまま職業生活に応用できませんかね?
教師が権威にならずに生徒の主体的な学習の支援に回る、ように、上司が権威にならずに部下の主体的な働き(仕事)の支援に回る、みたいな。
授業を受け身で聞いているより、自分から学んだ方がおもしろい、楽しい。
上司からやらされるより、自分から主体的に仕事したほうがおもしろいし、楽しい。
生徒であれ部下であれ「主体的に活動する場作り
のために、教師や上司は、どうしたらいいんだろう?
教師と生徒、上司と部下、の間の権威依存関係に代わる新しい関係ができたら、もっとみんな教室でも職場でも、いきいきできるんじゃないか?いい仕事ができるんじゃないか?
ALが学校であたりまえのことになり、AL型授業で育った学生達が社会に出ていく時、反転授業において教師と生徒の間で起こることが、職場でも起こると期待しています。
私は今「部長」という立場です。その時が訪れるのを待つのではなく、今の自分の職場で試してみようと思いました。AL型職場作り。「参加共生型職場」(笑)。
それから、前任の高校での状況が今から振り返ればまさにAL型。大ピンチだったんですけど(笑)。そんな体験談をお話しようと思います。よろしくお願いします。
お申し込み方法
(1)このページからお申し込みください
(2)自動返信メールに参加方法が書いてありますので、指示に従って参加してください。
※自動返信メールの内容
●●様
反転授業オンライン勉強会、運営担当の田原真人です。
このたびは、勉強会にお申し込みいただき、ありがとうございます。
日時 2016年1月18日(月)21:30-23:00※21:00からルームをオープンします。
第1部 スピーカー 和田美千代さん
第2部 オンライングループワーク
ビデオ会議に参加できる用意(マイク&Webカメラなど)を
ご用意ください。
当日は、Zoomというビデオ会議室を使用します。ルームURL
(メールでは、ここにURLがあります)Zoomの使い方については、以下の記事を参考にしてください。
(1)パソコンからアクセスする場合
http://zoom-japan.net/?p=54(2)iPad or iPhone、その他、スマホの方
http://zoom-japan.net/?p=17※PCからだと、ルームURLをクリックするとインストーラーが自動的に
ダウンロードされ、それをクリックすると自動的に繋がります。※何も始まらないときは、「downloard & run zoom」を
クリックしてください。※iPhoneやiPadからの場合は、Meeting IDの入力を求められますので、
(メールでは、ここにMeeting IDがあります)
を入力してください。※お願い【重要】
第2部のグループワークでは、ZoomのBreakroom機能を利用しますが、
アプリが最新版であることが必要です。以前にZoomアプリをインストールされている方は、
最新版に更新しておいてください。PCの方は、こちらから最新版をインストールできます。
https://zoom.us/support/downloadスマホやiPadの方は、ZoomのアプリをApp storeから
ダウンロードしておいてください。
また、すでにダウンロードしている方は、
最新版へアップロードしておいてください。それでは、当日お会いできることを楽しみにしています。
田原真人
info@flipped-class.net
『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』レビュー(1)
「反転授業の研究」の田原真人です。
『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』を読みながら、「反転授業の研究」の歩みを振り返っていき、連載レビューの形で皆さんと共有したいと思います。
劇場型授業との出会い
「反転授業の研究」は、2013年に本格的な活動を始めてから、いくつかの転換点を超えて、殻を破りながら不連続に発展してきました。
2014年に僕たちが抱えていたのは、どうやったらコミュニティ内の学びをもっとオープンでフラットにできるのかということでした。
「反転授業の研究」が運営するオンライン講座が、教える側と教わる側に分かれてしまっていて、主体的な学びを目指すグループでの学びが、一方向的になっているということに矛盾を感じていたのです。
回を重ねるごとに矛盾が大きくなっていき、終には、運営者として感じている苦しみをコミュニティ内でオープンにすることになりました。運営者がコントロールを手放したことで、たくさんの方が助けてくれ、新しい道が開けました。
せっかく開けた新しい道をどうやって進んでいこうかと、キョロキョロあたりを見渡していたときに出会ったのが、京都精華大学の筒井洋一さんでした。
「これだ!」と直感的に感じて、インタビューさせていただきました。
筒井さんの授業に導入しているCT(授業協力者)や見学者を、「反転授業の研究」のオンライン講座に導入したらどうなるのだろうか?
筒井さんのところでうまくいっているからといって、自分たちのところでもうまくいくだろうか?
様々な不安や疑問を感じながら、2014年12月に、コアメンバーと一緒に京都精華大学の筒井洋一さんの「情報メディア論」の授業に見学者として参加しました。
不安や疑問はありましたが、もう後戻りできないところまで来ていたので、清水の舞台から飛び降りる気持ちで、えいや!っと運営ボランティアを導入しました。
それから1年経ちましたが、運営ボランティアの導入には、メリットしか感じていません。
10名ほどのチームで場をホールドするため、オンラインに安心安全の場ができ、多くの知恵と労力を使えるため、チャレンジしやすくなりました。
1年間、運営ボランティアと一緒にオンライン講座をやったことで、他にはない価値を生み出すことができ、次のステップも見えてきました。
今から思えば、1年前に筒井さんの授業を見学に行ったときが、大きな大きな転換点だったと感じています。
筒井さん、CT、授業見学者が20名ほど集まって書いた『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』を読みながら、僕たちの1年間の歩みを振り返ることは、大変有意義な非同期の対話になると思います。
第1章 共感でつながるオープンな大学の教室
『CT(授業協力者)と共に創る劇場型授業』を読みながら、1年間の学びを振り返っていきたいと思います。
今日は、第1章。
いろんな人が、学習意欲を高めるための工夫をしています。
伝統的な授業では、
・面白い授業をする。
・褒めたり、叱ったりする。
・よい点数が取れる。
というようなものが使われることが多いのではないでしょうか。
僕が、予備校講師をやっていたころは、まさにこの3つを組み合わせて授業をやっていたような気がします。
サービス満点の授業で興味を引き付け、点数の取り方を教えて成績を伸ばし、ときどき褒めたり、叱ったり・・・・。
これは、1つの「あるべき姿」というゴールを設定し、そこへ向かって集団を引っ張っていくときには、有効な方法だと思います。
しかし、ここに欠けているのは多様性。
1つの基準で集団を測り、それによって序列化していく世界を、教師自身が内面化し、それを教室内で再生産しているわけです。
そして、その基準による競争が、協力しにくい状況を生み出し、個人を孤立化させているのです。
本来、人間には多様な個性があり、それぞれが、それぞれのやり方で幸せになる方法を見つけていけばいいし、お互いの違いから学びあったり、協力したりしていけばいいわけです。
この1年間、違いを認め合って協力し合った結果、安心感と幸福感を得ることができました。そして、自分を守る必要がなくなったことで、創造性も、以前よりも発揮できるようになりました。
このような関係性の構築を広げていけば、幸福感を感じられる人が増えていくだろうなーという確信が芽生えました。
筒井 洋一さんの授業は、そのような関係性を構築する方法を学ぶことができるものです。
学生は、「一元的な価値で測られる」というマインドセットにどっぷりつかっているので、それを動かしていくためには、「教授」という権威が大きな妨げになります。
だからこそ、学生と年代が変わらない「CT(授業協力者)」が、筒井さんと協力して授業を創っていくことに大きな意味があるのだと思います。
内発的な動機づけによって参加しているCTさんが、教壇に立つことで、学生のマインドセットは大きく揺すぶられるのではないかと思います。
外発的な動機づけが弱まると、内発的な動機によって動くことができる可能性が生まれます。
統制されている空間とは違い、それぞれが自分の気持ちで動き始めるとカオスが生まれます。
でも、このカオスこそが、自然な姿であり、カオスを共に乗り越えていき、何かを創るという体験こそが、本来の学びなのではないかと思います。
そして、それは、多様な社会の中で、自分の居場所を見つけて、自分と周りを生かしながら生きていく術を見つけるための学びにもなります。
自分と他人の違いから学ぶことができることの重要性に気づいたときに、教授、CT、多くの見学者からなる授業空間の多様な関係性が、学びの源泉になることに学生は気づくのではないでしょうか。
コラム(1)で戸田千速さんが述べているように、教室内に「教員ー学生という固定した関係性に留まらない多様な関係性の内包している」ことが大きな価値を生み出すのです。
コラム(2)で柳本英里さんが指摘しているように、CTと学生とが関係性を積み上げ、その上でフィードバックを送り合う相互関係の中でこそ、自己変革に繋がる学びが起こるのだと思います。
この学びは、学生だけにとどまらず、CTや見学者にも豊かな実りをもたらすものです。コラム(3)では、見学者として関わった遠藤龍さんが、まるっとーく in 綾部での場つくりの話を紹介していますが、筒井さんの授業を体験した学生、CT、見学者が、その衝撃によってマインドセットを変え、その関係を外部に広げていくという動きは、さらに広がっていくと思います。
僕自身も、筒井さんの授業をきかっけに、マインドセットを変え、オープンでフラットな学びを広げていこうとしている人の一人です。