登壇者紹介 教育と探求社代表 宮地勘司さん
「反転授業の研究」の田原です。
第8回反転授業オンライン勉強会「探求学習と学習意欲」まで、あと1日となりました。
本日、ご紹介するのは、教育と探求社の宮地勘司さんです。
宮地さんにオンラインでお話をうかがいました。
宮地さんが教育事業に踏み出したのは、日経新聞社に勤められていたときに、「日経エデュケーションチャレンジ」というイベントを自ら立ち上げたことがきっだったそうです。
このブログラムは、「高校生のための社会&科学スタディ」というキャッチフレーズのもと、社会で活躍している人を呼んで、高校生に授業をするというものです。
ここで、高校生がすばらしい質問をしたり、大人が元気になったり、相互に触れ合うことによって理解が進んでいくことを経験し、教育事業に大きな可能性を感じたのだそうです。
その後、さらに多くの高校生にこのような学びを届けるために、最初は、社内事業として教育事業を立ち上げることを目指したのですが、制約が大きいため、教育と探求社を起業し、高校生と現実社会とを結びつけるプログラム作りをはじめたのだそうです。
宮地さんが、安定した職を捨ててまで追い求めた教育事業の可能性とは何だったのか。
非常に興味が沸きました。
そこで、教育と探求社が、現在行っている「クエストエデュケーション」について、詳しくうかがいました。
「クエストエデュケーション」とは学校単位で導入するプログラムです。
総合学習の時間や、現代社会、国語など、通常授業のうちの24コマを使って一年を通して行われます。その最終発表の場が「クエストカップ」という全国大会です。
大会の概要を教育と探求社のホームページから引用します。
— ここから引用 —-
全国の中学生・高校生が、学校の授業の中で、実在の企業や人物を題材に、 「生きる力」を学ぶ「クエストエデュケーションプログラム」。
その1年間の取り組みの成果を発表する「クエストカップ2014 全国大会」が、 今年度も開催されます。
審査の対象は以下の3つの部門。
実在の企業から出されたミッションに応える「企業プレゼンテーション」部門。
夢を実現した先人たちのストーリーを追う「人物ドキュメンタリー」部門。
自分の過去と、未来の履歴書を執筆する「自分史」部門。
全国の応募作品の中から選出された代表が、各部門のグランプリを目指して創造性豊かなプレゼンテーションを繰り広げます。
— 引用ここまで —-
企業プレゼンテーション部門では、最初にアニメーションで「あなたが主役。先生はファシリテーター」であることが告げられ、生徒は自分で能動的に動くことが求められるそうです。
1学期は企業のインターンとして、「町に出てスカパーを探せ」など、企業から動画で与えられた指示に従いフィールドワークやアンケート調査などを行います。2学期になると、企業からミッションが与えられ、ブレインストーミングやロジカルシンキングを行いながら、企業からのミッションに対する回答を作成していきます。
そして、3学期に実施される「クエストカップ」で、実際に企業に向けてプレゼンテーションを行います。
千点を超える作品のなかから予選を見事勝ち抜いたチームが、大学キャンパスを借りて行われる本大会でプレゼンを行い、グランプリを目指します。
ここには、生徒のやる気を刺激する仕掛けが何重にも張り巡らされています。
・常に行動を求められること。
・チームで行うということ。
・クエストカップという晴れの舞台が設定されていること。
・自分たちが社会を変えられるという実感を持つこと。
・身近な先輩が活躍する姿を見て、自分もそうなりたいと思うということ。
これらの仕掛けは、既成の教育理論を越えて、現場の試行錯誤から臨床的に時間をかけて練られてきたものなんだそうです。
また、クエストエデュケーションは、教師にとっても貴重な学びの機会になるそうです。
クエストエデュケーションで教師に求められるのはファシリテーター。
答えを持たずに教壇に立つ恐怖を乗り越えることで学びの可能性を知るとともに、それまでには見られなかった生徒の新たな可能性に出会い、感動するそうです。
この体験の後、それまでは一斉授業だったのが、生徒中心のグループワークに変える先生も現れているそうです。
クエストエデュケーションでは、教育と探求社のスタッフが授業を行うのではなく、必ず先生に授業をやってもらうのだそうです。
その理由を、宮地さんにうかがいました。
宮地さん:外部からスタッフが入ると、そのときは楽しいけれど、プログラムが終わったら何も残らないんです。だから、学校からもお金をいただいて、
先生には予算を通してもらって、しっかりコミットしてもらって、一緒にやるようにしています。
この話をうかがって、宮地さんの考えていることを、一つ深いレベルで理解できた気がしました。
僕は、「反転授業の研究」の活動を通して、学習者中心の学びに関心がある教師のためのスキルアップの場をオンラインに作りたいと思っています。
その先には、個人レベルで実践が広がっていくことによって、教育のあり方にインパクトを与えたいという希望があります。
宮地さんは、クエストエデュケーションというプログラムを携えて学校現場に入っていき、地道に、そして、着実に教育のあり方に変化をもたらしています。
その方向性に共感すると同時に、方法論の見事さに感銘を受けました。
4月23日(水)22時からの勉強会で、宮地さんのお話をうかがうのが楽しみです。
反転授業オンライン勉強会への申し込みはこちら
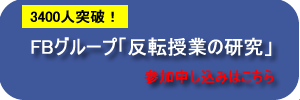
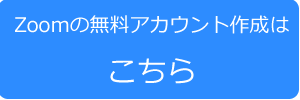

最近のコメント