登壇者紹介 小河節生さんにインタビュー
11月に実施する第14回反転授業オンライン勉強会でお話しされる小河節生さんにインタビューさせていただきました。
小河さんは、企業人としての経験が豊富なのに加えて、インターネットを通じたビデオオンデマンドの授業を提供しているビジネスブレイクスルー大学(BBT大学)でLearning Adviserをした経験をお持ちです。
教育関係者が多い「反転授業の研究」の中で、企業人としての経験が豊富な小河さんのお話は、アクティブラーニングとビジネスの現場とを結びつける上でも非常に参考になると思います。
グループワークに興味を持ったきっかけ
小河さんがグループワークに興味を持つようになったきっかけは?
会社での経験がきっかけです。
メーカーのA社に30年前に入社して、相手は、英国航空エンジンメーカR社とか米国G社とか相手に仕事をしていたら、彼らは非常に事業戦略をきちんと持った上で日本企業を相手にしてくるんですね。
彼らは、自分たちがいかに生き延びるのか、その(自分たちの利益を伸ばす)ために、日本をいかに利用するかという戦略で来るんです。
当時、1990年代ころは、日本も円が安く、日本人は勤勉だから仕事を任せても確実に期限までにやってくるので、うまく使える民族だなと思っていたんでしょうね。
当時の日本は、コスト競争力があり、日本人の年齢構成も若くバイタリティがありました。
安くて正確で速く仕事ができる。その割には、ビジネスにおいてはウブで利益よりも、仕事がもらえればいいやという人たちが多かったんです。
ですから、利幅の大きい稼げるところは欧米人がやって、勤勉にやらなきゃいけない現場の仕事とかを日本にやらせてやろうという感じで仕事を持ってきて、使われていたという感じでした。
やがては日本もだんだん円高になり、コスト競争力がなくなってきました。
じゃあ、利鞘の大きいところに行かなきゃいけないとなると、どうやって戦略的にそういうところに出ていかなければならないか、当時の経営者層は、そういうことが分からなかった。
経営戦略を立てる上でMBAを取っておかなきゃいけないなと思い始めたのが、90年代半ばでした。
欧米の企業の経営方法を学ぶ必要があると思ったのですね。それで、MBAを取りに行ったのですか?
当時、MBAを取ろうとしても、経営幹部には理解がなく、ビジネススクールに行きたいと言っても頭がおかしいと思われていました。それで、自分で通信制でMBAを取れるビジネススクールに通いました。そこで、問題解決力を理路整然とつけてもらえました。最初は基礎コースでしたので、状況をいかに情報収集して分析して問題点の根本を探ってどうやって解決していくのかということをやりました。
その前、2000年頃に米国航空エンジンメーカG社と仕事をした時に、チームワークで課題・問題の解決をするかを覚えました。それが、チームビルディング、チームの中のリーダーシップ、ファシリテーションというものの重要性を身をもって分かったという経験でした。
欧米は個人主義なんて、当時、言われていたんですけど、そうでもなかったです。チームで連携よく行動してくるというのを学びました。
米国航空エンジンメーカG社がやっていたシックス・シグマは、非常に優れたチーム活動で動いていまして、その中で、いかにしてチームを束ねて成果を出していくのかということを、よく学びました。
アメリカ人というのは、こんなにチーム力を生かしてやってくるというのは、驚きでした。
確かに欧米が個人主義で、日本はチームワークが得意というイメージがありましたが、違ったのですね。
80年代は、製造業を中心に日本のチームワークが有効で、Japan as No.1とか言われておだてられていたんですが、日本のいいところをアメリカが学びなおして、90年代になって反撃に来たという時期で、日本がJapan as No.1からひっくり返りかけていたころでした。そのときの日本を見ると、チームで活動できていなかったなと思います。
小河さんが、ご自身の経験から、ビジネスの現場ではチームワークが重要だということを感じて、グループワークについて学び始めたというのは、とても説得力がある話でした。製造業でグループワークがどのように行われているのか、さらに詳しくうかがいました。
アクティブラーニングは、ビジネスの現場でどのように役立つのか
仕事の現場で、グループワークはどのように利用されているんですか?
私は、今、A社から別の会社に転職して、ラーニングアドバイザーとか、地方の学生を集めて勉強会をやっているんですが、辞める直前に、バリューエンジニアリングという製品の品質とかコストを改善するためのグループワークをやっていました。
実際に製品の改良を、そのグループでやりました。
僕もそうなんですが、多くの教師は、グループワークが社会でどのように使われているのかぴんと来ないので、そういう話を教えていただけると、アクティブラーニングと仕事との関連性がイメージできるようになって助かります。
一般企業に勤めていないとぴんと来ないところもあるかもしれませんね。
私は、メーカー系の会社しか知らないですが、大手の製造業はグループワークで製品改良というのは、どこの会社でもやっていると思います。サービス業でやっているかどうかは、分かりません。
バリューエンジニアリングをやっているという企業、シックスシグマをやっている企業は、間違いなくグループワークを導入していると思います。
グループワークがうまくいくコツは?
グランドルールを作って、みなさんをその通りに従わせるというファシリテーターの役割が重要です。あるいは、リーダーとファシリテーターが一緒なら、リーダーがグランドルールを徹底するということだと思います。
自分勝手なことを言ったり、何も言わないという人はいますから、メンバー全員がグループワークに最初から適応するかと言ったら、それは無理だと思います。いかに話をうまく持っていくのかというのが、ファシリテーターやリーダーのスキルだと思います。
グループワークでは、ファシリテーターやリーダーの役割は、どのような役割を果たすのですか?
共通目標を見えるようにするのがファシリテーター、または、リーダーの役割だと思います。職場を改善したい、お客さんの満足度を50%から80%にしたいとか、メンバー全員に共通の目標を持たせるようにしていくのが重要ですね。私もファシリテーターとかリーダーの立場でものを言うと、自分のことではなくて、グループの共通の利益になるのは何かなというのをお互いに認識してもらって、「そうか、俺たち同じ船に乗っているんだね。じゃあ、こっちに向かって頑張ろうか」という風に持っていくんですね。そうすると、各自のやることというのがだんだん認識できるようになってきます。利己的でなく利他的でないといけないということです。
システム屋さんだったら、システムの改善をどうしたらよいかとか、モノづくりの作業工程を作る人だったら、現場に行って作業者がやりにくいところは何ですかねというのを聞いてくるようになるとか、そういう違いが出てくるかと思います。何したらよいかが、だんだんと分かってくるんです。
部門から代表が出てグループを作るのですか?
そうですね。部門ごとに分かれていることが多いので、設計者もいれば、営業の人もいる。資材調達の人もいる。実際に現場を持っている人もいる。アフターサービスもいるという状況で、お互いの組織の利害が中心になるのを、どうまとめていくかですね。
部分で最適化していたものを、組織全体で最適化する感じですか?
そうですね。サッカーで言ったら、スタンドプレーだけではだめなので、誰をおとりにして、誰がゴールを入れるのかといったチームワークですね。その辺が、90年代のアメリカ企業は、日本から学んで逆襲してきたわけですけど、いい成績を上げるためには、お互いの役目が分かって、連携して動けるというところがすごかったですね。最近は、アメリカ企業もまたおかしいですけどね。
大きな組織になると、多くの部門に分かれていて、それぞれの部門の利害と、組織全体の利害とが必ずしも一致しないときに、社内のステークホルダーが集まって、組織全体の利益を最大化するためにグループで話し合うというのは、とても分かりやすいお話でした。
欧米ではファシリテーターの地位が確立している
以前、シンガポールのワールドカフェホストの女性の自宅に招待してもらったことがあるんですが、彼女の夫は、アメリカのグループワークのトレーナーで、世界中を回ってトレーニングしているという人でした。豪邸に住んでいて、アメリカの会社では、グループワークが重要視されているんだなと感じました。
そうですね。IBMのCEOのルイス・ガースナーが、お菓子会社の社長から、IBMへ行って、業績が出せるというのは、コンピューターのことを知らなくても、まわりの人をまとめてIBMを立て直すことができたからでしょう。お菓子屋さんが、コンピューターの会社を立て直すことができるというのは、ファシリテーション力があって、ベクトルを揃えて、バラバラだったベクトルを一方向にしたらあれだけの業績が出るんですね。
アメリカと日本では、人材についての考え方が違うんですか?
アメリカでは、欲しいスキルのある人は、ドライにどこかから持ってきますね。引き抜いてくることもあるでしょうし、契約社員みたいな感じで持ってくることもあるでしょうし。今、その場にいる人を無理して育てようという感じは、あまりアメリカはないみたいですね。その分野で優れた人を連れてこようという感じですね。
ファシリテーターとしての経営者になるか、特定の分野、たとえば、プログラミングが優れているとか、何かの技術計算が得意な人だとか、マーケティングが得意な人だとか、特定な分野がすぐれた人になるかというのは、それぞれでしょうね。No1になれば、どちらでも非常に高いフィーがもらえると思いますけど。
どちらでも、自分が才能がありそうだというほうを磨いてくれればと思いますね。
私は専門じゃ無理だなと思うので、ファシリテーションの能力を磨いていこうかなと、まだ、この年で思っていますけど。
組織の中のベクトルを揃えることができれば業績が上がっていくということが共通認識になれば、そのためのスキルを持つファシリテーターの重要性も認識されるようになるのだと思います。現在の日本では、ファシリテーターの認知度はまだまだ低いと思いますが、今後、重要性が少しずつ認識されるようになってくるのではないかと思います。
逃げずに責任を取るのがリーダー
リーダーシップとファシリテーションの違いは何ですか?
ファシリテーション能力とリーダーシップの能力は、どちらも両方あるといいですね。
リーダーというのは、ビジョンがないといけないと思います。それを、自分で示しても良いですし、誰かからもらってきたものを示してもいいですけど、はっきり示さないとゴールが見えないですから。
リーダーとファシリテーターというのは、必ずしも一緒でなくても良いと思います。リーダーとしてビジョンを分かる人、グループをまとめあげる能力というのは、必ずしも一人の人が持っていないと思うので。
会社の経営を例に挙げると、昔のホンダだったら、本田宗一郎さんがリーダーで、「俺は、こんなバイクが作りたい、こんな空冷の車が作りたい」と言って、はっきりとしたリーダーシップを持つと。ただ、彼の場合は、すごく変わった頑固おやじだから、会社の経営はそんなに得意でないので、チームの和をまとめるのには、藤沢さんという方がファシリテーターとして組織を支えたんですね。
トヨタだったら、トヨタの本家の人と、大野耐一さんですかね。この二人がリーダーシップとファシリテーターを分担していると。
その組織をこうしていきたいんだよという強いビジョンを持つのがリーダーシップ。というように僕は理解しています。
後は、逃げないことですね。責任は、最後に取るということです。
うまくいかなかったら、それはお前らのせいだと言って・・そういう会社ありましたね。うまくいかなかったのは従業員のせいだって、そんなことを言っちゃだめですよ。
原発壊れちゃったのは、俺たちのせいじゃないって、それはリーダーシップじゃないですよ。
ビジョンを持って、逃げずに責任を取るのがリーダー。
チームを支えるためにはファシリテーターが、そうですね、野球で言ったらキャッチャーみたいな人が必要になるというイメージですね。
日本では、どうですか?
日本の場合だと、妬み嫉みのほうが多いのか、足を引っ張ることのほうが多いみたいですね。だから、全くしがらみのない外国人の経営者を連れてきて、その人にやらせるというのがパターンとしては多いですね。日本人でそれができる人というのはなかなか・・。
能力があっても、反感を買ってしまって周りが付いてこないというパターンが多いです。
それは、派閥の利害関係のほうが優先されてしまっているんですね。業績が悪化したりして危機感を感じる状態にならないと連携できないんですか?
不思議な日本人の精神構造だと思うんですけど、本当の危機になっても、ベクトルが揃えられないパターンがあります。光学機器メーカO社なんかもそうですね。派閥抗争を繰り広げて、結局、会社の業績が上がらないままということですね。不思議ですよね。
でも、倒産してしまったら、派閥とか意味がなくなるんですよね。それでも、派閥を手放せないというのはどこから来るんですか?
私の勝手な推測ですが、きちんと責任取っていないなと思います。自分の地位に安住することが優先。でも、そのまま行ったら沈没するという場合でも、どこかで誰かが助けてくれるという甘えがあるような気がします。
原発事故をやっても、だれも責任を取らないでみんな逃げちゃう。会社潰しても、私のせいじゃないといってみんな逃げちゃう。きちんと責任を取るということを教えていないという気がします。
小学生の時は、よく先生に「あなたの責任!廊下に立っていなさい」って怒られましたけど。そういうことは、それ以後、全然ないですものね。
僕たち団塊ジュニア世代の人は、偏差値教育のど真ん中で、テストの点数で振り分けられて、「あなたは理系、大学はこの辺、就職はこのあたり」って振り分けられていったという感覚があるんですよ。僕は、そこに強い反発があって、自分で選びたいと思っていたんですが、そのまま振り分けられていって、選んだという感覚がない人も多いと思います。それが、責任を感じないということと関係ありませんか?
それが、背景にあるかもしれませんね。
自分で選んだから、自分で責任を取るというのはあるでしょうね。
振り返って考えてみると、私は自分の人生を自分で決めていますね。最初に付きたかった仕事について、途中の転換も自分で決めていますもんね。
これが必要なんだという自分の気持ちに沿ってやっていますね。やれと言われたんならモチベーション低いんでしょうけど。
対話の中から、主体的に行動することと、責任感との関連性が見えてきました。アクティブラーニングによって主体的に行動する人を育成していくことは、同時に、責任感を持って行動する人を育てていくことにもつながるのではないかという思いが生まれました。
必要に応じて短期間で知識をローディングする
少し前に、TED動画で『Joi Ito: Want to innovate? Become a “now-ist”』というのを見たのですが、そこでは、高度に知識化する社会では、前もって学んでおくよりも、必要な時に学ぶスキルのほうが必要だと言っていました。必要な時には、学ぶ意味がはっきりしているので、一気に学べるんですよね。小河さんはいかがでしたか?
前もって学んだことで役立ったのは・・・
大学では工学部だったので、流体力学とか材料力学だとか習ったんですが、あまり役に立ったという記憶がないですね。
何が役に立ったのかというと、考えてみれば、グライダー部で学んだチームワークのほうが役に立ちましたね。
学校でやる基礎の学力って、あんまり役に立っていないなと。
実際にいついつまでにこういう成果を出さなくちゃいけないから基礎知識を勉強しなきゃといったほうがエネルギーの短期集中度は高いですね。
一時的にローディングするんで、そのときは専門家みたいに覚えているんですけど、あとは忘れますけどね。まあ、あとでまた、思い出すことはできますけど。
工学部で学んだことも、あまり役立たなかったと感じているのですね。
職場にもよりますけどね。いきなり空気力学の設計をやってというところなら、流体力学が役に立ったと思いますけど、私が行ったのは現場だったので、現場のおじちゃんたちをうまく動かすほうが中心でしたね。自分で飛行機を作れないんで。
だから、おじちゃんたちが気持ちよく、どうやって働いてくれるのかなということが関心でしたね。
モノを作る技量は、明らかに現場のほうが上ですから、教えることなんて何もなくて、教えてくださいです。
ただ、研究、設計部門の人に言わせると、大学でやってきたことというのは幼稚すぎちゃって、またそこにギャップがあって役に立たないって言っていましたね。
最先端の知識、技法は、短期で急速に覚えなくちゃいけないというところで同じですかね。ここまでの到達点をいつまでにやれというのがないと、しゃかりきになって勉強はできていないなという印象を受けます。
ここまでやらなきゃということになると、徹夜してでもやると。自分の経験や、まわりで起こっていることからすると、そちらのほうが多いと思います。
短期間でローディングして学ぶのに必要なスキルは?
手あたり次第文献を読んでみて、関係のありそうな文献を見つける嗅覚というのは必要かもしれません。全部読んでいたら終わりませんから。ぱっと目次を見て、中身をちらちらっと見て、これは関係ある、関係ないというのを選り分ける。そういうことですかね。インターネットができて本当に便利になりましたけど、紙の文献しかないときは大変でしたね。あの頃、取り寄せようと思ったら1?2週間、すぐに経っていました。
今は、速いですよね。
検索するとすぐに出てきて、有料でも電子データでもらえば、そんなにかからないですもんね。
たくさんの情報をパッと見て選り分けるというスキルは、必要だと思います。
それは、いつ身に付いたのですか?
会社に入ってからですね。1つのテーマに必要な資料をかき集めるというのは。
大学院に入ってから、指導教官と研究テーマが違ったので、資料調べから、仮説を立てて検証するところまで、全部一人でやっていたんですけど、今考えると、その経験がとても役立っています。
アクティブラーニングをやると、そういうのを自分でやらなくちゃいけないですもんね。自分のやろうとしているテーマに対してどんどん調べて、資料を集めてきて、必要なら実験してみるという考え、自分でそういうプランをしないといけないですね。そういうことが学べるということを考えても、教科、時間割を決められて、教科書が与えられて、それだけやっていればいいよじゃではない良さがありますよね。
そういう力こそが、社会に出てからは絶対役に立つと思うので。
社会の変化が速く、テクノロジーに関する知識があっという間に陳腐化してしまう時代には、将来に備えて知識を蓄えるよりも、必要に応じて知識をローディングするスキルを身につけるほうがよいということですね。それも、アクティブラーニングをやる意義の1つだということを、小河さんのお話によって気が付くことができました。
アクティブラーニングに期待していること
教育の場でアクティブラーニングを導入する必要性を、小河さんは、経験上、感じられているんですね。
受験最難関校出の部下を何人か持って、まわりに同じ大学出の人もたくさんいるんですけど、確かに教科書の知識で決められた試験を早く正確にやるのはできるんだけども、まず驚いたのは、自分の仕事のスケジュール、要するに、時間割を書きなさいというと書けないんですよね。「時間割は与えてくれるもんじゃないんですか」と、最難関校出てきた優秀な人が途方に暮れるという経験をしたんですよ。「えーー。自分で自分の時間割が作れないの!」って、これは驚きましたね。
この部下を持ったのは14ー5年前なんですけど、教育が、どこか違うんじゃないかと思いましたね。
いかに自分で学習していくという道を作るか、それをやる意味で、アクティブラーニングはしていかなくちゃいけないなと思います。いろんな社会の課題について、時間割を教えてください、教科書ないですか、と求める態度だと本当に困っちゃうんで。
僕の生徒で、興味のあることはすごく熱心にやるけど、興味のないことはさっぱりやらない生徒がいます。それは、すごく大事なんだけど、僕から見ると、捨ててしまっていることの中にも、彼の将来に役立ちそうなことがたくさんあるので、どうしようかなと思っています。
興味の持てるところから、周辺のところへの知識への拡大が必要だなと思います。飛行機の例を上げると、飛行機を作るために何が必要かなと思ったら、嫌いなこともやらなくちゃならないなというのがありまして、まず最初に、飛行機を作る会社に入ろうと思ったら、英語を分かんなくちゃだめだろうという話もありますしね。英語好きじゃありませんでしたけど、飛行機を作っている会社は欧米ですから、英語くらい分かるのは当たり前だよね。どうにかしなくちゃいけねぇかというのがありました。
やりたいことをするために、関連の勉強も必要というのも出てくると思いますね。やりたいことに引きずられて勉強しなくちゃいけないということもありましたから。
脳みその中でアドレナリンやドーパミンが出てくるような興味の持てることがあれば、それをコアに伸ばしてやるというのがいいのかなと思いますね。
そうですよね。でも、点数を取るための勉強をしていると、興味のあることが何かということが分からなくなってきますよね。
その辺の指導の仕方ですよね。中学高校になると同じような教科書が与えられて、同じように勉強するようになって、面白くないなということになっちゃうんで。興味の持てるコアの部分がどっかにいっちゃう。
アクティブラーニングをやる意味として、もう1つ出てきました。どうやって自分で学んでいく道を作っていくのかということです。脳からアドレナリンが出るような興味のあることをコアにして、そこから広げていくようにして、いろいろなものを関連付けていけば、生徒自身が、自分にとっての学ぶ意味を感じながら学んでくれるのかもしれません。
小河さんのここまでの話を整理すると、アクティブラーニングで学ぶ意味として、次の4つが出てきました。
・組織で仕事をするときにはグループワークが必要になること
・主体的に行動することで、責任感が生まれること
・必要に応じて知識をローディングするスキルを身に付けること
・自分で学んでいく道を作れるようになること
これらは、すべて小河さんの経験に根差したものなので、非常に説得力があると感じました。
BBT大学との関わり
小河さんは、ビジネスブレイクスルー大学(BBT大学)でLearning Adviserをした経験をお持ちですが、BBT大学とは、いつから関わっているのですか?
A社で働いていた当時、アメリカの人やドイツの人と会うと、ph.DかMBAを必ず持っていました。名刺を交換するとどちらかの学位を持っているんです。一方、我々日本人を見ると、誰も持っていない。これは、勝てんわと思いました。
それで、2005年からMBAコースに入りました。そこで入ったのは、大前研一さんがやっていた通信制の大学院でした。そこで遠隔教育を体験しました。仕事を中断して勉強させてもらえなかったので、夜とか休日に勉強しなければならないという状況でした。
Learning Adviserになったきっかけは?
社会人として、会社に言われなくても勝手に勉強するという仲間が通信制の大学院に50人くらい集まっていました。卒業してみると、同じような考えを持った人が結構いる。2009年に大学院だけじゃなく、4年生の大学も作りましたので、じゃあ、今度は指導する立場で、Learning Adviserでもやって恩返ししようかと思ってやることにしました。一人でも多く、戦略的な思考ができる人が増えていけば、日本も競争力が上がるんじゃないかと思ってやり始めました。
BBT大学では、学生はどのようにして学ぶのですか?
学生もビデオオンデマンドで勉強していますので、好きな時間に勉強しています。一斉授業というのは基本的にないです。2005年の段階から、「皆さんビデオを見てきてね」というやり方をしていました。ただし、ワークショップの形で集まって課題をやるような授業は今でもあまりないです。反転授業のベースが整っているので次のステージに行けるのですが、まだその機運できていないです。
Learning Adviserの役割は?
教授が授業を作りまして、学生は、疑問があれば、Air CampusというLMSに質問を書き込みます。それに対してLearning Adviserは、議論のきっかけとなるようなオンライン上でのファシリテートをします。「こういう質問が出ているけど、他の人たちはどう思う?」というような問いかけをしたりして、議論をしながら、新しい発見をするような指導をしています。
いきなり答は、わかっていても書かないようにしています。
LMS上でのファシリテーションというのも、一つのキーですね。
リアルで集まって学び合いをするという機会はあるのですか?
リアルで会うのは最初はなかったですね。3か月から半年、10―20時間のビデオがあって、それを見て、質問をします。それから、個人でやる課題もあります。設問があって、それに対してどういうデータを集めてきて、分析して、何がいるかというのを考えさせて、オンライン上で課題を提出させるというのもあります。
ただ、集まって、一つの課題を解いていくというのは、最近は必要性がようやく分かってきて、半年から1年のコースで1回か、2回くらいやりますね。
Learning Adviserとして採点したときに、オンラインだけで勉強した人の答案は、実際に会ってグループでディスカッションした人の答案に比べて差がありました。一人でビデオを見て独習して課題を出すというだけだと、差がつくなということを見てきています。
ですから、ワークショップをやるというのは重要だと思っています。
できれば、年に1―2回ワークショップをやりたくて、できれば、オンラインでやりたいです。というのも、生徒は日本全国どころか海外にも分散しているので、一カ所に会することは非常に難しいです。ですので、オンラインでディスカッションできればと思っています。
僕も物理ネット予備校で物理の動画講義をネット配信して、フォーラムのQ&Aでサポートして物理を教えるということを10年間やってきたので、動画配信のメリットを感じると同時に限界を感じています。そこから、ビデオ会議室システムを使ったアクティブラーニングと組み合わせる方法の試行錯誤を始めました。小河さんも非常に近い問題意識をお持ちで、リアルで集まってグループディスカッションをする場を作ったり、オンラインでグループディスカッションをすることを検討したり、様々なチャレンジをされています。
小河さんのやられているLMSでのオンラインでのファシリテーションというのは、リアルの場でのファシリテーションと比べて非言語的な情報がない分だけ、難しいものだと思いますが、そこで蓄えられたノウハウは、オンライン学習が増えていくこれからの時代に、役立つものではないかと思います。
小河さんの考えるファシリテーション
ファシリテーションで一番大切なことは何ですか?
ファシリテーションのテクニックについては、本とか現場体験をもとにやっているので、きれいにうまく説明できないですが、一番中心に来るのは傾聴力ですかね。
こちらの言いたいことを一方的に言っても、そっぽ向くだけですからね。相手の言いたいことを聞いてあげることが大切ですね。
私が若いころ、会社に入った時に感じたのは、上司ってのはいかに傾聴力がないかですもんね。一方的に指図するだけで、何か意見があって言おうものなら、10も20も反ってきて怒られるというパターンでしたから。
A社は、優秀な学生が入って来てはだめにしている会社だなんて陰口叩かれていましたから。いかに個々人の能力を伸ばすかということができていなかったか。まずは、聞いてあげることだと思います。
メンタルヘルスでも傾聴力ですけども、同じだなという感じしますね。
傾聴が、個人の能力を引き出すための第一歩なんですね。
そうだと思いますね。今、社会人を相手にしていると、人生の目標をみんな持っていないですね。7~8割が持っていないですね。とりあえず職は持っている。結婚して子供もいるけど、なんか人生の目標が違うんだよねという人がいっぱいいます。
これが自分の人生じゃないという人が結構いて、もっと他のことがやりたいはずだという人がいますね。
20代のオンラインの大学生でも、人生のビジョンがありませんという人がいっぱいいますね。おそらく潜在意識の中にやりたいことはあると思うんですけど、どうやって引き出したらよいのかなとよい方法を、今、検討中で、それらしい研究をしている人を二人ほど見つけました。
その人のやっているワークショップを受講してみようかと思っています。
いろんなしがらみで思考が規制されているので、意識の中にはあるんだけども表現できないものをいかにして引き出すのかというのが、私の課題で、今、勉強中です。
実際にやってみて、うまくひきだせたというケースもありますか?
そういうタイプの人を真剣に相手して5人くらい。一人くらいですね、やりたいことが見えてきたのは。対話していて、引き出せないのはまだまだ未熟だなと思っているんで、研究会などで習いに行こうかと思っています。
「反転授業の研究」のインタビューしていて、今やっていることのルーツを一緒に探っていくと、本人も意識していなかったようなつながりが見えてくるときがあったんですよ。はじめは、単に勉強会の発表者をみんなに紹介するためにインタビューしていたんですが、いろんな気づきがインタビューから生まれるので、これは、すごいと思って、モードが変わりました。
まさにそうだと思います。
加藤雅則さんという人がやっている「智慧の車座」が、僕がやりたいとしていることを補ってくれる優れたやり方のような気がして、これを直接、習ってみたいなと思っています。
うちの学生にやりたいと思って、今、整理中なんです。これで、自分がやりたいことが分かるというのが一人でも増えるかと思って、試してみたいと思っています。(このインタビューのあと試しに文献頼りに「智慧の車座」を開催。加藤さん直々のセミナーをH27年2月以降に開催する計画中。)
傾聴力の重要性は、僕自身も強烈に感じていたところだったので、小河さんから同じ言葉が出てきたことで、確信が強まりました。小河さんの学習者像はとてもポジティブで、「やりたいこと」が表面に現れていないとしても、潜在的なところには存在していて、それを一緒に考えていくことによって引き出すことができると信じているところがとても印象的でした。そして、引き出す能力を高めるために、小河さん自身が学び続けているのがすばらしいと感じました。
主体的に自分の人生を決めてきた
小河さんは、子どものころから飛行機のエンジニアになりたかったんですよね。その夢を抱くきっかけは何だったのですか?
子どものころにNHKのドラマで見た「あひるの学校」に出てきた芦田伸介が演じる飛行機のエンジニアがかっこいいなというのがきっかけだったんです。
それで飛行機作りたいなと思って、就職して30代くらいまではそれでよかったんですけど、だんだん会社の中の経営を見ていると、飛行機作るよりも、日本の会社の経営っておかしくないかなということで、意識付けが変わってきて、きちんとした経営をしなくてはだめだと思い始めました。日本の企業では、従業員が全然幸せじゃないよねと思ったんです。
そういう風になってしまうもともとの原因が、利益を欧米企業に搾取されていたりとか、経営自体がまずいんで、変なところにお金使っちゃていたりとかしていて、従業員が幸せになるためのお金の周りがよくなかったんですね。
福利厚生もひどかったですから。
そういうところをいかに直すか。まずは、利益を上げることが悪いという変な戦後教育があったんですけど、きちんと必要な利益を上げるような経営が必要だというところに意識付けが変わっちゃって、MBAのほうへ走っていたということなんです。
25年から30年前に、転換点がありました。
それで、経営に変えて、それからが長かったですね。
自分がいた会社も、このままでは経営不振になるだろうという危機感がありました。
その会社も、よいか悪いかは別にして、欧米型に変わって利益を出せる体質にはなったのでいいかなと思うんですけど、それを出てから、日本の働いていく人たちに、同じ間違いをせずに、いかに戦略を持って生きるかというのに寄与できるかなというのが、今のモチベーションです。
小河さんのように、自分のやりたいことをはっきりさせて、常に主体的に決めてきたという人のほうが珍しい気がするんですよ。
確かに、周りから変だと思われるのは、そこにあるんでしょうね。
だから、学生と話をしていて、「やりたいことないの?」「特にありません」と言われて、「変わった奴だな」と言うと「あなたのほうが変わっています」と言い返される羽目になりますからね。
その考えは、どこからきているんですか?
自分で選択するからには、自分で責任取れよということですよね。
それを、最初に言われたのはオヤジですね。「好きなことをやっていいよ。ただし、結果については自分の責任だよ。」と。
同じことを会社に入ってからも、最初の課長に言われましたね。
「自分の人生なんだから、やりたいことやりなさい。ただし、結果については自己責任だよ。」
同じことを言われましたね。そういうことを言ってくれる人がいるか、いないかもしれないですね。
ご両親が、小河さんをそのように育てたのですね。
親のいいつけが、「好きにやっていいよ」でした。
生まれたときに病気がちだったらしく、親が、生きているだけでもいいやと思ったと聞いています。無理に親の意向に沿わせなくてもいいやと思ったというのを、かなり大きくなってから聞きました。
あまり無理せずに好きなように生きてもらったらいいよという感じだったみたいです。
病気もせずに頑強な男の子だったら、もっとしごいたのになんて、冗談も言われました。
好きにやったという経験で、思い出すものはありますか?
学校の中では、小学校の5~6年生の担任の先生が、教科書を使わない人でしたね。自由に研究してきて、自由に調べて、好きなことを調べてこいという人でしたね。好きな本を読んではノートにまとめてということをやっていました。
それが小・中では印象に残っています。
あとは、特色のあることは、やっていないですね。昭和40年代ですから海外に行けるわけでもないし・・。
まだまだ日本は貧しかったですから。
アヒルの学校を見て、影響を受けたのは、いつごろですか?
小学校1―2年だったと思います。
その頃、思い描いた夢を、ずっと心の中に抱き続けるのはすごいですね。
だから、おかしいと言われるんですね。最初に飛行機に乗ったのは東京オリンピックの年なので幼稚園生のときでしたね。1964年ですね。あの印象が大きいのかもしれません。
東京に行ったら、たくさんの外国人がいて、飛行機に乗ってきたというインパクトが大きいのかもしれません。
それが続くんですよね。
他に興味があるものが出てこなかったということかもしれませんけど。
高校のころは、受験勉強がすきじゃなくて、勉強しませんでしたね。特定の教科で、なぜだろう、どうなっているんだろうと深掘りするようなことは好きでしたけども、暗記物はさっぱりやりませんでしたね。歴史なんて覚えませんでしたね。歴史で「なぜ、この人はこうしたんだろう」というのを調べるのは好きでしたけど、何年に何があったというのは、ほとんど暗記しようとしませんでした。
本を読んだり・・実際に乗り始めたのは大学ですね。グライダーに乗って空を飛び始めました。勉強しませんでしたね。笑
大学の中に航空部というグライダーに乗るクラブがあって、そこへ入って、そればっかり飛んでいたのを覚えています。
合宿費も高いんで、倹約したり、バイトに行って稼がなくちゃならなかったですね。
子どもに「好きなことをやれ」というのは、実際にはとても難しいことだと思います。でも、子どもの主体性を尊重することで、自分で道を作っていく力や、責任感が生まれるということを、小河さん自身が示しているように思いました。
主体性に火をつけるために必要なこと
小河さんと同じように、やらなくちゃならないからやるのではなく、やりたいからやるという人は、会社には、他にもいましたか?
A社に来る人は特殊ですね。入社する人のほとんどがロケットを作りたいですから。特殊な世界ですねあそこは。
ロケットに配属される人は少ししかいないんだから、みんなロケットはできないよということなんですけど。
中には、ガンダムが作りたいとかいう変な人もいましたね。現実にできると思っているのという感じで。そういうこだわりを持っている人も少しはいましたね。
でも、オンライン大学の学生に聞いてみると、自分の夢を持っているという人は極めて少ないですね。そのことが分かったのは、この4ー5年ですね。
他の人も、自分と同じように、こんなことをやりたいんだという夢を持っているんだと思っていたんです。それが違うというのを、この年になって悟りました。
主体的に学ぶために、どうやって心に火をつけることができるんでしょうか?
難しいですよね。
高校のころ、なんで学ばなくてはならないというのは、化学の先生が言ってくれたんです。
「君たち、こんな亀の子マークなど覚えて、何の役に立つかなと思うと思うけど、こういうことを学んでおかないと、知識のある悪意のある人に騙されるよ。」
「騙されないためには、勉強しておかないといけないよ。」
それは、あまり前向きじゃない動機ですけどね。
あとは、生きるために必要だという原始的な動機もありますね。高度に知識化された社会で生きるためには、勉強しておかなくちゃいけないよというのは、動機としてありますね。
最後に出てきた2つの教訓
・知識のある悪意のある人に騙されないために、自分で考える力をつける
・高度に知識化された社会で生きるための力を付ける
これらも、アクティブラーニングを考える際に、非常に重要なポイントだと思いました。
小河さんからお話をうかがい、アクティブラーニングをすること、主体的に学ぶことの意味が、これまで考えていたよりもたくさんあることに気づきました。そして、それが小河さんの経験に根差しているものであるところから、非常に説得力がありました。
「反転授業の研究」は、多様性のある森を育てることをコンセプトとして運営していますが、今回、インタビューさせていただいて、小河さんのように企業人として経験豊富な方がグループに加わっていることの恩恵を強く感じました。
勉強会でのお話が楽しみです。
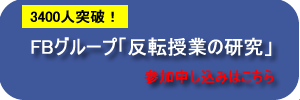
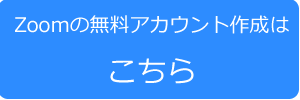

最近のコメント