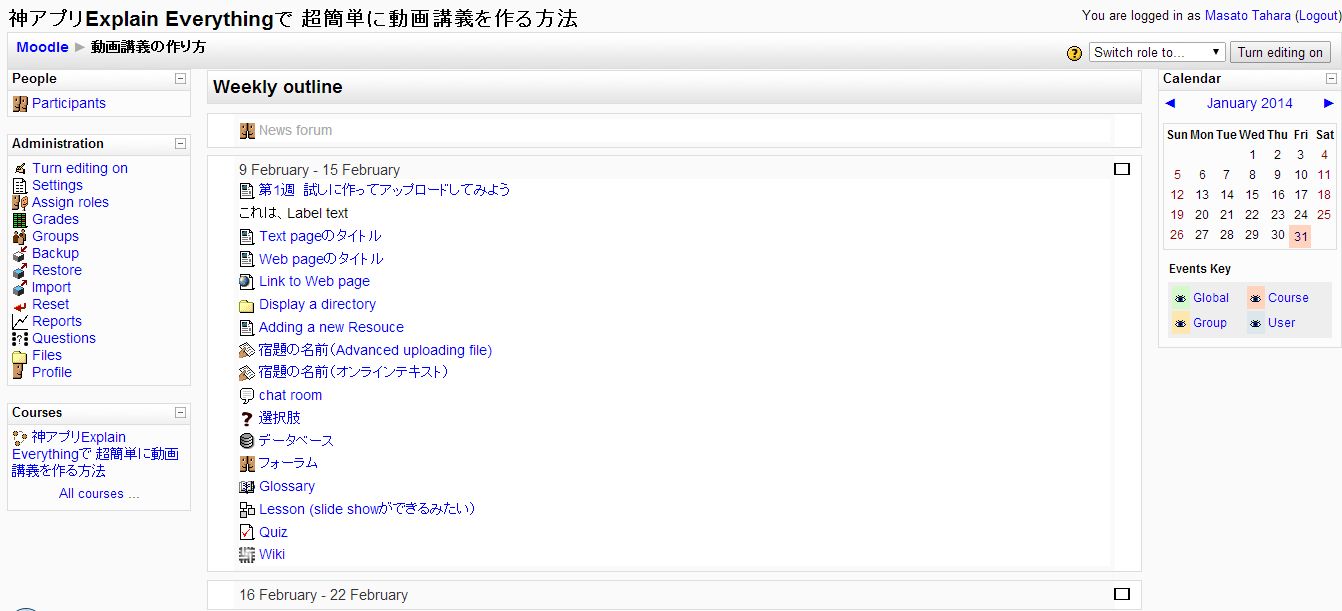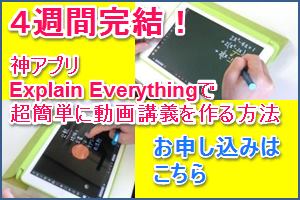インストラクショナルデザイン(ID)を用いて授業設計をするときの最重要点は、ゴールを明確に決めることです。ゴール到達への道筋を組み立てることがIDです。教育効果測定は、そのゴールに到達したことを客観的に判断するための方法論です。具体的にはデータを収集して評価を行います。ですからIDと教育効果測定は車の両輪の関係です。
そこで、教育効果測定のスペシャリストであり、『はじめての教育効果測定』『教育効果測定の実践』の著者である堤宇一さんにお話をうかがいました。
堤さんが、教育効果測定に関わることになったきっかけは?
(堤さん)もともとは、産業人を対象とした研修会社におりました。教育営業や通信教育のコンテンツの開発のマネージャーをやっていたんです。
あるとき、大手流通会社用に工夫を凝らした通信教育コンテンツを開発しました。受講者からの反応も良く、流通会社の人材開発担当者からも評価をいただき、教育効果も高かったと思います。しかし、その部署の部長が人事異動し、後任の新部長の一言で通信教育コースの継続が中止されました。その一言とは、「俺は通信教育が好きじゃないんだよね」でした。
これは、ちゃんと成果を証明しなくてはならないと強烈に感じました。キチンと効果を保証できる通信教育の開発技術を身に付けなくては駄目だと感じ、色々と探し回りました。そのようなときに、米島さんと出会い、CRI(Criterion Referenced Instruction)を勉強しはじめました。
学んだCRIを用いてコンテンツを作ろうと思ったら、通信教育事業部からアセスメント事業部(人の性格や能力を測定する部署)へと異動になったんです。
今まではコンテンツの作り方を勉強してきたけど、アセスメント事業部に来たんだから、測るということをやったらどうですかと言われて、教育効果を測るということをはじめたんです。
(田原)それは、いつごろですか?
(堤さん)1999年ですね。世の中がコンピュータの2000年問題で騒いでいたころです。当時は、教育効果を測定するなんていうことは、誰もやっていなかったし、世間一般には測れるものという考えが無かったです。
東京の八重洲ブックセンターで、当時の上司がジャック・フィリップス博士(教育効果測定の第一人者)の書籍(原書)を偶然見つけ、数名でこれを翻訳し、出版しました。その翻訳本を持って、ジャック・フィリップス博士に会いに渡米しました。ここから私の教育効果測定人生が動き出しました。
(田原)教育会社から日立総合経営研修所に移ったのは?どういう理由だったのですか?
(堤さん)ジャック・フィリップス博士とのネットワークを作り、また、日本に招いたりしました。教育会社で教育効果測定の事業化をプランニングしました。事業化計画は、最初、経営陣も乗る気でスタートしました。しかし段々と雲行きが怪しくなってきました。
パンドラの箱を開けることに恐れをなしたと言いますか、自分たちが提供している研修や通信教育が測定によって効果がないということになったらどうするだという話になったんですね。
総論は賛成なんだけど、各論になると反対する人が出てきて、教育効果測定の事業化は中止ということになったんです。
教育効果測定を諦める事が出来ず。現在私が勤務している日立総合経営研修所の当時の社長(定年退職後、個人で経営コンサルタントをやられています)に相談したんです。そうしたら、研修の品質管理をしないといけないと思っている。よかったら、うちに来るかとお誘いを受けたんです。
それで、2005年に日立総合経営研修所に移りました。
2003年頃より、教育会社で教育効果測定の事業化のために、専門家(コンサルタント、大学教授など)の方々と研究会を立ち上げ、活動をすすめていました。その中の数名の方から、せっかくここまでやったんだからNPOとして存続しようと提案され、そのことを日立総合経営研修所の社長にNPOを続けてもいいんだったら転職したいと相談してみたら、OKをいただいたんです。これが、転職とNPOを主宰するようになった経緯です。
それで、今は、サラリーマンとNPOの2足のわらじで行っているんです。
教育効果測定をする上で大切なことは何ですか?
(堤さん)教育をしていると効果を測りたくなるのが人情だと思うんです。私は企業のフィールドでやっているので研修が教育行為になります。教育効果測定が上手くできない最大の原因は、期待する効果を定義せず研修をスタートしてしまうことです。
私が講師を務める教育効果測定セミナーでは、効果を表す現象をグループで話し合っていただく演習を行います。そうすると、
・研修を受けてよかった
・資格が取れる
・スキルが身につく
・コーチングで部下のモチベーションが上がった
・売り上げ上がった
などといろいろな効果を示す現象が出てきます。
例を挙げて説明しますね。
研修が盛り上がるとか、議論が活発に行われるという現象を教育の効果だと思っている人材育成担当者もいます。教育は盛り上がることが目的ではありませんので、勘違いしている人が、少なくありません。この例は、研修の効果を明確にしていない典型ですね。
別の観点からもう一つ。
人材育成部署が「受講者がとても満足していました」と事業長や経営層に報告します。すると、「そんなのは効果ではないと報告された側が怒るわけです。経営者は、効果として業績上がることを望んでいたんですね。人材育成部門は「受講満足」を効果として研修を実施し、経営者は業績向上を期待して研修に投資をしたんです。それぞれはキチンと効果を定義しているんですが、組織全体として、今回対象になっている研修の効果を定義していなかったという事例です。
教育効果測定をするのであれば、最初に、何が効果なのかを明確にしなければなりません。
教育効果には、どのような種類があるのですか?
カートパトリックの教育効果のフレームワークというものがあります。世界で最も有名な効果を定義するモデルです。
レベルを1-4に分けます。
1 参加者が受けてよかった(研修の満足)
2 知識やスキルを狙い通り習得したか(ラーニング)
3 学んだことを実際に使っているのか、行動が変わっているか(行動変容)
4 組織業績に貢献したか‐売り上げ、CSが上がる、コストが下がる、リードタイムの短縮など(成果)
ID語られるテストは、通常、レベル2を意味しています。
学校や塾では、レベル3以上を求めることは少ないかもしれませんが、企業ではレベル3-4を求める傾向が強いです。
(田原)反転授業では21世紀型スキルも目標に入ってきます。コミュニケーションスキルやリーダーシップなどをどうやって測定するのかで困っている先生もいます。
問題演習で応用力をつけるということだけでなく、他の生徒とコミュニケーションを取るということや、他者性の獲得などもテーマになっています。
(堤さん)なるほど。数学の授業で数学の内容だけでなく、コミュニケーション能力なども伸ばしていこうというということになっているんですね。
本来、数学を学ぶというのは、狭義の意味では計算力を高めたり、公式を理解する事でしょうし、広義の意味では論理的思考力を強化することになると思います。それらと少し遠い関係のコミュニケーションやリーダーシップについても、数学の授業で身に付けさせようということですね。
授業というよりも、ワークショップみたいな学習方法になってくるんでしょうかね。
(田原)コミュニケーションやリーダーシップが学習目標になっているときは、ワークショップ型になる場合もあると思います。
(堤さん)IDは、教育工学として素晴らしい理論だと思います。けど万能ではありません。IDは体系化された知識を身につけさせる場合では非常に効きます。一方、一度決めたことは最後まで投げずにやり遂げる意志力とか、教室でたった一人になっても、いじめは断固反対を貫く勇気といった態度を強化する学習には強くない。苦手なジャンルといっても良いと思います。
態度強化の方法として、最近では、ゲーミフィケーションなどが活用されています。
シリアスゲームは、まさにその好例です。
※シリアスゲーム(Serious game)とは、エンターテインメント性のみを目的とせず、教育・医療用途(学習要素、体験、関心度醸成・喚起など)といった社会問題の解決を主目的とするコンピュータゲーム(エレメカも含まれる[1])のジャンルである。(出典:ウィキペディア)
ゲームの持つ強みは、競争させたり、成長を実感させたり、賞賛したりして、参加者を飽きさせない仕掛けです。また、参加者はゲームの主人公となり、その世界に没入し感情移入しやすいため、心に対して訴えかける力が特に強いです。企業では、ビジネスゲーム(模擬会社経営ゲーム)や飛行機の操縦シミュレーションなどにゲーム理論が活用されています。
ビジネスゲームは会社経営をリアルに再現し、学習者に会社経営の要諦を学ばせるツールです。ゲームの中で、うまく業績が出せこないと、工場を売却して雇用している200名の従業員の首を切って会社を存続させるわけです。ゲームだけど、自分の経営ミスが原因で解雇するという経験は、すごくいやな気持ちになる。IDで論理的に財務諸表の読み方や意思決定の仕方を学ぶより、ズンと心に響きます。経営者の責任の重さを痛感し、態度の強化につながりやすいのです。
IDは数学を数学のまま教えるのであれば、うまく適応するのだろうけど、数学を学ぶのを通してリーダーシップを学ぶという場合には、ゴールを再設定しなくてはならないです。再設定しないままで反転授業を取り入れても、反転授業の何を効果として測定していいのか分からないですよね。この当たりが効果測定をしたいけど一体どうすればよいのと感じる原因かもしれません。
学校と個人とでは評価の単位が違う
(堤さん)企業では、個人が一人で頑張ろうが、チームで頑張ろうが、他人のふんどしで相撲を取っていても、成果が出ればいいんです。プロセスよりも成果に重みが強いんです。
でも、学校はグループ全体で成果を上げても、最終的には、個人評価につなげないといけない。それもある分布に当てはめた評価にしなければならない。
協働の産物を関係者全員が納得できるように矛盾なく個人評価を行うことなんてできるんでしょうか。
協働とは、あるときは田原さんがリーダーで、別の場面では田原さんがフォロワーになるというようにダイナミックなものだと思うんです。動的に変化していく相互作用を精密に見極め個人評価を実施することは無理だと思います。
企業にもよる。同じ車の会社でも、セールスしているところなら個人にフォーカスできるけど、作っているところだと、タイヤのつけ方などにフォーカスしてもしょうがない。
(田原)なるほど。教育現場でも個人にフォーカスした評価だけでは限界があるかもしれませんね。
他人の意見を取り入れる方法について
(田原)企業で重要視されている能力を、学校の中で重要視されていないのが問題だと考えている方もいらっしゃいます。
人のふんどしで相撲を取るというようなことを、できるようになって欲しいということだと思います。
たとえば、SNSに自分の意見を書き込んで、お互いに参照しながら、意見をさらに書いていくという国語の授業をされている先生がいます。そこでは、多くの人の意見を取り入れて、自分の意見をよくすることに取り組んでいるんですよ。
(堤さん)企業のシーンで解釈すると会議が、他人の意見を取り入れる場に相当すると思います。
だめな企業の場合
・議題がないままに会議がスタート。
・抽象的な話をする。
・組織内ポジションが高い人の一言で、結論が決まる。
一方、ちゃんとしている企業では、
・会議の発起人が、「こういうことで困っているから意見を下さい」と目的を明確にしてスタート
・参加者は平等な立場で参加
・発起人は、意見の採択を自由にできる権限を有するが、同時に採択した理由、しなかった理由を説明する義務も有する
ここで、目的に沿って取捨選択していくのが大切なんです。
言いたいことは、他人のふんどしを借りる側が、明確な目的や判断基準(軸)持っていないとダメということです。それらがない人は、色々な意見に迷うだけで、結局決められません。
(田原)会社だと、会議のルール作りがあって、メンバーにはどのような役割を会議で果たすべきかということが研修などで徹底されて、その元で会議が行われるのですか?
(堤さん)うまくいっている会社ではそうなっています。
会議にも種類があります。
・意志決定のための会議
・問題解決やアイディア収集のための会議
・情報伝達のための会議
会議にあわせて誰を呼ぶかも、開く人の権限として与えられています。
(田原)僕のように会社に就職したことがなくて、教育の現場で実践ベースでやっていると、そういうのに疎いんですよ。グループワークについても、見よう見まねでなんとなくグループでやってみよう!ということになっているので、IDとか教育効果とかを勉強して改善したいと思っています。企業には会議やグループワークのノウハウが蓄積されているのだから、教育現場でもそこからヒントを得られたらいいのではないかと思いました。
教育効果という分野は、注目されているのですか?
(田原)反転授業のFacebookグループをはじめて、最初はネットで講座配信している人たちでディスカッションしていて、その後、アクティブラーニングをやっている先生方と出あったんですよ。
それで、アクティブラーニングをテーマにオンライン勉強会をやったら100名くらいが集まって、みんなびっくりしたんですよ。アクティブラーニングをやっている人がこんなにたくさんいることに。
リアルの世界では、周りにやっている人がいなくて孤独を感じていた人も多かったみたいなんです。ネットを通してどんどんつながっていきました。
(堤さん)教育効果測定も同じですね。企業の人材育成の中でも、IDとか教育効果測定をやろうとしている人は、完全にマイノリティなんですよ。
私自身2000年くらいからどうにかしたいと思って教育効果測定に取り組みだしたんですが、最初は変わり者扱いでしたよ。
それが、今では、研修はやりっぱなしではダメ、効果を測定すべきであるという流れに様変わりです。時代の移り変わりを感じます。
NPO活動に参加くださる方々の多くは、自分の所属企業には仲間がいない状況です。NPOに参加して、自分がやっていることの正しさや意味を確認したり、ノウハウ交換したりして現場に戻っていくという状態です。反転授業のグループのお話と同じですね。
反転授業グループは、ネットだから場所を問わずに多くの方々が集まれますけど、私の場合はリアルな場ですから、勉強会への参加人数は20~30名です。反転授業のFacebookグループと根っ子は同じです。
(田原)リアルの世界では、数パーセントに過ぎない少数派の人が集まるには密度が低すぎるから、そういう人で集まって突破口を作るのには、ネットで集まるのが効果があると思うんですよ。今回、グループにIDや教育効果測定をされていた教育工学の方たちが合流して、3つの大きなグループ間での学びあいが始まったのだと思います。これから、どんな化学反応が起こるのか楽しみです。
今日はありがとうございました。
※Facebookグループの人数が1000名を超えました。どなたでも参加することができます。参加希望の方はこちらからお願いします。
※2月26日に実施される第6回反転授業オンライン勉強会で、堤さんがお話してくださいます。
無料申し込みはこちらから