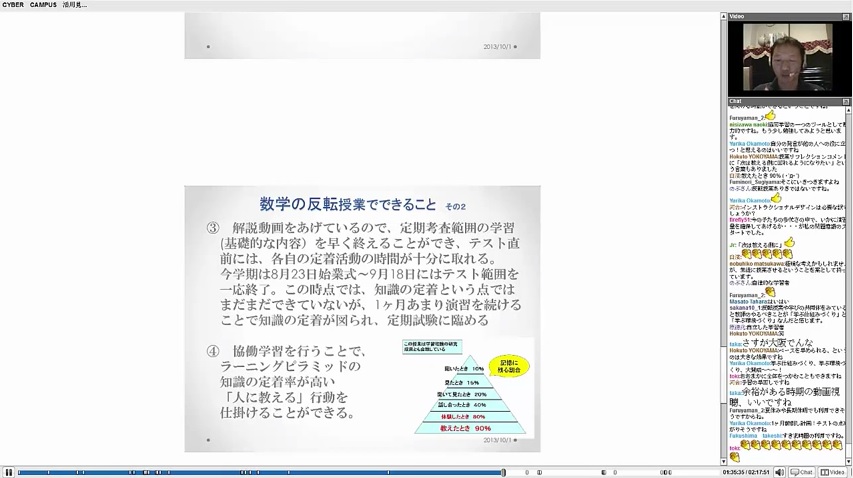「反転授業の研究」の田原真人です。
このグループが始まってから今までのストーリーを連載していくことで、新しく入られた方とも物語を共有していきたいと思います。
メルマガ「反転授業通信」に登録いただくと、第1話から順に配信されます。→ メルマガの無料登録はこちら
第3話 小林昭文さんとの出会い
2013年の夏、東京へ出張する機会があり、空いている時間に、誰かと会って話をしたいと思いました。
当時の僕は、
動画講義の作り方は分かるけど、教室でのグループワークがイメージできない
という状況でした。オンラインで読書会をやっていたメンバーは、みんな動画講義の経験はあったものの、グループワークをやったことがなかったのです。
それで、日本でグループワークをやっている人、東京で会って話が出来る人を探して、Googleで検索していたんです。
そのとき、初めて「アクティブラーニング」という言葉を知りました。
そして、小林昭文さんのブログ
「授業研究AL&AL」
http://d.hatena.ne.jp/a2011+jyugyoukenkyu/
を見つけました。
ブログにはメールアドレスが書いてあったため、そこに「お会いできませんか?」とメールを送りました。
その日の夜、メールに返事が来て、
「日程が合わないのですが、とりあえずスカイプで話しませんか」
ということが書いてありました。
スカイプをすることになり、小林さんのブログ記事を、片っ端から読んでいきました。
そこには、単に効率よくテストの成績を上げるということとは、全く別の次元のことが書いてあり、目から鱗が何枚も落ちました。
そのとき自分が感じていた心の底の深い部分と、「反転授業」が結びつきました。
それまでは、「生身の自分」と「仕事」との間には、少し距離があったのですが、このことをきかっけに2つが一致してきました。
小林さんとスカイプで話をしてから、
アクティブラーニングのことを学びたい。
自分もアクティブラーニングをやってみたい。
そういう気持ちが、沸々と湧いてきました。
小林さんのブログから刺激を受けて、たくさんの記事を書きました。
強い好奇心が湧いて、完全にスイッチが入った状態になりました。
●反転授業と生徒の多様性についての考察
http://flipped-class.net/wp/?p=98
●カンニング禁止はテストのルールであって勉強のルールではない
http://flipped-class.net/wp/?p=103
●日本で反転授業を成功させるためには
http://flipped-class.net/wp/?p=108
●「反転授業の効果は試験の点で5%アップ」について
http://flipped-class.net/wp/?p=113
●反転授業のデメリット
http://flipped-class.net/wp/?p=118
当時、僕は、予備校講師を辞めていて、ネット予備校でしか教えていなかったので、なんとかオンラインでもアクティブラーニングのエッセンスを取り入れる方法はないかと考えました。
それで、WizIQというWeb教室システムを使って行っている授業に、5分でもいいからアクティブラーニングの要素を入れようと考えました。
小林さんも見学に来てくれ、その中で授業を行いました。
電気回路の授業をやっているときに、受講生から、
「抵抗では、エネルギーが消費されるのに、電荷は消費されないのですか?」
という質問が出ました。
「それはね・・」
といつものように回答しそうになりましたが、
「あ、ここで、学び合いができるんじゃないか」
と思って、質問に対してどのように回答したらいいかを、受講者に問いかけて、チャットボックスに書いてもらいました。
チャットボックスには、たくさんのコメントが並びました。
その中で、水力発電を例にとった分かりやすい説明があり、その説明でみんなが納得しました。
僕は、その説明を書いてくれた人に「拍手」をするようにみんなに呼びかけました。
その授業の後のアンケートでは、ほとんどの人が、その学び合いについて書いていました。
90分間の中でわずか5分程度だった学び合いが、85分間の「予備校講師の授業」よりも受講者の心を捉えたという事実が、その後の僕の授業に決定的な変化を与えました。
次回の授業からは、その5分を90分に拡大することにしたのです。
さらには、オンラインでのグループワークにも挑戦しました。
そのときのことを、小林さんがブログに書いてくれました。
●オンライン授業を見学しました
http://d.hatena.ne.jp/a2011+jyugyoukenkyu/20130923/p1
小林さんとの交流が始まり、小林さんがブログとFacebookで僕のことを紹介して下さったおかげで、たくさんのアクティブラーニングの実践者と繋がることができました。
「反転授業の研究」で、動画の実践をしてきたメンバーと、アクティブラーニングの実践者とが混じり合いました。
お互いのやってきたことを教えあうことで、反転授業のやり方が見えてくるのではないか。
そんな思いから、WizIQを使ってオンライン勉強会をやることにしたのです。
それが、驚くべき事態を引き起こしました。
(第4話へ続く)
●編集後記
2013年ころに自分が考えていたことを改めて見直すと、知識という面では、今よりもだいぶ少ない状態で記事を書いているのですが、新しいものと出会った興奮というものが文章から出ていますね。
当時、本当にワクワクしていたんです。